この記事の要約
- LLM機能の失敗原因は「AI活用」の目的化 – 顧客の真の課題解決よりも技術導入が先行し、PoCで終わるケースが多発
- 成功の鍵はN=1の課題発見とロードマップ設計 – ユーザーインタビューで切実な課題を特定し、PoCから本番運用・グロースまでの計画を事前に明確化する必要がある
- 運用体制とバイアス対策が必須 – リリース後のデータ更新、モデルチューニング、倫理リスク管理の仕組みを最初から組み込まないと事業として成立しない
なぜ、「LLMを使った新機能」は失敗しやすいのか?
多くの企業がLLMを活用した新機能の開発にチャレンジしていますが、その成功確率は高くありません。大きな原因としては以下が挙げられます。
- 要求定義の曖昧さ
(大体は経営層からの命令で)「AIを使う」こと自体が目的化し、本来のユーザー課題が不明瞭なまま開発が進む。結果として、PoC終了後にビジネス要件と合致しないことが判明して頓挫。 - 顧客価値の言語化不足
LLMの機能を活かせば高度な分析や自動化ができるはずなのに、ユーザー側の文脈を踏まえた設計やUXが追いつかず、現場レベルでは「便利だけど、使わなくてもいいかも」という状況に陥りやすい。 - 継続的なデータ更新・管理体制の欠如
最初のPoCでそれなりの精度を出したAIモデルも、学習データの陳腐化やユーザー数の拡大による負荷増加に対応できず劣化。一度失敗すると、チームのモチベーションが下がり、プロジェクトが立ち消えになる。 - AIバイアス・倫理リスクの軽視
LLMならではの差別的、誤情報、攻撃的表現などのリスクを甘く見積もり、リリース後に炎上。信用失墜やクレーム対応に追われ、AI活用の価値が毀損する。
生成AIではありませんが、AI周りの失敗例としてこんな記事もありますね。

PdMが押さえるべき「LLMを活かして事業を伸ばす」ためのポイント
こうした失敗を回避しながら、LLMの新機能をビジネスの成長エンジンへとつなげるためPdMには以下の視点が欠かせません。
(改めて!)顧客の、N = 1の、“真の”課題を起点にする
LLMが生み出す機能はいくらでも“すごそう”に見えますが、ユーザーが「そこまで高機能でなくても良い」と思っている可能性があります。実際の業務や利用シーンを掘り下げるために、ユーザーインタビューが非常に有効。
「ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド」などを参考に、何を解決すればユーザーが本当に喜ぶのかを抽象度の高いレベルから具体的に落とし込んでいきましょう。これがLLM新機能の成功確率を左右します。
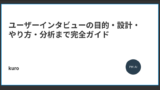
LLM関連の新機能だとしても、まずは「N = 1」の”自分で発見した”切実度の高い課題始めないと失敗するのは当たり前です。
PoCからグロースフェーズまでのロードマップを明確化
PoC段階では技術検証(精度評価やUIプロトタイプなど)に集中しますが、同時に「本番運用後はどのようにビジネスを伸ばすか」の絵を描いておくことが重要。具体的には以下のステップを意識します。
- PoC: モデルの精度やUXの評価を最小限のリソースで確認
- MVPリリース: コア機能を絞って本番環境に投入。ユーザーからのフィードバックを速やかに回収
- グロース戦略: 追加機能の優先度付け、データ更新フローの確立、運用体制(SREチームなど)の整備
ロードマップの合意形成ができていれば、PoCで得られた知見を次の段階に活かしやすく、“PoC止まり”を避けられます。
つまり、PoCの報告をして「で、どうするんだっけ?」と部長や役員から詰められる確率が減るということです。
LLM特有のバイアスや倫理リスクに対処する
LLMは既存のテキストコーパスを学習するため、偏った表現や誤情報を出力しやすいという特性があります。これを放置すると顧客体験を損ない、会社の信用を失うリスクも。PMとしては以下の対策を行いたいところです。
- バイアス検出&フィルタリング
不適切な回答を自動検知・抑制する仕組みをプロダクト内に実装。「AI Fairness 360」などのツールを活用するのも一手 - 多角的なレビュー体制
法務・データサイエンティスト・UXデザイナーらが参加する倫理委員会やレビュー会を定期的に開催 - ユーザーフィードバックループ
社内外のユーザーから誤情報や差別的表現に対する通報を受け付け、それを改善につなげる仕組みを早期に構築 - 週3-5人のユーザーインタビュー
週3-5人くらいインタビューをして画面を見せてもらえれば、大体のエラーに気づきます。サボらずやりましょう。
LLMだろうがなかろうが、「ユーザー体験設計」から逃げない
LLMが生成する出力は高精度・多機能になりがちですが、UIやUXが複雑になるほど、ユーザーの学習コストが高まるというトレードオフが発生します。
例えばチャットUIであれば、ユーザーがどのようにプロンプトを入力し、どんな応答が望ましいのかをチュートリアルやサンプルでガイドする必要があるでしょう。LLMによる出力を「シンプルに可視化」する仕組み(要約表示、タグ付けなど)も検討し、ユーザーが戸惑わずに使いこなせる状態を作ることが大切です。
LLMの機能になるとUXUIに対してふわっと意思決定されることが多いのですが、当たり前ですが後で痛い目みますよね。デザイナーを入れてプロトタイプを作ってユーザー検証しましょう。
LLMを顧客にとって“意味ある形”に仕上げるための具体策
コアとなる“ジョブ”を捉える
「ジョブ理論」(Clayton Christensen提唱)でも言われるように、ユーザーは何かの“ジョブ”(達成したいタスク)をこなすためにプロダクトを“雇用”します。LLMの新機能を導入する際は、ユーザーがどんなジョブを完遂するために本機能を使うのかを意識しましょう。
たとえば「営業メールの下書きを一瞬で生成し、担当者の業務負荷を劇的に減らす」というジョブが設定できれば、LLMの文章生成能力が顧客価値へ直結します。
ユーザーインタビューから要件定義を磨く
リリース前に実際のユーザーへインタビューを行い、どの部分が“本当に欲しい機能”なのかをヒアリングするステップは必須です。
詳しい進め方は「ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド」を、分析手法は「ChatGPTでユーザーインタビューの分析を爆速にする具体手法を解説」を参照。PM自身が現場の声を直接拾うことで、LLMが生成する範囲・プロンプト設計のヒントを得ることができます。
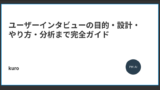

継続データ更新とモデルチューニングの計画
LLMプロジェクトで成功するチームの特徴は、「リリース後のデータ運用に本気で取り組む」点にあります。以下の施策が有効です。
- ログ分析: ユーザーがどんな入力を行い、どんな出力に満足しているかを週1回程度モニタリング。この時に利用回数などではなく具体的なインプットとアウトプットを見るのがおすすめです。
- モデル更新サイクル: 新たな学習データを一定周期で準備し、精度検証 → 本番反映を回す
- プロンプト強化: 問い合わせ頻度が高いトピックや誤作動が多い領域を洗い出し、プロンプトテンプレートやガイドラインを改善
こうした運用体制を定着させることで、LLMの劣化を防ぎ、常に顧客が求める最新の知見を反映できるようになります。
PoCからグロースまでのロードマップ例
では実際に、PoCからグロースまでの流れをどのように描けばよいのでしょうか。以下はあくまで一例ですが、ロードマップを意識的に組み立てると成功確率が一気に高まります。
- ステージ0: アイデア検証
ユーザーインタビューやリサーチを通じ、LLM機能によって解決したい主要課題を仮説化。ビジネスインパクトのコスト見積もりも同時に行う。 - ステージ1: PoC
小規模データセットやプロトタイプ環境でLLM機能を試作。精度・UX・バイアスリスクなどを検証し、ユーザーや社内ステークホルダーの反応を収集。 - ステージ2: MVPリリース
コアの課題解決に必要な最低限の機能を実装し、本番環境に展開。既存顧客を中心に利用を促し、フィードバックを即座に反映できる体制を構築。 - ステージ3: グロースフェーズ
ユーザー数拡大に伴い、追加機能・インフラ強化・バイアス対策のアップデートを継続。学習データ更新とA/Bテストを頻繁に実施し、“顧客価値の最大化”を追求。
今日から実践できるアクション
- 顧客課題を再点検:
LLM活用の前提として、“顧客が本当に困っていること”を改めて言語化。既存調査やインタビュー結果を再整理し、機能要件に優先度をつける。 - 早期のユーザー検証・プロトタイプ:
コストをかけすぎずにMVPやプロトタイプを素早く作り、実際の顧客や社内ユーザーに試してもらう。フィードバックを集めてPoC段階からロードマップの精度を高める。 - バイアスチェック体制の設計:
リリース前後で不適切出力がないか定期的に確認するフローを作る。緊急停止(キルスイッチ)やユーザー通報窓口など、障害発生時の対処プロセスも明確化する。 - 運用サイクルとリソースの確保:
リリース後のモデル更新やログ分析、問い合わせ対応に要するリソースを事前に確保。開発終了=運用スタートであり、長期的にブラッシュアップし続けられる組織体制を築く。
Q&A
- Q1: インタビューで顧客は「いいですね」と言ってました。
- A1: そんなものは嘘です。
「いいですね」ではなく、追加契約などコミットを図ったり比較対象を設けた上でNPSを比較する、usability benchmarkを利用する、など質的データとして有責なものを集めましょう。

- Q2: バイアスは完全には消せないのでは?
- A2: はい、完全にゼロにはできません。しかし、リスクを最小化する方法は多数あります。データソースの多様化、フェアネスチェックリストの導入、ユーザー通報機能の設置など、対策を積み重ねることで炎上リスクは大きく低減できます。
- Q3: PoCが成功したのに、本番移行で苦戦する理由は?
- A3: PoCは小規模データや限定されたユーザー環境で行われるため、本番環境での負荷、セキュリティ要件、UX最適化など別次元の課題が出てきます。PMはPoC開始時から本番リリース後の運用や拡張を視野に入れ、ロードマップとリソース確保を見据える必要があります。
参考情報
- Buolamwini, Joy and Gebru, Timnit. “Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification.” Proceedings of Machine Learning Research, 2018.
- NIST. “Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence.” 2022.
- Rachel K. E. Bellamy et al., “AI Fairness 360: An Extensible Toolkit for Detecting, Understanding, and Mitigating Unwanted Algorithmic Bias.” IBM Research, 2019.
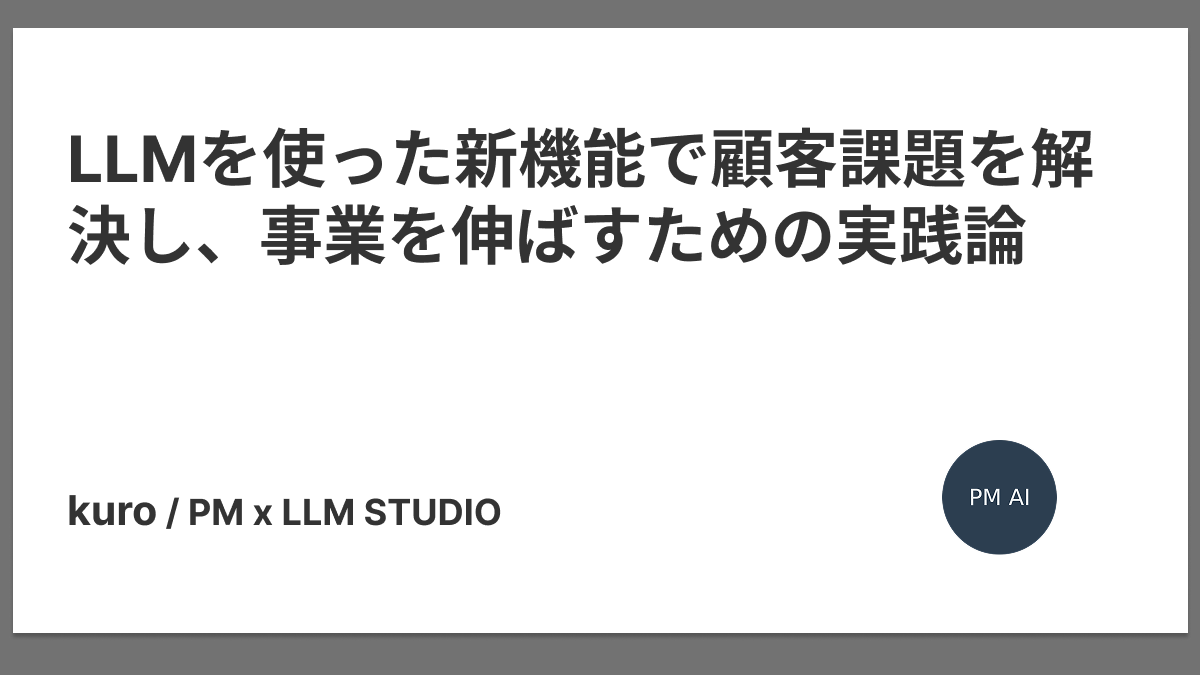

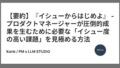
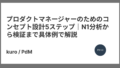
コメント