この記事の要約
- いらない機能を削除する決断には利用率モニタリングとVIPユーザーへの代替案提示を含む明確な意思決定フローが必要
- Feature FlagとFractional Rolloutsで全体の1-5%にテスト展開し、定量データと定性インタビューを組み合わせて本当の価値を検証
- 機能追加至上主義から脱却するには削除施策を表彰し、「作った実績」ではなく「利用率・KPI達成度」で評価する組織文化改革が不可欠
削る勇気を実践に移す:機能削除・ダウンサイジングの意思決定フロー
いらない機能を削ることは、組織的な力学や評価が絡むと難易度が上がります。また、ユーザー観点でも実際のユーザーに影響が出ますし、少数ながら利用している人がいれば苦情も出るかもしれません。
それでも、使われない機能を放置するコストは中長期的に見れば相当大きいです。保守運用の負債を減らすためにも、ダウンサイジングや削除の決断を先延ばしにしないのがポイント。

意思決定フローの例
- 利用率モニタリング:2~3ヶ月ごとに、各機能の利用頻度やエラー報告数を一覧化
- VIPユーザーへの確認:もし上位5%などのVIPユーザーが特定機能を使っているなら、代替案やオペレーションでの補完策を提案し説得
- プロダクト戦略との照合:将来のビジョンやロードマップで、この機能は本当に必要か?“コア価値”の邪魔をしていないか確認
- 削除リリースプラン作成:移行スケジュールやメッセージ文言をまとめて周知。
たとえば「次バージョンで正式削除します」という明確な日程設定 - リリースノートやFAQで丁寧に告知:ユーザーにネガティブな印象を与えない工夫。
「より良いUXのため」「保守負荷を減らしてメイン機能を強化するため」など意図を伝える
Betaテスト&Feature Flagの高度活用:定性×定量を融合
プロトタイプ検証だけでは「本当に使われるのか?」を見切れないケースが少なくありません。そこで力を発揮するのが、BetaテストとFeature Flagです。
Fractional Rolloutsとコホート分析
- Fractional Rollouts:ユーザー全体の1〜5%にだけ機能を有効化する。
→ 想定外の不具合や利用率の低さが判明しても影響が限定的 - コホート分析:機能を使い始めたタイミング別にユーザー行動を比較。
→ 「初週のリピート率が10%以下なら継続は厳しい」など明確基準を設定
これらの定量データに加えて、ユーザーインタビューによる定性情報を掛け合わせると、例えば「UIは好評だが実際は誰も使っていない」ような矛盾を炙り出せます。
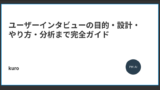
「機能」ではなく「UXフロー」を最適化する考え方
また、多くのチームが“機能追加”単位で考えてしまいがちですが、本来はユーザーがゴールを達成するまでの全体フローを見直すほうが効果的な場面は多いです。
ストーリーボードやユーザージャーニーを用いて、どこがボトルネックになっているかを明らかにすれば、そもそも“新機能追加”ではなく“既存フローの単純化”で済むケースも多いです。

ステップ
- ユーザーが達成したい最終目的を再確認(注文完了、情報取得、問い合わせなど)
- フロー上の各ステップを可視化(クリック数、入力項目数など)
- 真に必要なステップだけを残す(要らない画面やUI要素は排除)
- ユーザーテスト(Lostnessなどの指標も活用)
こうすることで、新機能の追加よりもフローの簡素化が優先課題だと判明するケースが少なくありません。

トップダウン要求との戦い方:ステークホルダーマネジメント実例
さらに、多くのPdMが悩むのは、上司や経営層、VIP顧客からの「この機能ほしい」「とにかくやろう」という要望。
ここで重要なのは、その要望の裏にある“本当に解決したい課題”を見抜くことです。
実例イメージ:営業チームからの要望
- 表面的な要求:「競合がチャット機能を入れてるから、うちもすぐにチャットを入れたい」
- 深層的な課題:「問い合わせ対応が電話だと時間がかかりすぎる。顧客は手軽なコミュニケーションを求めているのでは?」
- 打ち手:まず簡易的な“問い合わせフォーム”や“Bot対応”で十分機能するか確認。
Betaテストやインタビューでデータを集め、チャット機能そのものが最適とは限らないという仮説を提示
「要望をそのまま形にする」のではなく、「本当に必要な課題解決策は何か」を共に考えられると、不要機能の防波堤になります。

“価値創造型”の新機能:評価しにくいときの対処
課題が明確な“課題探索型(必要なことが明らかな機能)”に比べ、“価値創造型”(潜在的なニーズに基づいて実験的に導入する機能)はユーザー自身も気づいていない潜在ニーズを掘り起こすため、ROIの見極めが難しいです。
ただ、これを理由にまったく評価せずに作り込むと、「結局誰も使わなかった…」となるリスクが高まります。
Kanoモデルで失望度を計測
イノベーティブなアイデアをテストする際、Kanoモデルを使うと「なくてもいいけどあると嬉しい機能か、あっても意味がない機能か」をある程度把握できます。
プロトタイプを当ててみて、「もしこれがなくなったら、どのくらいがっかりしますか?」というネガティブ仮定で質問し、魅力的品質の可能性を探るのが1つの手段としておすすめです。(Kano, 1984)

リリースのスモールステップ
「大規模実装」ではなく、最小限の試作品をBtoB顧客の一部に提供して反応を見るなど、一気に賭けない体制が重要です。
万が一失敗しても損失を最小化でき、かつ成功すれば爆発的な伸びを狙えます。

ペルソナを再定義:誰のために機能を作るのか
「何となく従来のペルソナで開発していたら、いつのまにか市場やユーザー層が変わっていた…」
ありがちですが、ペルソナが古くなると、“いらない機能”が入り込みやすい環境になります。だからこそ、「誰のために作っているのか?」の象徴であるペルソナを作り、3ヶ月に1回などそのタームのインタビューを踏まえてズレていないか確認するプロセスを開発に入れ込みましょう。

ペルソナ再定義の流れ
- 既存ユーザーの行動データを収集:活用頻度、契約プラン、サポートへの問い合わせなど
- セグメント分割:新規ユーザー/熟練ユーザー、導入担当/実利用者など
- インタビューや観察で実態を確認:ペルソナが仮説とずれていないか、改めてヒアリング
- 新しいペルソナを策定:不要機能の温床にならないよう、ニーズと痛みを具体化
プロダクトが成長すればユーザー構成も変わります。
意識的にペルソナをアップデートしないと、「誰のための機能?」が曖昧になるのです。
ペルソナについてはこちらの記事をご覧ください

組織改革・文化醸成:機能追加至上主義からの脱却
最後に、いらない機能が生まれ続ける背景には、組織として「作った実績を評価する」風土が根付いている可能性があります。
これを変えるには、トップダウン+現場の両面から文化のテコ入れが必要です。
施策の例
- 削除施策を表彰:ユーザー満足度やコア指標が向上したら成果として認め、チームに広くアナウンス
- リサーチOps強化:リサーチ専任やツール導入(例:AIエージェントツールまとめ)でデータを根拠に議論できる環境を作る
- ロードマップの定期見直し:クォーターごとに「本当にこれはやるべきか?」を経営陣と再チェック
こうした取り組みを重ねると、機能を出す/出さないの判断が客観的になり、「作ればOK」文化から脱却できます。

今日から実践できるアクション
- 機能削除チェックリストを作成:既存機能をリストアップし、利用頻度や保守コストを加味して“削除候補”を明確化する
- Fractional Rolloutsの設定:次に新機能をリリースする際、全ユーザー展開ではなく一定割合でテスト運用し、ログと定性評価を突き合わせる
- ストーリーボードの作成:新機能ではなくUXフロー全体を可視化し、ボトルネック解消の手段として本当に新機能が必要か再考する
- ステークホルダーの「要望の裏」を聞く:営業や上司の“やりたい”を、そのまま受けずに「顧客課題は何か?」を一歩踏み込んでヒアリングする
- ペルソナを再定義:ユーザー構成が変化していないかログデータを確認し、必要ならば最新のペルソナ像をチームで共有する
Q&A
Q1. 削除するほどスリムなプロダクトを目指すと、新規機能リリースが減り、社内評価が下がる気がします。
A. “いらない機能を作らない”=“何も作らない”ではありません。あくまで本質的に価値のある機能に集中することです。成果指標を“機能数”ではなく“利用率”や“KPI達成度合い”に変換し、社内で評価軸を再設定しておくといいです。Q2. Betaテストでデータがどうにも微妙だった場合、実装しないで終わるのはもったいないですか?
A. そこは損切りコストの考え方(Cost of DelayやWSJFなど)を踏まえ、続行か撤退か判断します。微妙な機能を本番リリースした結果の長期コストは相当大きくなる可能性があるので、思い切った撤退は決して無駄ではありません。Q3. 「価値創造型」の機能で、Kanoモデルの満足度調査がピンと来ないんですが…
A. 普段の課題感が弱い領域ゆえに、ユーザーも明確な評価をしづらいのは事実です。ただ、「これがなかったらどのくらいがっかりするか?」を尋ねるのは、未来の喜びや驚きを測るひとつのアプローチ。必要に応じてA/Bテストや長めの検証期間を取り、最小限の機能セットでトライアルを実施すると良いです。
参考情報
- Kano, N. (1984). “Attractive Quality and Must-be Quality.” Journal of the Japanese Society for Quality Control.
- Holtzblatt, K., & Beyer, H. R. (1993). “Making Customer-Centered Design Work for Teams.” Communications of the ACM.
- Ries, E. (2011). The Lean Startup. Crown Business.
- Cagan, M. (2018). INSPIRED: How to Create Tech Products Customers Love. Wiley.
- Netflix Official Interviews (n.d.) [内部インタビューより].

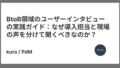
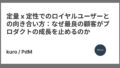
コメント