この記事の3行要約
- 人間の思考はシステム1(直感的・高速)とシステム2(論理的・低速)の二重過程で動き、95%の意思決定は無意識のシステム1が担っている
- 確証バイアスやアンカリング効果などの認知バイアスを理解し、プロダクト設計に組み込むことで、ユーザーの自然な行動を促せる
- 認知負荷を下げ、チャンク化やプライミング効果を活用することで、ユーザーが迷わず目的を達成できるプロダクトを作れる
サービス設計をしていると「なぜユーザーはこの選択肢を迷うのだろう?」とか「画面遷移が1ステップ増えただけで離脱率が急に上がるのはなぜ?」といった疑問を日々感じますよね。
こうした疑問を解き明かすには、「認知科学」の視点が有効。
認知科学は、脳がどのように情報を処理し、意思決定を下すかを学問的に扱う領域。
「認知科学」とは何か?プロダクト設計にどう関係するか?
認知科学は、心理学・言語学・AI・神経科学など多様な分野が交差する学際領域。
たとえば、Daniel Kahnemanの『Thinking, Fast and Slow』(邦題:『ファスト&スロー』)では、人間の思考プロセスを
- システム1(直感的・素早い)
- システム2(論理的・ゆっくり)
に分け、バイアスや意思決定の仕組みを解き明かしました。
プロダクトの中でもユーザーがUIを操作する際に
- “システム1的に素早く操作してしまう部分”
- “システム2的に熟考する部分”
が混在します。認知負荷が大きい場面ではユーザーが面倒になり離脱し、逆に直感的すぎると誤操作が増えるなど、絶妙なバランスが求められます。
僕自身、“なんとなくこうしたほうが良さそう”と考えることが多かったのですが、認知科学的アプローチはより一貫性のある設計や他者への設計を可能にしてくれます。
例えば、
- ユーザーが新機能を理解するために必要な“ワーキングメモリ”量
- エラーが起きたときの“意識的処理への切り替え”
など、科学的根拠を持ってUI/UXを見直すと納得感が増すのです。
認知負荷を意識する:ワーキングメモリとUI設計
とっつきやすい認知科学の概念として「ワーキングメモリ(Working Memory)」があります。
人間の脳は一度に保持できる情報量が限られており、複雑な指示や多すぎる選択肢を提示されると処理しきれず混乱しやすいとされています。
これはプロダクトのオンボーディングやフォーム入力などで顕著に表れます。
具体例として、会員登録画面をイメージしてみましょう。
ユーザーに入力を求める項目が多すぎる場合や、次々と別画面に飛ばされる場合、ワーキングメモリの負荷が一気に上がり離脱率が増加します。
そこで、フォームを段階ごとに分割し、各ステップは最小限の項目だけに絞る仕組みを導入すれば、ユーザーが瞬時に理解できる範囲に留められます。
このように「認知負荷を下げるUI」によって、結果的にコンバージョン率が向上する可能性が高まります。
意思決定理論を踏まえた選択肢設計:Choice Overloadを防ぐ
また、意思決定理論(Decision Theory)は、認知科学の中でもユーザーが選択肢をどう評価し、意思決定を行うのかを扱う分野で有名な概念。
中でも特に有名なのは“選択肢過多”による意思決定困難、いわゆる“Choice Overload”の問題です。
アメリカのジャムの売り場で選択肢が多すぎると購買意欲が下がるという実験(Iyengar & Lepper, 2000)は、プロダクトの機能選択やプラン設定にも通じる示唆があります。
例えば、プライシングプランが5種類もあるSaaSの場合、多くのユーザーは「どのプランが自分に合うかわからない」と戸惑い、結果的に購入を見送ることがあります。
ここで、プランを2〜3種類に絞る・プラン診断フローを設けるなどの設計が効果的になるわけです。
意思決定理論を意識すると、「選択肢はたくさんあったほうが良い」という安易な結論を避けられます。
「思考の2つのシステム」をUIやUXで活かす
先ほど記載した、Kahneman提唱の「ファスト&スロー」は、プロダクト設計において参考になります。
- ユーザーがシステム1(直感的・速い思考)で操作しているシーン
- ユーザーがシステム2(意識的・ゆっくりした思考)を使うシーン
を峻別することで、UIのレイアウトやエラーメッセージの出し方を最適化できます。
例えば、ECサイトのトップページから商品を探す場面はシステム1でサクサク操作するユーザーが多い(いわゆる「ザッピング」)。
ここで余計なポップアップや多すぎるバナーを出すと、システム1の流れを妨げて離脱につながる可能性があります。
一方、決済前の最終確認はシステム2が働く場面で、ユーザーが慎重になりやすいタイミングです。
そこでは選択肢や注意事項を少し詳細に書いても読み手が丁寧に確認してくれるため、「追加情報を埋め込むなら、ここがベスト」というように判断ができます。

認知科学を用いたエラー管理
また、ユーザーインターフェースにはどうしてもエラーがつきものです。
認知科学の視点から考えると、エラーは
- 「ワーキングメモリが足りない」
- 「誤ったメンタルモデルをユーザーが抱いている」
- 「システム1で早とちりした」
など、複合的な原因で起こります。
エラー予防策としては、
- フォーム入力のときに入力可能な範囲をビジュアルで示す
- リアルタイム検証する
などUI上でユーザーをガイドする手法が考えられます。
さらに、エラーリカバリでは、
- 「戻るボタン」を適切に配置
- エラーメッセージをわかりやすい言葉にする
などが鍵になります。
これらは単なるUI/UXのTipsに見えますが、認知科学では「人間の注意力がどこで切れやすいか」「誤操作をどうすれば最小化できるか」を科学的に検証しており、デザインに活かせる要素が多いです。
PdMができる具体的アクション例
では、認知科学の概念をどうやってプロダクト開発に取り込むか?
1)画面フローごとの認知負荷スコアリング
新機能や大きなUIリニューアルをする際に、各画面・各ステップで「これってユーザーのワーキングメモリをどれくらい使うかな?」と評価表を作ってみる。
具体的には、「入力項目数」「操作ステップ数」「追加で判断すべきオプション数」などをスコア化し、合計が高い部分は分割やリデザインを検討。
詳しくはこちらの記事をご覧ください

2)意思決定が発生するポイントの洗い出し
ユーザーがどのタイミングで迷う(システム2を発動する)のかを可視化する。
そこでは候補を絞るアフォーダンスを用意したり、デフォルト選択肢を設けたりしてChoice Overloadを防ぐ。
プライシングプランが多すぎる場合などはとくに有効。
3)バイアス研究と組み合わせる
人間は認知バイアスに日常的に惑わされます。「社会的望ましさバイアス」「確証バイアス」などを理解して、インタビュー時の質問設計やUIメッセージの文言を調整すると、より正直なフィードバックを得られるでしょう。
このステップを踏むと、ユーザーが本音を言ってくれやすい環境を構築可能です。

参考記事
- ユーザビリティテストの分析手法「Lostness」「タスク間連関分析」を解説UI操作の迷い度を数値化する「Lostness」の考え方は、認知負荷を見極める上で有用
- 心理学を活用してユーザーインタビューからバイアスを排除し“本音”を引き出すバイアスをどう抑制し、正確なユーザー意図を掴むかのヒントになる
- 「Usability Benchmark」を理解して、ユーザービリティも守備範囲なPdMになる認知負荷を数値的に測る指標づくりの参考になる
Q&A
Q1. 認知科学を学ぶのは大変そうで、どこから始めればいいですか?
A. スタートとしてはKahnemanの『Thinking, Fast and Slow』やHerbert A. Simonの意思決定理論をざっくり読むだけでも十分にヒントになります。PdM業務に直結する形で言えば「ユーザーがどのタイミングで認知的に疲れるか」を観察する意識を持つところからが手軽です。
そこまでやらずとも、amazonで出てくる「認知科学 入門」的なやさしい書籍でもOKだと思います。Q2. すでに出来上がった製品に認知科学の観点を導入すると手戻りが多そうです。
A. 確かに、既存UIの大幅改修にはコストがかかります。まずは新機能や部分的なリニューアルから適用し、小さな勝利を積み重ねて社内を説得するのが良い方法です。いきなり全機能の改修を狙うより、スコープを切って着実に進めると効果が見えやすいです。Q3. 認知科学を取り入れると、“ユーザーをコントロールする”ようで抵抗感があります。倫理的に問題ないですか?
A. ユーザーの脳内プロセスを考慮することは「コントロール」ではなく「本質的な使いやすさ」を高めるための手段です。もちろん、ダークパターン(ユーザーの意図に反して誘導するデザイン)を狙うのは倫理的に問題があります。正しい認知科学活用は、ユーザーの目標達成をサポートし、ストレスを減らす施策です。
参考情報
- Daniel Kahneman (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
- Herbert A. Simon (1957). Models of Man. John Wiley and Sons.
- Iyengar, S. S., & Lepper, M. R. (2000). “When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing?”. Journal of Personality and Social Psychology.
- Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things (Revised & Expanded). MIT Press.
- Stanford HCI Group (n.d.). “HCI Research and Cognitive Load.” Stanford University.
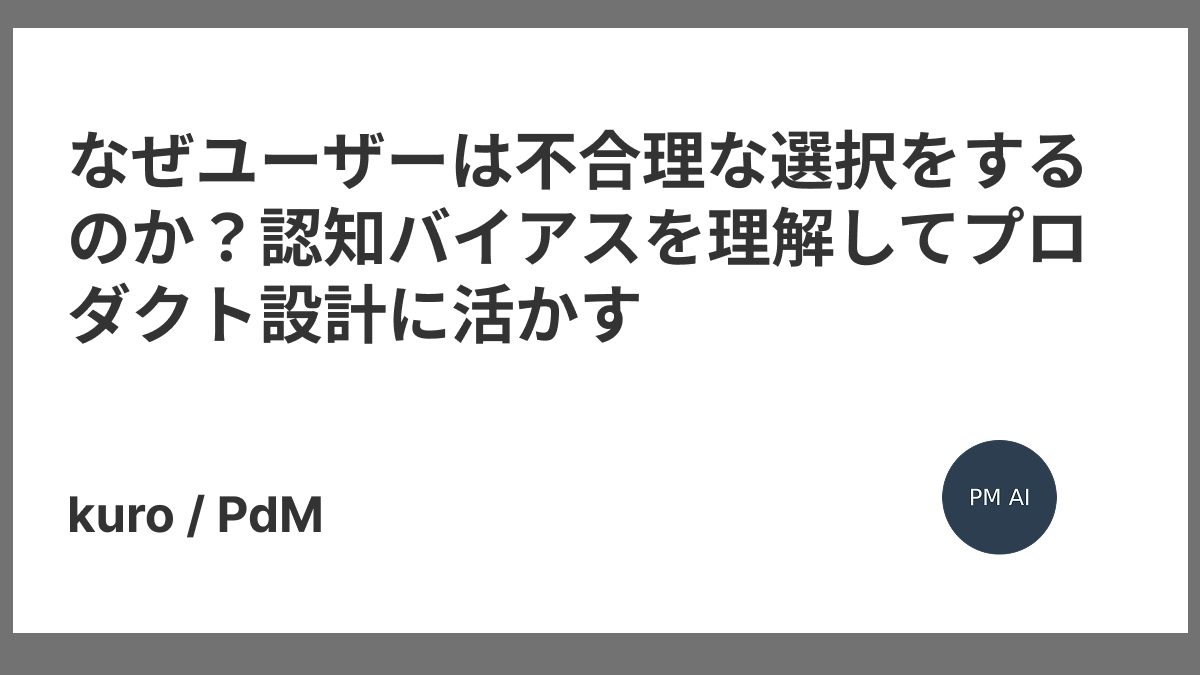


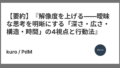
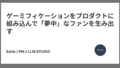
コメント