この記事の要約
- BtoBインタビューは導入担当と現場利用者の視点が異なるため、別々にヒアリングして両者のギャップを可視化することが重要
- セールス・CS・PMが持つ顧客情報を共通言語で一元管理し、定期的な会議で優先度を透明化する仕組みが必要
- プロトタイプを活用した早期検証により、長い導入サイクルでも手戻りを防ぎながら価値ある機能開発が可能
BtoB領域のプロダクトマネージャーにとってもユーザーインタビューは極めて重要。とはいえ、BtoCと比べて調整難度が高く商習慣や組織構造が複雑です。
本記事では、BtoBインタビューにおける典型的な課題を網羅し、意思決定者(導入担当)と現場利用者のギャップ、新機能検証でのプロトタイプ活用、セールス/CSとの連携、さらには組織内での「共通言語」づくりまでを解説します。
なぜBtoBインタビューは難易度が高いのか
BtoBインタビューの難しさは、主に次の3つに集約されます。
- 多様なステークホルダーの存在
経営層、導入担当(上司・管理職・購買部門)、現場利用者、会計・経理、法務、CS部門などが絡むため、対象を誤ると情報が散逸しやすい(N = 5やろう、となってもセグメントが異なる5人が集まってしまいやすい)。 - 商談と調査の混在リスク
リサーチ目的にもかかわらず、製品アピールや価格交渉に話が移り、ユーザーの本音を聞けないまま終わる。 - 守秘義務・情報開示の壁
NDAや競合比較の問題で、インタビューの深い話が得られにくい。
さらに、BtoBでは導入までのサイクルが長いことも大きな特徴。投資判断が慎重になるため、事前に丁寧なインタビュー設計が求められます。逆に言えば、複数のステークホルダーの視点を収集できるメリットも大きいのがBtoBインタビューの醍醐味です。
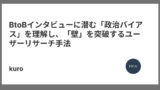
インタビュー設計の全体像
BtoBインタビューを成功させるには、アポイント獲得 → インタビュー準備 → 実施 → 分析 → 社内共有・意思決定の流れを一貫して考える必要があります。特に以下の3ステップがポイント。
- ステップ1: 対象者の洗い出し
顧客企業内のキーマン(経営層、導入担当、現場担当者など)をリストアップ。
米国Gartnerの調査によれば、BtoB購買判断には平均7名のステークホルダーが関わるとされています(※1)。 - ステップ2: インタビュー目的・スクリプト設計
インタビュー前に「筋の良い仮説」をチームで設定し、導入担当と現場利用者向けの質問を分けるなど、複数の質問セットを準備。 - ステップ3: NDA・日程調整など事前準備
管理部門や法務への連絡、NDAドラフトの用意など。スケジュール管理が甘いと当日質問できる範囲が狭まるので要注意。

セールス/CSチームとの連携がカギ
BtoBでは、セールスやカスタマーサクセス(CS)チームとの連携が欠かせません。
営業担当が日々の商談で得た顧客の生の声、CSがサポート対応で拾う課題感は、PMが直接接点を持たない視点を補完してくれます。
ただしセールスは受注を最優先しがちで、CSは顧客満足やサポートコストを最優先しがち。そのため、「今回は調査が目的なので、営業トークは最小限に抑える」といったルールを明示しておくことも大切。そうしないと商談モードに引きずられ、インタビューのゴールを見失いがちです。
また、営業やCSが既に一次情報を持っているのもBtoBならではなので、まずは彼らに1時間ほど話を聞く会議を設定してみましょう。その方がより良いインタビュー前のリサーチクエスチョン、仮説、スクリプトを作成できます。
インタビューを成功させる具体的Tips
オンライン・オフラインの使い分け
オンライン会議ツールであれば地理的な制約を超えて効率的に実施可能。一方で、大手企業やキーマンの場合は対面訪問でヒアリングしたほうが雑談や深い背景が引き出しやすいことも。
企業文化や相手のスケジュールに応じて柔軟に判断してください。
インセンティブ・謝礼の設計
個人へのギフト券等が受け取りにくいBtoBの場合、「試験利用の延長」「サポート優遇枠」など、企業としてメリットを感じやすい提案が効果的。ただし、CSや営業が良い関係を気づけていれば商談の最後の20分を謝礼なしでインタビューに当てさせていただく、なども可能なケースが多いです。
相手企業のコンプライアンス規定に配慮しながら設定を行いましょう。
ただし、既存顧客の場合は特に、「インタビューで聞いた情報をもとにプロダクトを劇的に価値あるものにする」ことこそが最大のお返しである、ということを忘れないようにしましょう。
NDA・契約面の壁を最小化
競合比較や内部資料の提示が必要なら事前にインタビューガイドや質問項目を共有し、法務部からOKを取っておくと当日踏み込んだ質問がしやすくなります。
曖昧なままインタビューを実施すると「それは話せない」と断られてしまうことが多いので、準備段階で壁を取り除いておくのが重要です。
新機能検証でのプロトタイプ活用
BtoBプロダクトの開発は導入サイクルが長く、ユーザーの要望を早期に確認しづらい面があります。プロトタイプを使ったユーザーインタビューを積極的に導入することで、意思決定者にはROIや管理画面の全体像、現場利用者には具体的なUI/UXを別々に提示。
これにより両者の視点をそれぞれ正しく把握し、新機能の方向性を早期にすり合わせられます。
「導入担当 × 現場利用者」のギャップを可視化する
HRテックなどでは、人事部(導入担当)が「効率化と可視化」を最重視する一方、現場は「入力が面倒」「習熟コストが高い」と感じている例が多々あります。
別々にインタビューし、それぞれの声を一覧化してから突き合わせることで、導入担当と現場利用者のギャップを明確化。共通認識をもとに優先度や仕様を決定するフローが理想的です。
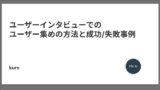
プロダクトマネージャー × 営業 × CSの「共通言語」作り
インタビューや日常対応を通じて得た「顧客の声」は、PM・営業・CSそれぞれの立場で微妙にニュアンスが異なることが多いです。ここではそれらを合意形成するための仕組みと会議設計を紹介します。
なぜ意見が合わない?
- PM視点: プロダクト全体の価値や中長期戦略を考え、機能要望を優先度付け
- 営業視点: 受注確度を上げるために、今まさに商談中の顧客ニーズを優先しがち
- CS視点: サポート窓口として、現場利用者が苦労している部分や問い合わせコストの大きい部分を重視
これらの優先度は当然異なってきます。そこで必要になるのが、「顧客課題の優先度」をみんなで合意できる共通言語です。
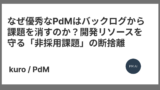
各部署の「顧客との接点」から得られる声をどう集約するか
まず、PM・営業・CSのそれぞれが「顧客とのどんな接点を持ち、どんな情報を得ているのか」をオープンにします。
たとえば下記のようなマッピングが考えられます。
- PM: ユーザーインタビューや業界調査、プロトタイプ検証から得た定性的・定量的なインサイト
- 営業: 商談中の課題・要望リスト、失注理由、商談成立率に影響する機能要件
- CS: 日々のサポート問い合わせ内容、対応工数の多いトラブル情報
これらを一元的に管理できるシートやデータベースを用意し、毎週または隔週の定例会議でアップデートする仕組みを作ると効果的です。

評価指標の可視化
- 顧客満足度(NPS、CSATなど)
特定機能への満足度を調査し、改善要望が多い機能がどこかを定量的に把握 - 商談成立率や失注理由
営業が商談中にヒアリングした「この機能があれば導入したのに」といった理由/背景を可視化 - サポート対応コスト
CSが負担しているサポート問い合わせ数・工数を見える化し、どの機能や課題がボトルネックになっているか把握
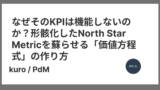
このように、各部署が持つデータを指標化すると、主観的な「要望が多い」「対応がきつい」から脱却しやすくなります。
決定プロセスを透明化する会議アジェンダ例
以下のようなアジェンダを設定し、PM・営業・CSが共通言語をもって議論すると建設的な合意が取りやすくなります。
- 前回までの取り組み・指標のアップデート
– NPSやサポート問い合わせ数、商談成立率の変動を確認 - 新たに出てきた顧客の声
– ユーザーインタビュー、商談で拾った要望やクレームを共有 - 優先度付けの再評価
– 重要度(事業インパクト、顧客規模など)と緊急度(トラブル度合い、売上影響など)をもとに機能要望や課題を並び替え - アクションプランと担当割り振り
– PMが仕様設計を担当し、営業やCSが顧客フォローするなど、具体的な責任分担を決める
こうした会議体を定期的に回すことで、「自分の部署の意見がないがしろにされている」という不満を減らしながら、意思決定のプロセスを透明化できます。

インタビュー実施後の分析と社内共有
インタビューは実施がゴールではなく、その知見をどうプロダクトや経営判断に活かすかが最も大切です。
- 文字起こし > 要点整理
録音/録画データから速やかに文字起こしを行い、重要な発言をピックアップ。
ChatGPTなどの生成AIを使えば、タグ付けやクラスタリングを効率化できます。 - 定性分析フレームワーク
KJ法やグラウンデッド・セオリーなどを用い、各インタビューから共通点や傾向を抽出。
具体的な顧客の声を引用しながらまとめると、意思決定者を説得しやすくなります。 - 社内プレゼン・レポート
経営層や他部署に共有する際には、ユーザーインタビュー結果の見せ方が鍵。
グラフやチャート、具体的エピソードを示しながらROIや事業インパクトを明確にすることで合意が得やすいです。
「グランデッド・セオリー・アプローチでユーザーインタビューからインサイトを掘り起こす」

成功事例と失敗事例イメージ
- 【成功事例】人事評価システム導入プロジェクト
-
- 導入担当(人事部長)へのインタビューで「評価プロセス可視化」「管理工数削減」が最重要課題と判明
- 現場利用者(マネージャーや従業員)への別インタビューで「入力負荷軽減」「スマホ対応」の要望が浮上
- 両者の期待を一元化し、プロトタイプで検証。UIはモバイル重視、人事部長には集計ダッシュボードを提示
- PM・営業・CSが定例会を開いて優先度を調整しながら仕様を確定。導入後の定着率と満足度が大幅アップ
- 【失敗事例】会計ソフトの機能追加
-
- 経営層だけにインタビューを行い、「コスト削減」「業務スピードアップ」に注目
- 現場の経理担当者の声を拾わずに機能を実装。結果、「ワークフローが複雑すぎる」と苦情続出
- 結局新機能は使われず、手戻り開発が発生。顧客満足度と社内評価が下がる悪循環に
まとめ
BtoBのユーザーインタビューは、多様なステークホルダーや長期的な導入サイクルがゆえに難易度が高め。しかし、しっかり設計し、PM・営業・CSが共通言語を持って情報を集約・分析すれば、非常に深いインサイトが得られます。特に、導入担当と現場利用者のギャップを明確にしたうえでプロトタイプを使い、効果的に検証を回すことがポイント。
さらに、部門間の合意形成のために会議体を整備し、決定プロセスを可視化することで、組織全体で納得感を持ったプロダクト開発を推進できます。
今日から実践できるアクション
- ステークホルダーリストの作成: 経営層、導入担当、現場利用者など、顧客企業内の登場人物を整理
- NDAや質問ガイドの準備: 法務や購買部門に相談し、当日の会話を制限しないための下準備
- セールス/CSとの事前すり合わせ: インタビュー目的を明確化し、商談と混在しないルールを共有
- プロトタイプの準備: ローファイでも良いので、導入担当向けと現場向けで見せるポイントを分ける
- 会議体の設計: PM・営業・CSが週次や隔週で集まり、顧客課題の優先度を合意する枠組みを作る
Q&A
- Q. インタビューを一括で済ませたいのですが、やはり意思決定者と現場利用者は分けるべき?
- A. 可能な限り分けるのがおすすめ。導入担当の前では現場が本音を言いにくいケースが多いです。両者から得られるインサイトはまったく違う視点なので、丁寧に切り分けましょう。
- Q. 営業チームから「今商談中の機能を優先して欲しい」と言われますが、どう折り合いをつければ?
- A. 週次・隔週の会議体で「商談規模」「サポートコスト」「プロダクト戦略」など、定量・定性指標をもとに議論を。データに基づく優先度づけができれば感情論を回避しやすくなります。あとは、その営業から、「その機能が欲しい背景/顧客の実現したいことは何か?」「それはどのくらいの人が欲しいと言っているか?」を忘れずにキャッチアップしましょう。
- Q. プロトタイプは完成度が低い段階でも見せるべき?
- A. はい、早めに見せてフィードバックを得るメリットは大きいです。ただし、理解不足で誤解を与えないよう、あらかじめ「検証目的の試作品であること」「リリースされることは確約されていない」ことを強調してください。
参考情報
- (※1)Gartner, “B2B Buying Journey Complexity” (2023)
- CEB(現Gartner)の調査(2015):「BtoB購買プロセスに関わるステークホルダー数」
- Harvard Business Review: “The B2B Elements of Value”, 2018
- 【要約】『The Mom Test』 ユーザーインタビューの「本当の声」を引き出す秘訣
- Rob Fitzpatrick著『The Mom Test: How to Talk to Customers & Learn If Your Business is a Good Idea When Everyone is Lying to You』
- 経営層・上司・メンバーを動かすユーザーインタビュー結果の見せ方・使い方
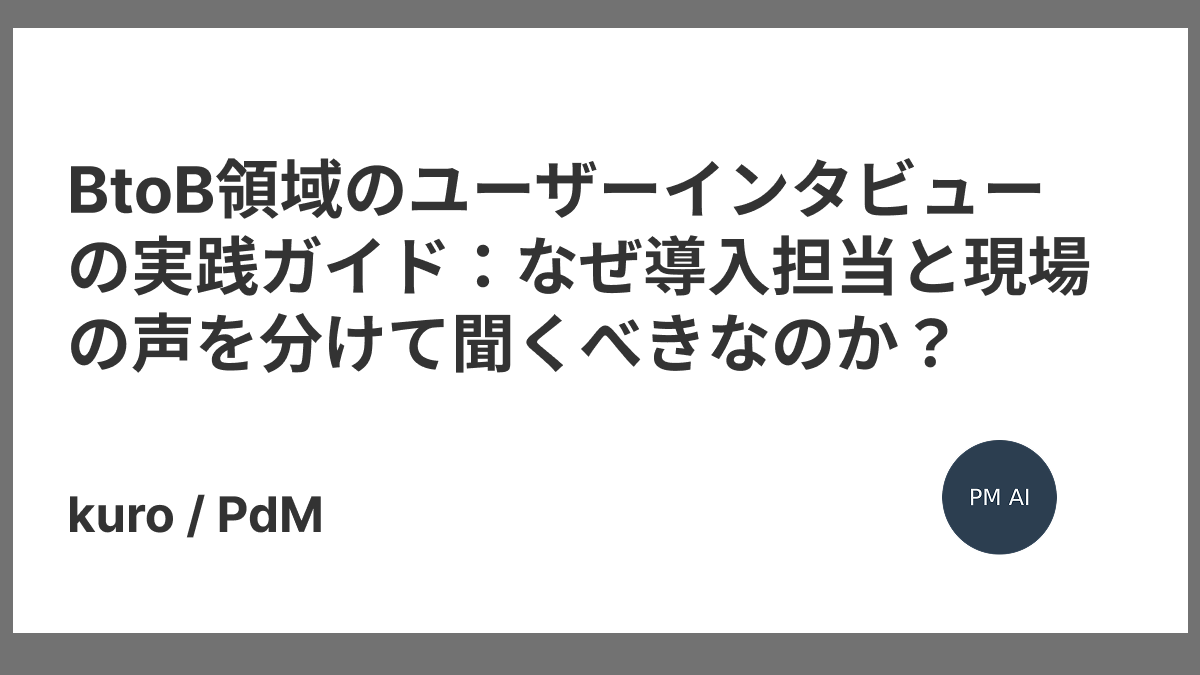
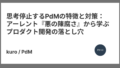
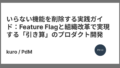
コメント