この記事の3行要約
- 箇条書きの要求リストでは、ユーザー体験の全体像と各機能の文脈を正しく捉えることはできない。
- プロダクトマッピングを行うことで、ユーザーの行動(横軸)とプロダクトの機能(縦軸)を二次元で可視化し、チームの視点を「木を見て森も見る」状態へと引き上げる。
- プロダクトマッピングという「共通の地図」をチームで持つことで初めて、建設的な議論や納得感のある優先順位付けが可能になる。
「リリースから時間が経って複雑化したプロダクトで、どの機能がどのようなユーザーニーズを満たし、どの課題を解決するのかが分かりにくくなってしまった…..」
こういった状態を放置すると開発の優先度が曖昧になり、ひいては不要機能の増加や重要度の高い機能の不十分な強化につながりますよね。
そうした課題を解消する手段の一つが「プロダクト構成要素マッピング」。プロダクト内の各機能を一覧化し、対応するユーザーニーズやユースケースと合わせて可視化することで、機能間の関連やカバー範囲を一望できるようになります。
機能一覧 × ユーザーニーズ × ユースケースでマッピング
まず、マッピングを作成する際に押さえておきたいのが「機能一覧」「ユーザーニーズ(課題)」「ユースケース」の三つ。具体的には以下の流れを踏みます。
ステップ1:機能の洗い出し
既存機能と検討中の新機能を網羅的にリストアップ。あらためてプロダクト内で何が可能で、何ができないのかを再確認する段階です。
ステップ2:ユーザーニーズの整理
ユーザーインタビューやアンケート結果、サポート窓口への問い合わせ内容などから、本質的なニーズや課題を抽出する。インタビューの設計・やり方については、こちらの記事も参考にしてください。
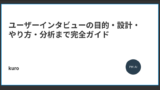
ステップ3:ユースケースの具体化
ユーザーニーズや課題が「どのような文脈」や「どのような場面」で発生するのかを具体的に想定する。社内で認識にズレがあると開発効率も落ちるため、場面と行動を一旦細かく書き出してから絞るのがポイントです。
ステップ4:三つの要素を紐づける
各機能が「どのユーザーニーズ」に対応し、「どんなユースケース」で利用されるかをマッピング表にまとめる。ここで機能間の重複や抜け漏れが自然と浮き彫りになります。
このステップを丁寧に行うだけで、不要機能の洗い出しや不足している領域の発見がしやすくなります。検討中の新機能が既存機能とどのように連携するのかを見極めやすいため、リソース配分にも役立ちます。
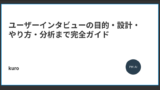
使用場面と解決すべき課題をインタビューで確認
マッピング作業を行ううえで鍵を握るのが、どのようなインタビュー情報を集めるかです。表面的に「この機能がいい」「あの機能は微妙」と評価をもらうだけでは、マップを充実させるだけの深い知見を得られません。
重要なのは「その機能を使う具体的な場面」と「どの課題を解決しようとしているか」を詳細に把握すること。
たとえばスケジュール管理機能であれば、「会議調整が頻繁にあるがツールがバラバラで混乱している」という課題を解決しているのか、「顧客とのやりとりを効率化したい」という課題を解決しているのかで、アプローチの仕方は変わりますよね。
ユーザーインタビューでは、抽象的に「便利」「使いにくい」と聞くのではなく、実際の利用シーンを深堀りします。
- どんなタイミングでこの機能を使うのか?
- その前後で何をしているのか?
- その機能がない場合どう対処していたのか?
こういった質問を繰り返すことで各機能が担っている役割を明確化できます。具体的な質問項目については、「ユーザーインタビューの質問項目大全」も参考にしてください。

また、データで見るときには以下の観点を見てみましょう。
- どれくらい使われているか?:利用頻度・回数・滞在時間
- どんな人に使われているか?:セグ別の利用頻度・回数・滞在時間
- どんなときに使われているか?:時系列昇順で並べた個別ログ、利用時間
- KPIに寄与する機能か?:機能利用頻度ごとのKPI action数や率
- どれくらい満足されているか?:取得しているならNPSなど
運用のコツ:マップを見ながらロードマップと連動させる
作成したマップは、単なるドキュメントではなくロードマップ策定や組織内での情報共有に積極的に使うのがおすすめ。
特に新機能を企画する際、既存機能や既存課題との関連性をマップ上で可視化すると以下を即座把握できます。
- この機能を追加するとどこに影響が及ぶのか?
- 今開発中の機能とターゲットがかぶらないか?
これにより、「実は似たような課題を解決する機能がすでにあるのでは?」といった気づきが得やすく、開発の優先度を見直す機会にもなります。
さらに、ユーザーインタビューの新しい知見が得られたときは、その都度マッピングにも反映し、アップデートを継続することが大切です。継続的にインタビューを行う方は、「リサーチデータベースを構築する」手段を導入して、チーム内での知見共有をスムーズにする取り組みも有効です。

参考情報
顧客に愛されるプロダクトを生むための考え方や組織運営が紹介されています。
『Running Lean』 (Ash Maurya 著) – ユーザーインタビューや実験を通じて最小限の機能に絞り込むプロセスが体系立てて解説されています。
- Harvard Business Review “How to Map Your Industry’s Profit Pools.” (2018) – 業界分析の枠組みをマッピングのアプローチとして活用する事例。
- IEEE Xplore (Academic Papers on Software Requirement Engineering) – 大規模なソフトウェア開発で要件や機能を可視化する意義に関する研究が蓄積されています。
今日から実践できるアクション
1. 機能一覧の作成
まずは現在提供している機能をすべてリストアップし、インターナル用のWikiやスプレッドシートに整理します。その際、隣のカラムに機能の「目的」や「想定ユーザー層」を書き込むだけでも違います。
2. インタビュー項目の見直し
次回のユーザーインタビューでは、「どんな場面で使っているか」「その時の代替手段は何か」を必ず聞くようにしましょう。こちらの記事「ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド」も参考になるはずです。
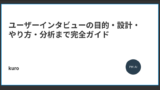
3. マッピングの試作と共有
簡易なマップを作って社内で共有し、意見を募る。デザインツールでも、ホワイトボードでも、マインドマップでも構いません。人によって機能の理解や捉え方が異なることを認識するのが第一歩です。
Q&A
Q1. マッピング作業に時間がかかりすぎるのでは?
A1. たしかに初回の作成には一定の時間がかかりますが、プロダクトの方向性を中長期的にブレさせないための重要な投資です。何より、マッピングから得られる「不要機能の早期発見」「機能開発の優先度の明確化」などのメリットは大きいです。
Q2. インタビューで全ユーザーニーズを網羅しきれない気がします
A2. すべてのニーズを完全に洗い出すのは難しいですが、代表的なペルソナや主要顧客層のユースケースをしっかり把握するだけでも効果はあります。継続的にインタビューや定量データを組み合わせて、マップをアップデートしていく運用が大切です。
Q3. 新機能を追加してはマッピングを更新するのが面倒です
A3. マッピングは“生もの”です。定期的に更新することで意味を持ちます。更新フロー自体を開発プロセスに組み込めば、面倒ではなく「当たり前のプロセス」に変わります。リリース前にサッと確認し、必要に応じて更新する習慣づけを目指しましょう。
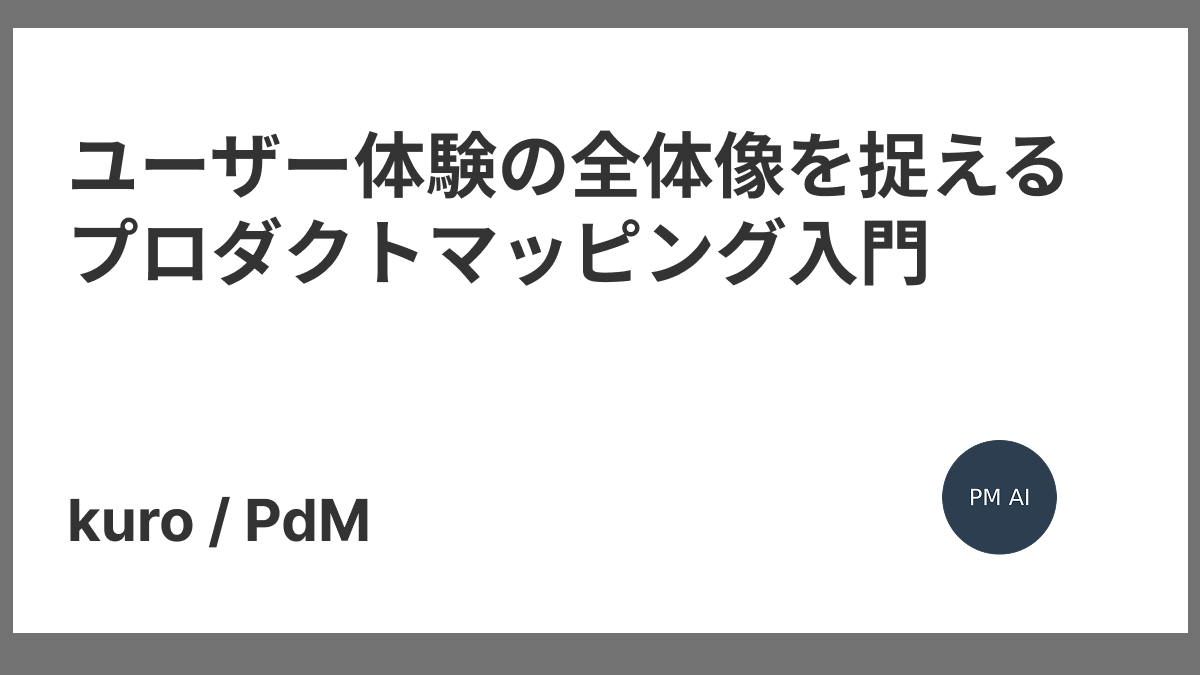


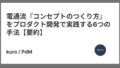

コメント