この記事の要約
- 最新の調査・研究から見る「初回オンボーディング」の重要性や成功事例を紹介
- NetflixやDuolingo、Notionなど実際のサービスの取り組み
- 押さえておきたい5つのHowを紹介
本記事では、toCサービスにおいて「最初のセッション」でユーザーを一気に惹きつけるためのノウハウをまとめます。研究データや業界事例を取り入れながら、オンボーディングで押さえるべきポイントを紹介します。
なぜ“初回オンボーディング”がそんなに重要なのか
toCサービスでは、新規インストールや初回登録をしてくれたユーザーの大半が、初日や初週にサービスを離脱してしまうといわれています。オンボーディング(初回体験のデザイン)を適切に行わないと、せっかく広告費をかけて集客したユーザーを無駄にしてしまう可能性も。
調査:2019年のLocalyticsレポートでは、モバイルアプリの21%がインストール後一度しか起動されないと報告しています。たとえアプリを起動しても最初の数分で価値を感じられないと判断したら、ユーザーは一瞬で離れていく時代と言えます。
また、別のUXリサーチ企業が2022年に実施した調査では、「初回登録フォームが長い」「説明やチュートリアルが冗長すぎる」という理由で、初回セッション中に4割以上のユーザーが離脱する結果が出ています。これは「最初につまづいたらとりあえず閉じる」という今の消費者行動を表しているとも言えます。
だからこそ、初回オンボーディングでいかに短時間かつ明確に価値を伝え、継続利用のモチベーションを芽生えさせるかが非常に重要になります。
【研究・事例から学ぶ】初回オンボーディング成功のカギ
ここでは、世界的に成功しているtoCサービスがどのようにオンボーディングを設計しているのか、具体例を元に解説します。
1. Duolingo:体験先行アプローチと目標設定による継続率向上
語学学習アプリのDuolingoは、初回セッションにおいて「体験先行型」のフローを採用しています。ユーザー登録を後回しにし、まずは短いクイズで“学習の楽しさ”を実感させる設計。これによって「登録が面倒だからやめた」という離脱を防ぎつつ、ユーザーに小さな成功体験を与えることに成功しています。
さらに、Duolingoはオンボーディングの中でユーザーに学習目標を設定させる工夫も加えています。たとえば「1日10分を目安に進めたい」「旅行のために基礎だけ覚えたい」など。こうした自己設定の目標は、心理学的にユーザーのモチベーションを高める作用があります(自己決定理論)。2022年のIPO関連資料で同社は、こうしたオンボーディング施策がD1(翌日)リテンションや月間アクティブ率の向上に寄与したと発表しています。
より詳しいDuolingoの仕組みは、「Duolingoに学ぶユーザーリテンション8つの心理トリガー」も参考にしてください。
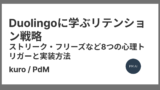
2. Netflix:登録フロー最適化×最初からパーソナライズ
動画配信サービスのNetflixは、新規登録時のステップ数をきわめてシンプルに設計しています。多くの場合、「メールアドレス入力 → プラン選択 → 支払い情報入力」の3ステップ程度で完了。その後、最初のプロフィール設定で“好きな映画ジャンル”を数個選ばせるだけで、いきなりホーム画面がパーソナライズされた状態になる仕組みです。
この「パーソナライズ」(ユーザーに合わせて内容を最適化すること)は、初回セッションで「興味のある作品がちゃんと並んでいる!」という期待感を生むため、離脱防止に効果的。Netflixはコンテンツ数が膨大な分、ユーザーが迷いがちな課題を、“最初に好みを聞いてホーム画面を最適化する”ことで解決しています。
さらに、余計なチュートリアルをほとんど表示しない点も特徴。「サービスを触ってみたい」というユーザー心理を優先し、スクロールや視聴の動線を妨げないよう配慮しているのです。
3. Notion:目的に応じて分岐するテンプレートとスモールチュートリアル
多機能なコラボレーションツールとして知られるNotionは、初回オンボーディングにおいて「利用目的やチーム規模」をヒアリングし、最初から適切なテンプレートを提示します。個人利用なら簡単なToDoリストや日記、チーム利用ならプロジェクト管理やナレッジ共有のテンプレがあらかじめ用意されている。
このおかげでユーザーは「ゼロから設計しなきゃいけない…」というハードルを感じずに済むため、登録後すぐ使い始めやすいです。Notionはユーザーがチュートリアルをすっ飛ばしたくなる気持ちを前提として、随所に“必要な時にだけ表示される”ヘルプやツールチップを実装し、冗長な説明でユーザーを離脱させない工夫をしています。
押さえておきたい5つの視点:最新ナレッジを踏まえて
ここまで挙げた事例に加えて、研究や業界レポートで強調されているポイントを5つにまとめます。
- 摩擦を最小限にする
- 「アハ!体験」をすぐ得られる導線
- ユーザー自身が目的を設定
- パーソナライズとコンテキスト対応
- データを見ながら継続改善する仕組み
1. 摩擦を最小限にする
「摩擦」(フリクション)とは、ユーザーが操作や入力を面倒に感じるポイントを指す言葉です。長い登録フォームや複雑なチュートリアルが典型例。
最新のUXリサーチでは、入力項目が1つ増えるたびに新規離脱率が上がる傾向が報告されています。どんなに優れたサービスでも、そこに至るまでにユーザーをウンザリさせたら終わり。
だからこそ「サインアップ後回し」や「SNSアカウント連携1クリックで完了できる」など、ハードルを下げる施策は依然有効とされています。実際、あるサービスでは初回登録フローを1/3に圧縮しただけでD1リテンションが約15%改善したとの事例も報告されました。
2. 「アハ!体験」をすぐ得られる導線
先述のDuolingoやNotionにも共通していますが、「ユーザーが小さな成功を感じる」までの導線をなるべく短くすることが鍵。これを「アハ体験」(aha moment)と呼ぶ場合もあります。
たとえば「ノートアプリなら、メモを1回入力して整理できるだけで“便利!”と感じられる」「語学アプリならクイズを少し解いて単語を覚えられる」など。ユーザーがワクワクや満足感を得られるシーンを初回セッション内に確実に仕込むのが理想です。
3. ユーザー自身が目的を設定
“あなたは何を成し遂げたいですか?”という問いを投げかけ、ユーザーにゴールを明確化させるアプローチは、近年多くのtoCサービスで導入されています。
2022年のMobile UX関連の学術研究でも、ユーザーが初回に自分の目標を設定すると継続率が向上するとの結果が示されています。特に学習アプリ、ヘルスケアアプリなど目的指向のサービスでは顕著です。PdMとしては、オンボーディング時に2〜3問の簡単な質問や選択項目を用意し、「ここで目的を決めるとサービス活用がもっと楽になりますよ」と促す施策を検討してみる価値があります。
4. パーソナライズとコンテキスト対応
Netflixのように、初回にユーザーが選んだ好みに基づいてコンテンツや画面を変える。Notionのように、目的(個人用か、チームか)に応じたテンプレートを自動表示する。
こうした「コンテキスト(利用状況)」や「ユーザーの興味・関心」をオンボーディング中からヒアリングし、その結果を即座に反映するパーソナライズが定着率を押し上げる、と多くのレポートが指摘しています。
パーソナライズといっても、最初から高度な機械学習を搭載しなければならないわけではありません。「好きなジャンルを3つ教えてください」というフォームを作って、その場でおすすめを出す程度でもユーザーの満足度は上がるので、まずはシンプルに始めてみるのが良いです。
5. データを見ながら継続改善する仕組み
オンボーディングは完成したら終わりではなく、常にユーザーの動きやフィードバックを観察しながら改善を重ねる姿勢が欠かせません。特にtoCサービスでは、ユーザー数が多い分、ファネル分析やA/Bテストを行いやすい強みがあります。
フォームの項目を1つ削るだけで何%改善するか、チュートリアルをスキップできるようにしたらどう変化するか、といった実験を積み重ねる。成功事例のほとんどが、この「継続的なテストと改善」を繰り返しています。
ちなみに僕の場合も、リリース直後の新機能オンボーディングを毎週A/Bテストし、ユーザーインタビューとログ分析を組み合わせて最適化したことがあります。興味があれば、「ログ分析→ユーザーインタビューの流れで、『本当に解くべき課題』を明確にする」もぜひご覧ください。
よくある失敗パターンと回避策
オンボーディングを設計する上で、注意しておきたい典型的な失敗パターンがあります。以下、いくつか紹介します。
- 入力項目の前倒し(Frontloading)
初回に必要以上の情報を集めようとしすぎる。フォームが長すぎて離脱される原因になるため、最低限の項目に絞り、不要なものは後から別途聞く工夫が大切です。 - ポップアップ地獄(Over-guidance)
チュートリアルや説明ポップアップを大量に出してしまう。ユーザーは早く触りたいのに邪魔と感じる場合が多いです。必要な情報を最適なタイミングだけ表示するよう工夫すること。 - 一方通行の教示(Lack of Interaction)
マニュアルを読むだけ、説明を聞くだけの受動体験は飽きられます。ユーザーが触って理解できるよう、インタラクティブな体験を通じて学べる導線を設計するのが望ましいです。 - 目的の不一致(Goal Misalignment)
ユーザーが何を求めているか理解しないまま、サービスの使い方だけ一方的に押し付けてしまう。事前にユーザーの用途や目標を把握しないと、的外れなサポートになりがちです。
オンボーディングを支えるユーザーリサーチの活用
実際に、オンボーディングを大幅改善するためには、ユーザーリサーチが欠かせないと僕は考えます。特に「どの画面で離脱が多いのか?」「最初にユーザーが躓くポイントはどこか?」を知るために、定量分析と定性調査を合わせて行うのが効果的です。
具体的には、ログ分析やコホート分析で「初回起動後、何ステップ目で何%のユーザーが離脱しているか」を把握し、その原因仮説をユーザーインタビューで検証する流れが代表的なアプローチになります。
参考としては、ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイドや、オンボーディングの「最初の数分の体験」をぶち上げるためのユーザーリサーチなどが役立つはずです。
僕も実務で、試作したオンボーディングをユーザーに触ってもらい「どこで混乱したか?」「この登録ステップは面倒に感じないか?」など細かくインタビューして、改善サイクルを回してきました。特にtoCサービスはユーザー母数が多いので、A/Bテストだけに頼りたくなるところですが、インタビューを併用すると具体的な不満点が明確になるのでかなりおすすめです。
【今日から実践できるアクション】
- 1. フォーム削減とサインアップ後回しを検討
現在の登録ステップを棚卸しし、本当に必要な項目だけに絞ります。可能ならアプリやWebを「体験優先」で触ってもらい、後から登録を促す流れを実装する。 - 2. 初回に小さな成功体験をデザイン
「メモを残す」「クイズを解く」「お気に入りに1つ保存してもらう」など、ユーザーが素早く達成感を得られる操作をガイドする。 - 3. ユーザーの目的を尋ねる仕組みを作る
オンボーディング中に2、3問の質問を入れ、なぜこのサービスを使いたいのかを簡単に聞く。その回答を元に画面やコンテンツを変えることで、パーソナライズ感を演出する。 - 4. チュートリアルは最小限&タイミング重視
いきなり全説明を詰め込むのではなく、必要な時に必要なチップやヘルプだけを表示。長々とした説明ポップアップは避ける。 - 5. データ+インタビューで継続的に改善
ファネル分析やコホート分析で離脱ポイントを把握し、ユーザーインタビューを実施して理由を深掘り。改善施策を検討し、ABテストで検証する。
【Q&A】
- Q1. オンボーディングが終わった後のフォローは必要ですか?
- A. 必要です。初回体験で「使えそう」と思っても、日常に組み込めるかは別問題。プッシュ通知やメールでリマインドしたり、翌日以降の再訪を促す仕掛けが大切です。ヘルスケアや学習系アプリは「ストリーク表示」や「ポイント付与」など継続を促す機能をオンボーディングの一環として設置することが多いです。
- Q2. BtoBサービスでも同じ考え方が通用しますか?
- A. 概ね通用しますが、toBの場合は組織内の権限や導入担当者が誰なのかなど別の要因が絡むため、一部要素が変わります。ただし「最初の数分でユーザーに価値を感じてもらう」「最初に目的を設定してもらう」という考え方は変わりません。詳しくはBtoB特化の記事も参照ください(例: BtoB領域のユーザーインタビューの難しさや実施方法を解説)。
- Q3. ゲーミフィケーションを使うべきでしょうか?
- A. サービス内容とユーザー層に合っていれば有効です。Duolingoのように学習をゲーム化して習慣づけを狙うのは典型例。リテンションが課題のサービスでは、「ゲーミフィケーションをプロダクトに組み込んで『夢中』なファンを生み出す」も参考になります。
参考情報
・Localytics (2019). “Mobile App User Retention — Industry Benchmarks.”
・Duolingo IPO Filing (2021). Securities and Exchange Commission (SEC) Document
・Notion公式ガイド (2022). “Getting Started with Notion for Individuals and Teams.”
・Netflix公式サイト (2023). “How to sign up & get started?”
・複数のUXリサーチ会社が発表した2022年以降の調査レポート(公表データより要約)
・Nir Eyal (2014). 『Hooked: How to Build Habit-Forming Products』
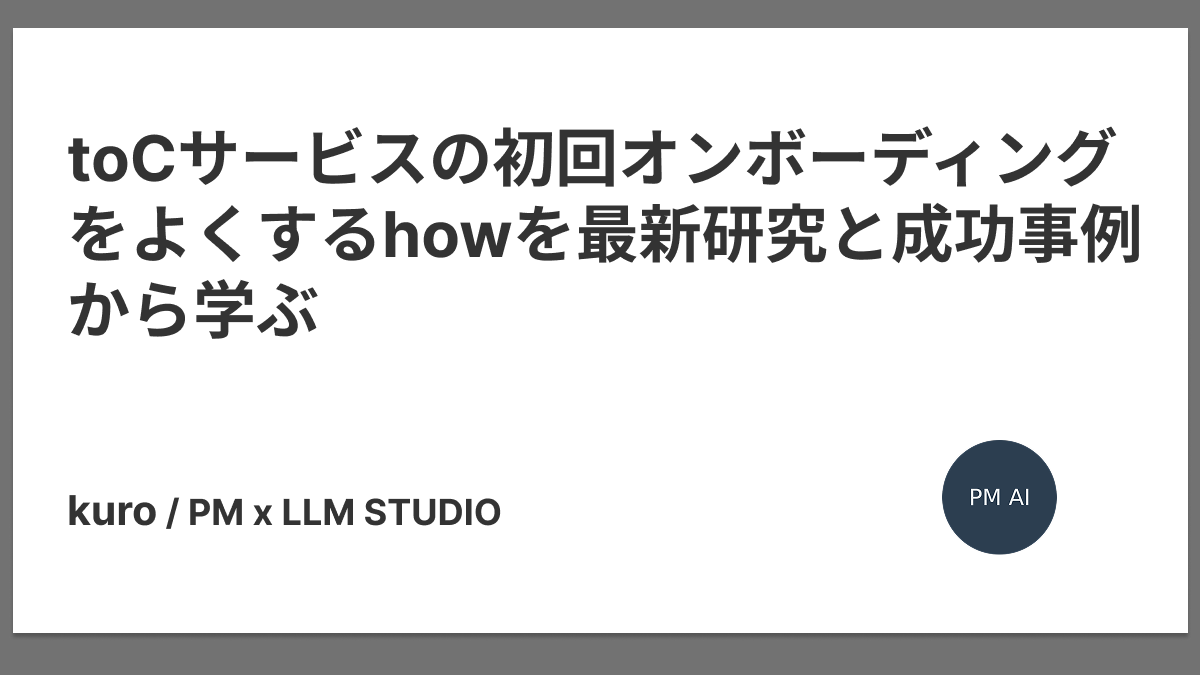
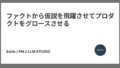

コメント