toCアプリのPdMやマーケターにとって、「リテンション(継続率)」は永遠の課題ですよね。そして、リテンション施策として最も手軽で、最も多用されるのが「プッシュ通知」や「メール」「LINE」といったコミュニケーション施策です。
しかし、こんな経験はありませんか?
- 「新機能リリースのたびに全ユーザーにプッシュ通知を送っているが、リテンションが上がっている気がしない」
- 「セールの告知メールを送れば送るほど、開封率もCTRも下がっていく」
- 「CTRは高いのに、なぜかチャーンレート(離脱率)が改善しない」
この記事は、そうした「とりあえず通知を送る」段階から一歩先に進みたいPdMやマーケターの皆さんに向けて書いています。
この記事の要約
- プッシュ施策のKGI(最重要目標)は「開封率」や「CTR」ではなく、あくまで「リテンションレート」や「LTV」に置くべき
- 「誰に」「いつ」「どのチャネルで」「何を」伝えるかを戦略的に設計し、「通知疲れ」によるチャーンを防ぐオーケストレーション(連携)が鍵となる。
- 施策の真の価値は「送らなかったグループ(CG)」とのA/Bテストで初めて計測可能であり、このプロセスこそが施策を「科学」する第一歩である。
なぜあなたのプッシュ施策は「リテンション」に効かないのか?
多くのプロダクトチームが、プッシュ施策を「リテンション施策」と呼びながら、実際に見ている指標は「開封率」や「CTR(クリック率)」です。
もちろん、これらの指標は重要です。しかし、これらはあくまで中間指標(KPI)に過ぎません。本質的なゴール、つまりKGI(重要目標達成指標)は、「N日後リテンションレートの上昇」や「LTVの最大化」のはずです。
ここに大きな落とし穴があります。
例えば、「【緊急】今だけ50%OFF!」という通知は、高い開封率とCTRを記録するかもしれません。しかし、その結果どうなるでしょう?
- セール時しかアプリを開かないユーザーを量産し、平常時のリテンションはむしろ悪化
- 「またセールか」と通知の価値が下がり、本当に重要な通知(例:サービス利用に関する重要なお知らせ)まで開封されなくなる
- 過度な通知が「通知疲れ(Notification Fatigue)」を生み、アプリの通知許諾自体をオフにされる(最悪の場合、アンインストール)。
これでは本末転倒です。
大事な発想は、プッシュ施策は「点を打つ」作業ではない、ということです。ユーザーの体験全体を俯瞰し「戦略的な線」として設計します。「送ること」と同じくらい「送らないこと」を重視し、すべての施策を「UX(ユーザー体験)の一部」として捉えます。
戦略の起点:「誰の」「どのリテンション」を上げるか?
施策設計の第一歩は、「リテンションを上げたい」という曖昧な目的の解像度を上げることです。
「リテンション」と一口に言っても、その中身は多様です。ここを定義しないまま施策を打つのは、目的の海図を持たずに航海に出るようなもの。まずは戦略の「起点」を明確にしましょう。
1. フェーズの特定:Day1か、Day7か、Day30か?
あなたのプロダクトは、どのフェーズの継続率に課題を持っていますか?
- Day1リテンション(オンボーディング期):
インストール翌日にアプリを開いてくれない状態。課題は明確で、「プロダクトの初回体験(Aha体験)」がうまく伝わっていない可能性が高いです。ここでの施策目的は「オンボーディングの完了」や「コア機能の初回利用」になります。(※オンボーディングについては、toCサービスで良い結果を残した生成AI関連機能を紹介の記事も参考にしてみてください) - Day7リテンション(習慣化期):
使い始めてはくれたが、習慣化に至らず離脱していく状態。目的は「コア機能の反復利用」や「関連機能の発見」を促すことになります。 - Day30リテンション(定着・ロイヤル化期):
一定期間は使ってくれたが、飽きたり、より良い代替手段を見つけたりして離脱する状態。目的は「アップセル・クロスセル(課金転換)」や「新機能の利用促進による再活性化」になります。

Day1リテンションが低いのに、Day30のユーザーに「新機能を使おう!」と通知を送っても、全体のリテンションは改善しません。まずは、プロダクトのコホート分析などを行い、最も改善インパクトが大きいフェーズを見極めることが重要です。

2. セグメントの特定:「全員」ではなく「この人」
次に「誰に」を明確にします。「全ユーザー」というセグメントは、基本的に存在しないと考えてください。それは「誰にも刺さらない」施策の第一歩です。
例えば、以下のように具体的なセグメントに分解します。
- 離脱予備軍: 過去7日間はアクティブだったが、直近3日間起動していないユーザー
- 休眠復帰ユーザー: 30日ぶりにアプリを起動したユーザー
- ロイヤルユーザー: 月5回以上課金し、かつ週3回以上起動するユーザー
- オンボーディング離脱者: プロフィール登録のステップで離脱したユーザー
3. KPIの具体化:その施策で「何」が動けば成功か?
フェーズとセグメントが決まれば、その施策で追いかけるべきKPIは自ずと具体的になります。
戦略起点の具体例
(Before: 曖昧な目的)
「リテンションを上げるために、休眠ユーザーにプッシュ通知を送ろう。KPIは開封率。」
(After: 明確な定義)
「Day7リテンション(習慣化)を改善するため、『オンボーディングの途中で離脱したDay2ユーザー』に対し、『コア機能の初回利用完了率』をKPIとしてプッシュ施策を打つ。」
ここまで解像度を上げて初めて、「じゃあ、何を、いつ、どうやって送る?」という具体的な戦術設計に移ることができます。
セグメンテーションの罠:「属性」から「モーメント」へ
第1章で「誰に」を定義しましたが、ここではその「セグメントの切り方」を深掘りします。
ジュニアなPdMが陥りがちな罠が、「属性」によるセグメンテーションの多用です。「20代女性」「東京都在住」といったデモグラフィック(人口統計学的属性)や、「アクティブユーザー」「非アクティブユーザー」といった粗い分類に頼ってしまう。
もちろん、これらが無意味とは言いません。しかし、リテンションに直結する施策において、より強力なのはユーザーの「行動」であり、特に「モーメント(瞬間)」を捉えたセグメンテーションです。
「属性」ではなく「行動」で切る
「20代女性」という10万人の集団より、「過去7日間にA機能を使ったがB機能は使っていない」という1,000人の方が、B機能の利用を促す通知を送る対象として遥かに適切です。
この「行動ベース・セグメンテーション」を考えるために有益なのがRFM分析(Recency, Frequency, Monetary)。
- Recency (最終利用日): いつ最後に使ったか?(例:昨日 vs 30日前)
- Frequency (利用頻度): どれくらいの頻度で使っているか?(例:毎日 vs 月1回)
- Monetary (課金額): いくら使ったか?(※ECやゲームの場合)
これらを組み合わせることで、「Rが低く(最近来てない)、FもMも高い(かつての優良顧客)」=「最優先で呼び戻すべき休眠ロイヤル層」といった、解像度の高いセグメントが浮かび上がります。
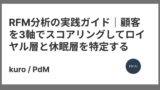
最強のトリガーは「モーメント」
行動ベースをさらに一歩進めると、「モーメント(瞬間)」の捕捉に行き着きます。これは、ユーザーが「今、まさに求めている」あるいは「今、つまずいている」瞬間をトリガーにする設計です。
古典的ですが最も強力な例が、ECアプリの「カート放棄」です。
ユーザーが「商品をカートに入れたが、購入せずにアプリを閉じた」というモーメント。これは、「購入意欲は高いが、何らかの理由(価格、送料、手続きの面倒さ)でためらっている」という明確なシグナルです。このモーメントをトリガーに、「カートに商品が残っています」や「限定クーポン」を送る施策は、全ユーザーにセール告知を送るより遥かに高いCVR(転換率)とリテンション効果が期待できます。
あなたのプロダクトにとっての「カート放棄」=「ユーザーが意図した行動を完了する直前で離脱したモーメント」はどこにあるでしょうか? それを見つけることこそ、PdMの腕の見せ所です。
チャネル最適化(Where/When):プッシュ・メール・LINEの「戦略的オーケストレーション」
さて、ここが本記事で最も実践的なパートです。「誰に」が決まったら、「どこで(Where)」と「いつ(When)」伝えるかを設計します。
ここでの罠は、各チャネルの特性を理解していても、それらを「単発」で使ってしまうこと。
よくある罠:
「これは重要なセール情報だ!確実に届けるために、プッシュ通知も、メールも、LINEも、全ユーザーに、同じ金曜日の19時に一斉送信しよう!」
結果は悲惨なことになるでしょう。ユーザーは3つのデバイスから同時に同じ通知を受け取り、「しつこい!」と感じます。そして、回復が最も困難な「通知許諾オフ」や「LINEブロック」を引き起こす。これはリテンション施策として最悪の手です。
リテンション設計に長けたPdMは、チャネルを「点」ではなく「線」で捉えます。ユーザーの状況やプロダクトとの関係性に応じて、各チャネルの役割を定義し、最適な順序とタイミングで「連携」させる——すなわち「戦略的オーケストレーション」を設計します。
1. 「チャネル・マトリクス」の再定義
まずは各チャネルの役割を明確に定義し直しましょう。例えば以下のような形です。
| チャネル | 役割(強み) | 最適シナリオ | リスク(弱み) |
|---|---|---|---|
| プッシュ通知 | 即時性 / 行動トリガー | タイムセール、リマインド、カート放棄(直後) | 最も「邪魔」になりやすく、許諾オフのハードルが低い。 |
| Eメール | 情報量 / 非同期 / 資産性 | 週次レポート、お役立ちコンテンツ、購入履歴レコメンド | 開封率が低い。迷惑メール判定リスク。 |
| LINE | 親密性 / 高開封率 | 限定クーポン配布、ファン化コミュニケーション | ブロックリスク最大。配信コストが高い。 |
| アプリ内通知 | 文脈依存 / ガイダンス | 新機能のオンボーディング、アップセル提案 | アプリを開かないと届かない。UXの阻害リスク。 |
2. シナリオ別オーケストレーション
さて、それぞれのチャネルをどう組み合わせたら良いのでしょうか?
シナリオA:オンボーディング完了促進(目標:Day7リテンション改善)
よくある罠:
未完了ユーザー全員に毎日「チュートリアルを完了しよう!」とプッシュを連打し、即通知オフされる。
解決のための戦略:
- Day1(アプリ利用中): 「アプリ内通知」で、ユーザーが次に行うべきアクション(例:プロフィール登録)をピンポイントでガイダンスする。
- Day2(未完了者へ): 「プッシュ通知」で「あと1ステップで【特典XXX】をゲット!」と、完了のベネフィットを簡潔に訴求する。
- Day3(それでも未完了): 「Eメール」で「(完了したユーザーの)活用事例紹介」や「この機能の隠れたメリット」を送り、プロダクトの価値をじっくり啓蒙する。
シナリオB:カート放棄(目標:CVR改善と離脱防止)
よくある罠:
カート放棄直後にプッシュ、メール、LINE全てで「お買い忘れがあります!」と通知し、ユーザーを怯ませる(ストーキング的と捉えられる)。
解決のための戦略:
- 1時間後: 「プッシュ通知」で「カートに商品が残っています」とライトにリマインド。
- 24時間後(プッシュ未反応/未購入の場合): 「Eメール」で「カート内の商品」を画像付きで表示し、関連商品や「閲覧履歴」もレコメンドする(情報量)。
- 3日後(購入なし/LINE連携済): 「LINE」で「カート内商品に使える【限定クーポン】」を提供し、最後のひと押し(インセンティブ)をする。
シナリオC:休眠復帰(目標:休眠ユーザーの呼び戻し)
よくある罠:
30日以上未起動のユーザー全員に「新機能が出ました!」と一斉プッシュを送り、誰にも響かず無視される。
解決のための戦略:
(まず、離脱直前のアクションに基づきセグメント化する)
- 「A機能のヘビーユーザーだった」層へ: 「Eメール」で「A機能があなたのフィードバックを元にこんなに進化しました」と、ピンポイントな価値を(情報量多く)訴求する。
- 「セール時のみ利用」層へ: 「プッシュ通知」で「まもなく【大型セール】が始まります」と、再訪の明確な「きっかけ」を作る。
- 「クーポン利用率が高い」層へ: 「LINE」で「あなただけの【特別復帰クーポン】が届いています」と、高い開封率で確実にインセンティブを届ける。
3. 「When」の解像度:タイミングと頻度の科学
「いつ」送るか?の設計で、細かいですがここで差がつきます。
- タイミング(Send Time Optimization):
「全員一律の19時」という発想を捨てます。過去の行動データ(アプリ起動時間、購買時間)に基づき、ユーザーごとに最も受容的な時間帯を狙う(多くのMAツールがこの機能を持っています)。あるいは、「カート放棄直後」のような行動トリガー(リアルタイム)が最強です。 - 頻度(Frequency Capping):
「うるさい」と思われないための上限設定は、リテンション施策の「守りの要」です。「プッシュは1日2回まで」「セール告知メールは週1回まで」など、チャネルごと・目的ごとに明確なルール(上限)を設計しましょう。
そして重要なのは、プロダクト設計の話になりますが、ユーザー自身が通知カテゴリを「選択・制御できる」設定画面(オプトイン/オプトアウト)をプロダクト内に実装することです。これは、ユーザーの「自律感」を守るために不可欠です(詳しくはユーザーの“自律感”を守るプッシュ通知を設計して、リテンションを高めるの記事でも触れています)。
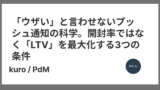
「何を(What)」伝えるか:CTRの呪縛から「価値提案」へ
「誰に」「いつ」「どこで」が決まったら、いよいよ「何を」伝えるかです。
ここでも「CTRの呪縛」があります。「開封率」や「CTR」だけを追うと、センセーショナルだが価値のない「釣り通知」になりがちです。ユーザーはクリックするかもしれませんが、「クリックして損した」と感じた瞬間に、あなたのプロダクトへの信頼は失墜します。
重要なのは、ユーザーが「開いてよかった」と感じるための「価値提案(Value Proposition)」です。
1. 価値提案(Value Proposition)の明確化
その通知は、ユーザーに何の価値を提供しますか?
- お得(割引): 「あなたへ限定オファー」
- 利便性(リマインド): 「予約時間が近づいています」
- 新奇性(新機能): 「あの機能がこんなに便利に」
- 自己実現(学習完了): 「7日間連続学習を達成!」
- 社会的つながり(承認): 「あなたの投稿に『いいね!』がつきました」
例えば、語学学習アプリのDuolingoは、「連続記録」という自己実現(と損失回避)をトリガーにした通知設計が非常に巧みです(Duolingoに学ぶユーザーリテンション8つの心理トリガーでも詳しく解説しています)。
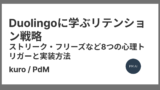
2. 行動経済学の応用
メッセージングは、ナッジ(行動経済学)の宝庫です。同じ内容でも、伝え方一つで行動は大きく変わります。
- 損失回避: 「50%お得」より「【本日終了】50%OFFのチャンスを逃さないで」
- 希少性: 「セール中です」より「閲覧した商品が【残り3点】です」
- 保有効果: 「クーポン配布中」より「【あなただけ】の特別クーポンが届いています」
ただし、これらのテクニックは諸刃の剣です。過度に使用するとユーザーは「また煽っている」と学習し、効果が薄れるだけでなく、ブランドイメージを損ないます。使う場面と頻度は慎重に選びましょう。

3. パーソナライゼーションの解像度
「XX様」と名前を差し込むだけでは、パーソナライゼーションとは言えません。
真のパーソナライゼーションとは、ユーザーの「コンテキスト(文脈)」に基づいていることです。
Spotifyの「Your Weekly Discover(あなたのための新曲プレイリスト)」通知は、その好例です。単なる新譜通知ではなく、「(あなたの聴取履歴に基づいた)あなただけの」という深いコンテキストと、「(新しい音楽との出会いという)価値提案」が組み合わさっています。だからこそ、ユーザーは「広告」ではなく「自分ごと」として通知を受け入れます。
「あなたが前回閲覧したAに関連するBが入荷しました」
「あなたがフォローしているCさんが、新しい投稿をしました」
こうしたコンテキストに基づいたメッセージこそが、ユーザーの心に響き、リテンションに繋がります。
効果測定と「送らない」ABテスト
施策を設計し、実行したら、最後にして最重要のプロセスが「効果測定(How)」です。
多くのPdMが、施策の「やりっぱなし」で終わっています。「プッシュを送ったら、開封率がXX%で、CTRがYY%でした。前回の施策より良かったです(悪かったです)」——この報告で満足していては、効果は上がれません。
なぜなら、その施策が「本当にリテンションに効いたのか」が全く分からないからです。もしかしたら、その通知を送らなくても、ユーザーはリテンションしていたかもしれません。もっと言えば、通知を送ったせいで、むしろ離脱(通知オフ)したかもしれません。
この「施策の真のインパクト」を測定す方法が、「コントロールグループ(CG)」を置いたA/Bテストです。
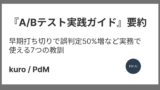
コントロールグループ(CG)の絶対的重要性
コントロールグループ(CG)とは、「あえて施策(通知)を送らなかったグループ」のことです。
- (TG)ターゲットグループ: 「カート放棄1時間後」にプッシュ通知を送る
- (CG)コントロールグループ: 「カート放棄1時間後」になっても、あえてプッシュ通知を送らない
この2つのグループを比較して、初めて施策の「純増効果」が分かります。
例えば、結果がこうなったとします。
- TGのCVR(購入転換率): 10%
- CGのCVR(自然購入率): 8%
この場合、施策の真のインパクトは「10%」ではなく、「10% – 8% = 2%」の純増だったと科学的に言えます。
見るべきKPIの使い分け
CGを置いたら、見るべき指標を「短期」と「長期」で分けます。
- 短期指標(プロセス指標): 開封率、CTR、CVR
- → これらは「メッセージが意図通りに機能したか?」を測るための指標です。
- 長期指標(本命のKGI): TG vs CG の比較
- → N日後リテンションレート(施策群の方が高いか?)
- → チャーンレート(離脱率)(施策群の方が低いか?)
- → 通知許諾オフ率(施策群の方が高くなっていないか?)
もし、「CTRは上がったが、TGとCGのリテンションレートは変わらなかった(むしろTGの通知オフ率が上がった)」という結果が出たなら、その施策は「失敗」です。短期的にはクリックを稼げても、長期的にはユーザーの信頼を失い、リテンションを毀損している可能性が高い。この「失敗」に気づけることこそが、CGを置く最大の価値です。
「自動化」と「UXとしての通知」
ここまで解説した戦略を「手動」で運用し続けるのは不可能です。第2章の「モーメント」や第3章の「オーケストレーション」を実践するには、MA(マーケティングオートメーション)ツールやCDP(顧客データ基盤)の活用が前提となります。
シニアPdMは、これらの施策を「シナリオベースで自動化」するだけでなく、最終的には機械学習(ML)を用いて「個に最適化されたレコメンデーションやタイミングの自動化」を目指します。
しかし、ツールや自動化はあくまで手段です。
最も重要な視座は、「プッシュ施策を、プロダクト体験(UX)の一部として設計する」というマインドセット。
プッシュ通知は、アプリの「外」にある機能ではありません。ユーザーにとっては、アプリのボタンや画面遷移と同じ、プロダクト体験の「内」にあるものです。通知が「邪魔」で「ノイズ」であれば、プロダクト全体の体験価値が下がります。
だからこそ、優秀なPdMは「送らない」という戦略的判断を重視します。通知の価値を維持するために、あえて通知を送らず、ユーザーの自発的な訪問を促す。そのバランス感覚こそが問われます。
プッシュ施策は、企業からの一方的な「広告」ではありません。ユーザーの状況とニーズに寄り添う「対話」です。その対話をどう設計するかが、PdMの腕の見せ所です。
まとめ
本記事では、toCアプリのリテンションを「科学」するためのプッシュ施策戦略について、ミドルPdMが陥りがちな罠と、そこから脱却するための思考法を解説しました。
- 「開封率」の呪縛から逃れ、KGIを「リテンション」に置く。
- 「誰の」「どのフェーズの」リテンションを上げるか、目的の解像度を上げる。
- 「属性」ではなく「行動」、さらには「モーメント」でセグメントを切る。
- チャネルを「単発」で使わず、「オーケストレーション(連携)」で設計する。
- 「釣り」ではなく、コンテキストに基づいた「価値提案」をメッセージに込める。
- 「送らないグループ(CG)」を必ず置き、施策の真のインパクトを測定する。
- 通知を「運用」ではなく「UXの一部=対話」として設計する。
これらの思考法が、皆さんのプロダクトのリテンションを本質的に改善する「次の一手」に繋がることを願っています。
今日から実践できるアクション
- 直近の施策で必ず「コントロールグループ」を設定する。
まずは10%でも構いません。「あえて送らない」グループを設定し、施策の「純増効果」を測る文化をチームに根付かせてください。 - 既存施策のKPIを「リテンション」で定義し直す。
現在追っている「開封率」や「CTR」が、最終的に「DayNリテンション」や「LTV」のどの指標にどう貢献するのか、ロジックツリーを描き直してみましょう。 - 「全ユーザー向け」通知を1つ止め、行動ベースのセグメント通知に置き換える。
例えば、「全ユーザーへの新機能告知」を止め、「その新機能と関連性の高い行動をしたユーザー」に限定して「アプリ内通知」で伝える、といった小さな改善から始めてみてください。
Q&A
- Q1: 通知の「最適」な頻度は?
- A1: 残念ながら「全てのアプリで週3回が最適」といった唯一無二の正解はありません。プロダクトの特性(例:毎日使うニュースアプリ vs 月1回使う旅行予約アプリ)や、ユーザーセグメントによって全く異なります。
重要なのは、第5章で述べたコントロールグループ(CG)との比較です。「通知オフ率が上がらず、リテンションが最大化される」スイートスポットを、ABテストを通じて自社プロダクト固有の値として見つけるプロセスそのものが答えとなります。そして、最も重要なのは、ユーザー自身が通知頻度やカテゴリを「制御できる」選択肢をプロダクト内で提供することです。 - Q2: LINEとプッシュ通知、どちらを優先すべきですか?
- A2: 目的によります。第3章のオーケストレーションの通り、使い分けが基本です。
・緊急性・即時性(例:タイムセール開始、予約時間のリマインド)や、行動トリガー(例:カート放棄)には「プッシュ通知」が適しています。
・確実に届けたいインセンティブ(例:特別なクーポン)や、親密な関係構築(例:ファン向けのライトなコミュニケーション)には、高開封率の「LINE」が適しています。
ただし、LINEはブロックリスクが最も高く、配信コストもかかります。LINEでしか送れない「特別な価値」を提供できない限り、プッシュやメールで代替すべきか常に天秤にかける必要があります。 - Q3: プッシュ通知の開封率が低い時の対処法は?
- A3: 主に「タイミング(When)」と「コピー(What)」の2軸で見直します。
・タイミング: 「全員一律の19時」で送っているなら、A/Bテストで「12時」や「22時」のグループと比較します。可能なら「Send Time Optimization(最適時間配信)」を導入します。
・コピー: 第4章の「価値提案」を見直します。その通知はユーザーにとって「お得」なのか「便利」なのか「新しい発見」なのか、一目でわかる件名になっていますか? 「【あなただけ】」「【本日終了】」といった行動経済学のトリガーをテストするのも有効です。
これらを試しても低い場合、そのセグメントにとってプッシュ通知というチャネル自体が最適でない(例:本当はメールでじっくり読みたい内容だった)可能性も疑いましょう。
参考情報
- Andrew Chen. (2018). “The new rules of push notifications for 2018 (and beyond)”. (リテンションとプッシュ通知に関するデータと考察)
- Leanplum. (2019). “Retention, Revealed: The Need-to-Know Benchmarks”. (モバイルアプリのリテンションに関するベンチマークレポート)
- リチャード・セイラー, キャス・サンスティーン (著), 遠藤 真美 (訳). (2018). 『ナッジ 実践 行動経済学』. 日経BP.
- ニール・イヤール (著), 高橋 璃子 (訳). (2014). 『Hooked ハマるしかけ―――人を動かすプロダクトデザインの原則』. 翔泳社.
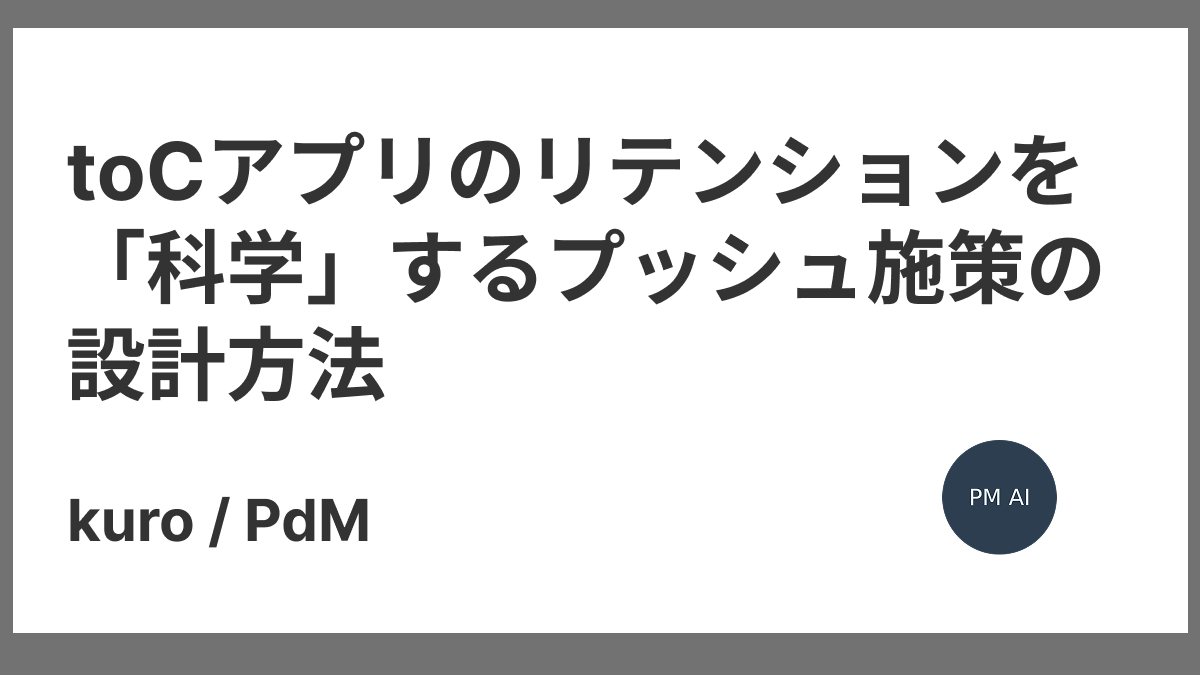
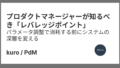

コメント