この記事の要約
- インタビューで“Why”を重ねすぎるとユーザーを追い詰める
- 自己開示の段階理論を応用し、心理的安全性を守る質問順序を設計する
- ラポールを築く感情質問テク&リカバリーフレーズでインサイトを引き出す
ユーザーインタビュー中に「なぜ?」を繰り返し、相手が戸惑って答えが浅くなる
――そんな“尋問疲れ”を経験したはないでしょうか?
僕は、「Whyは万能ではない」と考えています。本記事ではユーザーのエネルギーを保ったままインサイトへ到達する方法を考えてみます。
誘導・プレッシャーを生む質問パターンの実例
“Why”を連発すると、まるで刑事事件で犯人候補を尋問しているような形になってしまいます。また、それ以外にもいかようにユーザーを誘導したり、プレッシャーを与えてしまう質問があります。
| NGパターン | 理由 | ユーザーの反応 |
|---|---|---|
| Why連打型 「なぜそう思うんですか?」×5 |
質問者が“正解”を期待している空気を醸成し、 防御的認知(守りの姿勢)を誘発 |
「いや、別に…」「うーん」など思考停止 |
| 選択肢圧迫型 「AとBならどちらが良いですか? なぜ?」 |
前提を限定し、潜在解をつぶす | 「その2つなら…」と消極的回答 |
| 価値判断誘導型 「本当に便利だと思いますか? なぜ?」 |
Yesを期待するバイアス質問。 社会的望ましさバイアスを増幅 |
忖度回答になりがち |
「Why」自体が悪ではありません。連続・限定・価値判断との“セット使い”がプレッシャーを生むと覚えてください。
Self-Disclosure(自己開示)段階理論で組む安全な質問順序
自己開示段階理論(Altman & Taylor, 1973) は、人が表層→中核へ徐々にプライベート情報を開示する心理過程をモデル化したものです。これをインタビューに当てはめると、質問は以下の4層で設計できます。
| 段階 | 質問例 | 狙い |
|---|---|---|
| ①基本情報 | 「利用歴はどれくらいですか?」 | ウォームアップ |
| ②行動事実 | 「最後に使ったのはいつですか?」 | 客観ファクト |
| ③感情・評価 | 「使ってみてどう感じました?」 | 主観的感情 |
| ④価値観・動機 | 「なぜそれを重要視しますか?」 | コアの動因 |
Whyは④段階で初めて“1〜2回”投入すればOK。早い段階でWhyを連発すると、ユーザーは心理的な“壁”を上げてしまいます。
つまり、最初から広く、答えにくい部分から聞くから”なぜ”の連発になってしまうのです。上記のように④の段階で初めてWhyの質問をすることで連発を避けられるはずです。
ラポールを築く小ネタ
とはいえ、場合によっては(言い換えを変える必要は最低限ありますが)Whyを2-3回連続してしまうこともあるでしょう。その時に、「この人なら話せそう」と思ってもらうためのラポール(信頼関係)を作るには、Feelingを聞くのも効果的です。具体的には以下のような形。質問を変えたり、間にバックトラッキングを挟むことでガチのWhy連発は避けられます。
- 肯定のバックトラッキング
「●●と感じたんですね」と言葉を反射し、理解を示す。 - 比喩で寄り添う
「それは“通知の洪水”みたいな状態でしょうか?」とユーザー比喩を拝借。 - 10点スケール
「満足度を10点で表すと何点?」→数字+感情深掘りが両立。 - ポジネガ対比
「最も嬉しかった瞬間」と「最もストレスだった瞬間」をセットで聞く。 - 前提をファンタジーにする
「もし魔法が使えたら現状の何がどうなって欲しいですか?」
感情を扱う質問は心理的安全性を高め、続くWhy質問のハードルを下げる効果があります。
反応が鈍った時のリカバリー・クッションフレーズ集
また、Why連発などでインタビューが詰まってしまった時には以下の“クッション”を挟むだけで空気が和らぎます。
間接リフレーズ
「少し整理させてください。○○という流れで合っていますか?」
選択肢追加
「他にも思い当たることがあれば、あとで教えてくださいね」
自己開示
「僕も同じ課題に悩んだことがあります」と軽く共有して壁を下げる
今日から実践できるアクション
- 次回インタビューの質問表を4層構造に再配置し、Whyは④層のみ最大2回に制限
- ラポール小ネタ5選のうち1つを必ず実戦投入
- 録音を聞き返し、Why質問→ユーザー沈黙までの秒数を計測して改善
Q&A
- Q1: Whyを控えると真因が取れないのでは?
- 感情や行動フローを先に押さえると、1〜2回のWhyで十分に真因へ到達できます。
- Q2: 時間が短い場合の優先順位は?
- ②行動事実→③感情→④Whyの順で縮めれば、熱量あるテーマだけを深掘りできます。
- Q3: オンライン面談で表情変化が読みづらい…
- 音声のトーン変化と回答速度に注目。遅延やためらいは“疲弊シグナル”です。
参考情報
- Irwin Altman & Dalmas Taylor (1973) Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationships
- Amy Edmondson (2019) The Fearless Organization
- Rob Fitzpatrick (2013) The Mom Test
- Kara Pernice (2017) “User Interviews: How, When, and Why to Conduct Them”, Nielsen Norman Group
- 心理学を活用してユーザーインタビューからバイアスを排除し“本音”を引き出す
- ユーザーインタビューの質問項目大全
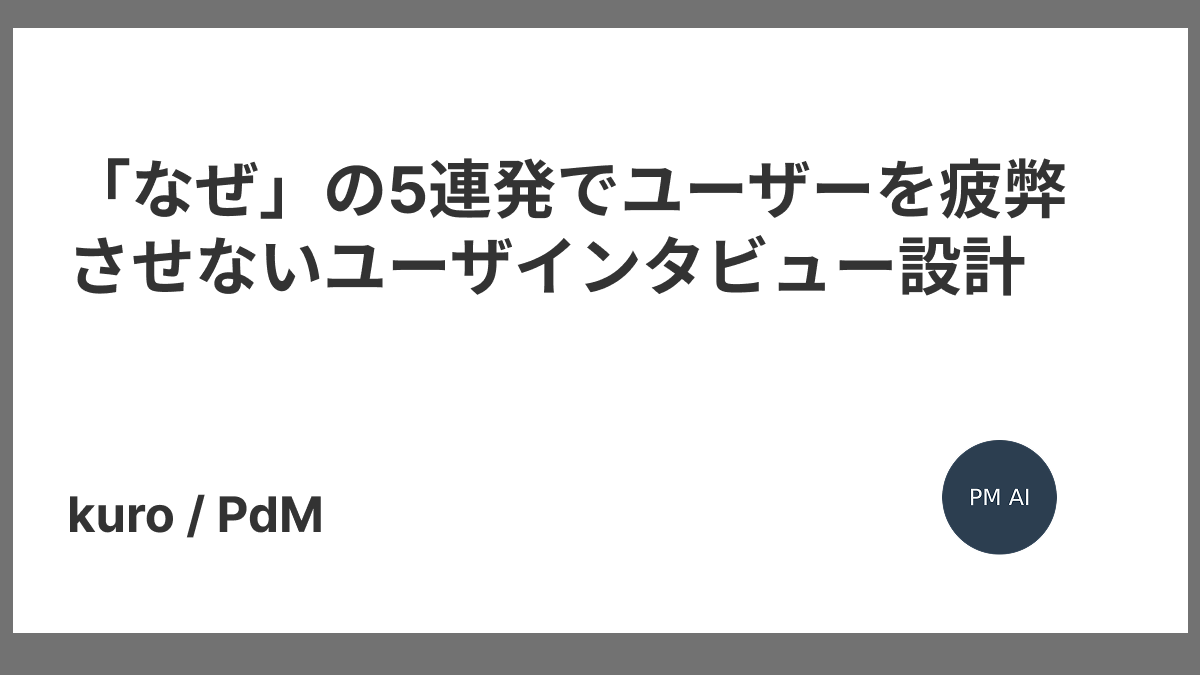
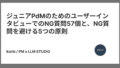
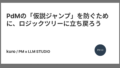
コメント