この記事の要約
- NPSは推奨度を測る指標だが、オンボーディングの課題や実際の使用感は捉えきれないため、CSAT(満足度)・CES(労力)・SUS(使いやすさ)などと組み合わせる必要がある
- 指標を導入する際は、プロダクトのフェーズや目的に応じて対象ユーザーとタイミングを設計し、ログ分析とユーザーインタビューを併用して定量と定性を照合する
- 数値が変動したら仮説を立ててインタビューで検証し、改善案を実装して指標の変化を追うサイクルを回すことで、ビジネスゴールと連動した改善が可能になる
なぜNPSだけでは不十分なのか
「NPS(Net Promoter Score)」は非常に有名で、多くの企業が導入しています。ただ、NPSは「推奨度」を測る指標であり、ユーザーが製品をどのように感じ、使い続けるかを一元的に表すわけではありません。たとえば、導入初期のオンボーディングに課題があるのにリファラル(紹介意欲)はそこそこ高いケースなど、NPSだけでは解像度が低いと思われる場面に直面することもあります。
また、BtoBとBtoCでのNPSの扱い方も異なる点が大きいです。
- BtoC:大規模ユーザーの声をスケールメリットで集計しやすく、測定データが比較的安定しやすい
- BtoB:導入担当者と実際のユーザーが異なることもあるため、誰のNPSを測定するのかが複雑になりがち。「導入担当者は製品に好感を持っているが、実際に使う現場担当者は不満を抱えている」といったケースも
NPSは指標として分かりやすい反面、定量データから読み取れる以上の深掘りや補完が必要です。
このように、NPSは顧客のロイヤルティを測る強力な指標である一方、ユーザーの詳細な体験や製品利用の真のハードルを明らかにするには不足する面があります。そこで、他の指標を組み合わせて多角的に顧客満足度を捉えることがPdMには求められます。
各種指標の特徴(CSAT・CES・SUSなど)
NPSに加えて押さえておきたい指標としては、たとえば以下があります。
- CES(Customer Effort Score)
- SUS(System Usability Scale)
- CSAT(Customer Satisfaction)
CES(Customer Effort Score)
CESは「顧客が製品やサービスを利用するときにかかる“手間”の度合い」を測る指標。「この問題を解決するために、どれほどの労力が必要でしたか?」といった質問を投げ、回答者に1〜7段階で評価してもらう形です。
CESは特に、オンボーディングや継続利用におけるハードルを見極めるのに役立ちます。もしCESが高い(=労力が大きい)と判明すれば、UI改善やサポート体制の強化が急務だと分かります。
NPSが高い人、低い人でセグメントを切ってCESと組み合わせてみるのがおすすめ。
Customer Effort Score(CES)― 質問例
- CES 1.0(5段階)
「ご要望を処理するために、お客様ご自身はどの程度の労力を払う必要がありましたか?」
1 = 非常に少ない … 5 = 非常に多い
- CES 2.0(7段階リッカート)
「この会社は私の問題解決を容易にしてくれた」という文にどの程度同意しますか?
1 = まったく同意しない … 7 = 非常に同意する
- 平易バリアント(Ease 指標)
「本日の問題解決はどのくらい簡単でしたか?」
任意の 5・7・10 段階「とても難しい ~ とても簡単」尺度
参考文献
[1] Harvard Business Review (2010) “Stop Trying to Delight Your Customers”.
[2] NICE (2025) “What is Customer Effort Score (CES) and how to Measure it?”.
SUS(System Usability Scale)
SUS(System Usability Scale)は、John Brooke氏が1986年に考案した古典的かつ世界的に使われているユーザビリティ測定方法です。
10項目の質問に5段階評価で回答してもらい、最終的に0〜100のスコアに落とし込みます。操作の分かりやすさやエラー時の対処のしやすさなど、実際の製品利用シーンに近い評価が得られる点が特徴。数値が高いからといって必ずしもすべてのユーザーが満足しているとは限りませんが、UI/UX面のボトルネックを定量的に掴むには十分活用できる指標です。
System Usability Scale(SUS)質問項目 ― 日本語版
- 私はこのシステムを頻繁に使いたいと思う。
- このシステムは不必要に複雑だと感じる。
- このシステムは使いやすいと感じる。
- このシステムを使うには技術者のサポートが必要だと思う。
- このシステムではさまざまな機能がうまく統合されていると感じる。
- このシステムには一貫性が欠けていると感じる。
- ほとんどの人はこのシステムをすぐに使えるようになると思う。
- このシステムは操作が煩雑だと感じる。
- 私はこのシステムを使いこなせると確信している。
- このシステムを使い始める前に多くのことを学ぶ必要があると感じる。
参考文献
- Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale.
In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland (Eds.),
Usability Evaluation in Industry (pp. 189-194). Taylor & Francis. - 山内 繁 (2016). 「福祉用具におけるSUS」― 原著者 John Brooke 氏の許諾による日本語訳を収録。早稲田大学資料。
CAST(Customer Satisfaction)
CSATはシンプルに「この製品に満足していますか?」などの質問で測る満足度をパーセンテージなどで示す指標。
ユーザーにとって答えやすく、回答率も高い反面、調査時点の短期的な感情に左右されやすいという短所があります。セール担当やカスタマーサポートとの接触が直後だと、回答が高くなる場合もあるため、設計時には留意が必要です。
指標を実際に導入するステップ
まずはどの指標を導入するかを明確化しておくことが不可欠です。NPSを補完したいなら、CSATやCESのような「体験の一部」を測る指標や、SUSのように「使いやすさ」にフォーカスした指標を選び、プロダクトのフェーズや目的と照らし合わせて導入します
その際、ユーザー調査を一度にまとめて行うのではなく、目的に応じて質問のタイミングや対象ユーザーを分けるのがコツ。たとえばBtoB製品であれば、導入直後の管理者層、継続利用中の現場担当者など、ロールや利用タイミングで区切って実施することが多いです。
調査設計では、ツール選定も重要になります。オンラインサーベイツールを使うだけでなく、ログ分析との連動も考えたいところです。具体的には、使い方が怪しいユーザーを特定し、そのユーザーに対してSUS調査を行うなどのアプローチが考えられます。また、定量データの数字の背景を深掘りするために、ユーザーインタビューを組み合わせるのがおすすめです。たとえばユーザビリティテストの分析手法「Lostness」を活用しながら(こちら)、ユーザーが具体的にどこで苦戦していたのかを定量・定性で照合すると、改善領域を絞り込みやすくなります。

運用開始後は、結果をそのまま受け取るのではなく、数値の変化を観察しながら仮説検証を進めることが大切。指標を計測していくと、定量データとユーザーインタビューの内容に食い違いが生じる場合があります。そうした場合は、「定量データとユーザーインタビューが食い違うとき、どう再設計するか?」を参考に見直すのも一つの手です。

指標を変化させる因果をどう仮説検証するか?
また、当たり前ですが指標を導入したからといって自動的にプロダクトが改善されるわけではありません。PdMとしては「数値が上下した背景には何があるのか?」を掘り下げる姿勢が求められます。
僕は以下のサイクルを意識して運用しています。
- 数値変動の検知(ダッシュボードなど)
- 仮説
- インタビュー
- 検証
- 指標の変化
まず、指標の数値変動を発見したら、その背後にあるユーザー行動や心理を仮説として立てます。次に、実際に該当セグメントのユーザーにインタビューを行い、仮説が正しいかどうかを確認します。もし仮説が裏付けられれば具体的な改善案を打ち出し、実装後に指標がどう変わるか追うのです。
仮説検証の際に、コホート分析などを組み合わせると効果的。たとえばオンボーディング前後でのCSATやCESがどう変化しているか、月ごと・ユーザー群ごとに把握することで、いつのタイミングで満足度が下がっているのかを明確にできます。詳しい手法は「コホート分析でリテンションを高める」を参考になると思います。いずれにしても、指標の数字だけを見て一喜一憂するのでなく、その変動要因を仮説とデータを行き来しながら検討する作業が欠かせません。

さらに、ビジネスゴールとの連動も当然大切。満足度指標は「今の顧客がハッピーか」を知るためのものですが、売上やLTV、リテンションなどのKPIとも密接に関係しています。経営層との会話では、NPSやCSATなどの数値変化がビジネスインパクトにどう直結しているのかを整理しながら説明する必要があります。
社内周知とレポーティング
そして、新たな指標を導入したら、社内への周知やレポーティング方法にも工夫が要ります。定期レポートや全社朝会などで指標の数字を報告するだけでは、十分に改善アクションに結びつかないケースも。
- 「なぜこの指標を測っているのか」
- 「指標が今どうなっていて、その理由をどう仮説立てているのか」
をセットで共有し、各チームが具体的なアクションを取れるように道筋を示すことが大切だと感じています。
PdMだけでなく、エンジニアやサポートメンバーも指標変動の意味合いを捉えられるようになると、組織全体で改善に取り組むムードが高まります。
データの見せ方も重要で、スライドやダッシュボード上で数字だけを見せるのではなく、ユーザー引用コメントや簡易ペルソナ、導線の図解なども交えて「ユーザーが何に困り、どう感じたのか」をイメージできるようにするのがコツです。こうした工夫が、ステークホルダーの納得感につながります。
まとめと参考情報
NPSは確かに強力な指標ですが、それだけでは捉えきれないユーザーの満足度要素があるのも事実。CSATやCES、SUSなどを組み合わせることで、ユーザーの感情・行動・使い勝手をバランスよく把握できます。それらの数値が変化した背景を仮説化し、インタビューやコホート分析で検証する流れを回すことで、PdMはより精度の高い意思決定を行いやすくなります。社内での周知・レポーティングでは数字だけにとどまらないユーザーの生の声や行動データを見せると、チーム全体が動きやすくなると感じています。
ただ、どの指標も魔法の杖ではない点に注意が必要です。結局のところ、指標をどう読み、どのように改善に反映させるかがPdMの腕の見せどころとなります。僕自身、ユーザーインタビューを累計700人以上行ってきた経験から、定量データだけでなく“現場の声”を組み合わせてこそ、真にユーザーに寄り添ったプロダクト開発が可能になると実感してきました。生成AIの進化でデータ分析が加速している今だからこそ、複数の指標と定性リサーチの掛け合わせがますます重要です。
参考情報
- Reichheld, Frederick F. (2003). “The One Number You Need to Grow.” Harvard Business Review.
- Brooke, J. (1996). “SUS: A ‘Quick and Dirty’ Usability Scale.” In Usability Evaluation in Industry, CRC Press.
- Jeff Sauro, James R. Lewis (2016). Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research. Morgan Kaufmann.
- Nielsen Norman Group (公式サイト): https://www.nngroup.com/
- 関連内部リンク:
今日から実践できるアクション
1. 追加指標の導入を試す:NPSのみ運用している場合は、CSATかCES、SUSなど1種類で構わないので新たな指標を試してみる。オンボーディング直後にCESを尋ねるなど、具体的なタイミングを決めると導入しやすい。
2. インタビューとセットで結果を解析:数値が低下または上昇した際には、そのユーザーに対して短いインタビューを実施する。背後の理由を直接確認することで、優先度の高い改善施策を素早く検討できる。
3. レポートのフォーマットを整える:社内共有の際は、数字だけでなく具体的なユーザーコメントやUIのスクリーンショットを添付し、改善領域を明確化して全体を巻き込む。
Q&A
Q1: NPSとCSATは併用したほうが良いですか?
A1: 併用すると、プロダクトの「長期的なブランドロイヤルティ」と「直近の満足度」の両面が分かるため、PdMとしてはより立体的な把握ができます。特にBtoBではNPSを経営層、CSATを現場担当者に向けて実施するケースが多いです。
Q2: CESを測定してみたものの、数値が高いか低いかの基準が分かりません
A2: 業界や製品特性によって理想値は異なるため、まずは自社の過去トレンドを蓄積することが大事です。また、競合と比較できる機会があれば、ベンチマークとして活用し、相対的に高いか低いかを評価しましょう。定性的インタビューと併せると、数値だけでは見えない意味づけが可能になります。
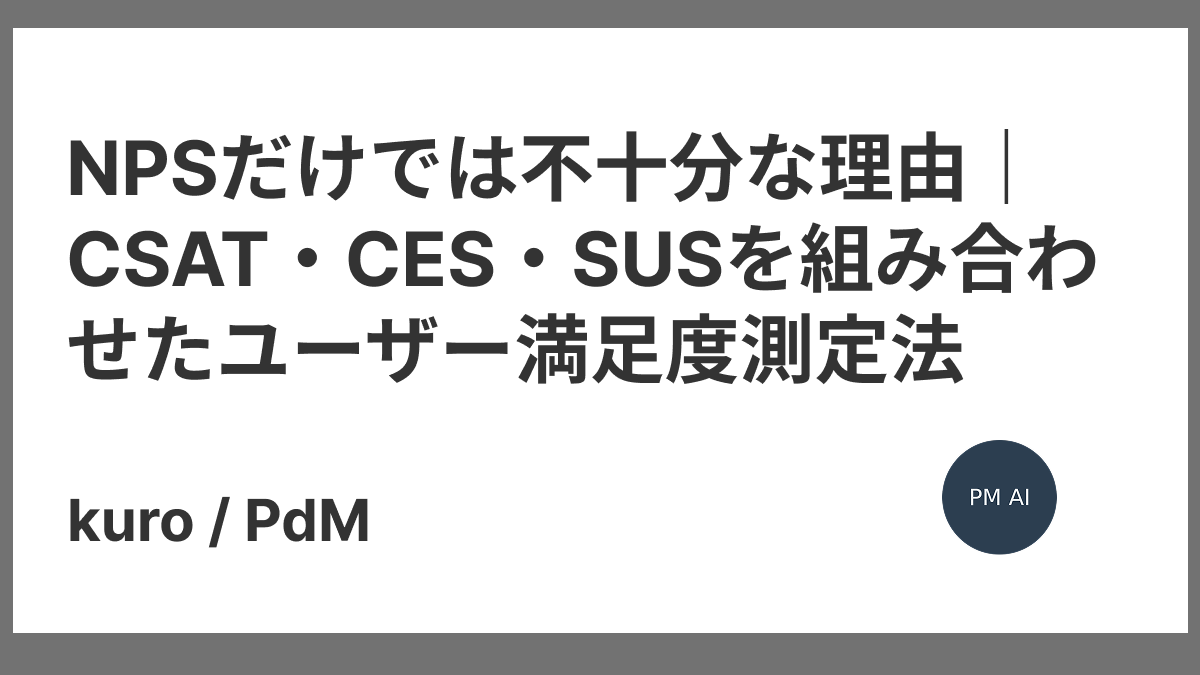

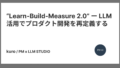
コメント