ユーザーインタビューの「組織化」に一度取り組んでみたものの、いつの間にか回数が減り、情報が共有されず結局属人化に逆戻り。。。。。。。。。
(そして特定のPMが業務過多に)
そんな経験ありませんか?僕はめちゃくちゃありました、というかだいぶ失敗してます。
標準テンプレや週次会議など一通り整備して「よし、これでいける」と思っても、半年後には誰も見学に来ない…、という何とも悲しい状況。
本記事では、「一度ユーザーインタビューの組織化を試みたが、うまく定着しなかった」人向けに、どうすれば良いか?を考えたのでよくある課題とその克服アイデアを含めて解説します。
続かない…….。インタビュー組織化を阻む3つの壁
最初に、組織的なユーザーインタビュー体制を立ち上げたにもかかわらず、いつの間にか失速する理由3つを振り返ります。
- 形式だけ整い、ゴール曖昧
テンプレや会議体は整備したが、「何をゴールとしているのか」「インタビューをどのテーマの施策に繋げるか」がチームで合意されていない。 - 情報更新が滞り、データ陳腐化
始めの数週間は熱心にスナップショットを共有していても、月日が経つにつれてアップロードが後回しに。やがて古いデータばかりが残り、検索しても使えない状態に。
例:日々の業務に追われ、インタビュー録画や要約を“あとで整理しよう”としているうちに溜まってしまう。 - 新規参画メンバーが増え、テンション乖離
せっかく仕組みを作っても、異動や転職で主要メンバーが抜け、ノウハウが途切れる。営業のようにロールプレイや研修がないため、次の担当者が「どこから手をつければいいの?」となりがち。
再チャレンジに必要な4つの対策:継続と進化の仕組み
じゃあどうすれば、、、。
ということでここからは、上記の壁を乗り越え、ユーザーインタビューを自社文化として根付かせるための具体的な手法を4つ紹介します。
対策1:インタビューに「明確なアウトカム」と「期限」を設定
「何のためにインタビューをやるのか」をさらに鮮明にし、「いつまで、誰が、何をどうするか?」を明文化します。例えば、
- インタビューで出てきたxxxという課題について[個人名]が[3/20]までにPRDに落として[個人名]に展開する
こうした“締め切り”をロードマップに組み込み、インタビュー結果が即アクションにつながるように設計すれば、メンバーのモチベーションが下がりにくい、というかインタビュー聞いてないとできないから聞かざるを得ない。
僕は、インタビューが終わって課題でたら、関係するメンバーをメンショして、「これどう思います?」って聞くようにしてます。
また、定量指標(例:エンジニアのプルリク件数のうち、インタビュー起点の改善が何件あったかなど)を追うのもおすすめ(バックログでもOK)。成果が見える化されれば、続ける意義を全員が再認識できます。
対策2:新規参画メンバー向けの「Onboarding資料」
「一度は整備したのに、担当が変わったら何もわからない」とならないために、入社や異動直後のメンバーが最初に受ける15分のセッションと事前に読めるA4 1-2枚のオンボ資料を作るのがおすすめ。
こんなことを紹介するとよいというポイント
- なんでユーザーインタビューを大事にすることになったか?
- 典型的なペルソナにしているN = 1の動画リンク
- 当社のユーザーインタビューで大事にしていること
- よくあるNG質問
- インタビュー準備から施策に落とすまでのロードマップ
また、以下のような仕組みもおすすめです
- バディ制: 新メンバーが最初の2回はベテランと一緒にインタビューを実施し、仕組みとスキルをキャッチアップ
- 視聴会:金曜日のこの枠はみんなで見る枠、として新規参入者もslackとかで話しやすい状態にする(みんな or 自分ののインタビューに対する温度を伝達する)
これにより、担当者が変わっても仕組み自体は回り続ける状態を維持できる確率が上がります。まあエンジニアがちゃんと引き継ぎDocとかマニュアルとか作るのと同じテンションでインタビューもやろうぜ、だってそれが本当に大事だと(少なくとも誰かが)思っているんでしょ、という。
対策3:データを最新化するための「継続的リマインド」と評価制度
ユーザーインタビューの最終成果は、録画やスナップショットを社内に蓄積すること。ただし、更新が止まると一気に価値が目減りします。
そこで、継続的に更新されるインセンティブを組み込みましょう(特にあなたがマネージャーなら)。
- 毎週or隔週の「リポジトリ更新日」
スプリント終わりの金曜午後などに、Slackで「インタビューした人は要約と録画をアップデートしてください」というリマインドを自動発信。
担当リーダーが完了をチェック。 - 評価や表彰
「最も貢献度の高いインタビュー実施者」「最も優れたスナップショット賞」といった形で社内イベントやオールハンズで表彰するなど。
多少カジュアルでも、承認があるだけで更新意欲が保ちやすくなります。
対策4:上層部やステークホルダーの巻き込みを拡大する
「プロダクト開発チームだけ」で完結させようとすると、いつかリソース不足が起きたり、優先度が下がりがち。
経営陣やビジネスサイド、CS部門など幅広いステークホルダーを巻き込むと継続力が増します。例えば、
- 役員やGMがインタビュー定例会を10分だけ視聴
影響力のある人が興味を持ち続けるほど、周囲も「顧客の声を共有するのは大事なんだ」と認識。本当は役員、CEOが自分でインタビューする姿を見せるのが一番。 - CSや営業へのフィードバック枠
得られた顧客課題を商談やアップセルのトークスクリプトに活かすなど、機能開発以外でも成果が出せるとわかると、社内的に支持を得やすい。
インタビューは開発チームだけのものではなく、ビジネス全体の成果につながる活動であると位置付けることがカギです。
上級者向け:インタビュー活用をより洗練させるワークフロー
さらに余裕がある場合、以下のアクションに挑戦すると、データ活用の精度やスピードが一段と高まります。
- AI要約+エンベディング検索
ユーザーインタビューの文字起こしデータをGPTなどのLLMで要約し、要点のみをスナップショットにまとめる。
Notionや専用ツールで検索時に「利用ログが少ないユーザーの声だけ抽出」などを実現。
これにより、膨大な定性データからも瞬時に関連箇所を検索できる。
インタビューの声をインプットしたGPTsを作っておくのもおすすめ(規約注意)。 - アジャイルテストサイクルとの統合
プロトタイプやA/Bテストと連動し、「試作機能を使ってもらう→インタビュー→即改善」という超短期ループを可能に。
“ユーザーと話す”活動が日常的なイテレーションの一部に組み込まれる。
というか、ユーザーと話していない奴には企画の資格なし、にする。 - 外部の専門家による監査
3カ月~6カ月に一度、UXリサーチやインサイト発掘の専門家を呼んで、蓄積データの品質をレビューしてもらう。
適切にタグ付けされているか、偏りはないか、運用のボトルネックはないかをチェックし、常に改善を続ける。
ゲスト呼んでテンション上げようぜ、という。
今日から実践できるアクション
- 次期リリース目標とインタビュー数をひも付ける
「◯月の機能アップデートまでに、5つのペルソナセグメント×3人ずつ合計15インタビューを完了する」など具体的なゴールを設定し、担当者を割り振る。 - 運用マニュアル&研修で新人フォローを再整備
異動や新入社員が来た際に、まず見てほしい動画orスライドを10分程度で作成。バディ制度を再度活性化する。 - 「毎週のリポジトリ更新日」を復活
スプリント後などにSlackリマインドを自動送信し、インタビュー結果のアップロード&タグ付けを促す。
運用リーダーが完了状態をチェックし、小さな表彰文化などを導入する。 - CS・営業部門との橋渡しを強化
ユーザーインタビュー成果を商談やオンボーディングに使うシーンを見つけ、販促効果なども追う。上層部へのレポートに盛り込むことで社内的評価が高まる。
Q&A
- Q1. 以前は週次ミーティングをやっていましたが、忙しくなると中断してしまいます。
- A. 定例が長引いたり、目的が不明瞭だと「仕方ないか」となりがち。短時間(30分以内)で議題を絞り、「確認→ディスカッション→アクション割り当て」の流れを必ず踏むと、会議の価値が維持しやすい。
また、隔週や月1でもいいので、安定開催が大事です。 - Q2. 上層部がユーザーヒアリングに興味を示しません。どうすれば巻き込めますか?
- A. 「どれだけ売上やNPSに影響したのか」を具体的に報告するのが手。インタビューから生まれた機能が◯%の顧客離脱を防ぎ、年間売上に貢献した…など、経営指標と結びついた成果を見せると関心が高まります。
- Q3. 過去インタビューのデータが膨大すぎて整理しきれません。
- A. 全てを詳細に整理する必要はなく、「重要セグメント×直近1年」など優先度で絞るのも一手。
AIツールを使い、要約やタグ付けを半自動化すれば、重要キーワードの抽出も効率アップします。
定期的に「古いデータをアーカイブする」ルールを設けておくのも有効です。
参考情報
- 田所雅之『起業の科学』(日経BP)
- FoundX Review「ユーザーインタビューの基本」
- Rob Fitzpatrick『The Mom Test』
- 「ユーザーインタビューガイド」(当サイト)
- Shin note「全PMが知るべき『本当の課題』を知るユーザーヒアリング手順と失敗例まとめ」
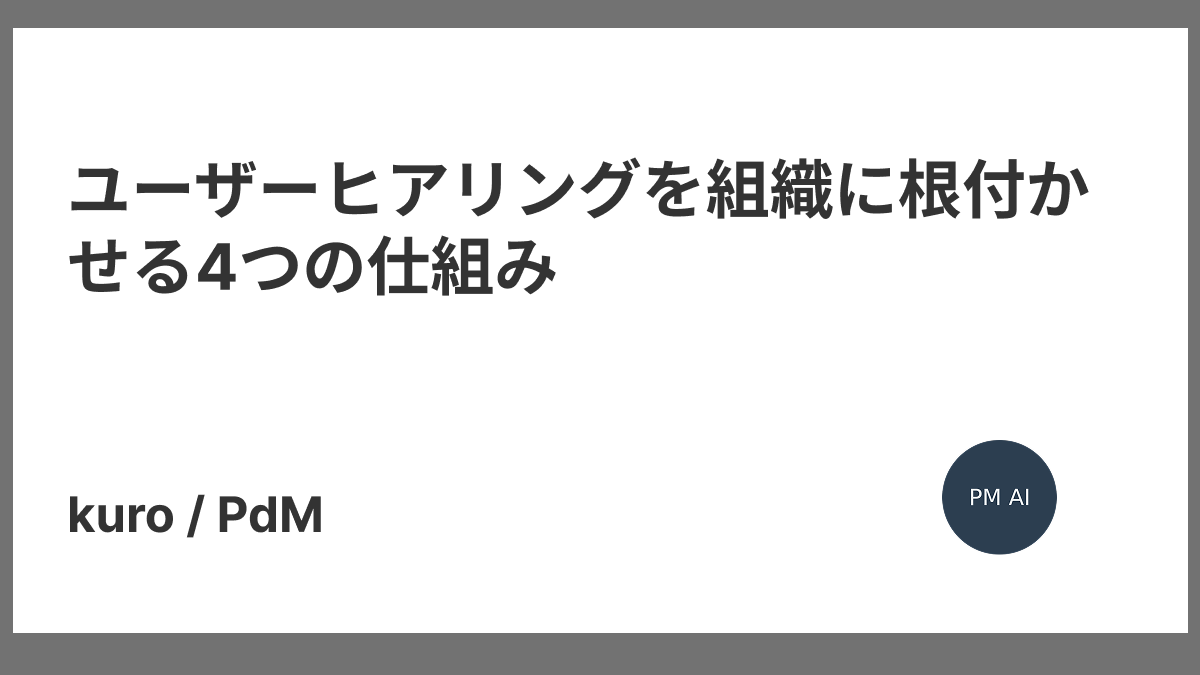
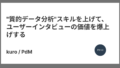

コメント