この記事の3行要約
- 社内ユーザーは日々の業務で生の課題に直面しており、外部インタビューでは見えない業務フローや意思決定プロセス特有の背景が詰まっている。これを知ることがプロダクト改善の大きなヒントになる
- 「社内インタビュー → 分析 → プロトタイプ → 再テスト」の短期フィードバックループを回すことで、外部ユーザーより圧倒的に速く仮説検証を重ねられ、実装スピードとプロダクト品質が同時に高まる
- ただし忖度・愛着などの社内バイアスが発生するため、匿名アンケート併用や第三者ファシリテーター起用、定量データ・外部インタビューとのTriangulationで客観性を担保する必要がある
なぜ社内ユーザーインタビューが有益か
プロダクトマネージャーにとって外部ユーザーへのインタビューが重要なのは言うまでもありませんが、プロダクトによっては自社の社員がユーザーであるケースも多々あります。
ユーザー兼社内の営業・サポート・開発メンバーは、日々の業務で生の課題や要望に直面しています。そこには、外部ユーザーのインタビューではなかなか見えない、業務フローや内部の意思決定プロセス特有の背景が詰まっています。こうした“組織文化や業務プロセスに根付いたリアル”を知ることは、プロダクト改善の大きなヒントになります。
ただし、社内ユーザーインタビューでは以下のような注意点も。
- 「自社の立場ゆえに発言しにくい」
- 「遠慮して本音を言わない」
そこで、社内ならではのバイアスを理解し、客観的データと突き合わせるプロセスが必要です。
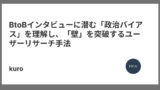
社内ならではのバイアスと対処策
社内メンバーを対象にしたインタビューでは、どうしても「遠慮」「忖度」「上司や経営層への配慮」などが生まれやすいです。加えて、プロダクトに対して愛着が強かったり、単に慣れで不便を不便と感じなくなっているケースも多く見受けられます。これらはすべて“社内特有のバイアス”です。
チームメンバーとしては、プロダクトを否定しているように思われたくないし、組織内で悪い印象を残したくないために言葉を一定は控える傾向にあります(もちろん中にはズバズバ言ってくれる人も大勢います)。
対処策は以下の通り。
- 匿名化・アンケートの併用:インタビューの前後に匿名アンケートを実施し、忖度なしのフィードバックを集める。
- インタビュアーの第三者性:プロダクトに直接関与しない、別チームや外部のファシリテーターを起用して中立な視点を保つ。
- フレームワーク活用:バイアスを徹底攻略するために、心理学的なバイアスの分類やチェックリストを用意する。【2025年】ユーザーインタビューで起こるバイアスを徹底攻略!などを参考に、回答バイアスを最小化する仕組みを取り入れる。

質問設計:忖度を防ぎ、リアルな感想を引き出す
社員へのインタビューで何よりも重要なのは、忖度を防いで“リアルな感想”を引き出すことです。そのためには外部ユーザーと同様に質問設計が鍵を握ります。社内ユーザーの場合は先述した社内バイアスもあり意外とハードルが高いです。
そこで具体的には、以下のような工夫が効果的です。
状況描写を問う
- 「普段どんな場面でこの機能を使いますか?」
- 「どんな時、業務フローに組み込んでいますか?」
など、使い方や事例を尋ねることで、抽象的な賛否ではなく、実際の使い方の中に埋まっている課題を引き出す。外部ユーザーへのインタビューと同様に「ファクト」をとにかく集めるということです。
オープンエンドの質問
「もしこの機能を別の人に紹介するとしたら、どんな説明をしますか?」など、答え方を制限しない形で意見を聞く。そのなかで、ポロッと出る不満や違和感を捕ましょう。
詳しい質問設計については、ユーザーインタビューの質問項目大全も参照してみてください。社員インタビューでも同じような原則が応用できます。

実装へのフィードバックループを組む
社内インタビューで得た示唆をすぐにプロダクト改善につなげるためには、フィードバックループが不可欠です。
- インタビュー実施
- 分析
- 施策のプロトタイプ
- 再度社内ユーザーでテスト
といった流れを短いスプリントで回すことで、素早く仮説検証を重ねられます。これが繰り返されることで、実装スピードが上がり、プロダクト品質も高まります。
ただし、主観的な意見に偏りすぎると、プロダクトの方向性が社内の都合だけに寄ってしまう可能性があるため、定量データや外部ユーザーからのフィードバックと照らし合わせる“ハイブリッドアプローチ”が重要。「ログ分析→ユーザーインタビュー」の流れで改善仮説を立てる方法は、ログ分析→ユーザーインタビューの流れで解説しています。
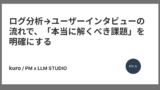
社内コミュニケーション強化と導入効果
また、社内ユーザーインタビューを重ねると、チーム内コミュニケーションが密になるという副次的効果も期待できます。インタビューの場を設けることで、社員が自分の課題を整理し、プロダクトへの意識が高まります。結果的に、開発メンバーと営業、サポートなど複数の部署間の連携がスムーズになり、情報共有の質も向上します。
社内インタビューの結果を共有することで「自分たちの声がプロダクトに反映されている」という実感が得られ、社員のモチベーションアップにもつながります(一応留意点ではこれはあくまでサブ効果であり主目的ではありません)。この社内で生まれた熱量は、外部ユーザーにも波及していきます。「このプロダクトは本当に使い勝手を考えてくれている」と対外的にも評価が高まる可能性があるのです。
一方で、社内の意見だけを重視しすぎると、外部視点とのズレが生じることもあります。そうしたときは、定量データとユーザーインタビューが食い違うとき、どう再設計するか?などを参考に、客観的データで社内の意見を検証するプロセスを踏むとよいです。

客観的データとの整合性を見るフレームワーク
最後に、社内インタビューで得られた定性情報を客観的データと突き合わせるフレームワークを紹介します。僕がおすすめするのは、「Triangulation(トライアングレーション)アプローチ」。
これは
- 定量データ
- 社内ユーザーインタビュー(内部視点)
- 外部ユーザーインタビュー(外部視点)
の3つを組み合わせて総合的に評価する手法。
進め方のイメージは以下です。
- 定量的なログ・KPIの確認
- 実際に利用率や離脱率などの数値を把握し、問題点を仮説化する。
- 社内ユーザーインタビュー
- 社員に対して日々の業務における使い方、困っている点、アイデアなどを聞き出す。
- 外部ユーザーインタビュー
- 顧客や一般ユーザーの声を集める。社内と外部で認識の差がないか比較する。
- 結果の突き合わせ
- 定量データで示された問題と、社内・外部それぞれのインタビュー結果を重ね合わせ、違いがあれば深堀りし、本質的な課題を特定する。
このアプローチは、定性・定量をバランスよく掛け合わせ、主観だけでも数字だけでもない“実態把握”を実現できます。もしデータとの齟齬があれば、「なぜ社員はこう思っているのに、データは違う傾向を示すのか」をさらに深堀りすることが、イノベーションの種を見つけるきっかけになるのです。
参考情報
▼書籍・論文・研究
- Rob Fitzpatrick (2013)『The Mom Test』
- Steve Portigal (2013)『Interviewing Users: How to Uncover Compelling Insights
- Carl F. A. Orphanides et al. (2021), “Biases in Organizational Decision-making,” Journal of Product Management Research
- Triangulation手法に関する各種学術論文(Mixed Methods Researchなど)
今日から実践できるアクション
1. 社内アンケートの実施
インタビュー前の“ウォーミングアップ”として、Googleフォームなどで匿名アンケートを取り、社員の率直な意見を把握します。これだけでも社内バイアスがどの程度あるのか掴めるはずです。
2. 短期プロトタイプサイクル
インタビューで出てきた改善アイデアをすぐに試作し、再度ユーザー(社員)に使ってもらう。この短期PDCAを回すことで、バイアスも含めた多様な意見を集約しつつ、素早く改善できます。
3. Triangulationで外部ユーザーと比較
外部ユーザーの声と社内ユーザーの声を並べて比較する習慣をつくる。ギャップが見えたら、さらに詳細のインタビューを行い、原因を深堀りしていきます。
Q&A
Q. 社内メンバー全員にインタビューする時間がない場合、どう優先度をつけたらよいでしょうか?
A. まずはプロダクトの利用頻度が高い部署や、実際に機能を使っているキーユーザーから着手するのが効果的です。利用状況や部門の重要度を指標に優先度をつけましょう。
Q. 社内ユーザーがネガティブな意見を言いづらそうなときはどうしたらいい?
A. 匿名アンケートやオンラインフォームで先に本音を収集したり、第三者のファシリテーターを入れるなど、遠慮が生まれにくい仕組みをつくると有効です。
Q. 社内メンバーにインタビュー結果を共有する際の注意点は?
A. まとめた結果を共有するときは個人が特定されるような情報を避け、あくまで建設的な意見として扱うことが大切です。また、インタビュー参加者へ感謝を伝えつつ、施策への反映プロセスも合わせて説明しましょう。
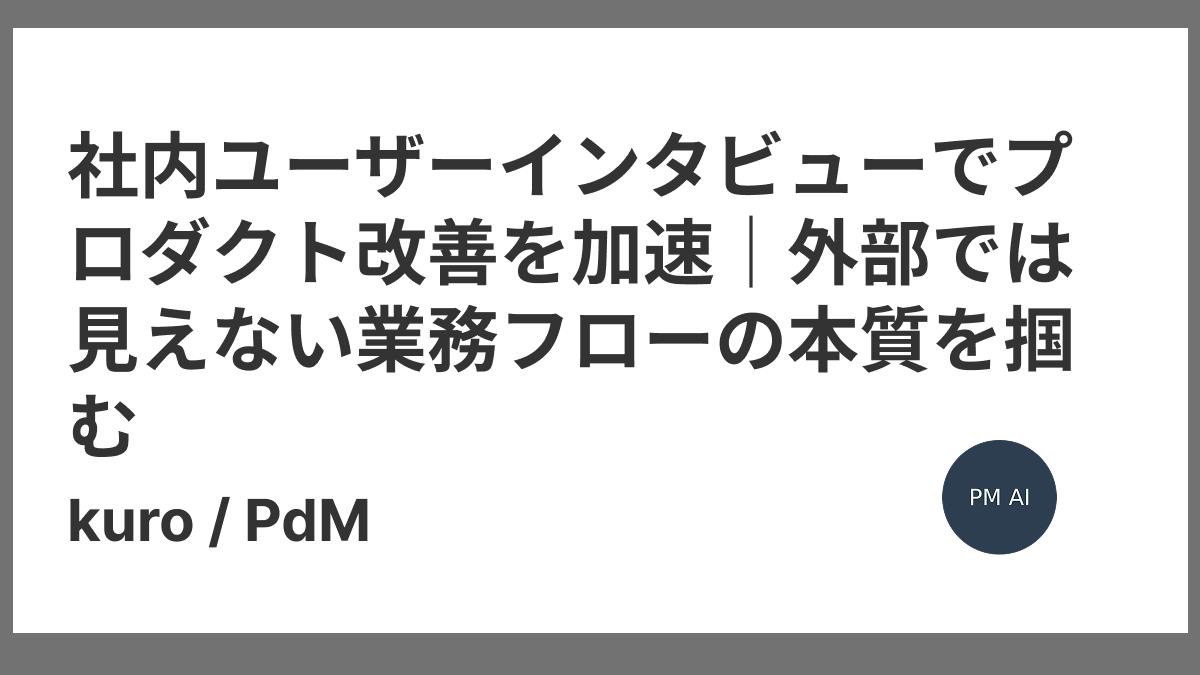
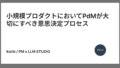

コメント