この記事の要約
- 新規事業やリニューアル時に詳細なペルソナを作り込むと方向修正が困難になるため、仮説ベースの「プロトペルソナ」で複数のユーザー像を並行検証することが成功の近道
- プロトペルソナは5分程度で作成し、5〜10名のインタビューとプロトタイプ検証を通じて1〜2週間単位で柔軟にアップデートしていく前提で運用する
- 大企業の大規模UX変更でも「小さな実験で失敗・学習を繰り返す」アプローチにより、投資リスクを抑えながら社内合意形成とスピードを両立できる
「プロトペルソナ」という考え方
プロトペルソナは、「まだ顧客像が明確に固まっていない段階で、まずは仮説ベースでまとめるユーザープロファイル」です。
新規事業はもちろん、大幅なUX変更や既存サービスのリブランディングでも活用できます。
以下のような特徴があります
- 作り込み度合いが低い:明確なデータがない段階で細部まで練り込んでも、外れた場合の修正コストが大きい
- 学習サイクル前提:最初はざっくり設定し、インタビューや試験的リリース後のデータを踏まえてアップデートすることが前提
- 複数の仮説ユーザー像を並行検証:「20代フリーランス」「副業を検討中の会社員」「転職を考える大企業勤め」など複数案を立てて、実際の声やログで優劣を見極める
対して、通常のペルソナ(本ペルソナ)はユーザーインタビューや定量データなど、ある程度裏付けを取ってから作成するのがセオリー。
初期不確実性が高いプロジェクト(大規模リニューアルや新事業)で作り込むと、方向修正が辛くなるリスクが大きいのです。
特に複数ペルソナ作っておき、それごとにインタビューをして想定する課題を一番切実に抱えている人を後々ペルソナに設定するのが超おすすめです。
リーンスタートアップ × プロトペルソナ
米国の起業家エリック・リースが提唱したリーンスタートアップは、「素早く検証し、フィードバックを得て学習する」ことを重視するスタイル。
もはや当たり前に実践している方が多いかもしれませんが、以下プロセスで進行します
- 仮説を立てる(例:今回のリブランディングは20代の新社会人を取り込める)
- 最小限の実装やプロトタイプを用意して検証
- 得られたデータや定性フィードバックをもとに仮説を修正
プロトペルソナは、この「1.仮説を立てる」段階を具体化するためのツール。
サービスリニューアルや大規模UX変更の際にも、「この変更はこういうユーザー層に喜ばれるはず(喜ばせたい)」という仮説ペルソナをまず立て、小規模テスト→ユーザーインタビュー→ログ分析などで検証を繰り返します。
もしズレを感じたら、プロトペルソナごと方向転換してもOK。これが、“作り込み型ペルソナ”に比べた柔軟性とスピード感を生むわけです。


プロトペルソナは新規事業以外にリニューアルや大幅UX変更にも効く
- 「既存ユーザーが飽和してきたから、新しいユーザー層を取り込みたい」
- 「リブランディングでサービスの見た目やメッセージを刷新するが、ユーザー層がどう変わるか未知数」
- 「大幅なUI改修を計画しているが、どのユーザーがどう感じるのか手探り状態」
こうした状況でも、プロトペルソナを使って仮説ユーザー像を複数パターン作り、軽量なプロトタイプやベータ版リリースで反応を確かめるアプローチが有効。
いきなり全ユーザーを対象に大改修を打ち出すのではなく、特定の少数ユーザー像に向けてテストを重ねることで失敗リスクを下げられます。たとえば、BtoBサービスのUI刷新なら「既存の熟練ユーザー」「導入直後の新規ユーザー」「トライアルユーザー」など別々のプロトペルソナを検証材料にするのも手です。
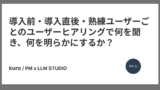
プロトペルソナを使った実践ステップ
ステップ1:仮説ユーザー像を複数用意する
初期段階では、どのユーザー層に刺さるか分かりません。リブランディング時でも「全員を狙う」はだいぶ危険。そこで複数の仮説ユーザー像をサクッと描いてみます。
1ペルソナ5分以内で、最もそのドメインに詳しかったり、最もユーザーと対話している人に書く権利があります。
- 既存の熟練ユーザー: 現行UIに慣れているが、不満もあるかもしれない
- ライトユーザー: たまにしか使わないがブランドイメージを気にするタイプ
- 新規参入層: 他社から乗り換えてくるユーザー像(競合比較が前提)
※もちろん、フェーズ以外にデモグラやサイコグラフィックで作成したり、クラスタ的なものを置いたり、実際にいた複数のユーザーを置いてみるのもありです
スライド1枚でOKで、「年齢/職業/利用動機/技術リテラシー」など基本情報を超ざっくりまとめ、チームで「どの層がどんな課題を抱えていそうか」話し合います。
ステップ2:とっととインタビュー&プロトタイプ検証
仮説ユーザー像を設定したら、ユーザーインタビューや簡単なプロトタイプ検証へ。
- リニューアルの場合:既存ユーザーの一部を招いて、デザインモックやプロトタイプを見せる
- 新機能の場合:プロトタイプを使った早期ヒアリングを実施し、ニーズや使い勝手を探る
- リブランディングの場合:新しいロゴやUI、メッセージの印象をユーザーに聞き、「このブランドをどんな人が好みそうか」を質問
ここでも「本当にこの改修が“ジョブ”を解決するか?」という視点が大切。
ユーザーインタビューのやり方や、「筋の良い仮説」をチームで設定する方法も参照ください。
オンライン調査や生成AIを組み合わせ、GPTs Builderで動くデモを作ると検証スピードがさらに上がります。
ステップ3:データ分析&フィードバックを即時反映
インタビューやプロトタイプ検証で得たデータや反応を整理。
「どのプロトペルソナに近い人が多かったか」「価格設定やデザインへの感想は?」などを一気にまとめます。
チームで週1回くらいのペースでレビューし、プロトペルソナをアップデート。
もし必要なら、「当初想定したライトユーザー層ではなく、意外とヘビーユーザー層が新機能を待っていた」といった気づきに合わせて全体戦略を変える決断を行います。
大規模UX変更の場合は、ログ分析との組み合わせで精度がアップ。
実際の行動データを見ながら“定量×定性”の両面で検証すると、誤学習を減らせます。
よくある失敗と対処策:プロトペルソナ運用で陥りがちな罠
失敗1:いつのまにか詳細化しすぎる
リブランディングや新機能リリースで、つい一部のフィードバックだけでペルソナを作り込みすぎるリスク。
早期の手応えに寄りかかると、想定外のユーザーが出てきたときピボットが難しくなる
対策
「プロトペルソナは暫定」と文書化し、1〜2週間単位でレビューする仕組みを設ける。スライド1枚の量は絶対に超えず、文字サイズも11pt以上と決めましょう。
失敗2:検証サンプルが少なすぎて誤学習
インタビューを2〜3人で終わらせ「ほぼ確定!」は危険。
少なくとも5〜10人、できれば複数パターンのペルソナでインタビューやテストを並行実施。
対策
大規模リニューアルなら内部メンバーの協力も得て、オフライン・オンライン両方でサンプルを増やす。
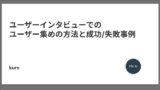
大企業でこそ使いたい理由:スピードとリスク低減の両立
大企業における大規模UX変更やリブランドでは、意思決定者が多い分、プロジェクトが遅延しがちです。しかしプロトペルソナなら、「これは暫定のターゲット設定なので、失敗してもダメージ小さめ」と説明しつつ、小さな実験を繰り返せます。
社内承認を得る段階でも、短期検証 → データ報告 → 次のステップという形を推し進めやすいです。大きな予算を投下する前に、ユーザーニーズの確からしさを素早く見極められる点が、大企業ほど有用。
今日から実践できるアクション
- 1. 仮説ベースのユーザー像を複数並べる:
リブランディングでも新機能開発でも、1つのペルソナに固執せず3パターン程度比較検証。「筋の良い仮説」の設定も参考になる - 2. 5~10名のインタビューを最低限確保:
新規事業・既存サービス問わず、ユーザーインタビューは必須。ユーザー集めの方法やオンライン調査など柔軟に併用 - 3. 小さなプロトタイプを用意:
プロトタイプ×ユーザーインタビューで早期フィードバックを得る。大規模改修でも全ページを作らず、要所だけモックを作る - 4. 定期レビューでプロトペルソナを更新:
スプリントやQごとに「想定ユーザー像はどこまで合っているか」を議論し、毎回アップデート。ログ×インタビュー分析で裏付けを取る - 5. 社内合意形成を加速する:
「大きく投資する前に小さな検証でリスクを下げる」というメリットを強調。経営層や上司を巻き込みやすくなる
Q&A
Q1. 作り込み型ペルソナではダメなのか?
A. 初期の不確実性が高いときは作り込みが逆にリスクに。新規事業やリニューアルでまだユーザー像が読めないなら、まずはプロトペルソナで小さく学習を回す方が合理的です。Q2. プロトペルソナはどうやって卒業すればいい?
A. ユーザーインタビューやログ分析で「実際のセグメントと一致してきた」と判断した段階で、本ペルソナに移行します。それまでは“仮設”として何度でもアップデートを。Q3. 大企業で承認を取りにくい場合は?
A. 「最小限の実験で失敗・学習を繰り返す」仕組みを社内に理解してもらう。インタビュー結果の見せ方や実証プランを資料化し、短い検証サイクルで進める旨を強調すると通りやすいです。
参考情報
- Pruitt, J. & Adlin, T. (2006). The Persona Lifecycle. Morgan Kaufmann.
- Ries, E. (2011). The Lean Startup. Crown Business.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. John Wiley & Sons.
- ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド
- ユーザーインタビュー前に「筋の良い仮説」をチームで設定する具体的な方法やフレーム
- ユーザーインタビューでのユーザー集めの方法と成功/失敗事例
- プロトタイプを使って、ユーザーインタビューで新機能の検証を行う方法・Tips
- 経営層・上司・メンバーを動かすユーザーインタビュー結果の見せ方・使い方
- GPTs Builderでプロトタイプをすることで、仮説検証を高速にする
- ログ分析→ユーザーインタビューの流れで、「本当に解くべき課題」を明確にする
- 導入前・導入直後・熟練ユーザーごとのユーザーヒアリングで何を聞き、何を明らかにするか?
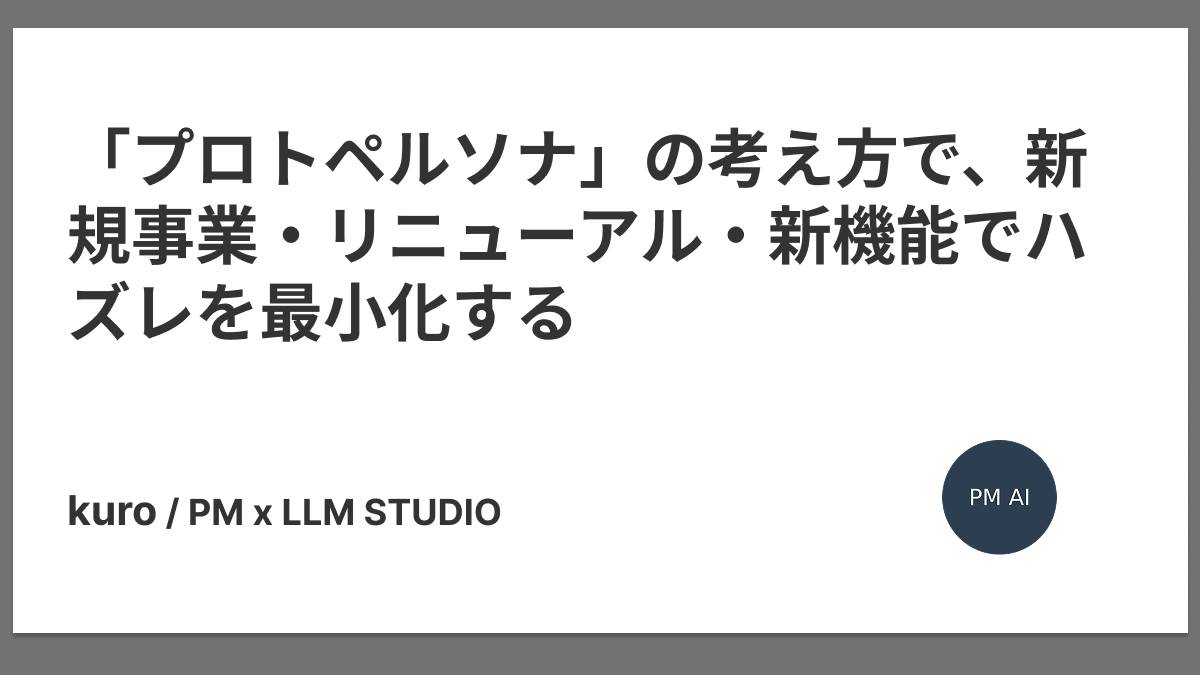

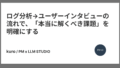
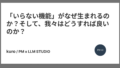
コメント