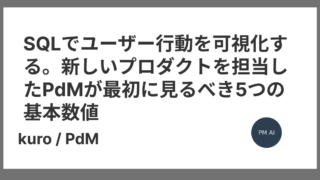 キャリア
キャリア SQLでユーザー行動を可視化する。新しいプロダクトを担当したPdMが最初に見るべき5つの基本数値
この記事の要約 PdMが自らSQLを操ることは、エンジニアへの依存を脱却し、憶測ではない「事実データ」に基づく迅速な意思決定と合意形成を可能にする武器になる 分析の第一歩は複雑なクエリを書くことではなく、データベースのスキーマ(構造)を理解...
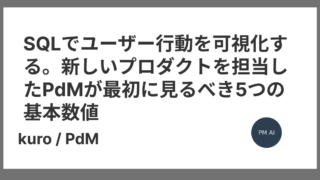 キャリア
キャリア  ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 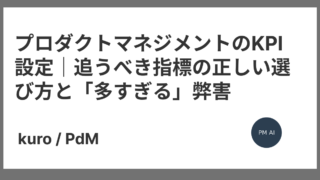 プロダクト推進
プロダクト推進 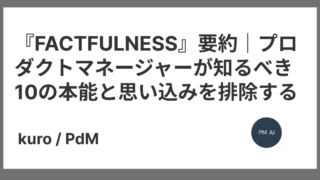 PM関連本
PM関連本  ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 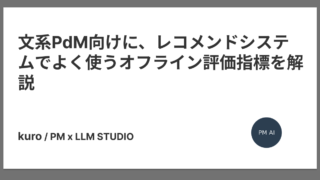 プロダクト企画
プロダクト企画 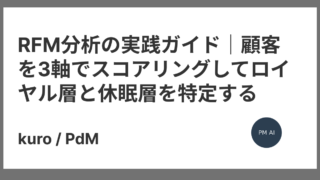 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 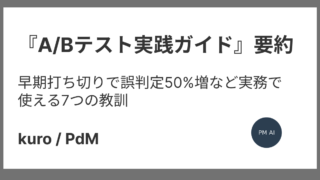 プロダクト推進
プロダクト推進 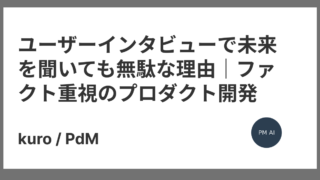 プロダクト企画
プロダクト企画 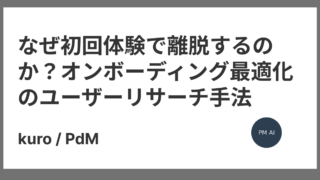 プロダクト企画
プロダクト企画 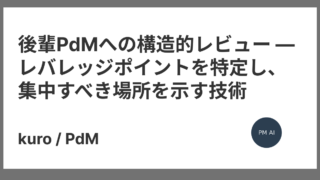 プロダクト企画
プロダクト企画 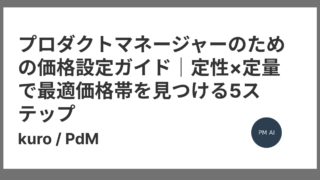 プロダクト推進
プロダクト推進 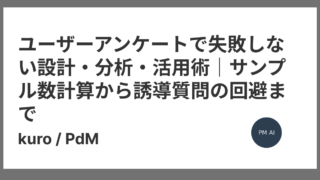 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 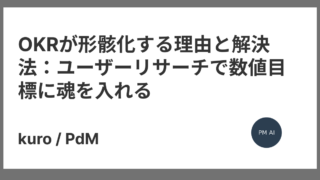 プロダクト推進
プロダクト推進 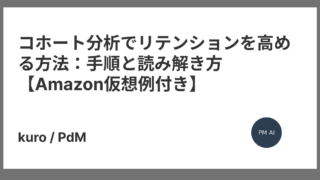 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 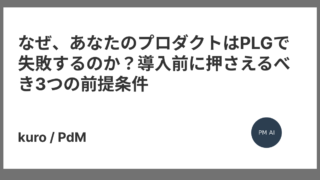 プロダクト推進
プロダクト推進 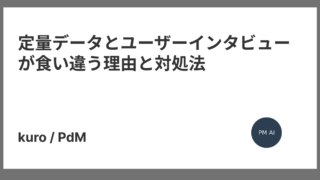 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 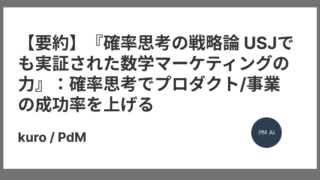 PM関連本
PM関連本 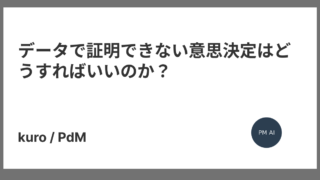 プロダクト企画
プロダクト企画 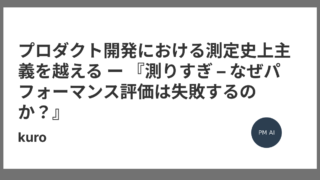 PM関連本
PM関連本 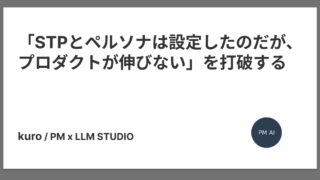 プロダクト企画
プロダクト企画 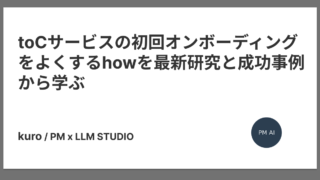 プロダクト企画
プロダクト企画 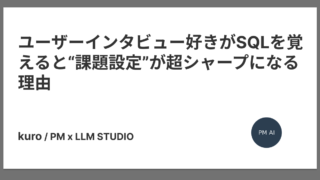 プロダクト企画
プロダクト企画