この記事の要約
-
マーケター出身PdMが成功する鍵は、プロモーション思考を捨て、顧客の潜在課題を発見する「インサイト洞察力」をプロダクト開発の最上流で発揮することにある
- 技術知識の不足は致命傷ではない。エンジニアが持っていない「ユーザー視点」と「Why(なぜ作るか)」を言語化する力こそが、開発チームにおける独自の武器となる。
-
「Product(製品)」作りに関わることは、単なる職種転換ではなく、マーケターが本来の「4P」を統合し、市場価値の高いプロダクトリーダーへと進化するキャリア戦略である。
「マーケターからプロダクトマネージャーになれるのか?」
「マーケター出身のプロダクトマネージャーだけど何を武器にすればいいんだろう?」
マーケター、もしくはマーケ出身のプロダクトマネージャーでこのように思っている方も多いのではないでしょうか?
本記事では実際にマーケターからプロダクトマネージャーに転身した僕の経験を元に、マーケ出身のPdMならではの強みや弱み、そして具体的なムーブをまとめています最後まで読んでいただければ、「マーケ視点を持つPdMがプロダクト全体にどうインパクトを与えられるのか」が見えてくるはずです。
マーケターからPdMへのキャリアチェンジ
僕は最初、博報堂で3年半マーケターとしてキャリアを積みました。クライアントワークを通じて、主にtoC向けのマーケティング施策に携わり、合計10社以上のブランドやサービスのプロモーション戦略を担当。
そこでは4Pのうち、特に「プロモーション」に深く関わる機会が多く、KPIを達成するためにデータマーケティング中心に広告費の最適化やキャンペーン企画などを行っていました。
ただ、そのうち「広告をどれだけ打っても、プロダクト自体が本質的にユーザーの課題を解決していなければ、長期的な成長には繋がらない」という思いを抱くようになりました(クライアントワーク x プロモーション領域中心だったのもあり)。
実際にクライアントの売上を伸ばす中で、「もっとプロダクトそのものの改善に踏み込めれば、マーケの施策だけに頼らない持続的な成長ができるのに」というもどかしさが強まっていきました。そして、そもそもマーケティングとは本来4Pに「Product」が含まれるようにプロダクトまでが守備範囲であり、当時の僕はプロダクト改善に踏み込めないもどかしさを感じていました。
そこで、社内異動のタイミングで、まずは博報堂の中でプロダクトマネージャーポジションへ挑戦。その後、自分でwordpressで教育系のサイトを作ったり、副業でtoCスタートアップのCOO兼PdMを2年ほど経験したり。さらにリクルートへ転職してHR領域のプロダクトを担当するようになりました。「マーケの視点を活かしながら、プロダクト全体の成長へコミットする」。このスタンスを貫いてきたのが、僕がPdMとして歩んできたストーリーです。
マーケター出身のPdMが持つ強み
マーケターとしての経験はPdM業務を進める上で大きなアドバンテージになると思っています。ここでは特に大きい強みとして、(1)ユーザー目線、(2)データ分析力、(3)ブランディング思考/市場理解、そして(4)グロース視点の4つを挙げてみます。
(1)ユーザー目線
マーケティング活動の本質は「ユーザーが本当に何を求めているか」を洞察すること。僕は博報堂時代から、ユーザーインタビューやデータ分析を重ねることで顧客の課題やインサイトを読み解いてきました。このスキルはPdMとしても本当に役立っています。
たとえば新機能のアイデアを検証するとき、インタビュー設計の段階からユーザー心理を深掘りしやすいのです。より詳しいインタビューの進め方は、ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイドも参考にしてください。
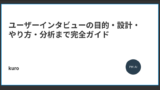
(2)データ分析・セグメンテーション
マーケティングの世界では、A/Bテストやセグメント分析が日常茶飯事。たとえば広告素材やランディングページのCTR(クリック率)を比較し、どのペルソナにどう訴求すれば最も効果的かを検証します。
PdMでもユーザー行動ログの分析やABテストを多用しますが、マーケ出身ならデータ分析設計および量的なデータを中心に、データを多角的に見る視点がすでに染みついているはずです。
(3)ブランディング思考・市場理解
プロダクトの差別化ポイントやポジショニングを明確にする上で、ブランディングや競合分析は重要。マーケター時代に培った「市場を俯瞰して強みを打ち出す」視点があると、プロダクトコンセプトやメッセージを考える際に強みを発揮できます。
実際、僕は博報堂でも市場調査や競合ベンチマークなど、3Cの視点を中心に何度も何度も分析を行なって、対象プロダクトやサービス、製品のコンセプトを定義するタスクを頻繁に行ってきました。その経験は、プロダクトのポジショニング設計にも活きています。
(4)グロース視点
マーケ活動は認知獲得からリテンション施策に至るまで、ユーザーのライフサイクル全体を俯瞰します。同様に、PdMもプロダクトリリース後のユーザー定着を見据えた「継続的な成長戦略」を考える必要があります。マーケター出身なら、キャンペーン設計やプッシュ通知、メールマーケティングなど具体的な施策アイデアを豊富に持っているため、リテンション向上策をすぐに打ち出すことができるのです。
マーケター出身のPdMが陥りやすい弱み
もちろん、マーケ出身であるがゆえの落とし穴も存在します。ここでは主に、(1)技術バックグラウンドの不足、(2)他部署との連携不足、(3)短期指標への偏重の3つを挙げます。
(1)技術的バックグラウンドの不足
エンジニアリングの知識が薄いと、開発チームとのコミュニケーションや見積もりの精度に影響が出ます。たとえば新機能を企画しても、「実装難易度が極めて高い割にリターンが少ない」仕様になってしまう場合があります。
僕自身、初めて副業スタートアップでPdM兼COOを担ったとき、エンジニアから「その機能を作るなら他に影響が大きい」というフィードバックを受けて学ぶ機会が多々ありました。
こちらの書籍はwebサービスを支える技術を網羅的に理解できるのでおすすめです(自分が技術的な問題に対してアレルギーを発症しないか?をチェックする一冊としても)。
(2)営業やCSなど他部署との連携不足
マーケ視点だと、どうしてもユーザー獲得やコンバージョン向上を優先しがちです。
しかし、プロダクトの営業担当やカスタマーサクセス(CS)は、別の指標やオペレーションを大切にしていることが多いもの。そこに目が向かないと、営業プロセスの現実や顧客サポートの実態に即した施策が打ちにくくなります(特にBtoBの場合)。
(3)長期視点より短期的数値に偏りがち
広告効果やキャンペーンの成否は、どうしてもCVRやCPAなど短期指標 x キャンペーン単位の短期サイクルで評価しやすい傾向があります。
マーケター出身のPdMは、ついつい目先の売上やインストール数に意識が行きがち。しかし、プロダクトの中長期的な方向性や、大胆なアップデートの必要性を見落としてしまうリスクがあります。開発ロードマップの長期視点を持ち、バランスを取ることが重要です。
プロダクト開発の基本ムーブ:マーケスキルの活かし方
マーケター出身のPdMがプロダクト開発を進める際、どのような動き方をすると強みを最大限に発揮できるのでしょうか?
ここでは(1)ユーザー課題の明確化 (2)プロダクトビジョン策定 (3)MVP・プロトタイプ検証 (4)ローンチ後のグロース施策の4フェーズで考えます。
(1)ユーザー課題の明確化
マーケティングの強みである「顧客を深く知る」アプローチを、まずは徹底的に活かすべきです。
- 質的インタビュー
- アンケート
- データ分析
などで、どんな課題・ニーズが潜んでいるかを徹底的に追い込みます。
僕自身、仮説を立ててからインタビューを行うときは「ユーザーインタビュー前に『筋の良い仮説』をチームで設定する具体的な方法やフレーム」に記載した考え方で進めています。マーケ出身だからこその顧客理解の圧倒的な深さと、顧客解像度を上げるスキルや経験があるはずです。

(2)プロダクトビジョン策定
プロモーションの経験があると、「作ったプロダクトや機能がユーザーにどうイメージされたいか?」というブランド視点を持ち込みやすいです。
たとえば「どの市場で、どんなユーザーに、どんな価値を提供するか」を言語化するとき、マーケ的なコピーライティング含めたベネフィット表現が役立ちます。ここに開発チームのフィードバックを加え、実現可能性と差別化要素をすり合わせる形でビジョンを固める流れが理想です。
(3)MVP・プロトタイプ検証
マーケターはA/Bテスト文化に慣れているため、機能の肝となる部分を小さく作り、すぐにユーザーの反応を確かめる“MVP思考”に馴染みやすい傾向があります。
UIデザインをv0、Lavable、codeXなどでいくつか用意して、「クリック率」「滞在時間」「登録率」など具体的な指標を設けて検証するといったプロセスが典型例です。短いスプリントでPDCAを回す手法は、Lean Startup(Eric Ries, 2011)の概念にも通じます。
(4)ローンチ後のグロース施策
リリース後はマーケティングで学んだリテンション施策が真価を発揮します。
- プッシュ通知
- メール施策
- SNSキャンペーン
- オンライン広告
- TV CM
またそれらの連動施策など、多様な集客チャネルを組み合わせながら、ユーザーを再来訪・継続利用へと導く。KPIとなるリテンション率やLTVを追いつつ、プロダクトのフィードバックループを形成します。
副業で習慣化アプリを提供するtoCスタートアップをやっていた時のPdM実体験
ここからは、僕が副業でCOO兼PMを担当したtoC向け習慣化アプリの例を紹介します。マーケ出身だからこそ役に立った局面と、苦労した局面を3つの事例で振り返ります。
事例1:ユーザーインタビュー200人の知見から得たUI改善
習慣化アプリは「ユーザーがどんなモチベーションで継続しているか」が極めて重要です。僕はリリース初期から徹底的にユーザーインタビューを実施し、わかりやすいもので言うと
- 「目標のハードルが高すぎると挫折する」
- 「裏切れない顔の見える人と一緒に取り組むと継続しやすい」
- 「人の習慣化のサポートは自分の習慣化よりも必死になる」
といった生の声やインサイトを集めました。その声を踏まえてUIにチェックリスト形式の達成度表示を導入したり、家族でグループを組める機能を導入したり。
結果、ユーザーのリテンションでapp storeのトップ5%タイルに入ることができました。このプロダクトだけで、僕は200人以上自分自身でユーザーにインタビューをしています。
事例2:ローンチ時のPR戦略とリテンション施策の両立
初動でアプリを盛り上げるために、PR TIMESにPR記事を投稿したり、機能追加時にも同様にPRリリースを出したりしました。加えて、複数メディアへの掲出などメディアマーケティングの知見も生かしていました。
これらの施策はマーケターとしての経験が活きた場面です。一方で、導入ユーザーの継続利用を高めるため、アプリ内のガイドツアーやプッシュ通知によるフォローも同時に行いました。
事例3:エンジニアやデザイナーとのコミュニケーションギャップへの対処
一方、僕が最初に躓いたのは、エンジニアとデザイナーの要件調整です
マーケ思考で「あれも実装したい、これも入れたい」と要望を詰め込んだり、どこまでをエンジニアに用件定義としてパスすべきかが曖昧で、超スモールチームのリソースを現実的に捉え切れていなかったのです。
そこで失敗を繰り返したり、書籍を100冊近く読んだり、エンジニアやデザイナーと飲みに行ったりしながら学んだのが以下のようなことでした。
- 「技術的難度を把握しつつ、優先度を明確化するフレームワーク」
- 「プライドを捨ててエンジニアに教えを乞う”助けてもらう精神”の重要性」
- 「“しょうがいないからこいつを助けてやるか”と思ってもらえるようなビジョンの伝達と熱量を行動を伝える重要性」
タスクのスコープやインパクトを視覚化し、チームで優先度をスプリント単位で合意形成し、さらに実際に自分でフロントの機能を実装してみることでこの課題を解消しました。
マーケター出身PdMの価値と今後の展望
マーケター出身のPMは、ユーザーへの共感能力とデータドリブンな施策構築力を兼ね備えている点が大きな武器だと感じます。
- 市場を客観的に分析し、
- ブランド価値を高める視点を持ちつつ、
- 実際にユーザーが使いたくなる機能やUIを顧客起点で考え抜くことができる
しかし一方で、技術面や他部署との連携など、新たに学ばなければならない領域も多々あります。短期的な数値成果を追いかけることは必要ですが、同時に中長期的なプロダクト戦略や開発計画を俯瞰する視点も欠かせません。
僕は今後、生成AIの活用などによりマーケティングとプロダクト開発の境界はますます薄れていくと予想しています。ユーザーインタビューやデータ分析、そして市場全体を見渡すマーケの知見は、プロダクトの“本質的な価値”を磨き上げるためにますます重要になるはずです。マーケ出身だからこそ描ける未来予想図を持ちつつ、プロダクト全体を伸ばしていくPdM像を追求していきたいと思います。
マーケ出身のPdMの方やPdMになりたいマーケの方、ぜひお話ししましょう!(ぜひお気軽にXにDMください!お話ししましょう!)
参考情報
- Eric Ries (2011). The Lean Startup. Crown Business.
- Marty Cagan (2018). INSPIRED: How to Create Tech Products Customers Love. Wiley.
- Geoffrey A. Moore (2014). Crossing the Chasm. Harper Business.
今日から実践できるアクション
- 優先度フレームワークの導入
マーケ視点で機能要望が増えすぎないよう、ICEスコア(Impact, Confidence, Ease)やMoscow法などを使い、開発チームと一緒に優先度を明確化する。 - ユーザーインタビューの型を整理
これまでマーケ調査で使っていた質問項目を、プロダクト改善に直結する形にアップデート。必要であれば「ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド」も参照して、体系的なインタビュー設計を行う。 - 長期視点を意識したOKR運用
短期的なCVRやMAUだけでなく、3ヶ月先・半年先を見据えたOKR(Objectives and Key Results)を設定。マーケ施策と開発ロードマップをつなぐ形で運用する。
Q&A
Q1:技術の知識が足りないのですが、どこから学べばいいですか?
A1:基礎的なプログラミングの勉強や、エンジニアとの1on1ミーティングなどで学習すると効果的です。また、スクラム開発やアジャイル手法についての理解も同時に進めると、チームと共通言語を持ちやすくなります。僕は技術系の書籍を合計100冊以上は読んでいます。
Q2:マーケターからPMになって、どのようにチームをリードしていくべきでしょうか?
A2:ビジョンを明確に言語化し、ユーザーにどんな価値を届けたいのかを常に共有することが大切です。マーケティングの得意分野を活かしつつ、開発やCS、営業と連携するための“場”を定期的に設けるとスムーズな連帯感が生まれます。
Q3:短期指標と長期戦略をどのようにバランスさせればいいですか?
A3:四半期ごとのKPIに加え、半期や1年スパンでのロードマップを設定しておくと良いです。OKRなどの枠組みを活用し、短期目標と長期目標を紐付けて可視化することでバランスが取りやすくなります。
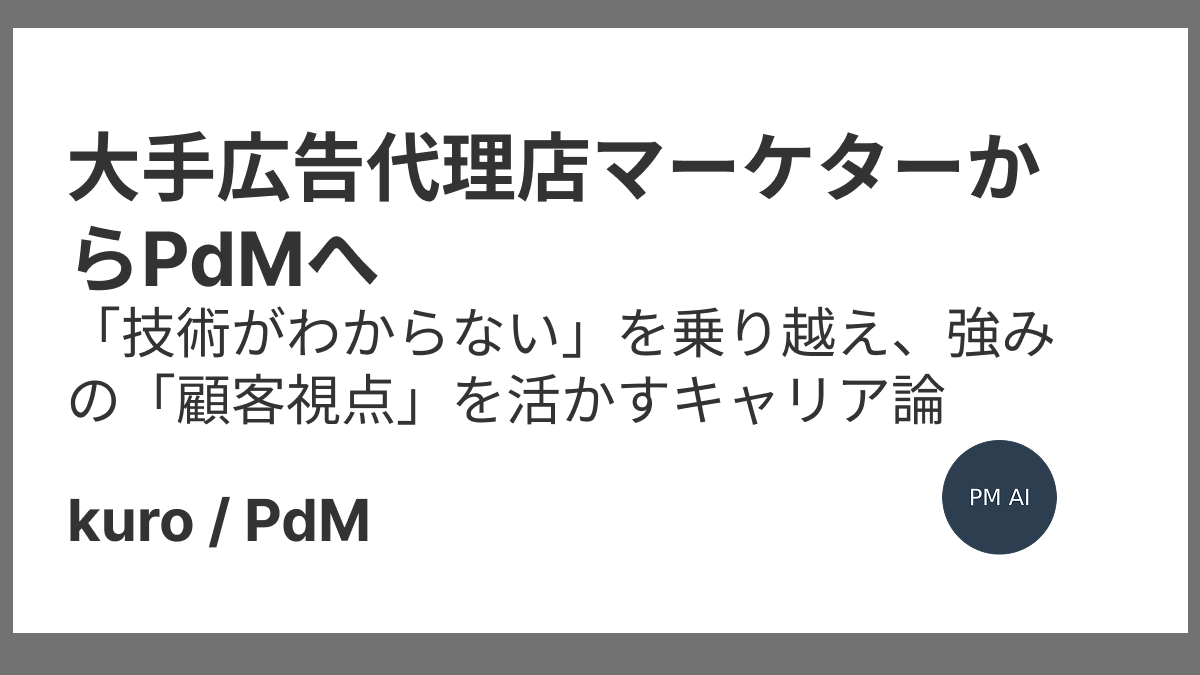


















コメント