「インサイト起点の成功事例として語られているプロダクトのインサイトが、当たり前に見えてしまう」
「ユーザーインタビューで得たインサイトが、どうにも当たり前すぎて拍子抜け」
と感じたことはありませんか?
僕自身、数多くのユーザーインタビューを行ってきましたが、「これはごく普通の課題だよな」と見落としかけた声が、実際にはプロダクトの根幹を形作るケースがあると思っています。ありきたりに見えるインサイトでも、そこに一貫した“ストーリー”が紐づけば、強力な競争優位や事業成長につながり得るからです。
本記事では、「当たり前」に見えるインサイトがなぜ大きな可能性を秘めているのか、という点について『ストーリーとしての競争戦略』(楠木 建 著)が提唱する“ストーリーの一貫性”を交えながら解説します。
こんなのがインサイト?
ユーザーインタビューを分析して、いざ発見したと思えるインサイトが特に目新しさがなくありきたりに見える時、「もうみんなが言ってるし特別な発見ではないのでは?」と思いがちです。僕も累計600名以上をインタビューしてきましたが、「当たり前すぎない?」と感じた声は多々ありました
ただ、その“ありきたり”が実際には競合他社が解決できていない本質的課題だったりします。本質とは往々にしてシンプルで、だからこそ多くの人が知りつつも対策を後回しにしていたりします。ここにこそ、事業成長のヒントが潜んでいるのです。
楠木 建氏の『ストーリーとしての競争戦略』では、「優れた戦略には首尾一貫した物語がある」と説かれています。どれだけ”ありきたり”に見えるインサイトでも、それを核にストーリーの整合性を高めれば、差別化や競争優位の源泉になり得ます。要するに、“当たり前”に見えるインサイトも、ストーリーのつなぎ方次第でまったく別の価値に化けるということです。

有名プロダクトにみる“ありきたり”インサイトが花開いた3事例
ここでは、世の中に広く認知されているプロダクトが、ユーザーの「当たり前」な声を活かして成長した具体例を3つ挙げます。それらがどのようにストーリーと結びついていったかも併せて考察します。
① Instagram:写真を気軽に加工・共有したい
Instagram(当初の“Burbn”)誕生の背景には、「加工アプリが難しくて面倒」「フォロワーと写真をやりとりしたい」というシンプルなニーズがありました。写真共有自体は既存のSNSやアプリでも可能でしたが、Instagramは加工をワンタップで完結させるというストーリーを軸に、操作性・見た目・コミュニティ感を一貫して作り込みました。
ユーザーから見ると「写真を共有したいのなんてみんな思っている」という当たり前の声が、「ワンタップで写真がおしゃれに変わる」「アップロードしたらすぐ反応が返ってくる」という価値のストーリーに結びつき、世界的SNSへ成長したのです。
② Slack:メールの煩雑さをなくし、チームとすぐ話したい
Slackがビジネス向けチャットツールとして急成長したのは、「メールが面倒、すぐ答えを得たい」というユニバーサルな不満を軸に、検索性や連携サービスの充実、心地よいUIを一貫したストーリーとして実装したからです。
既存のツールでもチャット機能はありましたが、Slackは「仕事の情報はスレッドやチャンネルで整理し、いつでも検索できる」というストーリーを明確に示しました。ありきたりに見える“メールを減らしたい”という願望を、エモーショナルかつ合理的な体験に変えたところが勝因です。
③ Netflix:好きなときに好きな動画を観たい
NetflixがDVD郵送サービスからストリーミングへと一気に移行したときの根底には、「DVDを返却するのが面倒」「自由な時間に映画を観たい」という、こちらもありきたりな声がありました。それを真摯に受け止め、「視聴者一人ひとりが選びたいときにすぐ視聴できる」というストーリーをデザインし直し、世界的プラットフォームへと拡大しました。
これらの事例に共通するのは、ユーザーの声自体は平凡だという点です。しかし、それを自社プロダクト全体のストーリーへ落とし込んだことで、他社にはない整合性や体験価値を生み出し、競争優位を確立しました。まさに楠木氏が強調する「首尾一貫した物語」が事業成長の土台となったわけです。
「当たり前じゃね?」と思う感想の危うさ
インタビューやユーザーテストで得られる声について、「それは当たり前」だと感じたら、むしろ要注意です。その裏には、強固なニーズと潜在的な伸びしろが眠っている可能性が高いからです。
実際、ありきたりなインサイトであっても多くの企業が着手しきれていない現実があります。誰もが知っていても解決策が見出せていない、あるいはリソースや優先度の問題で後回しになっている。だからこそ、“当たり前”の声をいち早く吸い上げ、徹底的に磨き込んだ企業が市場をリードできます。
また、人間の認知バイアスの一つである「ハインドサイト・バイアス(後知恵バイアス)」も影響します。成功した後には、「そんなの最初からわかってたよ」と思いがちですが、成功前にその価値を発掘して、全社的なリソース配分をできる企業は意外と多くありません。
楠木氏は『ストーリーとしての競争戦略』で「優れた戦略は、単なる発見を大きな物語として組み立てるプロセスが不可欠」と述べています。すなわち、初見では瑣末に思えるユーザーの声こそ丁寧に拾い上げ、そこから物語を編み上げることが差別化の源になるわけです。
いいインサイトの条件:ストーリー性が鍵
ありきたりに思える発見でも“いいインサイト”になる条件は何か。僕の経験と、楠木氏の「ストーリーとしての競争戦略」の知見を組み合わせると、以下のポイントに集約されます。
1 / 行動変容をもたらす
インサイトをもとに施策を行ったとき、ユーザーが実際に行動を変えてくれるか。変化が起きるレベルならば“当たり前”と侮れない
2/ プロダクトや事業の方向性と整合する
組織が目指すビジョンや方向性と矛盾がなく、むしろ深める役割を担う。ストーリーが一貫しているかどうかが重要
3 / シンプルかつ強固である
複雑でコピーライティングされたおしゃれな文章で構成される仮説より、誰が聞いても理解できるシンプルな着眼点のほうが社内外で合意形成しやすい。シンプルが強力
ありきたりに見えるインサイトほど、実は多くのユーザーが共通して抱えている可能性が高いです。そしてそれをビジネス上で突き詰めるためには、「一貫した物語を築きあげる」「競合もやっているかもしれないけどそのインサイトにフルベットする」ことが必須になります。物語の要素が欠けていると、「分かるけど何かピンと来ない」という曖昧な施策に留まってしまいがちです。
どうやって当たり前のインサイトを“ストーリー”で捉えるか
「本当にシンプルな要望や課題を、どうやって物語として構築すればいいの?」という疑問もあるでしょう。以下に、よく使うアプローチを4つ紹介します。
1. ユーザーインタビュー × 観察で“ファクト”を捉える
例えば“UIがわかりにくい”という声だけではストーリーになりません。そこに「どんなユーザーが、どんな状況で、なぜ使いにくいと感じるのか」を詳細に描写し、ファクトを把握するのです。
エスノグラフィー的な視点でインタビューや観察を行い、ユーザーの日常や心理を深く知ることで、「○○さんは業務の合間にしかこの機能を触れない。だから数秒の手間でもストレスになる」というように具体的なファクトに基づいた考察を行えるようになります。


2. 定量データを“起承転結”に落とす
ストーリーには起承転結が必要です。ログ分析やアンケート結果を見つつ、
- 現状(起)
- 問題や課題の発生(承)
- 解決策の取り組み(転)
- 結果・変化(結)
と時系列で並べると、当たり前のインサイトでも流れができてきます。
この時、ユーザーが抱える課題の“大きさ”や“頻度”を定量データで示すと説得力が増すため、エンジニアやデータ分析チームと協力して数字を集めることが効果的です。
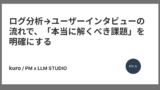
3. シンプルな機能改善を小さくリリースして検証
「こんなの当たり前だし、本当に効果あるの?」と社内で言われた場合は、ABテストや小規模リリースで実際に検証するといいです。小さな成功体験が生まれれば、それが“転”の部分を証明する事例となり、一貫した物語(成功パターン)が社内に共有されやすいです。
「当たり前のインサイトを拾って小さく試す」というプロセス自体が、リーンなアプローチとしても非常に有効です。

4. 社内共有時に“ストーリー”を具体的に演出する
楠木氏は著書の中で、“内部説得”でのストーリーテリングの重要性にも触れています。社内共有の場では、ユーザーの具体事例や感情を交えながら物語として語ると理解が深まります。
実際、僕も「○○さんはこういう日常を送っていて、こんなときにサービスを使う。そのときにあまりにも画面が複雑で離脱してしまう…でもここを改善すると○○さんは喜んで使い続けてくれる」といった形で説明します。すると「確かにそれは直してあげたいね」という共感が生まれやすいです。

参考情報
- 楠木 建 (2010). ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件. 東洋経済新報社.
- Ries, E. (2011). The Lean Startup. Crown Business.
- Stanford Graduate School of Business. (2018). Research on iterative user feedback and product success.
- 「顧客インサイト」を理解した上で、発見し活用する
- ユーザーインタビューで「非言語情報」から「本音」を見抜く観察手法
今日から実践できるアクション
- “どんなストーリーに接続できるか”を考える
既存のプロダクト戦略やビジョンと、ありきたりインサイトがどのように噛み合うかを明文化する。ピースをはめ込むように、一貫性を作り上げる - 社内外の意見を拾い、ストーリーの整合性を更新
リリース後のデータやフィードバックで新しい発見があれば、ストーリーをアップデートする。常に一貫性を保つために、継続的な見直しを怠らない
Q&A
- Q1: インサイトをストーリー化するコツはありますか?
- ユーザーの具体的な行動・心理を時系列で描くことがポイントです。加えて、“起承転結”のように問題発生→施策実施→結果・解決へと流れを設計し、それをビジュアルや図表で見せると社内説得がスムーズになります。
- Q2: インサイトを発掘しても、経営層が「当たり前すぎる」と却下してきます……どう説得すれば?
- “当たり前”だからこそ影響度が大きい可能性を定量データで示すと良いです。ユーザーの何%がその課題に該当し、どのくらい離脱に繋がっているかなど、ビジネスインパクトを数字で可視化すれば、社内合意を得やすくなります。また、小規模での成功実験を見せるのも有力です。
- Q3: ストーリーを作っても、施策が多岐にわたるとブレそうです……
- 楠木氏の言う「首尾一貫した物語」は、すべての施策が根本の“核”に繋がっている状態を指します。施策が増えても、“コアバリュー”や“プロダクトの世界観”を明確にしておき、定期的に点検することでストーリーの整合性を保つことができます。
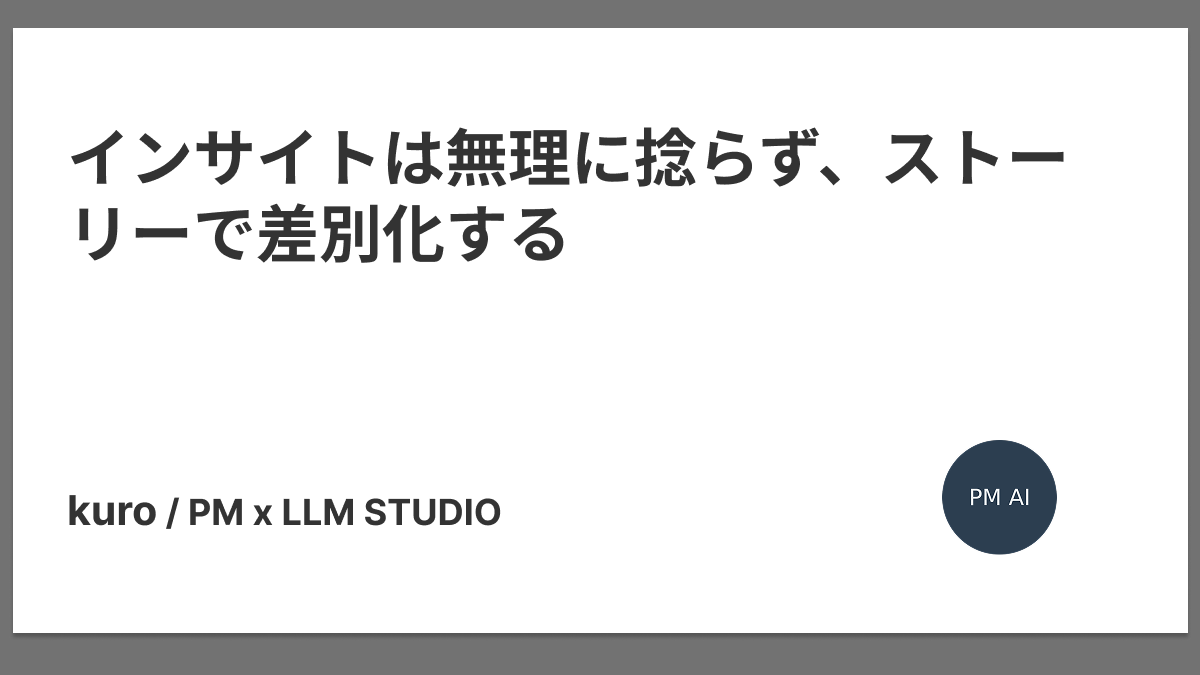

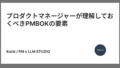
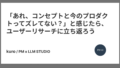
コメント