この記事の要約
- 「自分の希望を叶える完璧な活躍の場」を組織が用意してくれると思うのは幻想
- 組織都合や情報ギャップを埋めるには「実績作り」「明確な主張」「勝手にやる」「場を移す」が必須
- PdMとして自分の価値を高め、主体的に活躍の場所を切り拓く
「上司や組織が“自分の経験・スキル・希望”をしっかりくみ取って、ピッタリ合う環境を整えてくれるのではないか?」
これは、まあ幻想ですよね、、。たしかに理想は、上司が自分のスキルを認め、やりたい領域や希望のキャリアに寄り添って、完璧なポジションやプロジェクトをアサインしてくれること。でも現実には、組織全体の都合や情報ギャップなどから思うような配置にならないことも多々あります。
米国Gallupが発行した2022年のグローバル職場調査によると、世界的に見ても「自分の仕事が活かされている」と高く評価している従業員の割合は約2割という結果が出ています。多くの人が「自分はもっと違う形で活躍できるのでは」と悩んでいるのが現状です。
しかし、そこで立ち止まって嘆いていては、自分とプロダクトの成長が止まってしまう。そこで、本日では4つのアクションを紹介します。
なぜ「上司が完璧な場所を用意してくれる」は幻想なのか?
まずは、その「幻想」が生まれる背景と、なぜ幻想に終わりがちな理由を整理します。
- 組織都合:チーム編成はリソース配分や経営指標など、個々の希望だけで決まるわけではない。例えば、緊急で対応すべき障害対策プロジェクトに最適なエンジニアが不足している場合、PdMも含めて様々な人がそこに投入される
- 評価と情報のギャップ:上司があなたのスキルや成長意欲を正しく理解していないケースも多い。定期面談や1on1の回数が少なかったり、プロジェクトレビューの機会が十分になかったりと、単純に情報不足な場合も珍しくない
- キャパシティ不足:仮に上司が優秀で「最適な配置」を考えようとしても、常に全メンバーに対して完璧なサポートができるわけではない。理想的な配置を考える前に、日々の業務に追われてしまうこともある
もしも「全員にとってベストな活躍の場所」を同時に用意できる組織があるのなら、そこでは誰もが高いモチベーションを維持し、結果的に“爆裂成長”を遂げるでしょう。ですが、そんな組織は稀であり、多くの場合はギャップや歪みが生じます。そのとき、どう動くかでPdMとしてのキャリアやプロダクトへのコミットメントが変わってきます。
「活躍の場」を自ら切り拓く4つのステップ
では、環境や上司が必ずしも理想通りに動いてくれない中で、どうやって主体的に活躍の場を確保し、成長を加速していくのか?僕が考えている具体的な4つのアクションを紹介します。
1. 実績作り:小さな成功事例を積み重ねる
どんなに「自分は優秀だ」「もっと戦略フェーズに関わりたい」と言っても、周囲には実績として示さなければ説得力が生まれません。「自分の実績はまだないけど、やる気はある」というアピールだけでは限界があるのです。まずは今アサインされている領域や、小規模でも任されているプロジェクトで結果を出す。はい、めっちゃ正論ですがこれがベースだと思っています。
- 一見地味でも、OKRやKPIなどで数字をきちんと伸ばす
- エビデンスベースの改善提案を通す
- プロジェクト管理をきっちり行い、チームの信頼を獲得する
小さい成果が積み上がると、自分の主張に「実績」という裏付けがついてきます。PdMとしては自分の得意領域を最大限生かせる形で成果を出すことが重要。「ユーザーインタビューで知見を引き出すのが得意」ならば、今のプロダクトの課題を分析し、新施策で成果を出すとか、既存の課題の優先度を上げて解決に導くなど。“小さな成功の積み重ね”が周囲の眼を変え、自分の希望を通しやすくします。
2. 明確な主張:自分の希望・意図をわかりやすく伝える
上司や組織に「本当はこういう領域でチャレンジしたい」「こういうキャリアを目指している」と明確に共有できていますか? 多忙な環境の中、言わなくてもわかってくれる、察してくれる――そんな期待が叶うことはほぼありません。
- 「自分はこうしたい」
- 「こういう強みがある」
- 「こういう目的でプロダクトに貢献したい」
という意図を、短い言葉で端的にまとめて何度も伝えることが大切です。
例えば定例会議や1on1の場で、ドキュメントを用意するのも効果的。上司の反応が薄ければ、「今後半年でどう成長してほしいと思っているか」「どういう領域なら活躍できると考えているか」など質問を投げかける。
3. 勝手にやる:組織が与えないなら自分で作り出す
「やりたいことがあるけど、まだ権限が与えられていない」という場合も、まずは小さく動いてみることをおすすめします。たとえば、新機能のアイデアがあれば紙芝居形式や簡易プロトタイプでユーザーインタビューをして反応を集める。仮説を示すためのスライドを作ってチームに共有する。あるいはログ分析のレポートを自主的にまとめてみる。
現状の業務範囲を超えているからと言って、必ずしも止められるわけではありません。むしろ、PdMなら領域を少しずつ広げて、チームに新しい知見を提供し、自分の成長機会を作り出すという姿勢が評価されやすいです。最近は、生成AIツールの活用などでプロトタイプを作るハードルも下がっています。勝手にやってしまう勢いを示すことで、上司や周囲から「じゃあ任せてみよう」という流れが生まれるのです。
4. 場を移す:もし組織内で限界なら、転職や部署異動も視野に
どうしても自分の希望が通らないケースでは、思い切って場を変えることも選択肢になります。特にPdMは、業界や事業フェーズによって必要とされるスキルやプロセスが変わり、得られる経験値も大きく異なります。「いまの会社で修行を積むのも良いけど、違うプロダクトに携わった方が成長が早いかもしれない」と感じるなら、早めにアクションしても損はありません。
僕自身、以前勤めていた会社ではマーケ領域中心のキャリアを積んでいましたが、「新規事業を立ち上げたい」「PdMとしてUXリサーチを徹底的にやりたい」という希望が強くなり、思い切って転職を選択しました。結果として、今の環境ではユーザーインタビューをはじめとしたリサーチやUX改善に大きくコミットできています。
キャリアパスや転職について深く考える際は、【要約】『転職の思考法』でPMが自分の市場価値を確かめ、高めるも参考になるはずです。自分の強み・弱みを客観視し、自分が「活かされる場」を主体的に探す視点を得られます。
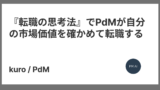
組織がすべて用意してくれなくても自分で動く時代
近年のプロダクト開発現場では、PdMが担う領域も幅広くなってきています。“こんなことまでPdMがやるの?”という部分に手を広げなければいけない場合も多い。逆に言えば、そこにこそ学びと成長の機会があります。組織や上司にすべてをセットアップしてもらわなくても、自分でプロダクトにインパクトを与えられる時代だからこそ、主体的に活躍の場を作る人が圧倒的に成長できるのです。
米国HBR(Harvard Business Review)が提唱している「自己決定理論(Self-Determination Theory)」の文脈でも、人が動機付けられるのは「自分がコントロールできている感覚」が大きいと言われています。上司が完璧に環境を整えてくれるのを待つのではなく、自分が主体的に動く。その過程で得られる自己効力感こそが、PdMとしてのキャリアを加速させます。
環境を嘆くより、自分を磨き続ける
「上司がスキル・希望・モチベを加味した完璧な活躍の場を用意してくれる」――その可能性がゼロとは言いません。ただし、組織には組織の都合があり、あなたの意図が必ずしも共有されているわけではない。全員が理想的な環境を手にできるほど、世界は甘くありません。だからこそ、“主体的に場を作り、価値を発揮する”行動が求められるのです。
実績で示し、明確に主張し、勝手に動いて、そのうえでどうしてもダメなら場を移す。これらをセットで考えていくことで、PdMとしても個人としても、長期的に高いモチベーションを維持しながら成長できるはずです。
今日から実践できるアクション
- 1on1でのアピール内容を明確化する
次回上司との1on1に向けて、「具体的に何をアピールしたいか」「どんなキャリア希望があるか」を箇条書きにして、短くまとめる - 小さな成功体験を増やす
担当領域のKPIやユーザーの声など、身近なテーマで成功事例を積み重ね、数値など事実ベースで共有する - 自主的な試作・検証
新機能や改善案が頭にあるなら、紙芝居やノーコードツール・AIツールなどを活用して、勝手に小さく実験する - 情報収集とネットワーク構築
自分の興味のある分野や部署の人に話を聞き、場合によっては部署異動や転職の選択肢を常にアップデートしておく
Q&A
- Q: 既存業務が忙しくて「勝手にやる」余裕がありません…
- A: すべてを完璧にこなすのは難しいですが、まずは週1時間でも時間を確保できないか試してみましょう。AIツールやノーコードツールで試作品を作れば、短時間でも意外と形にできます。また「業務の優先順位を少し変えてでも挑戦する価値がある」とチームに説明すれば、理解してもらえるケースもあります。
- Q: 上司が全く興味を示してくれない場合はどうすれば?
- A: 上司が興味を示す「ファクト」を用意することがコツです。例えばユーザーインタビューの結果や売上貢献のデータなど、ビジネスインパクトを数値で示すと、興味を持ってもらいやすくなります。それでもダメなら、さらに上の経営層や別のチームへのアプローチ、もしくは部署異動や転職など“別ルート”を検討する段階です。
参考情報
- Gallup. (2022). State of the Global Workplace 2022 Report
- Harvard Business Review. (2001). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. ※自己決定理論に関する研究
- Pink, D. H. (2009). Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. Riverhead Books.
- 「【要約】『転職の思考法』でPMが自分の市場価値を確かめ、高める」(https://pm-ai-insights.com/careerchange/)
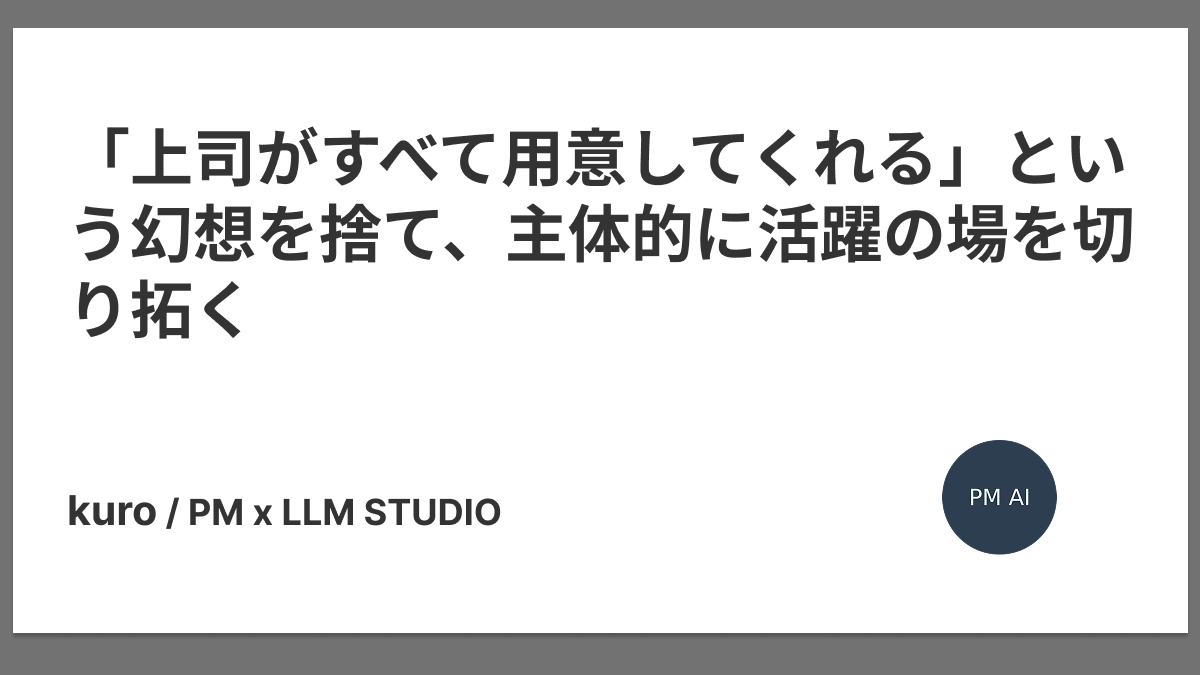
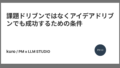
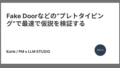
コメント