- 「泥臭い」実践が新規事業を強くする
- 少人数で始めるために、 外注すべきでない「コア領域」を決める
- 成功を引き寄せる「3つの力」 – Network・Execution・Knowledge
- 新規事業が失敗する最大要因は「誰も必要としないモノ」を作ること
- 顧客課題を深掘りする「3つの問い」
- 社内会議を減らし「顧客×仮説」に全振りする
- 300回顧客と対話することで“才能”の壁を超える
- MVP期の「理論上到達可能な最高売上」を算出する
- 新規サービス成功のカギは「LTV > CAC」
- 新規サービス立ち上げ直後は「3P」に注力する
- 「最初の顧客」の定義とPDCAを回す「3C」
- 社内提案で押さえるべき「6点セット」と数字ロジック
- 新規事業の数字設定では「数値を分解する」癖をつける
- 参考情報
- 今日から実践できるアクション
- Q&A
「泥臭い」実践が新規事業を強くする
新規事業の立ち上げには、仮説と顧客接点を高速に回すための泥臭い現場対応が欠かせないもの。麻生要一さんの著書『新規事業の実践論 (NewsPicksパブリッシング)』は、まさにこの領域を深く掘り下げた一冊です。
本書は、社内起業やスタートアップにおける新規事業の立ち上げをリアルに描くと同時に、「何を外注してはいけないか」「MVP立ち上げ時に注力すべき指標は何か」など具体的なヒントを示してくれます。
少人数で始めるために、 外注すべきでない「コア領域」を決める
本書では、社内起業でもスタートアップでも、開発チームは3人以下の少人数でスタートすることが望ましいと説かれています。人数を絞ることで、議論がシンプルになり、意思決定のスピードを最大化できるからです。

同時に指摘されるのが「絶対に外注してはいけない役割を見極める」という視点。例えば検索エンジンを核としたサービスなら、アルゴリズム開発は自社のコア技術なので外注すべきでない。逆に、それ以外の部分(UIデザインやフロントエンドなど)は実績のある外部パートナーに頼むのも手。新規事業の競争優位をどこで作るかを社内で明確に定め、コア領域はチーム内で内製化するのがポイントです。
成功を引き寄せる「3つの力」 – Network・Execution・Knowledge
また、本書を通じて、新規事業で必須と強調されるのが以下の3つの力。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| Network | 自分の専門領域外を含む、さまざまな人脈を築く力 |
| Execution | スピード優先でやり抜く行動力。躊躇なく手を動かす姿勢 |
| Knowledge | 文理を問わず幅広い知見を学び続ける。技術的背景もビジネス的視点も大切 |
特に社内起業の場合、異なる部署や経営層との調整が不可避なのでNetworkが成果を大きく左右します。例えば、BtoB向け新規プロダクトを短期間で検証するには、顧客候補との繋がりを広げるだけでなく、エンジニアやデザイナーの外部パートナーにもスムーズにアクセスできる環境を整える必要があります。Executionは、企業内の承認プロセスに振り回されないためにも重要です。Knowledgeは、多角的な視点で顧客課題を理解し、仮説を高度化するための基盤になると本書では繰り返し言及されています。
新規事業が失敗する最大要因は「誰も必要としないモノ」を作ること
スタートアップの失敗要因を調査したCB Insightsのレポートでも、約4割が「Market Needsがなかった」、すなわち市場に求められていないプロダクトを作ったことと報告されています。本書でも、社内起業でありがちな「ビジョンや開発技術はあるのに、顧客がいない」状況こそが最も危険とされています。
ビジョンと技術力だけで突き進み、実際の顧客インタビューを後回しにすると、「誰も使わないサービス」へまっしぐら。そこで本書が強調するのは、「とにかく顧客の声を聞く」こと。社内の議論やエクセル上のプランではなく、現場で課題を抱える人に直接コンタクトして初めて、有効な方向性が見えてくると説かれています。
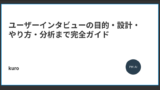
顧客課題を深掘りする「3つの問い」
本書では、新規事業の立ち上げで常に意識するべき3つの問いを紹介しています:
- 顧客の課題は何か?
- 机上の論理ではなく、顧客の声を聞いた後でも「本当に存在する」と言い切れるか?
- その課題は顧客にとってどれほど深刻か?
たとえば「自社内の経験から見て需要があるはず」と思い込むだけでは不十分。実際の顧客へのヒアリングを通じて、その課題の切実度合いを確かめる作業が欠かせません。BtoCの例として、グリー株式会社は初期の頃、ユーザーがコミュニケーションにどんな課題を感じているかを膨大なインタビューで探ったことでソーシャルゲーム事業へ展開するヒントを得たという事例があります。強い課題意識があるからこそ、ユーザーは「本当に使いたい」と感じるのです。
社内会議を減らし「顧客×仮説」に全振りする
本書では、新規事業の立ち上げ期にありがちな
- 上司への根回し
- 競合事例のリサーチ
- 無数の会議や資料作成
などを捨て去る大胆な姿勢が推奨されています。理由は、新規事業はまだ確固たるデータや事例がないため、内向きの作業ばかり増やしても実態が見えず、意思決定が遅れるだけだからです。
代わりに、時間を「顧客に仮説をぶつけに行く」ことへ集中投下する。具体的には、週10件のペースでインタビューアポを取り、仮説に対するフィードバックを得て高速で修正する。ユーザーインタビュー前に「筋の良い仮説」をチームで設定し、毎週アジャイルに回すイメージ。大企業であっても、新規事業は小さなスタートアップのような俊敏性が求められます。

300回顧客と対話することで“才能”の壁を超える
本書には「才能よりも、顧客と対話した回数が未来を拓く」という重要なメッセージが書かれています。少数の顧客ヒアリングだけでわかった気になってしまうと、ユーザー層によっては全く異なる意見が出てくる可能性を見落としてしまいます。
300回という数字は極端に映るかもしれませんが、それだけの回数をこなす中で初めて見えてくるインサイトも存在します。たとえば、株式会社メルカリは初期の段階で数多くのユーザーインタビューとアプリデータ分析を繰り返し、「誰でも簡単に売買できるUI設計」の要点を磨き込んだことで市場を切り拓いた経緯があります。数回やってダメだから諦めるのではなく、回数を重ねて修正を繰り返す地道な活動が不可欠です。
MVP期の「理論上到達可能な最高売上」を算出する
本書には、新規事業のMVPをローンチする際には「理論上到達可能な最高売上」をあらかじめ計算しておく手法が紹介されています。たとえば以下のような計算式です:
理論上到達可能な最高売上 = (顧客あたりの平均売上/年) × (理論上到達可能な最大顧客数)
ここで大切なのは、これが単なる机上の数字ではなく、顧客インタビューやベータユーザーへのテストで確かめた根拠を基にした推定値であること。市場規模レポートだけで楽観的に作った数字ではなく、あくまでも「この機能なら顧客は年間○万円までなら払う」「国内で類似課題を抱えるのは最低○○社はいる」といった事実から逆算していくプロセスが求められます。
新規サービス成功のカギは「LTV > CAC」
新規事業でサービスを立ち上げると、つい広告やPRに目が向きがちですが、本書では「LTV(顧客生涯価値) > CAC(顧客獲得コスト)」が成り立つまでは大々的なマーケティング予算を投じないように警告しています。LTV > CACが成立しない段階で広告費を大量に使えば、赤字を増やすだけだからです。
Slackの事例などが示す通り、初期ユーザーがしっかり価値を実感し、口コミで広げてくれる状況をまず作ることが第一。そのタイミングで初めて広告や広報に力を入れれば、効果的にユーザー数を伸ばせます。新規事業では、まずは少数の顧客を“顧客成功”に導くための地道なサポートに注力し、LTVを高める仕組みを育てることが大切です。
新規サービス立ち上げ直後は「3P」に注力する
一般的なマーケティングでは4P(Product, Price, Place, Promotion)を重視しますが、本書では新規サービスが立ち上がった直後こそ下記の3つのPが重要とされます:
- Product:顧客の課題を解決する機能とUI/UXの磨き込み
- Price:顧客の支払い意欲と課題の深刻度に合致した価格設定
- Primary Customer Success:最初の顧客を徹底的に成功させるオンボーディングとサポート
初期顧客が満足してくれれば、その声が社内外への説得材料となり、追加投資や口コミ拡散の可能性が広がります。逆に、いきなりマーケティングや広告にリソースを割いても、十分なプロダクト品質や価格設計が整わなければ失敗する可能性が高いと本書は警鐘を鳴らしています。
「最初の顧客」の定義とPDCAを回す「3C」
新規サービスの最初の顧客とは、以下の条件を満たす人や企業と定義されています:
- 身内や関係者ではない
- 営業されて初めて知り、正規価格で購入した
- 継続的に使用し、「払ってよかった」と満足している
これを実現するための実務フレームが「3C」です:
- Channel:採算度外視であらゆるチャネルを試す。SNS、カンファレンス、紹介など幅広く
- Communication:商談やインタビューの場で顧客の反応を見ながら営業トークを磨く
- Customer Success:購入後のサポート体制を構築し、顧客が満足を感じられるよう徹底する
とにかく幅広いチャネルにアタックし、顧客と接触する場を増やす。そこから得たフィードバックを素早くコミュニケーションやプロダクトに反映し、一人ひとりの顧客成功へ導くサイクルが必要です。【要約】『Running Lean』で顧客開発を加速させるの手法と合わせると、具体的な実行プランが構築しやすくなるでしょう。

社内提案で押さえるべき「6点セット」と数字ロジック
社内起業家として経営会議を突破するには、以下の6点セットが効果的と本書は述べています:
- 数字ロジック
- 顧客の“生”の声
- リスクシナリオと撤退ライン
- 関連法規の調査
- 社内キーマン・社外権威者のコメント
- 会社全体の方向性や既存事業との接続ロジック
顧客への仮説検証と並んで重要なのが「数字ロジック」。たとえば売上を「顧客単価×顧客数」に分解し、顧客単価は顧客インタビューから得た許容価格、顧客数は市場調査や実際の営業リストなどと突き合わせる。これにより、単なる理想論ではなく、裏付けのある数字として経営側を納得させやすくなります。
新規事業の数字設定では「数値を分解する」癖をつける
本書のメッセージとして、「その数字を採用した理由を説明できるか」を常に意識することが挙げられます。売上・利益・顧客数など、どの指標も「なぜその値になるのか」を分解し、パラメータごとに根拠を揃えておく。そうすると、提案時に「客単価の試算はユーザーインタビューで○件取材した結果」など具体的に答えられるため、説得力が段違いです。
大企業の新規事業提案でも、小さなスタートアップでも、この分解思考ができるかどうかで経営層や投資家とのコミュニケーションがスムーズになります。曖昧な数字ではなく、顧客の声や使用実績を土台にしたロジックを積み上げましょう。
参考情報
※本記事は、麻生要一 著『新規事業の実践論 (NewsPicksパブリッシング)』の内容を、僕の読書メモと各種信頼できる事例を交えながらまとめたものです。詳細は原著を参照してください。
- 麻生 要一 (2022). 『新規事業の実践論』. NewsPicksパブリッシング.
- CB Insights (2021). “Top 12 Reasons Startups Fail.”
- Eric Ries (2011). 『The Lean Startup』. Crown Business.
- 日本経済新聞. (2022). 「社内起業成功事例」特集.
今日から実践できるアクション
1. 「絶対に外注すべきではない領域」を明確化する
新規事業で競争優位となるコア技術やアルゴリズム、顧客開発ノウハウなどは外注に頼らないと決め、優先度を上げる。逆にデザインや広報などはパートナーに委託できる余地を探るとスピードアップが図れます。
2. 1週間に10件の顧客インタビューをこなす仕組みを作る
300回の顧客対話は時間がかかります。アポ取得・スケジューリング・ヒアリングから分析までをパッケージ化し、チーム内でローテーションを組む。ChatGPTでユーザーインタビューのログ分析を効率化する方法も活用しましょう。
3. MVP前後で「理論上到達可能な最高売上」を算出して社内に共有する
顧客インタビューやベータテストで判明した利用意欲・価格帯と、実際にアプローチ可能な顧客数を掛け合わせる。機上の空論ではなく、リアルに検証した数字として社内提案に使うと説得力が段違いです。
Q&A
Q1. 「社員3人で新規事業を始めよ」とは極端に感じますが、本当に大丈夫でしょうか?
A1. 本書が提案する少人数体制は、あくまでもスピード重視の初動を指します。大企業の場合は周囲のサポートも得ながら、コアチームを最小に保つことで意思決定を早める狙いがあります。進捗次第で必要なリソースを適宜拡大すれば問題ありません。
Q2. 300回の顧客インタビューを達成するには時間がかかりすぎると思うのですが、短縮策はありますか?
A2. 完全に短縮はできませんが、同時並行でアポ取りや分析を進めたり、ユーザーインタビューの設計を標準化したりすれば1件あたりの負担を減らせます。オンライン商談ツールを使えば移動時間も削減できますし、仮説→検証→修正のスピードが上がりやすいです。
Q3. 初期顧客を満足させる「Customer Success」はどう始めればいいでしょうか?
A3. まずは手厚いオンボーディングを設計し、顧客がプロダクトを使いこなせるまでの伴走を行う仕組みを作ると良いです。初期の顧客は数が少ないので、PdM自身が直接対応するのも手。要望や課題を吸い上げ、すぐにプロダクトへ改善ループを回すことで「買ってよかった」と思ってもらえる状態を目指してください。
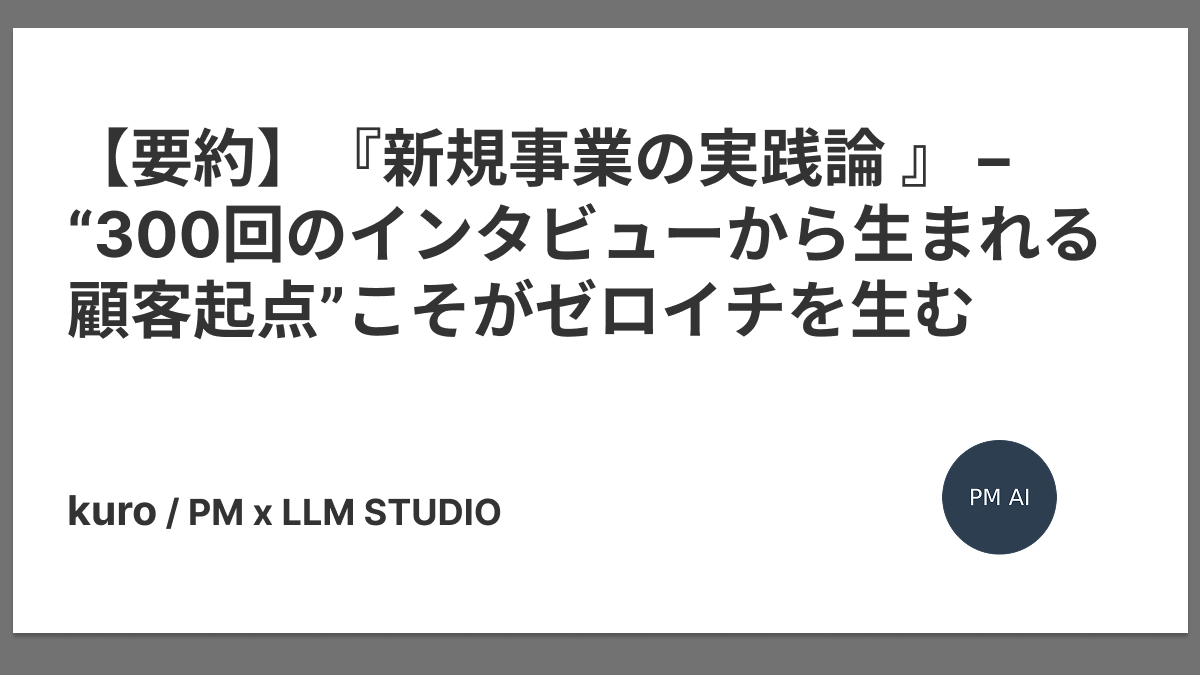

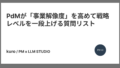
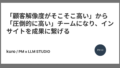
コメント