この記事の要約
- STPとペルソナは理論上は正しいが、現場でのデータ・顧客の声との融合が不足すると“机上の空論”になる
- 顧客のジョブ理論(JTBD)や実際の行動データの検証サイクルを回し続け、ペルソナをアップデートし続ける
- 継続的なインタビュー・分析に基づきポジショニングをUI/UXへ落とし込み、組織全体での合意形成を図る
STP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)のプロセスを踏み、ペルソナを作り込んだのに「なんだかユーザーに刺さらない」「プロダクトが思うように伸びない」——こんな経験をしたPdMの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、STP理論やペルソナ設計がなぜ“机上の空論”になりがちなのか、そして実際にどう改善すれば「本当に届けたい顧客」にリーチできるのかを考えていきます。
STP理論の基本と限界
まずSTP理論とは、
- 市場をSegment(細分化)し、
- 狙うTarget(ターゲット)を決め、
- そのターゲットに対する自社の独自性・価値をPositioning(ポジショニング)
で確立するマーケティングのフレームワークです。
このフレームそのものは非常に有効ですが、実際のプロダクト開発現場では、以下のような“限界”や“陥りがちな穴”が見え隠れします。
- 定量調査の偏り:サイズの大きい市場を狙いにいきがちで、ニッチセグメントを置き去りにする
- 競合環境の動的変化:ポジショニングが競合の真似になったり、いつの間にか似通ったサービスになってしまう
- 現場での“腹落ち”不足:STP理論を作って終わり。実際のユーザー体験やUI/UXに落とし込まれず、チーム全体が方向性を掴めない
ペルソナ設計で陥りがちな“ズレ”
またペルソナは、ターゲット像を具体化するために有効な手法です。にもかかわらず、「ペルソナを作ったのにまったく刺さらない」状態に陥るのはなぜでしょうか。失敗要因を大きくまとめると、以下の通りです。
- 仮説上の人物を固めすぎる
ペルソナを精密に描くあまり、想定が現実を上回って静的化など、「そんなやついねえよ」「そいつはどこの誰だよ」的なペルソナを描きがち - インタビューやログ分析の不十分さ
「何となくこういう人がターゲットだよね」という主観先行で、実際のユーザーインタビューやログ分析の結果を十分に反映していない - JTBD(Jobs to Be Done)が抜け落ちる
ジョブ理論(JTBD)(ユーザーが達成したい仕事/解決したい課題)があいまいで、プロダクト利用の“本当の動機”とペルソナの姿が結び付いていない - チーム”全員(特に意思決定者)”がペルソナと日常的に接していない
インタビューを一回して終わり。継続的に顧客の声を聞かないため、感覚が更新されずにずれていく。 - 継続的な検証サイクル(反復)がない
STPやペルソナを一度作ったら終わり。ユーザーニーズや市場環境の変化に追いつかず、ジリ貧になる。
データと顧客の“生の声”の融合で状況を好転させる
では、どうやって解像度を上げ、STPとペルソナを「実際にユーザーに響く」レベルへ高めていくか。ポイントは“定量×定性の融合”。
1. 定量データで「どのセグメントが望ましいか」を俯瞰する
ログ分析やアンケート調査を行い、どのセグメントが継続率・LTV(Life Time Value)が高いか、あるいは逆にサポート負荷が低いかなどのデータを洗い出す。実際の数値の裏付けを得て、ターゲットセグメントをより精密に絞り込むのが狙いです。
2. 定性調査(インタビュー)で「なぜ?」を深掘りする
ログから見えた仮説を、ユーザーインタビューやエスノグラフィー調査を通じて検証します。具体的には「なぜ、その機能をよく使うのか」「何が導入の決め手になったのか」などを聞く。仮説と事実のズレを見つけたら、即ペルソナに反映する。
過去記事「ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド」でも詳しく書いていますが、インタビューの設計段階からゴールを明確に持ち、ログで得た数字の意味を問い直す質問設計が大切です。
また、このフェーズで、「この人の課題を解決するのだ!」と言う実在するN1のユーザーを見つけることが超絶重要です。
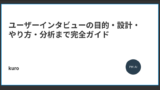

3. JTBD(Jobs To Be Done)を掛け合わせる
ペルソナは属性情報だけでなく、「ユーザーがどんな“JOB”を雇用したいのか」を扱うジョブ理論(JTBD)で補完すると、より解像度が上がります。単に「従業員300名の人事部長」ではなく、「離職率を下げるために現場評価システムを使いたい」「実質1人で採用から評価まで見る必要がある」というジョブを明確にするイメージです。

4. ペルソナは架空のキメラ的な人物ではなく、実際にあったN1にする
ユーザーインタビューログを統合してペルソナを作ると、どうしても「そんなやついねえよ」という”キメラペルソナ”が出来上がります。当然、そんな人は実在しないのでプロダクトの方向性はずれます。そこでやるべきことは、インタビューした中で「自分たちの想定する課題を最も強く抱いている(すでに代替手段を講じていて多大なコストを払っている)実在する1人」をgoogle slide1枚にまとめてペルソナにすることです。脚色が不可能になります。
ポジショニングをユーザー体験まで落とし込むフレームワーク
ターゲットやペルソナが再定義できたら、それをユーザー体験設計(UX)まで具体的に落とし込みましょう。いくら理想のターゲット像が明確でも、UI/UXが全く合っていないとプロダクトは伸びません。
- カスタマージャーニーマップを作成する
カスタマージャーニーマップ(ユーザーが製品を認知→興味→導入→利用→継続にいたるプロセス)を、ペルソナに併せて描く。ペルソナAが「導入判断」をするシーンはどういうタイミングか、どんな課題があるのかを洗い出す。ここに関しても、「実際にあったN1の実在する行動」をまずは書いてみることがおすすめです。 - タッチポイントごとに必要な施策を検討
例えば「導入前に競合と比較検討するフェーズ」では、製品情報が分かりやすく比較できる資料や無料トライアル環境が大事。実運用フェーズでは、チュートリアル動画やチャットサポート対応がキーポイントなど。 - 継続的に利用状況を可視化
各フェーズでのユーザー行動(トライアルからの本契約転換率、1か月後の継続利用率など)を計測し、想定との乖離が出ればすぐインタビューや追加調査で原因を追究し、ペルソナや導線を修正。
STP・ペルソナは“調整弁”であり、進化させるもの
抽象化すると、STPとペルソナは決して「完成図」ではなく、「調整弁」であり「変化し続ける対象」。
市場の変化や競合の動向、ユーザーの心理的変化は常に動き続けます。それらに合わせて、仮説をアップデートし続けることが大切です。
一度作って満足するのではなく、顧客のリアルな声と定量データを活用して再設計を繰り返すことで、“想定ユーザー”が“現実のユーザー”に近づいていきます。結果として、プロダクトの伸びにつながり、ユーザーにもより価値を感じてもらえるわけです。
今日から実践できるアクション
- 1. ログデータやアンケートの再分析:
特に「どの顧客層が継続利用率高いか」「導入後のサポート負荷はどうか」を確認し、稼ぎ頭セグメントを洗い出す - 2. 代表的ユーザー数名に再インタビュー:
「なぜ選んだのか?」「何が決め手だったのか?」を深堀りし、ペルソナの仮説をアップデートする - 3. JTBDを整理:
「ユーザーはどんな“仕事”を達成したいのか?」をペルソナ毎に言語化し、資料や機能の見せ方を修正する - 4. カスタマージャーニーマップを新たに作成:
具体的な導入ステップや躓きポイントを可視化し、UI/UXやサポート体制に反映 - 5. 定期的な見直し:
市場やユーザーの変化をキャッチできるよう、3か月・6か月ごとにログ分析とインタビューを実施
Q&A
- Q1. 小規模なチームでリソース不足なのですが、どうやって定性・定量分析を両立すれば良いですか?
- A1. ログ分析は最初に確認すべき指標(継続率、解約率など)を絞り込み、インタビューも「代表的なユーザー」数名に限定して行うと良いです。少人数でも月5人程度インタビューを実施すれば、ペルソナ仮説は十分に更新できます。
- Q2. 複数ペルソナがあり、それぞれニーズが異なるときはどう絞り込めばいいのでしょう?
- A2. 最初は「最も収益性や継続率の高いペルソナ」から手を付けると合理的です。焦って全ペルソナに対応しようとすると、メッセージが分散しがちです。高優先度ペルソナを軸に、他ペルソナの機会も徐々に検証を進める形がおすすめです。
- Q3. 経営層がペルソナやSTPを「一度作ったら固定」と思い込んでいるのですが…
- A3. データを使って「実は想定外のセグメントがコアユーザーになっている」「更新しないと収益機会を逃す」事例を示すと説得しやすいです。HubSpotやSlackの例を紹介して、アップデートの重要性を強調すると良いでしょう。
参考情報
- [1] Harvard Business Review. (2021). “Translating Strategy into Customer Experience”.
- [2] HubSpot Investor Relations. (2020). Q3 Earnings Report.
- [3] Slack. (2022). Customer Case Studies: Enterprise Solutions.
- [4] Forrester. (2022). The State Of Customer Obsession.
- その他参考文献:コトラー, P. (2016). マーケティング・マネジメント. Pearson.
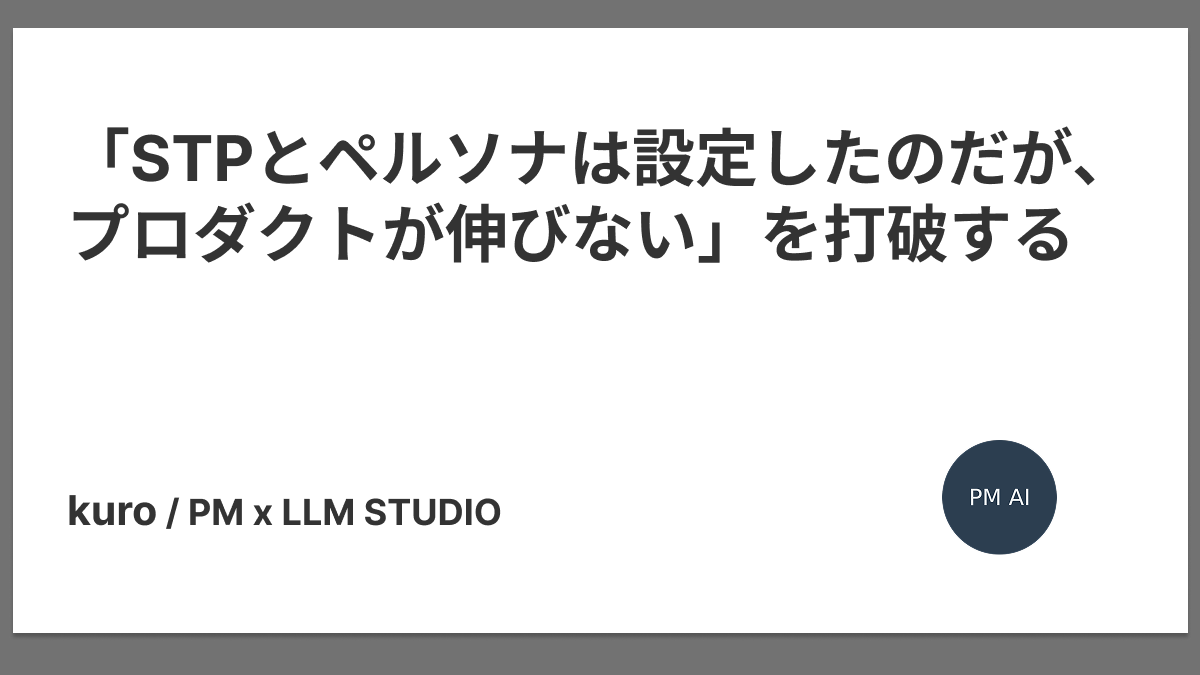

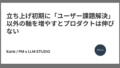
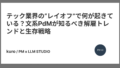
コメント