この記事の要約
- ファクトは前提として超絶ウルトラ大事
- ただ、ファクトを過度に信頼すると、破壊的イノベーションの芽をつぶしてしまう
- 実務では「ファクトを起点にしつつ、ユーザー自身が想像できない未来」を構想することが鍵
プロダクトマネージャーなら誰しもが「ファクトこそ正義。ユーザーインタビューやデータ分析で得られる事実情報を重視すべきだ」と考えますよね。僕も徹底的にファクトを集めることには大賛成です。
ただ、ファクト”だけ”を過度に信じてしまうと、次世代の大きな飛躍を阻害する可能性があります。なぜなら、ユーザーですら自分の“未来の欲求”を言葉にできないことが多いからです。
本記事では、ファクトの重要性を前提としながら、そこに“仮説の飛躍”をどう組み込むかを深堀りしていきます。既存ユーザーの声だけでは生まれにくい破壊的イノベーションを実現するためのヒントを具体的な事例やフレームワークとともにお伝えします。
ファクト過信の落とし穴
ファクトを大切にするのは、プロダクトマネジメントにおける鉄則のようなものです。実際、ユーザーインタビューや行動ログ分析などを通じて事実情報を集め、そこから課題を抽出する方法は、より正確な意思決定に寄与します。僕自身も累計700人以上へのインタビュー経験を通じて、ファクトがどれほど組織の混乱を減らすかを実感しています。
とはいえ、ここで気をつけたいのが「ファクト過信(収集したデータを絶対視し、そこに表れない可能性を排除してしまう傾向)」です。ハーバード・ビジネス・スクールのClayton M. Christensenが著書『The Innovator’s Dilemma(1997)』で指摘したように、既存ユーザーの声や現在のデータは、破壊的イノベーションの可能性をあまり示してくれません。ユーザーが現時点で認識している課題や欲求に応えるだけでは、革新的なジャンプを起こせないのです。
既存ユーザーの声ばかり聴いて“破壊的イノベーション”を見逃す
破壊的イノベーション(既存の市場や技術を一変させる、新しい価値提案)は、多くの場合、既存ユーザーからは「そんな機能は必要ない」と否定される段階からスタートします。有名な例が最初期のiPhone。当初、多くの携帯電話ユーザーは「QWERTYキーボードのないタッチスクリーンは使いづらい」「スマホはニッチ」などと言いがちでした。実際のユーザー調査でも「物理キーボードが欲しい」という声が相次いでいたようです。
しかしAppleはユーザーが明言しない“理想の体験”を先取りし、結果的にモバイル業界を一変させました。もし「大多数のユーザーがキーボードを望んでいるから」と鵜呑みにしていたら、あの革命的なUIは生まれなかったかもしれません。
マーケットリサーチの盲点(ユーザーも未来を語れない)
ファクトに頼るときの前提として、「ユーザーが必ずしも自分の未来や真の欲求を語れない」という点を常に念頭に置く必要があります。ユーザーはあくまで現在の使い方や不満点を言語化してくれますが、“潜在ニーズ”や“そもそも考えたことがない新しい体験”は言及されにくいです。
こうした現実を踏まえると、ファクトは重要でも、そこだけに依存していたら大きなチャンスを逃してしまうということです。
イノベーションを生む「データ×ビジョン」の両輪
では、どうすればファクトを活用しつつも、その枠組みに縛られないイノベーションを起こせるのでしょうか。僕がよく意識しているのは、「データ×ビジョン」の両輪を回すというアプローチです。これは事実に基づく“現実把握”と、PdMやチームが描く“理想像”を組み合わせる考え方です。
スティーブ・ジョブズの事例:ユーザーデータが無い状況からの発想
Appleのスティーブ・ジョブズはよく「ユーザーは自分が何を求めているかを知らない」と言う趣旨の発言をしていました。彼が初代iPodを提案したときも、当時のMP3プレイヤー市場はデータから見ると「音楽ファイルを持ち運べればOK」「本体をもっと小型化すべき」という方向に収斂されがちだったようです。しかしジョブズは、“ポケットに何千曲もの音楽を入れる”という新体験のビジョンを示し、インターフェースの使いやすさを追求することで市場をリードしました。
これは「現状のデータ」よりも、「実現したいビジョン」から逆算してハードウェアやUIを設計した好例です。
Amazonの“Working Backwards”とビジョンドキュメント
Amazonで有名な手法にWorking Backwards(逆算思考:理想のプレスリリースを書くなど、完成形から開発に着手する手法)があります。これは新製品や新機能をリリースする前に、まず理想的なユーザー体験やストーリーを文章化するやり方です。
例えば「ユーザーがどんな課題を抱えていて、製品をどう使い、どんなメリットを得るか」を具体的なシナリオとして作り上げます
その後に、必要な機能や開発工程を逆算で洗い出していくのがポイントです。データ分析を駆使するAmazonであっても、必ずしもデータだけが起点ではなく、ビジョンを先に描く姿勢が徹底されています。
ファクトからの一歩先を発想する具体的手法
「ファクトを10集めたら、そこから先の“1の飛躍”を必ず設計」するプロセスが重要です。これは要するに、現状のユーザー発言やログ分析から得られた事実をしっかり把握したうえで、「もしこうなったらどうなる?」という仮説を組み立てるプロセスです。以下に2つの手法を例示します。
“仮説の飛躍”をあえて作り出すブレスト手法
定番ですが、ブレインストーミングのときにあえて「ユーザーが『それはちょっと考えつかなかった』と思うような発想を混ぜ込む」ことを意識します。具体的には以下のようなステップを踏みます。
- ステップ1:ファクト整理
ユーザーが現在抱えている課題を列挙。定量ログや定性ヒアリングで判明している事実を可視化 - ステップ2:飛躍させる問いを設定
「もしユーザーがキーボードを使わなかったら?」「もしUIが存在しなかったら?」など、常識を崩す問いを投げる - ステップ3:アイデア出し
条件や制限を一時的に無視し、バカバカしいと思える案までひたすら出す - ステップ4:再評価と実現可能性の検証
そのアイデアを現状のファクト(ユーザーの行動傾向、技術的制約など)と照らし合わせて精査
こうすることで、「実際はユーザーがまだ言葉にできていない潜在ニーズ」をすくい上げやすくなるのです。
デザイン思考との組み合わせ
デザイン思考(デザイナー的な問題解決プロセス)では、「観察→共感→問題定義→アイデア創出→プロトタイプ→テスト」といったプロセスを繰り返します。
観察や共感のフェーズではファクトを重視し、ユーザーがどう動いているのかを正確に把握します。そのうえで問題定義の段階で「ユーザーの深層欲求は何か?」と問いを立てると、自然と「目に見えない痛み」や「新しいワクワク感」を発見できる場合が多いです。
デザイン思考によって出てきたアイデアを、さらにブレストや仮説検証で膨らませると、ファクト×飛躍をうまく組み合わせる形になります。
事例:データが示すものと異なるコンセプトで成功したプロダクト
ファクトを無視するのではなく、そこに縛られない飛躍を作り出した成功事例として、Nintendo SwitchやDysonの掃除機がよく挙げられます。2つともユーザーの声だけをそのまま反映していたら生まれにくいイノベーションでした。
Nintendo Switch
従来の据え置き型と携帯型のゲーム機は別物というのが常識でした。しかしSwitchは「家でも外でも同じゲーム体験」を実現するというビジョンを先に掲げ、ハードウェアを柔軟に使い分けるコンセプトを実装。発売前のユーザー調査では「そんなに需要があるの?」と言われたそうですが、結果は大ヒット。複数の利用シーンを行き来する楽しさをユーザーが“使い始めてから”実感する形となりました。
Dyson掃除機
一般的なユーザー調査では「もっと安くて軽い掃除機が欲しい」といった声が多かったといわれます。しかしJames Dysonはモーター技術とサイクロン方式に可能性を見出し、「吸引力が変わらない掃除機」というブレイクスルーを実現。価格は他社製品より高くなりましたが、圧倒的な機能価値とブランド体験が支持されました。ユーザーが抱えている不満を徹底観察しつつ、そこに縛られず独自の新技術に挑戦した好例です。
実務への応用
では、PdMが日々の開発業務でどう「ファクトを生かしつつ、それを超える仮説」を立てるのか。ここからは具体的な実務イメージをいくつか紹介します。
ファクトを補強材料にしつつ、先を見据えたシナリオづくり
まずは“今”のユーザーが抱えている課題や不満を、インタビューやログ分析でファクトとして集めます。この時点で、ユーザーが挙げる「欲しい機能」や「使いづらい点」は、あくまで現時点での最適解です。次に、そこから「この問題が完全に解決されたら、ユーザーの行動はどう変わるか?」「もし一つ上の体験価値を届けられたら、ユーザーの日常はどうアップデートされるか?」をストーリー化します。
このストーリーを作る際は、必要であれば社内ワークショップを開いて、多角的な視点を取り込むのがおすすめです。想像力豊かなエンジニアやデザイナー、カスタマーサクセス担当などとディスカッションを重ねると「そこまで実現できれば最高だけど、現状だと足りない要素は○○だね」という会話が増え、具体的な実装プランが見えてきます。
ファクトを「起点」として“ユーザーすら気づかない価値”を創出
“顧客は未来を語れない”というフレーズを、こちらの記事でも紹介しましたが、やはりユーザー自身が思い描けない未来の価値はPdMが積極的に想像して提示していくべきです。
たとえばHRテックの例で言うと、ユーザーが「求人入力が手間」と言うのであれば、それを自動化するだけではなく、「そもそも求人入力自体が不要になる世界」を視野に入れることが重要です。
「候補者が自動で案件へマッチングされる」仕組みを作るとか、「求人入力せずにSNSのプロフィールから自動生成される」仕組みを考えるなど、既存の枠組みを壊すシナリオが新しいチャンスを生みます。

ファクトがなければ混乱、ファクトだけでは発展しない
ファクトの重要性を否定するつもりは、まったくありません。むしろ、PdMにとっては不可欠な基盤です。
ただ、そこに100%頼り切ってしまうと、ユーザー自身がまだ想定していない新しい体験を提案できなくなります。僕自身、ユーザーの声に耳を傾けつつ、「もしこういう未来だったら?」とチームで妄想を広げる瞬間が何より楽しい。そこにイノベーションの鍵があると信じています。
事業を飛躍させるには、現実を直視するファクトと、既存の常識をぶち破るための仮説の飛躍。その両方をバランスよく扱うことが欠かせないのです。
今日から実践できるアクション
- データ収集のフェーズと「仮説の飛躍」フェーズを意識して分ける
– まずはファクトを正確に把握。そのうえで、飛躍的なアイデアを出す時間を別枠で確保する - アイデアワークショップで“制限解除”のブレストを定期実施
– 参加メンバーを多様にし、あえて突拍子もない発想を出す場を設ける - ビジョンドキュメントを先に書く
– AmazonのWorking Backwardsのように、新機能リリース前に“理想のプレスリリース”やユーザーストーリーを文章化する - プロトタイプを迅速に試す
– 仮説を形にし、ユーザーや社内レビューで早期にフィードバックを得る
Q&A
- Q1. ファクトと仮説のバランスを取るうえで気をつけるポイントは?
- A1. 一番大事なのは順番と割合です。最初に徹底してファクトを洗い出し、現実的な制約やユーザーの課題を把握します。そのうえで、あえてブレイクスルーを起こす発想時間を持つとバランスが保たれます。
- Q2. ユーザーが想像できない未来をどう説得すればいい?
- A2. プロトタイプやビジョンドキュメント、具体的なシナリオを作り込んで「体験を疑似的に見せる」ことが有効です。エモーショナルな要素を加えて、未来像をリアルに描写するのも効果的です。
- Q3. 社内から「そんな非現実的なアイデア出しても…」と突っ込まれたら?
- A3. まずは既存のファクトを踏まえた上での仮説だと示し、実験的な検証計画を提示して説得するのがおすすめです。「根拠ゼロの妄想」ではなく、「将来を見据えた挑戦」であることを明確にすると反発が緩和されやすいです。
参考情報
- Clayton M. Christensen (1997) The Innovator’s Dilemma – 破壊的イノベーションの理論と実例
- Bill Carr, Colin Bryar (2021) Working Backwards – Amazonで活用される逆算思考の実践例
- Tim Brown (2009) Change by Design – デザイン思考に関する代表的書籍
- “顧客は未来を語れない”から、徹底的にファクトを集めてPdMが未来を妄想する
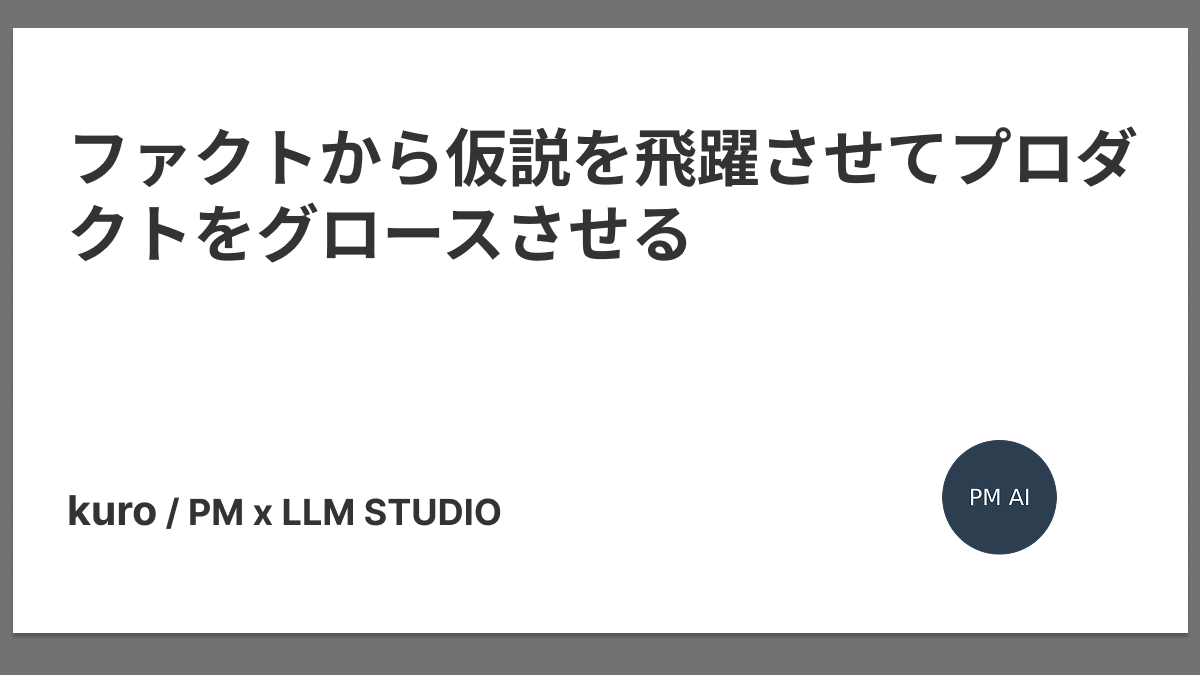
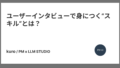
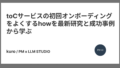
コメント