この記事の要約
- OKRはKPI・MBOと異なり挑戦的な目標設定と学習を重視し、評価と直結させずストレッチゴールを追求する
- Objectiveは定性的でワクワク感を与え、Key Resultsは2-4個の定量指標で測り、週次・月次のレビューでPDCAを高速で回す
- 組織ビジョンとの接続とチーム合意形成が不可欠で、失敗を許容する文化がなければ無難な目標しか立たず形骸化する
OKR(Objectives and Key Results)は、組織がめざす大きな方向性(Objective)と、それを測定する指標(Key Results)を設定し、チームが一枚岩になることを目指すフレームワーク。
シリコンバレーのテック企業を中心に広まり、GoogleやIntelなどが取り組みを公表したことで一気に注目度が高まりました。現在では日本企業にも浸透しています。
本記事ではそんなOKRについて、概念、設定方法、運営方法までの基本から応用までを解説していきます。
OKRが注目される理由
OKRが注目を集める理由は、「実現したい目標」に向けてチームの意思決定をブレさせず、高速にPDCAを回せる点にあります。
会社全体のビジョンを具体的な形で四半期や月次の目標に落とし込み、実際の成果指標(KR)で達成度合いをチェックするため、組織全体での共通認識が取りやすくなります。ユーザーが本当に求める価値を継続的に提供するには、こうした“指標にもとづく客観的な評価”が必要。
特にGoogleは創業期からOKRを採用して成果を上げてきた企業として有名です。社内におけるOKR導入のエピソードはJohn Doerr氏の著書『Measure What Matters』で取り上げられ、多くの企業が導入の参考としています。
KPI・MBOとの違い
OKRと混同されがちな概念に以下が存在します。
- KPI(Key Performance Indicators)
- MBO(Management By Objectives)
KPIは特定の業務指標(売上・アクティブユーザー数など)を追う場合に用いられることが多い反面、OKRではより“挑戦的な目標”を設定し、そこに向かう行程で得た学びも重視します。たとえば「今期中に顧客満足度をNPSで +10 上げる」など、ややストレッチしたゴールが好まれます。
一方、MBOは上司が部下に対して目標を設定し、評価と結び付ける仕組みが中心になりがちです。OKRでは、必ずしも“評価”と直結するわけではなく、挑戦を促し、失敗や学びを許容する文化を作ることが重視されます。数字を達成するだけでなく、次の打ち手や組織学習につながる体制こそが、KPIやMBOとの大きな違いです。
OKRの構成要素と基本用語の理解
まずは、OKR運用上欠かせない要素である以下3つを解説します。
- Objectives(目標):なぜその目標を掲げるのか
- Key Results(主要な結果指標):どう達成度を測るのか
- そしてInitiatives(取り組み):具体的に何をやるのか
Objectives(目標)
Objectiveは定性的に「こうありたい」「こうなりたい」という方向性を示す言葉。
- 「ユーザーが毎朝一番最初に開かれる習慣化アプリの実現」
- 「日本で一番バイラルによる広がるを実現できるSNSをつくる」
など、チームを鼓舞するインスピレーションを与えるように設定します。組織→チーム→個人という階層に分けて設計する場合は、各レイヤーでのObjectiveが互いに矛盾しないように注意が必要です。
ここで覚えておきたいのは、Objectiveは定性的でいいという点です。数字よりもワクワク感を与えることにフォーカスし、「自分たちは何のために頑張るのか」を共有することが鍵になります。例えば、クライアント企業の“従業員の意欲向上”に本気で寄り添うため、「常に期待を超える驚きを提供する」というObjectiveを掲げてチームの士気を高める、などもアリです。
Key Results(主要な結果指標)
Key Results(KR)は、Objectiveを達成したかどうかを測定するための定量指標です
- デイリーアクティブユーザー数(DAU)
- 月間リピート率
- NPS(Net Promoter Score)
など、実際に数字で測れる項目を設定します。OKRの運用では、1つのObjectiveにつき2~4個程度のKRを置くことが多く、あまり多すぎるとチームのフォーカスが散逸してしまうため注意が必要です。
たとえば「ユーザーが毎朝使いたくなるプロダクトを目指す」というObjectiveに対しては、
- 「DAUを20%増やす」
- 「リピート利用率を40%以上に上げる」
- 「毎日7:00までの起動したDAUを30%増やす」
などのKRが考えられます。なぜその数字なのか、どう達成度を測るのかといった根拠をチーム内で共有しておくと、ロードマップの判断がスムーズになります。
Initiatives(取り組み/アクション)
Initiativesは、KRを達成するために実施する具体的な施策やプロジェクトを指します。ここがOKRにおける“行動計画”の部分で、プロダクトマネージャーはロードマップに落とし込みながら各機能開発や改善を進めます。例えば、
- 「プロダクト立ち上げのための商談100件」
- 「オンボーディング改善の新機能5つをリリース」
といったInitiativesをOKRと連動させてチームに展開するイメージ。
ここで大事なのは、Objectiveを達成するための打ち手が何種類か存在するという事実を前提にすること。たとえば同じDAU向上を目指すにしても、
- 「オンボーディングプロセスの改善」
- 「UI/UXの大幅リニューアル」
- 「ゲーミフィケーション要素の導入」
など複数の施策が考えられます。OKRではまずKRが到達点として定義され、その後にチームで手段を模索する流れを取るのが一般的です。
OKR導入前に必要な下準備:現状分析・チーム合意形成
OKRを始める前に必ず押さえておきたいのが、“現状分析とチーム合意形成”です。特に、会社や事業のビジョンをPMレベルだけが理解していても、現場レベルで認識が共有されていなければ、ObjectiveとKRが形式的にしか機能しません。まずは組織ビジョンや事業計画との接続を整理し、チームの声を拾うワークショップを実施する、などもありです。
組織ビジョン/ミッションとの接続
そもそも会社全体でどんな未来を描いているのかが定まっていないと、OKRでどれだけ定量指標を整備しても本質的なコミットメントは得られにくいです。たとえば「人と組織を豊かにするHRテックを世界に広めたい」というビジョンがあるなら、そのビジョンを達成するために、なぜ今期そのObjectiveを設定するのかを丁寧に言語化します。ここがブレていると、OKRが“作業管理ツール”のように扱われてしまうため要注意です。
ビジョンの再確認には、経営陣だけでなく現場チームの声も重要です。例えば、全社ワークショップ形式で
- 「このビジョンに共感できるか」
- 「今あるプロダクトが解決している課題は何か」
などを話し合うなど(人数にもよりますが)
チームインタビューやステークホルダーの巻き込み
OKRの最大の特徴は、トップダウンだけでなくボトムアップの意見を取り込む点にあります。そこでおすすめなのが、「ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド」でも触れているようなインタビューを社内向けに応用すること。メンバーが抱えているペインやモチベーションの源泉を聞き出すと、「どんな目標なら頑張れるか」や「成功したらどんな未来が待っているか」が明確になります。
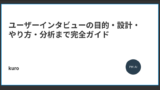
たとえばセールスチームやカスタマーサクセス(CS)チームに話を聞くと、彼らが日々直面している顧客の課題をより深く理解できます。それをもとにObjectiveを再定義すれば、現場が腹落ちする形でOKRをスタートできるはずです。巻き込むステークホルダーが増えるほど時間はかかりますが、その分だけ導入後の推進力が高まることを実感しています。
既存の評価制度・KPI管理との整合性
多くの企業では、既にKPIやMBOによる目標管理制度が走っている場合が少なくありません。そうした組織にOKRを導入する際は、評価制度と直接リンクさせないことが勘所です。あまりにもOKRが業績評価と結び付きすぎると、“達成できそうな安全圏の目標”しか設定されなくなる恐れがあります。
また、既存のKPIを上手に活かしつつ、そこに挑戦的なObjectiveを掛け合わせる形も有効です。たとえば、「これまで追ってきた営業指標はKPIとして残すが、それを大きく伸ばすための挑戦目標をOKRとして設定する」など、役割を明確に分けることでチームの混乱を回避できます。
OKR設定の実践プロセス
実際にOKRを設定する際は、期初のタイミングでワークショップを行うケースが一般的。PdMの立場からすると、ロードマップと整合をとりながらOKRを組み込むため、1~2週間ほど準備期間を設けるとスムーズに進みます。ここでは実践的なステップを具体例とともに紹介します。
期初に行うOKRワークショップ
期初のワークショップでは、まず経営層・PM・チームリーダーなどが集まり、組織全体のObjectiveを検討します。その後、チームごとのObjectiveとKRをブレストで洗い出していきます。僕の経験上、最初はどうしても欲張って「Objectiveを5つ以上」などと多めに設定してしまいがちですが、焦点を絞るために3つ以内(理想は1つ)に絞るほうが効果的です。
KRの数値も、チームごとに3個以下を目安に設定します。たとえばHRテックのSaaSを運営する場合、KRとして「ユーザーオンボーディング完了率」「導入後1週間以内の再訪率」などを定義し、そのレベルをどれだけ引き上げるかを決めるといった具合です。ここで重要なのは、メンバーに「やりがいがある」と感じてもらえる程度にチャレンジングな数値を設定することです。
タイムラインと頻度
多くの企業では、OKRを四半期(3ヶ月)単位で運用しています。大体最初の1ヶ月はイレギュラーが多いため、月次でチェックポイントを設けたりします。さらに週次での進捗確認も組み合わせることで、適度な緊張感を維持できます。特にスタートアップのように変化が速い組織では、月ごとに修正をかける体制が向いているケースもあります。
OKR設定のイメージ
例として、HRテックSaaSのプロダクトチームを想定してみます。
- Objective
- 「ユーザーが導入直後から“自走”できる世界観を実現する」
- KR
- 導入後1週間以内のアクティブ率を50%→70%に引き上げる
- 初期離脱率を20%→10%以下に削減する
と設定したとしましょう。
このKRを達成するためのInitiativesとして、
- 「オンボーディングUX改善」
- 「チュートリアルコンテンツのABテスト」
- 「週次フォローの自動化」
などをリストアップします。
こうしたOKRは、ログ分析やユーザーインタビューの結果とも密接にリンクします。導入初期の離脱が多い原因がUIの分かりづらさにあるのか、それとも機能の使いこなしに不安を抱えているのかを調べるために、ログ分析→ユーザーインタビューの流れで、「本当に解くべき課題」を明確にする方法が役立ちます。そのインサイトを元にKRをチューニングすれば、より実効性のあるOKRに進化します。
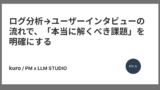
OKR運用:定期レビューと実際のPDCA回し方
OKRは「設定して終わり」ではなく、運用の仕組みを作ってからが本番です(そして、最初の方は大体失敗します)。週次や月次でレビューを行い、達成度を共有し合いながらボトルネックを解消していきます。
ウィンセッション/チェックインの進め方
“ウィンセッション”や“チェックイン”と呼ばれるレビュー会では、Key Resultsの達成状況をスライドや可視化ツールで振り返ります。良かった点はメンバー全員で称え合い、課題があれば「何が阻害要因になっているのか」を短時間でディスカッションします。KRが思うように進んでいない場合、Initiativesの優先順位を変えたり、新しい打ち手を追加したりするのが一般的です。
大事なのは、数字を追求するだけでなく、チームで学んだことを言語化することです。たとえば「オンボーディングメールを改善した結果、1週間以内の再訪率が5ポイント伸びた」という成果があったなら、どの要素がユーザーに響いたのかを検証しておきます。次の施策に活かすことで、OKRがより強力な学習サイクルを生み出します。
他チームとの連携
OKRは部署横断のコミュニケーションを促進しやすいフレームワークでもあります。PM・エンジニア・デザイナー・CS・マーケなど、多様な専門性を持つメンバーが同じObjectiveとKRを意識することで、スムーズに知見を共有できます。可視化のためには、Notionなどを使い、どのKRにどの施策が紐づいているかを一覧化すると便利です。
特にCSチームとの連携は重要。なぜならCSはユーザーの声を最前線で拾う立場にいるからです。OKRの観点では、CSが抱えている顧客課題を素早くPMやエンジニアに伝えられるほど、KRの達成が進むケースが多いです。
ロードマップとの連動:OKRを形骸化させないために
OKRを形骸化させないためには、プロダクトロードマップの更新タイミングでOKRを照らし合わせる習慣を作ることがポイント。ロードマップを変更する理由のひとつとして
- 「OKRの数値が達成できていない」
- 「新たに見えた顧客ニーズがある」
などが挙げられます。ここで矛盾や衝突が起きるようなら、改めてObjectiveやKRを再定義する判断をする柔軟性が必要です。
OKR成功事例とアンチパターン
OKRを導入して成果を上げる企業は少なくありません。実際にインテルやGoogleといった大手企業だけでなく、日本国内でもSansan、freeeといったSaaS企業がOKR導入の事例を公表しています。共通しているのは、挑戦的なObjectiveと明確なKRを組み合わせ、チームが主体的に目標達成に取り組む文化が醸成されている点です。
国内外の成功事例
例えばGoogleの事例では、創業期にJohn Doerr氏がOKRを導入したことが有名。Google社員は四半期ごとに自分のOKRを設定し、チームでも設定し、会社全体でも設定するという多層構造を採っています。OKRは実際の業績評価とは完全に切り離されていて、挑戦的な目標を遠慮なく掲げられる仕組みが根付いています。実際、「検索速度をさらに高速化する」「YouTubeのユーザーフレンドリー化を推進する」などの大きなテーマが達成されてきた背景には、OKRの効果が大きいと言われています。
一方、日本のクラウドサービスを提供するSansanやfreeeなどでも、部門ごとにOKRを設定し、数字の進捗を社内共有しているそうです。担当者レベルで「自分のKRがどれくらい達成できているか」をリアルタイムで把握できる仕組みを整えており、四半期毎にOKRの達成度と学びをまとめて次の期に活かしているとのことです。こうした取り組みにより、新プロダクトのアイデアや機能追加がスピーディーに立案・実装されやすくなっています。

失敗事例(アンチパターン)
一方で、OKRがうまく機能しなかった失敗事例も存在します。数字にばかりフォーカスしてしまい、目的意識(Objective)がチームに浸透しないケースがあります。
たとえば「売上を○%上げる」というKRばかり追いかけていると、チームが新規施策を打つ時の意義や顧客目線が置き去りになりがちです。結果、メンバーのモチベーションが下がり、数字も停滞するという悪循環に陥ることがあります。
また、OKRを人事評価と結び付けすぎるのもリスクです。挑戦的な目標を掲げると達成率が下がる恐れがあるため、メンバーが「できそうな目標」しか設定しなくなる事態に陥ります。そうなるとOKRの本来の魅力である“ストレッチゴール”がなくなり、普通の目標管理制度と変わらない形骸化が進んでしまいます。
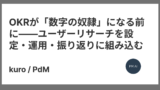
OKRを自社文化に根付かせるための工夫
OKRは単なるフレームワークではなく、“挑戦を許容する文化”を育む装置として機能する点が大きな魅力です。導入して終わりではなく、組織全体が試行錯誤を歓迎し、達成や失敗から学ぶ土壌を作っていくことが重要になります。僕も経験を通じ、意外なほど小さいチームからOKRを始めたほうが根付く場合があると感じました。
OKRと企業文化の相乗効果
失敗を許容しない風土だと、誰もが無難な数値目標を選んでしまい、挑戦的なObjectiveは立てづらくなります。
逆に、学習を評価する姿勢があれば、「結果は達成率50%だったけれど、得られた知見が大きい」といったケースでも成功体験として扱えます。
OKRが組織改革の鍵を握る理由は、この“学習を促進する仕組み”にあります。
そしてユーザーインタビューや社内ヒアリングを組織的に取り入れている企業ほど、OKRが活きる傾向が強いです。チームが顧客の声を直接理解し、「ここを改善すれば、Objectiveに近づく」と腹落ちすれば、実行力が高まります。これらの成果は、定期的に社内で可視化し、共有し合うことで、さらに強固な文化へと発展します。
目標達成を祝う仕組み・次のステップへの接続
そして、OKRは達成してもまた次の挑戦が待っています。そこで大切なのは、一定の区切りごとに目標達成を祝うイベントや場を設計し達成のプロセスをみんなで振り返ることです。振り返りの中で得られた学びを社内ドキュメントに残し、次回のObjective設定のヒントへ反映します。これこそが“OKRらしい学習サイクル”を形成する鍵です。
達成率が70%や80%でも十分成功だと見なす風土を作ることも重要です。ストレッチゴールを掲げるOKRでは、完璧な達成を求めるよりも「いかに高い目標に挑んで、何を得られたか」のほうが価値を生み出します。たとえば四半期末のレビューでは、KPIとの乖離や想定外の成果などをオープンに話し合い、次の期のOKRに盛り込んでいきます。
Q&A:よくある疑問と解決策
「OKRをチーム全員にどう浸透させる?」
トップダウンだけではなく、ワークショップ形式や社内発表会を通じて全員が目的・KRを理解する場を作ると効果的です。週次のミーティングでOKRを必ず確認し、メンバーが自分の取り組みと紐付けて話せるような文化づくりが鍵になります。
「現行KPIやMBOと混在しているが大丈夫?」
事業や組織の現状によっては、KPI・MBOをすぐに廃止できないケースがあります。その場合はあえて並走させ、KPIを維持しつつOKRを実験的に導入する手もあります。重要なのは、評価とOKRを必要以上にリンクさせないルールづくりです。初期は“KPI=守りの指標”と“OKR=攻めの目標”を分けて運用するパターンが多いです。
「途中で目標が変わったらどうする?」
四半期の途中でも目標をアップデートすること自体は問題ありません。市場環境やプロダクト戦略が変われば、ObjectiveやKRを修正するのも自然な流れです。ただし、度重なる変更はチームの混乱を招くため、その時は「どんな学びがあったのか」「なぜ変更が必要か」を丁寧に共有すると納得感が得られやすいです。
次のアクション:まずは1期分のOKR策定&振り返りを
OKRには興味があるけれど、どこから始めればいいかわからないという声もよく聞きます。個人的には、まず1期(四半期)分だけのOKRを試験運用してみることを推奨します。小さなチームや1つのプロジェクト単位でObjectiveとKRを設定し、3ヶ月後にどんな学びが得られたかを振り返ってみてください。小規模でも成功体験を積めれば、全社導入へのハードルが格段に下がります。
もし導入に際してユーザーリサーチの活用方法を学びたいと感じたら、「ユーザーヒアリングを組織に根付かせる4つの仕組みを考察した」も参考になるはずです。

参考文献・関連記事
さらに深く学びたい方は、John Doerr氏の『Measure What Matters』などを読んでみると、OKRの事例がより具体的に理解できます。実際の導入事例や運用失敗例も数多く掲載されているため、とても参考になるでしょう。
- John Doerr (2018) 『Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs』Penguin
- Felipe Castro (2021) “OKR: The Simple Idea that Drives 10x Growth,” OKR Resources
- Larry Page (Google) – OKR関連インタビュー (Business Insider, 2017)
- Sansan株式会社, freee株式会社 – OKR導入事例(各社公式ブログ)
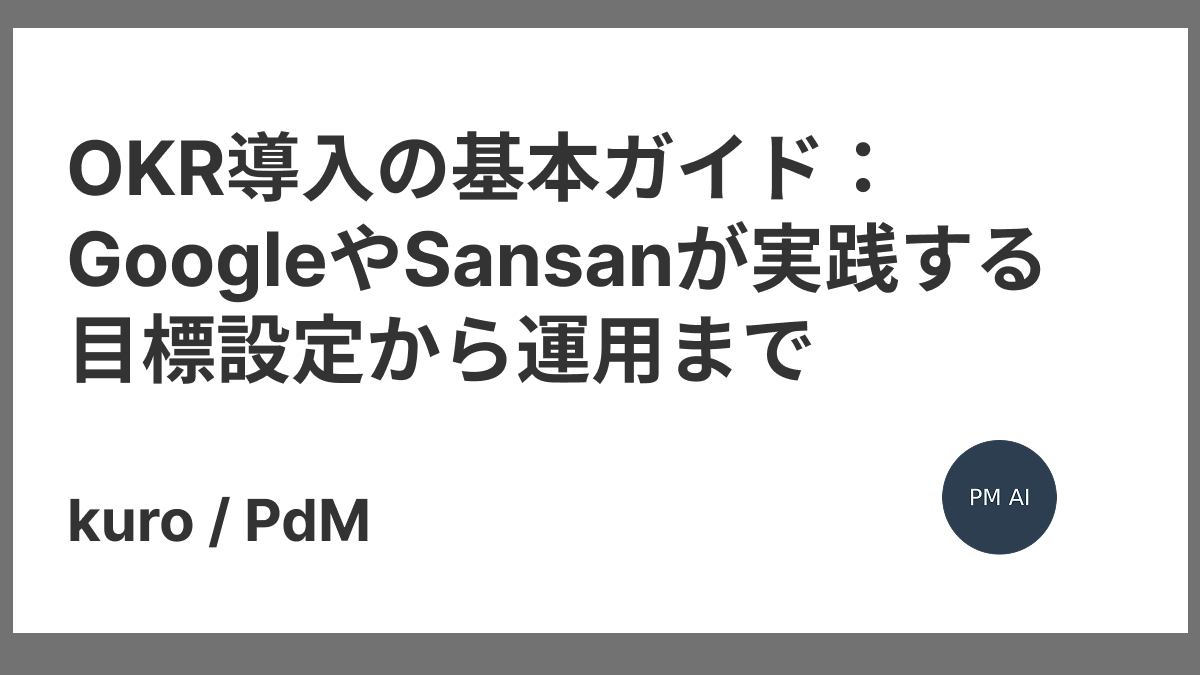





コメント