この記事の3行要約
- OKRが形骸化する原因は、KR(数値)ばかりが注目され、Objective(目的)の本質やユーザーの声が無視されることで、数字達成だけが目的化してしまうこと
- OKRレビュー前に最低1件のインタビューを実施し、「なぜ達成できないか」を深掘りすることで、数値の裏にある構造的問題や現場の実態を把握できる
- PdM・エンジニア・CS・経営層が各1〜2件ずつインタビューを行い、ダッシュボードなどに定性コメントを付記することで、組織全体に「声」を重視する文化が定着する
OKR(Objectives and Key Results)は、組織やプロダクトチームが「何を目指すのか」を明確にし、成果を可視化するためのフレームワーク。

しかし「OKRを導入したけれど、結局数字だけ追う形で形骸化してしまった…」という状態はあるあるだと思っています。
僕はその大きな原因の一つが、“ユーザーリサーチ”の不足だと思っています。数値の裏にある“本音”を見失うと、OKRはただのチェックリストに成り下がります。そうなってしまうとObjectiveというコンテクストや国語的意味を持つ指標ではなく、普通にKPIとサブKPIで運用する状況の劣化版になってしまうんですよね。本来はObjectiveを設定してまで実現したいユーザーや事業の状態があったはず。
本記事では、OKRにユーザーリサーチを組み込むことで組織とプロダクトを強くする方法を深掘りします。
なぜ、OKRが形骸化してしまうのか
数値目標だけが独り歩きする危険性
OKRは、「”大胆な”目標(Objective)」と「主要成果指標(Key Results)」をセットで定義し、組織やチームがゴールに向かって協働するための仕組みです。
John Doerrの著書『Measure What Matters』にも事例が多く示されており、Googleなどの大企業が採用して成功したことでも知られています。
しかし現実には、以下のような問題が生じがちです。
KRばかりが注目される
- 数字達成そのものが目的化し、どんな価値を創出したいのかが疎かになる
Objectiveの曖昧化
- 数字を上げろ、と言っても何をどう変えるかが見えず、形式的な目標だけが存在
ユーザーや現場の声が取り込まれない
- プロダクトや施策で不満が起きていても、数値上は表れない場合がある
このように、数字至上主義になりすぎると以下のような本質が見えなくなるリスクがあります。
- なぜこんなにもユーザー体験が変わらないのか?
- 数字が達成できない構造は何か?
- なぜメンバーがモチベーションを保てないのか?
定性面を無視すると見落とす“ヒト”の要素
組織が成長しない原因は、必ずしもメンバーのスキルや時間不足だけにあるわけではありません。
たとえば、社員へのインタビューから「タスクのやり方が分からないまま手探りで進めている」「プロセスが複雑すぎて意欲が下がる」といった声が聞こえることもあるでしょう。
OKRが形骸化すると、こうしたリアルな声を拾う機会が失われがちです。外部のユーザーや顧客の声も同様。
数値では「離脱率が高い」と見えても、なぜ離脱したのかを聞かなければ根本的な施策は打てません。結局のところ、数字と“人の声”の両方を組み合わせないと、目標達成の難しさや失敗の原因を正しく捉えきれないのです。
ユーザーリサーチをOKR管理に組み込む重要性
「ユーザーリサーチ × OKR」の相乗効果例
例えばOKRの策定・振り返り・更新の各プロセスにおいて、ユーザーや社内メンバーへのインタビュー結果を反映すると以下のメリットが得られます。
目的のリアリティ向上
- ユーザーが実際に求める価値や現場の課題がObjectiveに反映され、形骸化を防止
KRの根拠強化
- 数値だけでなく、なぜそのKRを追う必要があるのか、ユーザー目線の裏付けが得られる
チームメンバーの納得感アップ
- 現場や顧客の声が計画に織り込まれることで、主体性とモチベーションが向上
社内外のリサーチが重要な理由
「ユーザーリサーチ」というと顧客向けだけをイメージしがちですが、OKR運用では社内メンバーへのリサーチも重要。
特に、
- OKRがチーム全体に理解されているか?
- 大きすぎる目標が現場を圧迫していないか?
- 部署間で連携がうまくいっているか?
- ステークホルダーがそのObjectiveに対してワクワクし実現したいと思っているか?
などは、インタビューやアンケートでないと掴めない場合が多いです。
また、外部ユーザー(顧客)に対しても定期的にインタビューを行うことで、数値に表れない「使い勝手の不満」や「新しいニーズ」を把握し、それをOKRに活かせるようになります。
ユーザーインタビューをOKR管理に導入する仕組みづくり
インタビュー対象の選定とステップ
「じゃあユーザーインタビューやろう」といっても、意図なく数を増やしても負担が大きくなります。まずは、OKRで課題が明確になっている領域から始めるのが得策。
例えば、「登録後10分の体験を改善し、離脱率を50%削減する」というOKRがあるなら、以下のようにターゲットを絞ります。
- 社外:オンボーディングに苦労したユーザー、新規導入したばかりのユーザー
- 社内:導入サポートを担当しているCSチーム、実装フローを握っているエンジニア
インタビュー項目はOKRの達成度合いや、KRで挙げた数値がなぜ動かないのかを中心に設計。ユーザーが実際に感じている障壁や、現場が抱えるオペレーションの問題を探ります。
OKRレビューサイクルにリサーチ時間を組み込む
多くの組織が月次、四半期、もしくはスプリントごとにOKRの進捗を確認しているはず。このレビューサイクルに合わせて、少数のインタビューを回す仕組みを作りましょう。
以下のようなステップを習慣化すると、数字だけのレビューで終わらずに、「なぜうまくいかないのか/うまくいったのか?」「どこにニーズがあるのか?」を毎回得られます。
- OKRレビュー前に、社内外に対して必要最小限のインタビューを実施
- インタビュー結果を要約し、OKR達成度と並べてチームに共有
- レビュー会議で問題の本質を議論し、新たなアクションやOKR修正を検討
定量データと定性データを組み合わせる具体フロー
仮説ベースのリサーチ設計
OKRにおいて定量データ(MAU、CVR、オンボーディング完了率など)は一定明確に管理されているはず。
この定量データから見える「離脱が多い」「利用率が低い」といった現象に対して、まず「なぜか?」という仮説を立てます。
仮説の例
- 「オンボーディング画面が多すぎてユーザーが途中で嫌になるのかもしれない」
- 「社内のエンジニアが他の業務に追われて、機能修正に割く時間がないのではないか」
こうした仮説を検証するための質問をインタビューで用意し、真の原因を突き止めるのが効率的です。
質問はこちらの記事を参考に考えてみてください

調査→施策→検証のループをOKRと紐づける
ユーザーリサーチを行った結果、
- 「○○画面で7割のユーザーが戸惑っている」
- 「そもそも説明が不親切」
などの課題が見つかることがあります。
これを踏まえて施策を講じ、その後再びOKRレビュー時に「改善策は有効だったか?」を定量データと新たなインタビューで検証。
この定量→定性→改善→再度定量・定性チェックのループこそが、OKRを机上論から実践論へと引き上げるポイントです。
つまり、当たり前の話にはなってしまいますが、OKR達成のために細かいスプリントを回しましょう、ということです(OKRレビューの1ヶ月前とかだけ焦ってやらない)。
類似のプロセスは、「ログ分析→ユーザーインタビューの流れで、本当に解くべき課題を明確にする」記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。
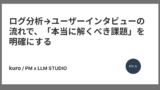
ユーザーリサーチとOKRを組織に定着させるには
チーム体制:一部の専門家任せにしない
「ユーザーリサーチ」はリサーチ部門やデザイナーだけの仕事だと思われがち。
ただ、OKR運用で成果を出すには、PM、エンジニア、CS、さらには経営層もリサーチ参加する形が理想です。
それぞれが1~2件ずつでもユーザーインタビューを行い、結果を共有することで多角的な視点が集まりますし、「自分のこの顧客 / 事業をよくする当事者なのだ」という自覚を持ちやすいです。
プロダクトマネージャーだけが情報を握っている状態では、全員に“当事者意識”が生まれにくいものです。
カルチャーづくり:数値だけでなく“声”を共有する習慣
OKRレビューや定例ミーティングなど、チームで数字を見る場は多いかもしれません。そこに必ず1~2分でもいいので“声”を挟むことをルール化すると、定性面を軽視しなくなるきっかけになります。
例えば:
- 週次・月次の報告資料に「顧客の声ピックアップ」「社員インタビューの抜粋」を載せる
- OKRダッシュボードに定性コメントを付記して、数値と一緒に可視化
- 毎週金曜日に1枠だけ、zoomのウェビナー機能や録画などを使ってステークホルダー全員が陪席するインタビューの枠を設ける
こうした“小さな取り組み”を継続し、成功体験を社内でシェアしていくと、ユーザーリサーチが組織に根付いていきます。
社内インタビューで経営層と現場のギャップを埋める
OKRは経営層の視座で設定されることが多いですが、実際に手を動かす現場メンバーが納得していないと、形骸化しやすいものです。
なので、簡単で良いので社内インタビューをしましょう。
- OKRのObjectiveを理解しているか?
- 数値目標(KR)と実務の折り合いがついているか?
- どんなリソース不足や手間があるか?
これらを聞き取り、都度フィードバックを経営側に渡す仕組みを作ると、OKRの修正や運用がスムーズに進みます。
逆に現場が主体的にOKRを決定するケースではプロダクトオーナーや事業責任者、CxOなどに以下をインタビューしたり、質問シートを作成して回答してもらいましょう
- この事業 / サービスは会社にとってどんな立ち位置と捉えているか?
- 5年後、この事業 / サービスに期待している状態は?
- どんな課題を解決するためにこの事業 / サービスをはじめたか?
- あなたの視点で今一番の課題は何か?
今日から実践できるアクション
- OKRレビュー前に最低1件のインタビューを実施
大規模調査ではなくても、小回りの利く少数インタビューを毎回回せば積み重ねが大きくなります。 - インタビュー項目はOKRの達成度に紐づける
「なぜ達成できないか?」という問いを深掘りする質問設計を行い、真因を発見。 - ダッシュボードや報告資料で“声”を見せる
KPIグラフの隣にユーザーや社員の本音を抜粋して掲載するだけでも意識が変わります。 - インタビュー結果をOKR自体に反映させる
新たなObjectiveやKRを設定する際に、インタビューの学びを明文化。形だけの変更ではなく根拠づけを。 - 成果が出たら共有し、評価する
インタビューを契機に課題発見→解消まで至った事例を社内に広め、リサーチ文化を育てましょう。
Q&A
- Q. インタビューするリソースが足りません。どの規模で始めるのがいいでしょうか?
- A. 1人でも、週1回・月1回など小さくて構いません。重要なのは継続と共有。大掛かりに始めず、小さな一歩を積み重ねる方が定着します。
- Q. 経営層が数字重視で、定性面に時間を割きたがりません。
- A. 数値の裏にある原因を説明するために「具体的な声」を交えてレポートすると、説得力が高まります。経営指標の変動を「なぜ」と問えば、耳を傾けてもらえる可能性が高いです。
- Q. ユーザーリサーチで得られた情報をOKRにどう紐づければいいですか?
- A. ユーザーの課題や満足ポイントを、Objectiveの方向性やKRの指標に反映します。たとえば「不満として最多だった操作性を改善する」をObjectiveにし、「操作時間を半減させる」「問い合わせ数を3割削減する」などをKRに置き換えると効果的です。
参考情報
- John Doerr (2017). Measure What Matters. Portfolio.
- Eric Ries (2011). The Lean Startup. Crown Business.
- Harvard Business Review (2021). “What Makes an OKR System Successful?”
- Nielsen Norman Group: Articles on User Experience & Research
- McKinsey & Company (2020). “Data to Value” (Organizational Research)
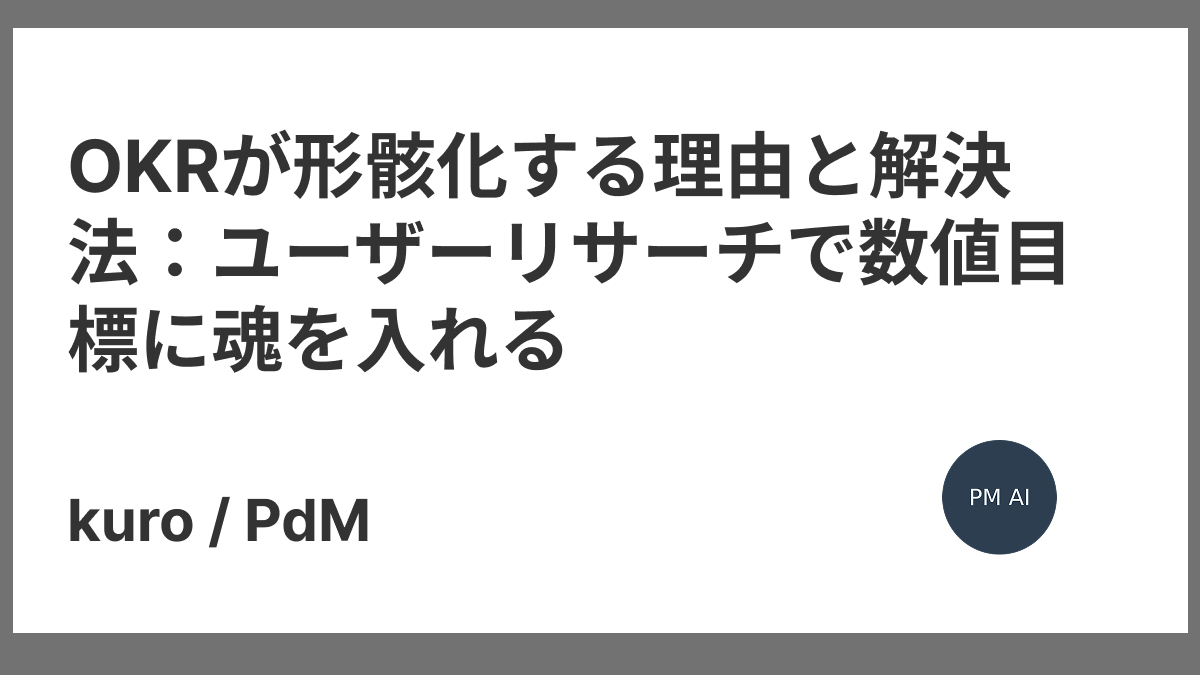





コメント