この記事の3行要約
-
ユーザーの現場を観察して、言葉に出ない行動や背景を事実として記録するのがエスノグラフィー。インタビューの弱点を補完できる
-
エスノグラフィー調査の進め方は「対象と許可の確定 → 客観的な観察・記録 → 追跡インタビュー → データ統合」。実施後はチームで共有し優先度づけへ。
-
ログ分析やLostness指標と組み合わせると、観察対象を絞り原因特定が速くなる。改善施策に直結しやすい。
「インタビューなどユーザーが口頭で語る情報は大切だけど、それだけでは実際の行動やコンテキストを十分に把握できないのではないか?」と思ったことはないでしょうか?
実際、僕自身プロダクトマネージャー、マーケターとして700人を超えるユーザーインタビューを行ってきましたが、インタビューだけでは掴みきれない課題に直面することも多かったです。
そんなPdM、マーケター、リサーチャーの方におすすめしたい手法が「エスノグラフィー調査」。エスノグラフィー調査は、ユーザーの現場を観察し、言葉だけでは表現されない行動や心理をリアルに捉える手法です。インタビューを補完し、顕在化しきっていない課題やニーズを浮き彫りにするために有効なのです。
特にデジタルプロダクトでは、UI上の小さな違和感や実際の操作方法など、ユーザー自身が認識していない“使い方の癖”が存在します。エスノグラフィーを導入すれば、ユーザーがどのような環境・気持ちでアプリやサービスを利用しているのか、より深く探れるのです。
インタビューの限界とエスノグラフィーの必要性
言葉では語られない本音や背景
ユーザーインタビューは、ユーザーの声を直接聞くことができる手法ですが、どうしても「ユーザーが語れる範囲での回答」になります(もちろんその中で最大限ファクトを引き出すことが重要)。
ユーザー本人が意識していない問題点や、“無自覚の使い方”は表面化しづらいケースも。インタビューの最中に思いついたことだけを述べるケースも多く、そこには潜在ニーズの見落としが潜んでいます。
一方、エスノグラフィー調査ではユーザーの実生活や実使用の現場を観察し、言葉には出てこない行動を事実として捉えることができます。
体験の文脈(コンテキスト)の重要性
ユーザーがプロダクトを使う状況は多種多様です。たとえば、
- どんな端末を使っているのか
- 周囲の環境は騒がしいのか
- 利用時間は深夜帯なのか
そうしたコンテキストが変わるだけで、UIの使い勝手や機能の優先度も変化します。
エスノグラフィーでは、ユーザーの“置かれている環境”そのものを記録し分析します。これにより「実際の利用状況では、想定していないデバイスを使っていた」などの予想外の事実を発見でき、プロダクト開発の方向性を修正するきっかけになります。

エスノグラフィーとは何か?
文化人類学に由来する手法
エスノグラフィーはもともと文化人類学の調査手法として生まれた考え方で、特定のコミュニティや文化に入り込み、その人々の行動や価値観を観察・記録することに主眼を置きます。社会の現場を直接見ることで、インタビューや質問票では得られない“生の情報”を把握するのが特徴です。
ビジネスやUXリサーチの領域でも、この「現場に張り付いてを実際に観察する」アプローチが注目され、ユーザーがどのようにプロダクトやサービスを使っているのかを生々しく把握するために使われています。
サービス開発やUXリサーチにおける活用事例
たとえば、以下のようなケースが挙げられます
- 小売
- 店舗での顧客行動を記録し、商品配置やレジ動線を最適化
- toCソフトウェアプロダクト
- ユーザーの自宅や職場を訪問し、どのようにデバイス操作を行っているかを観察する
- アプリが生活者の実態の利用時間の中でスムーズに使えるUIUXの着想を得る
- toBソフトウェアプロダクト
- 採用担当者がどのようなタイミングでツールを開くか
- どんなデバイスで応募者情報を確認しているかを現場で観察し導線設計を大幅に見直す
エスのグラフィー調査のプロセス
ここでは、実際にどうやってエスノグラフィー調査をやっていけば良いのか?という点について解説します。
調査対象の選定や事前許可
エスノグラフィーを始める際、まずは観察対象のユーザーを決めます。どの属性の人を観察すると得られるインサイトが大きいのかを明確にし、事前に「どの場所・どの時間帯」を観察させてもらうかを取り決める必要があります。
また、ユーザーや組織によってはプライバシーや情報セキュリティ上の懸念もあるため、観察や記録に関して十分な許諾を得ることが不可欠です。秘密保持契約(NDA)などを結ぶ場合もあります。
実際の観察記録とノートテイキング
観察時には、「何が起こっているか」を客観的に記録するスタンスが重要。
- ユーザーの操作時間や動線
- 会話の内容
- 表情
- しぐさ周囲の環境
のような定性情報も収集します。
スマホでの撮影やメモ帳でのタイムスタンプ付き記録を併用し、後で見返したときに“行動の変化”を捉えやすいようしておくのがおすすめ。また観察後には速やかにノートを整理し、発見や疑問点をまとめるのがコツです。
情報量が莫大なので、全力で、かつ即時メモしないと忘れます。
インタビューとの組み合わせ、データの統合
エスノグラフィー単体では“行動の事実”が中心になるため、観察後にはユーザーへの簡単な追加インタビューを行うのがおすすめ。
- 「なぜ、その操作をしたのか」
- 「どういった背景があるか」
などを当人に確認し、観察内容と紐づける形で理解を深めます。
最終的には観察データ(行動記録)とインタビューの音声や発言内容を1つのリサーチデータベースに格納し、タグ付けや分類を行うと後から分析しやすくなります。詳しくは、質的データ分析に関する「『質的データ分析』がプロダクトマネジメントにもたらす価値とは?」を参照ください。

エスノグラフィーで明らかできる「潜在ニーズ」とは
顧客自身が気づかない行動や工夫
ユーザーは、日常の中で自然に生まれたワークアラウンド(本来の操作手順とは違う独自の使い方)を行っていることがあります。
たとえば、システム上の制約を回避するために「別のアプリにコピーして作業する」など、ユーザーが“勝手に”開拓した手順です。
このような裏技的行動は、本人ですら「普通にやっているだけ」と考えている場合が多いですが、それはプロダクトへの課題を示唆する大きなヒントでもあります。
実際に、「ユーザーの『裏タスク』を特定して、プロダクトグロースのチャンスを見つける」の記事でも触れていますが、ワークアラウンドの発見こそが、プロダクトの進化を加速させる場合があるのです。

調査後、具体的にプロダクトへ反映する方法
エスノグラフィーで得た知見をどのようにプロダクトへ活かすか?
まず観察時の動画や写真、メモを抜粋してチーム全体に共有するのが最初の一手。百聞は一見に如かずで、テキストだけでは伝わらない“現場の温度感”がチームの共通認識になりやすいです。
その後、発見した課題や機能要望をリストアップし、優先度を検討します。単に「こう使われていた」という事実だけでなく、
- 「なぜそうしなければならなかったのか」
- 「どうすれば解消できるのか」
などをチームで議論すると、具体的な改善施策の方向性が見えてきます。
ログ分析・ユーザビリティテストと組み合わせ
ログ分析で絞り込み→エスノグラフィーで深掘り
ユーザー数が多いサービスでは、まずログ分析で
- 「どの画面で離脱が多いのか」
- 「どのボタンが意外とクリックされていないか」
などを把握するのが効率的。そのうえで、特定の現象が多発しているユーザー群を選び、エスノグラフィーで実際の使い方を観察すると“理由”を突き止めやすくなります。エスノブラフィーや行動観察はインタビューに比べると長く時間を取れることが多いので、ついつい「仮説なし」「仮説が曖昧」な状態で臨んでしまいがちなんですよね。
このような定量(ログ分析)と定性(エスノグラフィー)の組み合わせは、データドリブンとユーザードリブンを両立させる手堅いアプローチです。
Lostness指標との組み合わせる
また、ユーザビリティテストで用いられる「Lostness指標」は、ユーザーがどれだけ迷走しているかを数値化する指標。定量的に「ここで迷っているユーザーが多い」とわかったとき、実際の使用場面をエスノグラフィー的に観察すれば、なぜ迷っているのかの具体的要因が明確になります。
エスノグラフィーを実施する際の対象を絞る手段として、こうした定量的指標を参考にするのは効率的です。迷っている場面のリアルな行動や心理を観察すれば、根本的なUI設計や情報配置の問題点を発見できます。

ユーザーインタビューとの使い分け
- インタビューはユーザーの声を聞く“言語ベース”のアプローチ
- エスノグラフィーは行動を中心に観察する“実地ベース”のアプローチ
両者を組み合わせることで、ユーザーの「言動の不一致」まで含めて把握できる点が最大の強みといえます。
もし、インタビューが形骸化しがちだったり、ユーザーが本音を隠しているように感じたら、ぜひエスノグラフィーを導入してみてください。僕自身、実際にユーザーのオフィスで操作画面を観察したり、ユーザーが普段使っているカフェでサービス利用以外も含めた生活を見せてもらった際に、「そんな実態があったのか!」と思った経験を何度も味わっています。
参考情報
・Spradley, J. P. (1980). Participant Observation. Thomson Learning
・Blomberg, J., Giacomi, J., Mosher, A., & Swenton-Wall, P. (1993). Ethnographic field methods and their relation to design. *Participatory design: Principles and practices*
・Crabtree, A., Rodden, T., Tolmie, P., & Button, G. (2009). Ethnography considered harmful. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*
・「質的データ分析」がプロダクトマネジメントにもたらす価値とは?
・ユーザーの「裏タスク」を特定して、プロダクトグロースのチャンスを見つける
・ユーザビリティテストの分析手法「Lostness」「タスク間連関分析」を解説
今日から実践できるアクション
- ログ分析やインタビュー情報を活用して、観察対象を絞り込む:定量データで「離脱や迷いが多いユーザー層」を把握し、その中からエスノグラフィーの対象を選定する
- 現場観察のプロトタイプ実施:まずは少人数のユーザーを対象に、1~2時間程度の観察を行う。撮影やメモを徹底して現場のリアルを捉える
- 観察後すぐに追加インタビュー:なぜその行動を取ったのか、違和感があったのかなどを本人に直接確認して、観察データと発言を紐づける
- 結果をチーム全体で共有:可能なら写真や動画を編集し、開発チームやデザイナーが視覚的に理解できる状態にまとめる。次の開発アイデアを出す場に活用する
Q&A
Q1:エスノグラフィーの実施に時間やコストがかかりすぎるのではありませんか?
A1:確かにコストはかかりますが、その分得られるインサイトも深いです。全部のユーザーを対象にする必要はなく、ログ分析やアンケートで現象を絞り、その上で代表的なユーザーを数名観察するだけでも大きな発見につながります。
Q2:観察時にユーザーが緊張して、普段の行動をしてくれないことはありますか?
A2:最初は意識してしまうユーザーもいます。ただ、時間が経つにつれて慣れ、自然な行動を取ってくれることが多いです。あらかじめ「目的は使いづらい点を改善するため」などを説明して、協力を仰ぐと良いです。
Q3:社内でエスノグラフィーの必要性を理解してもらえない場合、どう説得すればいいでしょうか?
A3:観察映像や具体的なエピソードを共有すると説得力が増します。目に見える形で「ユーザーはこんな行動をしている」という事実を示せば、定性調査の価値が伝わりやすいです。また、インタビューだけでは得られない新しい課題やアイデアが生まれる事例を提示するのも効果的です。
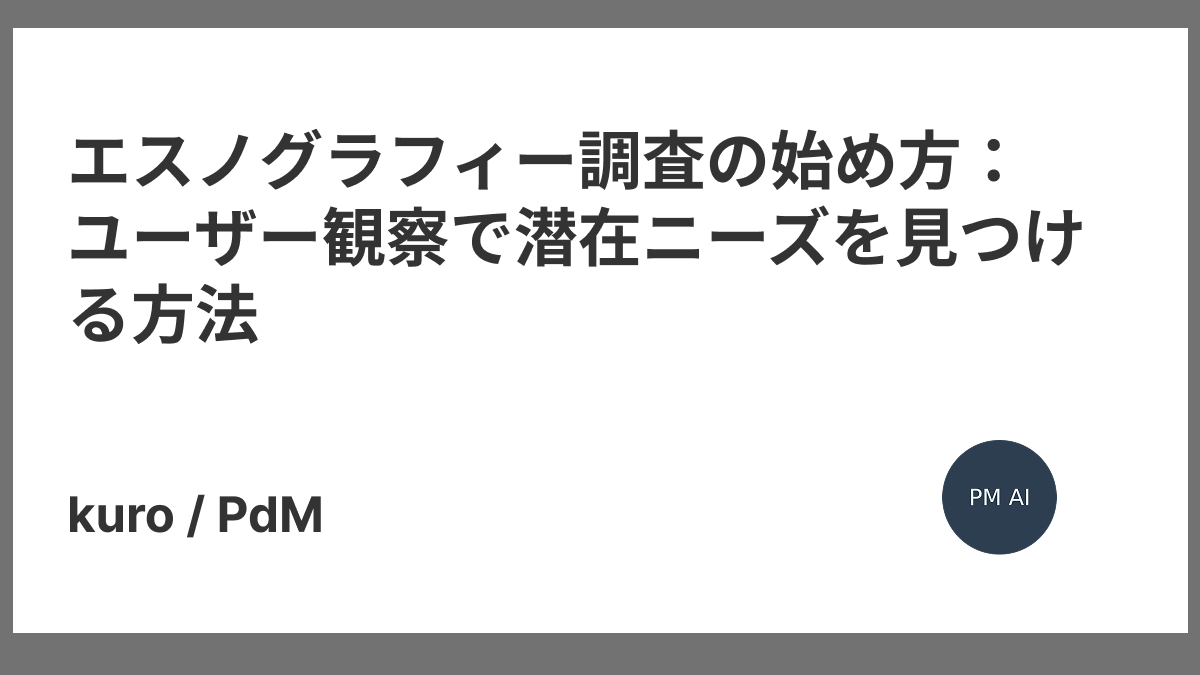
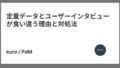
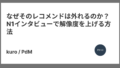
コメント