この記事の要約
- “確率思考”とは不確実な状況で「起こりやすさ」を数値化し、期待値計算により合理的な意思決定を行うフレームワーク
- プロダクト開発では機能の成功確率×インパクトで優先順位を決め、複数シナリオを想定してリスクを最小化できる
- ベイズ推定により初期仮説を新データで更新し続けることで、少ないサンプルでも精度の高い予測が可能になる
- USJ再生の裏にあった“数字で語る”マーケティング
- 「絶対に失敗できない」場面でこそ、確率思考マーケティングが威力を発揮する
- ポイント ①:マーケティングの3要素「プレファレンス・認知・配荷」
- ポイント②:NBDモデルによる“プレファレンス”の数理的理解
- ポイント③:「プレファレンス」を生む3つの要素
- ポイント④:「差別化」は“M”を増やすための手段にすぎない
- ポイント⑤:プレファレンスを高める「水平拡大」と「垂直拡大」
- ポイント⑥:明確な目標設定とギャップ分析で感情に流されない
- ポイント⑦:戦略家の仕事は「自分と他人の時間配分」を管理すること
- ポイント⑧:「組織づくり」から逆算せよ – データドリブン文化を根付かせる
- 参考情報
- 今日から実践できるアクション
- Q&A
USJ再生の裏にあった“数字で語る”マーケティング
『確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力』(著:森岡 毅・今西 聖貴)は、日本を代表するテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」の経営再建を通じて得られた“数字に基づくマーケティング”手法を明らかにした一冊。
USJはかつて集客低迷に苦しんでいましたが、ハリーポッターエリア導入などの施策で見事にV字回復を成し遂げました。その際に著者らが実践したのが「確率思考」と呼ばれる定量分析手法。
具体的には、「ここに投資すれば成功確率が高い」という領域を精緻な分析によってあぶり出し、失敗が許されない大きな賭けを成功へ導きました。本書では、このときの考え方やフレームワークをマーケター向けに解説しています。ですが、その本質は単にテーマパークに留まらず、プロダクトマネジメントの現場でも応用できる示唆に溢れています。特に、大型施策を打つ際に「数字による裏付け」をどう取り入れるか、その方法を学べるのが本書の魅力です。
本書全体は、数理的マーケティングの基礎から、USJでの具体的実践、さらに組織づくりに至るまでを段階的に解説する構成です。マーケティングの歴史的背景や、ブランド・エクイティー、認知度、配荷(チャネル戦略)の重要性が紹介され、最終的にはどのように組織を構築すれば「確率思考」を全社レベルで浸透させられるかが説かれています。
「絶対に失敗できない」場面でこそ、確率思考マーケティングが威力を発揮する
USJにおいてハリーポッターエリアの導入は、数百億円単位の大規模投資を要するプロジェクトでした。失敗すれば経営に甚大なダメージを与える、まさに「絶対に外せない勝負」。そこで著者たちが重視したのが、“合理性で担保されている領域”を極限まで大きくすることです。
本書によると、思いつきや勘に頼るのではなく、市場調査やユーザーデータをもとに「勝てる確率」を高めるアクションを徹底的に積み重ねる。それによって失敗のリスクを最小化し、成功の蓋然性を高める考え方が「確率思考」です。
PdMの視点でも、新規機能の投入や大規模リニューアルは多くのリソースがかかる一大プロジェクト。失敗の可能性を少しでも減らすには、ターゲット設定や需要予測などの検証を入念に行う必要があります。本書が示す「理詰め」での攻め方は、こうしたPdMの課題解決にも応用できるはずです。

ポイント ①:マーケティングの3要素「プレファレンス・認知・配荷」
本書はマーケティング施策を設計する際に、
- プレファレンス(支持・好意度)
- 認知(ブランドや製品を知ってもらう)
- 配荷(流通・チャネル施策)
の3つに注目せよと提唱しています。
これは消費者がなぜその商品を継続的に選び続けるのかを分解しています。
具体的には、以下の通り
- プレファレンス(M):消費者がブランドや製品を「好き」「選びたい」と感じる度合い
- 認知:そもそもその製品があることを知っているかという基本的条件
- 配荷:製品がどこでどれだけ流通しているか、買いやすい環境があるか
たとえばUSJの場合、新施設導入という大ネタで認知を拡大すると同時に、TVCM・広告などの戦略を駆使して「行ってみたい!」というプレファレンスを高めることに成功。さらに交通の便やチケット販売チャネルなど、配荷の側面で障壁を減らす努力も行いました。PdMの立場でも、たとえば「新機能が存在していることを十分周知できているか(認知)」「ターゲットユーザーの課題に直結する価値を提供し、ファン化しているか(プレファレンス)」「ユーザーが実際に導入しやすい購入/登録フローは整っているか(配荷)」を点検する必要があります。本書は、その整合性こそが施策成功の前提だと強調しているのです。

ポイント②:NBDモデルによる“プレファレンス”の数理的理解
プレファレンスが重要なのはわかったとしても、それをどう定量化すれば良いのか。そこで登場するのがNBDモデル(Negative Binomial Distribution)です。これは「ある期間内にユーザーが何回製品を購買・利用するか」という頻度分布を扱うモデルで、マーケティングの世界では購買頻度やリピート率を分析する際にしばしば用いられます。
NBDモデルでは以下の2つのパラメータが重要とされます。
- M:ユーザー1人あたりの平均的な購買回数(または利用頻度)
- K:個々のユーザーが購買・利用する確率分布の形状を決めるパラメータ
本書によれば、企業側がコントロール可能なのは主に「M=プレファレンス」のみ。「K」については、ユーザー固有の属性や外部環境に左右されがちで、企業が直接働きかけにくい領域とされています。したがって、プレファレンス(M)をいかに引き上げるかがマーケティング戦略の要。裏を返せば、プロダクトへの愛着やロイヤルティを高める施策こそが最も重要だといえます。
USJでは、このNBDモデルを活用して、エリア導入後にリピート来場者がどれくらい増えるか、どのくらいの期間で投資を回収できるかをシミュレーション。投資のリスクとリターンを冷静に評価したことで、合理的な根拠を持ってハリーポッターエリア導入を決定できたわけです。
PdMの世界でも、新機能リリース後の継続利用率アップやユーザー当たりの利用頻度向上を数理的に見積もるフレームとしてNBDモデルを応用可能です。
ポイント③:「プレファレンス」を生む3つの要素
プレファレンス(M)を高める具体的な要因として、本書はブランド・エクイティー、価格、製品パフォーマンスの3つを挙げています。ここでブランド・エクイティーが最重要とされている点がユニークです。
- ブランド・エクイティー:ユーザーが持つブランドイメージや世界観、ポジショニングなど。ここが高いと「多少価格が高くても選ぶ」「多少欠点があっても愛用し続ける」という心理的ロイヤリティが生まれる
- 価格:ユーザーが同様の価値を感じる他製品と比べてお得感があるか。コストと価値のバランス
- 製品パフォーマンス:品質・性能の高さやユーザー体験の良さ
USJの事例では、「USJに行くと夢の世界に浸れる」というブランド・エクイティーを大幅に強化したうえで、チケット価格とアトラクションの質(製品パフォーマンス)のバランスを調整し、結果としてユーザーの来場意欲を高めました。
PdMとしては、たとえば新機能やUI/UXを向上させるだけではなく、「このサービスならではの世界観・メッセージ」がユーザーの頭にインプットされているかを意識する必要があります。ブランドの核を押さえることで、ユーザーの支持や愛着が得やすくなるのです。
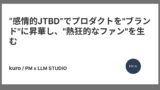
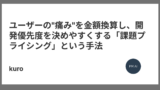
ポイント④:「差別化」は“M”を増やすための手段にすぎない
多くの企業が市場で勝つために「差別化」を掲げます。しかし本書は、「差別化の目的を取り違えてはならない」と警鐘を鳴らします。そもそも差別化とは、「プレファレンスを高める」ための手段にすぎないというのが著者の主張です。
サービスやプロダクトにユニークな機能を入れるだけでは、ユーザーの心を掴めないケースがよくあります。競合と違う点を作っても、それがユーザーの求める本質とズレていれば、利用頻度も上がりませんしファン化もしません。重要なのは「競合とは異なる強み」がユーザーの重視ポイントに合致しているかどうか。
PdMは、ユーザーインタビューや定量調査を通じて、ユーザーが本当に望む価値を正確に把握することが必要です。そのうえで強みを尖らせることこそが、確率思考マーケティングの成果を最大化するカギといえます。

ポイント⑤:プレファレンスを高める「水平拡大」と「垂直拡大」
マーケティングにおいてユーザーの支持度(プレファレンス)を伸ばすには、大きく2つの方向があります。「水平拡大」と「垂直拡大」です。これは本書でも具体的事例を交えながら紹介されています。
- 水平拡大:ユーザー数そのものを増やす。幅広い層に対して製品の魅力をアピールし、新規利用を促す。USJの例なら、ファミリー層から大人層まで広くターゲットを取り込んだキャンペーンを打った。
- 垂直拡大:既存ユーザーの利用頻度や課金額を高める。たとえばハロウィンイベントやハリーポッターの新プログラムなど、リピーターがさらに来場回数を増やす仕掛けを提供。
本書の見立てでは、大衆市場を狙う場合は水平拡大が先行しやすいという指摘があります。母数が大きければ口コミやSNSでの拡散効果も高く、ブランド認知とプレファレンスが相乗的に上昇するためです。
ポイント⑥:明確な目標設定とギャップ分析で感情に流されない
本書では、「目的と目標を明文化し、その達成に必要な要素を定量化せよ」と繰り返し強調されます。USJのハリーポッター導入も、どのくらいの来場増加が見込めるか、チケット単価の上昇やリピーター増加がどれほどになるかなど、シミュレーションを積み重ねたからこそ意思決定できたと言います。
PdMの立場で言えば、
- 「リリース後6か月で○万人の新規ユーザーが欲しい」
- 「月間アクティブユーザー(MAU)を○%向上させる」
といった形で、数字を使ってゴールを定めることが肝要。さらに、現状と目標の間にあるギャップを洗い出し、「ここを埋めるためにはどの施策が最も効果的か?」を考え、優先度をつけてリソースを投下する。これがいわゆる「確率思考マーケティング」のコアでもあります。
このフレームワークがあると、上司の鶴の一声や過去の成功体験に引っ張られすぎず、理性に基づいて意思決定しやすくなるメリットがあります。実際に日本企業では、曖昧なコンセンサスを重んじる文化が強く、感覚や空気感で決まる施策も多い。しかし本書のメッセージは明確。「データや定量的根拠を中心にすべきだ」と強く訴えています。
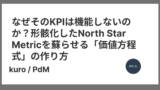
ポイント⑦:戦略家の仕事は「自分と他人の時間配分」を管理すること
本書後半の大きなテーマが「戦略家の思考法」。
著者らはマーケターの仕事を「A)自分の時間をどう使うか」「B)他人の時間をどう集中させるか」の2軸で捉えます。PdMも、ロードマップ策定や機能優先度決定などで、チームのリソース配分をコントロールする立場にありますが、日々のこまごまとしたタスクに追われるあまり、本来の戦略立案に十分な時間を割けないことがあります。
著者が語るのは、戦略家は意図的に「実行の最前線」を一歩引いて見渡す必要があるということ。USJの例でも、森岡氏が自らマーケティング施策を細部まで全部やるわけではなく、彼の考え方をチーム全体に浸透させ、各部署が主体的に動ける状況を作り上げました。PdMもエンジニアやデザイナー、セールスなど多職種の力を連結させる存在であり、適切に意思決定の優先度を伝え、彼らが成果を最大化できるように導くのが理想的な姿といえます。

ポイント⑧:「組織づくり」から逆算せよ – データドリブン文化を根付かせる
本書終盤では、確率思考マーケティングを社内に根付かせるための組織デザインが取り上げられます。具体的には、マーケターと調査部門(データアナリストなど)がダイレクトにつながる構造にすること、経営トップがマーケティングを経営戦略の中核と位置づけることの重要性が語られます。
この点はPdMの業務にも直結します。製品開発とデータ分析、ユーザーリサーチが断絶していると、どれだけ優れた施策も反映までに無駄なタイムラグが生じがち。理想的にはPdMが定性・定量データを常に参照できるよう、ダッシュボードやリサーチレポートが統合された環境を持つ。さらには、社内の誰もが「数字で語る」文化を共有し、プロダクト指標をウォッチしたうえで改善アイデアを出せるようにする。こうした組織基盤こそが、本書の言う「確率思考マーケティング」を推進する土台と言えます。
参考情報
- 森岡 毅 & 今西 聖貴 (2016) 『確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力』 東洋経済新報社
- Andrew Ehrenberg (1959) “The Pattern of Consumer Purchases.” Applied Statistics
- Philip Kotler, Kevin Keller (2016) 『Marketing Management 15th Edition』 Pearson
- 安宅 和人 (2012) 『イシューからはじめよ』 英治出版
- 日本マーケティング協会 (2020) 『マーケティング戦略研究事例集』
今日から実践できるアクション
1. 定量的な目標設定とNBDモデルの導入
NBDモデルを完璧に使いこなす必要はありませんが、ユーザーあたりの利用回数やリピート率を計測し、施策との相関を試験的に調べるだけでも有意義です。「M」を伸ばす施策に注力する意識をチームに浸透させましょう。
2. ブランド・エクイティーを可視化する
価格や機能だけでは測れない「ブランドの魅力」「世界観」を評価する指標を持ち、ユーザーインタビューやアンケートで定期的に測定する。競合と比較した際の自社の“差別化ポイント”がプレファレンスを高めるものかどうかを確かめましょう。
Q&A
Q1. ハリーポッター導入の成功ポイントをPdMに置き換えると?
A1. USJは大規模投資を回収するために明確な集客シミュレーションを行い、「絶対にコケられない施策」の成功確率を高めました。PdMで言えば、新機能やリニューアルの投入時に予算対効果を冷静に見積もり、エンジニアやデザイナーを巻き込んで成功シナリオを練ることに似ています。
Q2. NBDモデルに馴染みがない場合はどう始めればいい?
A2. まずはユーザーの利用回数を定期的に追跡し、セグメント別に違いを見比べるだけでもOK。たとえばリピート率が高い層と低い層でどんな特徴があるのかを把握するだけで、次の施策アイデアが出やすくなります。そこから徐々に統計的手法を導入すれば十分です。
Q3. プレファレンス(M)を高めるにはどうすればいい?
A3. 製品の基本性能(パフォーマンス)や価格競争力を整えるのは大前提。そのうえでブランド・エクイティーを高めることが鍵になります。具体的には「このブランドらしさ」をユーザーに強く印象づけるUIデザイン、コミュニティサポート、ロイヤルユーザーへの限定特典などが有効です。
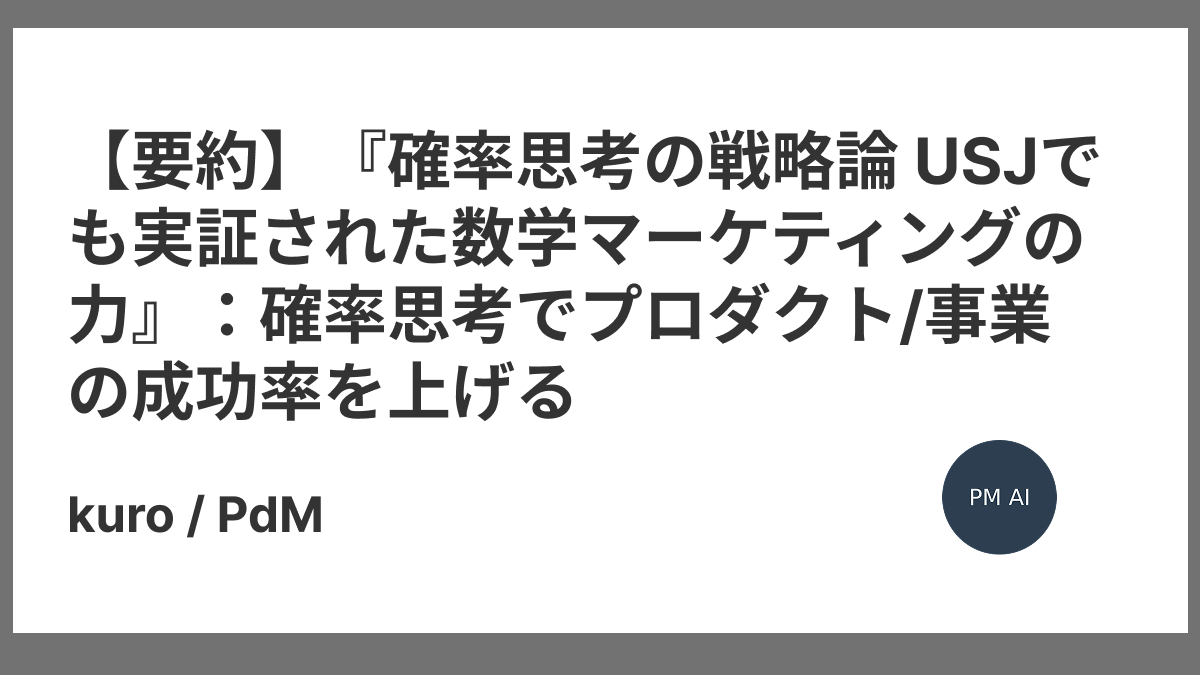



コメント