この記事の2行要約
-
プロダクトチームで日常的に使う言葉は思考や判断を誘導し、文化やアウトカムに影響する
-
「脳死」などの表現は議論の質やモチベーションを下げやすく、代替フレーズへの置換が有効
なぜ“チーム内で使う言葉”がプロダクトに影響するのか
プロダクト開発は、複数の機能やロードマップを検討しながら進みますが、その根底にあるのがコミュニケーションです。
どんな機能も、最初は「こんな価値があるはず」「ユーザーはこう感じるはず」という言葉のやりとりから始まり、最終的に合意してリリースに至ります。
もし言葉がネガティブ過多だったり、無意識にユーザーを蔑視するような表現が混ざっていると、チーム全員の思考回路や価値判断に影響を及ぼしやすいです。
言語学にSapir-Whorf仮説(言語相対論)でというものがあるそうなのですが、そこには「使う言語が思考や認知の枠組みを規定する」という考え方があります。
厳密にこの仮説がどこまで当てはまるかは議論の余地がありますが、実際、チーム内の日常的な言葉が“当たり前の思考パターン”を作る現象はしばしば観察されます。
例えば「ユーザーが脳死で使う場面」とかの言葉は細かいですが、「それ、本当にユーザー目の前にしてその言葉使う?」という問いに対して自信を持って「yes」と言えるでしょうか?
「脳死」発言は何が問題か?言語が思考を誘導する
「脳死で作業/ユーザーが脳死で使うシーン」という表現をチームで何気なく使っていませんか?
この言葉は確かに「頭を使わないで機械的に進める」という状態を表しているかもしれません。
しかし、それを“脳死”というセンシティブな言葉で雑に表すと、思考停止を肯定しているような雰囲気を醸成する危険があります。
実際、「脳死でやる」と常態化している組織は、“どうせ考えても変わらない”とか“作業なんてそんなものだ”という無意識の風潮を作ってしまう可能性が高いです。加えて、仮にユーザーの関係者に本当にそういった状態になっている人がいるということに想いを巡らせると、自然とそんな表現は使わなくなるはずです。
もし
- “ユーザー理解”
- “クリエイティブな発想”
- “ユーザーファースト”
を求めるチームなのであれば、この言葉は深刻なブレーキ、もしくは誤った方向へのアクセスになり得ます。
少しだけ学術的視点で、言葉がチーム文化を育む仕組みを解説
言葉がチームの文化や思考習慣に影響を与える背後には、社会言語学や認知言語学の理論があります。
言語相対性仮説(Sapir-Whorf)やラベリング理論を引き合いに出すまでもなく、普段使う単語が思考をフィルターにかける作用は、日常会話でも感じられるはず。
プロダクトチームでは、議論やユーザーストーリーの策定など、言葉のやりとりが大半を占めます。
このときポジティブな言葉遣いが多いチームほど、失敗を許容しやすくイノベーションが起こりやすい(Edmondson, 1999 “Psychological Safety”の概念とも関連)という指摘もあります。
一方で「どうせ無理」「面倒くさい」といった表現が跋扈するチームは、新しい試みに腰が重くなる。
関連リンク
- ユーザーヒアリングを組織に根付かせる4つの仕組みを考察した
チーム文化・仕組みづくりの視点 - 心理学を活用してユーザーインタビューからバイアスを排除し“本音”を引き出す
言葉が思考バイアスにどう関係するか - 生成AI時代のプロダクトマネージャーが果たすべき役割とスキル
言葉やコミュニケーションの重要性にも通じる話題
今日から実践できるアクション
- 代替フレーズを検討:
「脳死→ルーティンタスク」「面倒→時間コストがかかるが有益」など、言い換え案をチームで話し合う。 - 3~5個の価値観を決め、その言葉を日常で使う:
例:「ユーザーに寄り添う」「失敗を許容し、学習する」「データで会話する」。このフレーズを議論で意図的に用いる。 - “言葉のガイドライン”を可視化:
NotionやConfluence、Slackの固定投稿などで一覧化し、新メンバーにも共有。 - 定期的にフィードバック:
面白い発言や不適切な表現が出たら軽く指摘し、みんなで習慣づける。強制ではなく合意形成を重視。
Q&A
Q1. ネガティブな言葉を一切使わないのは不自然ではありませんか?
A. 本質は“禁止”より“価値観を見失わない言葉遣い”を目指すことです。例えば「面倒くさい」と言いたいときも、「ここに工数がかかる」と事実ベースで説明し、チームでリターンとのバランスを議論できる表現にするのが理想です。Q2. 普段使わない言葉を無理に入れると、逆に表面的になりませんか?
A. 確かに行動が伴わなければ“言葉だけ”の飾りに終わります。ただ、日常で言い換えを意識するだけでも、思考や態度が微妙に変わるという研究結果(Lupyan, 2012)もあります。実践を続けていくと、その言葉に合った行動が自然と育っていくことが多いです。Q3. チームは若い人が多く、スラングやネタ表現が多くて、注意すると萎縮しそうです。
A. 完全に排除する必要はありませんが、“ネタ”が特定の人を傷つけたり、思考停止を招いたりしないかが判断基準です。言葉を変えるのはあくまでチームの成長のため。背景を丁寧に説明し、「こういう意図で変えていきたい」と合意を得ることで反発を抑えられます。
参考情報
- Sapir, E. (1929). “The Status of Linguistics as a Science.” Language.
- Whorf, B. L. (1956). Language, Thought, and Reality. MIT Press.
- Lupyan, G. (2012). “Linguistically modulated perception and cognition: The label-feedback hypothesis.” Frontiers in Psychology.
- Edmondson, A. (1999). “Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams.” Administrative Science Quarterly.
- Atkinson, D. (2004). Language Socialization. In: Sociolinguistics (Cambridge University Press).
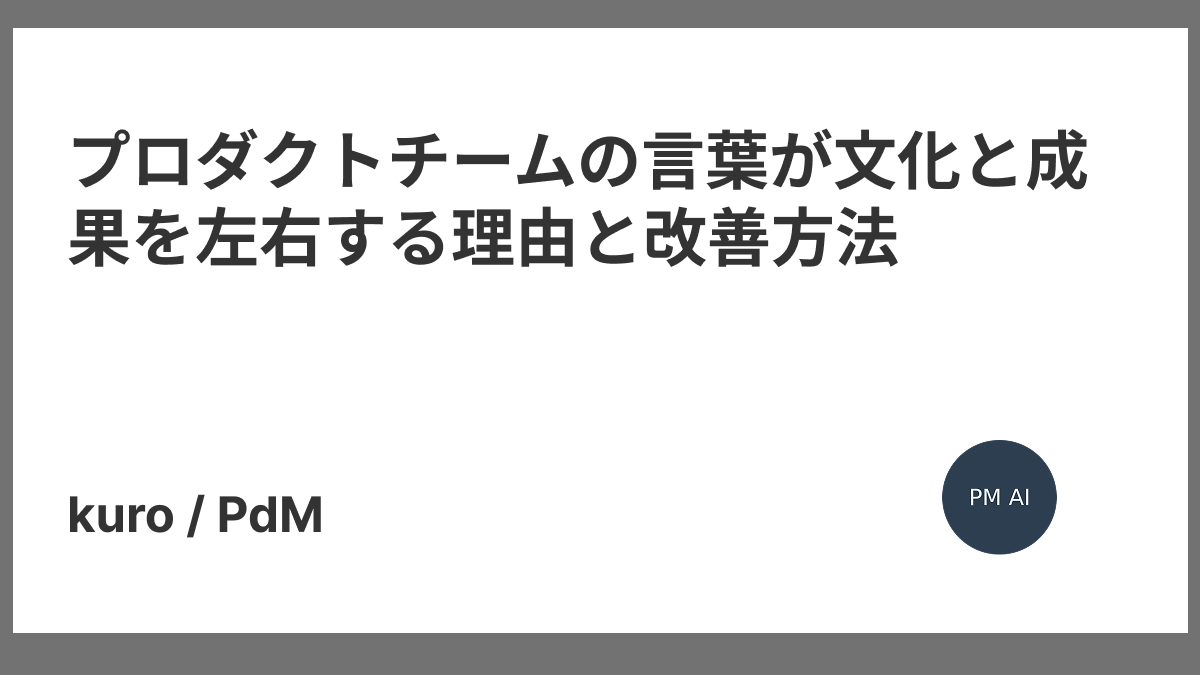
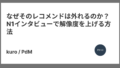
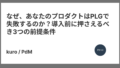
コメント