この記事の要約
- 競争優位は個別施策の優劣ではなく、各要素が因果関係で結びついた「ストーリー」の一貫性から生まれる
- 部分的に模倣されても全体の物語が異なれば同じ価値は再現できないため、持続的な差別化が可能
- プロダクトマネージャーは新機能単体でなく、プロダクト全体の物語における役割と連動性を設計すべき
『ストーリーとしての競争戦略』について
「ストーリーとしての競争戦略」(著:楠木 建、Hitotsubashi Business Review Books)は、企業や組織が競争優位を築くうえで重要な“戦略の一貫性”を「ストーリー」として描くという独自の視点を提示する一冊。
従来、戦略論というと数値的な分析やフレームワークの適用が中心になりがちでした。しかし著者は、「戦略は全体が連動した物語として機能してこそ意味がある」と強調します。戦略上のさまざまな要素が互いに結びつき、筋道を通したストーリーへと昇華されることで、はじめて強い競争優位が生まれるという考え方です。
本書が説くのは、決してロマン的な物語づくりではありません。あくまでビジネスのリアルに根ざした“因果関係のかたまり”としてのストーリーです。市場環境、顧客ニーズ、競合の動き、自社リソースなど、戦略上の要素を点ではなく線で捉える。そして相互に支え合い、論理が破綻しない構造を築くことで、他社には真似しづらい「独自の物語」をつくり出すことが可能になるのです。
論理の積み上げを「物語」に変換する
多くの企業は、戦略を策定するときに因数分解やSWOT分析、PEST分析などのフレームワークを使います。しかし、それらを「部分ごとの集まり」として眺めるだけでは、統合的な競争優位を生むには不十分です。点在する施策がどうつながり合い、どこに歪みが生じているかを把握しにくいからです。そこで著者が提唱するのが、“論理の積み上げをストーリーとして捉える”アプローチです。
たとえば、ある新機能を投入したい場合、その目的は市場ポジションの強化か、ユーザー体験の向上か。それを採用する顧客はどのような行動特性を持ち、どのようなペインを感じているのか。そして社内リソースや技術との親和性はどうか。それらを一つひとつ検討し、因果関係を解きほぐす。最終的に筋が通った仮説と施策のつながりをつくれば、“独自のストーリー”として競争優位を構築できます。事実、「イシューからはじめよ」(当サイトに要約記事あり)でも、論理を骨太に通すことが最大の成果を生む鍵と説いていますが、それをさらに“物語”へ結晶化するのが本書の魅力です。

他社に真似されない「独自性」とは
戦略論には「持続的競争優位をどう築くか」という大命題があります。Michael E. Porterが提唱する「差別化戦略」や「集中戦略」などもそうですが、ただ単純にコスト面やプロダクト品質で差をつけるだけでは、競合にコピーされやすい現実があります。
一方で、本書で言う「ストーリーとしての競争戦略」では、すべての要素が有機的につながり合うため、部分的に真似されても全体の再現は容易ではありません。
- なぜ顧客がそれを必要とするのか?
- なぜ自社がそれを提供しうるのか?
- なぜ今、それを市場に出すのか?
これらの問いが示す部分要素が、ゆるぎなく論理的につながっていると、そこにしかない世界観=物語が構築されます。たとえ1つの施策が模倣されても、全体のストーリーが異なれば、同じ価値は生まれません。独自性の源泉は、この「連鎖した因果関係の塊」をいかに強固につくり上げるかにかかっています。
プロダクトマネージャー視点での活用ポイント
プロダクトマネージャーとしては、単に新機能や新規サービスを立ち上げるのではなく、それらが「プロダクト全体のどの物語に接続するのか」を意識する必要があります。ユーザーストーリーを定義する際に、顧客の行動フローを段階ごとに細分化して顕在ニーズや潜在ニーズを洗い出す。次に自社の提供価値との接点を明確にし、その接点がどこで強みとして発揮されるかを具体化する。そうすることで、ただ便利な新機能を追加するだけではなく、既存の機能や将来の機能とも整合性のある“プロダクトの物語”を描くことができます。
たとえばユーザーインタビューの設計段階でも、「筋の良い仮説」をチームで設定する(関連記事)フェーズから「ストーリー」を意識しておくと、インタビューを通じて得られる定性データとのひもづけがスムーズになります。
- 回答者の声が戦略上のどこに結びつくのか?
- 施策同士の因果関係は矛盾なく成り立つか?
こうした視点で進めると、点在しがちなユーザーインサイトを一本のストーリーへと編み上げ、競争優位につながる施策の選定が行いやすくなります。

ストーリーを強化するための具体フレームワーク
本書の考えをプロダクト戦略に適用する際、活用できるフレームワークはいくつかあります。
その一つが「カスタマージャーニーマップ」。顧客が製品・サービスに触れる前後の行動を可視化し、痛みや喜びのポイントを洗い出す手法です。これを施策単位で分解してしまうと、部分最適な施策ばかりが乱立する危険があります。しかし「ストーリーとしての競争戦略」を意識しながらジャーニーマップを作ると、各タッチポイントが互いにどんな意図を持ち、どう結びつくのかがクリアになります。
カスタマージャーニーについての理解を深めるためにこちらの書籍もおすすめ。
また、リーンスタートアップ的な反復アプローチを取り入れるのも効果的。リーン・スタートアップ(当サイト要約記事)でも「検証と学習のサイクルを高速で回す」ことを推奨していますが、その際に「物語全体の流れ」を見失わないようにするのがポイントです。ある施策で得た学習が、ストーリー全体のどこにプラスをもたらすのか。もしくは矛盾を生じているのか。こうした視点を常に忘れないことで、単なる反復実験に終わらず、連動性の高い競争戦略へとつなげることができます。

事例から見る「ストーリーとしての競争戦略」
IT系スタートアップが自動化機能を次々と開発する一方で、あえて人的サポートを重視し、カスタマーサクセスを強化して成功した例があります。
自動化ソリューションの開発自体は大手企業が資金力で一気に模倣しやすい。そこだけで勝負するとすぐに差が縮まる可能性がある。しかし、人的なコミュニケーションを丁寧に積み上げることで、顧客の課題を深く理解し、機能改修との連動性も高められた。この“テクノロジー×人的サポート”が連動した全体設計は模倣難易度が高く、結果的に差別化要因として定着しました。
このケースでは「部分的な施策」だけ見れば、技術要素やサポート施策はいずれも既存の手法に過ぎません。けれども、それらが一つの連続した価値提供サイクルを生み出している点に独自性があるのです。技術と人的サポートの両面にわたる顧客理解の深さ、アップデートの早さ、導入効果の共有方法などがストーリーとして有機的に結びつくことで、他社が単に“真似する”だけでは到達しにくい競争優位を得ています。
また、『ストーリーとしての競争戦略』の中ではスターバックスの「直営店比率を極限まで上げたこと」が模倣不可能性を高めた一手と紹介されており、個人的にはとても学びがあったので実際の書籍の事例もチェックしてみてください。
物語性と数字をどう両立させるか
ストーリーと聞くと「論理よりも感性を重視するのか」と思うかもしれません。
ですが、本書でいう“ストーリー”は論理構造がベースにあります。むしろ、適切なKPIや財務指標を提示することで、物語の要所要所で検証可能な形を作り上げるのが大切です。どのフェーズでどんな数字を見て意思決定をするのか。それが戦略全体のどの部分と結びついているのか。それを筋道立てて示すことで、「この施策は何を狙っているのか」も自然と腹落ちするようになります。
プロダクトマネージャーの観点では、新機能リリース後の継続率やABテストの結果、ユーザーインタビューで得られる定性フィードバックなど、計測すべき数字が多岐にわたります。部分的な数値評価だけに振り回されないよう、数値指標をどのようにストーリー全体に組み込むかがカギ。なぜこの数字を追うのか、どの指標同士が因果関係を持つのかを明確にすると、チームのコミュニケーションや優先度設定もスムーズになります。
組織全体で「ストーリー」を共有するためのポイント
「ストーリーとしての競争戦略」は、トップマネジメントだけが理解していれば成立するわけではありません。むしろ、実行部隊の一人ひとりまで“自分たちのやっていることがストーリーのどこに貢献しているのか”をイメージできる状態を作ることが欠かせません。そうすることで、どの局面でも“自分が担っている要素は戦略全体の中でどう機能するか”を考える習慣が根付きます。
ここで効果的なのが社内向けのストーリーブック、あるいは「戦略マップ」のビジュアル化です。プロダクトロードマップや事業ロードマップに加え、それらを貫く物語を図式化し、各施策がどんな因果関係で効果を発揮するかを書き込む。さらに、定例会や週次ミーティングなどでこまめに「ストーリーの整合性をチェックする時間」を設ける。こうした仕組みが、社内全体で戦略意図を共有し、優先度の判断を素早く行う助けになります。
「ストーリーとしての競争戦略」の実践ステップ
最後に、本書のエッセンスを踏まえつつ、プロダクトマネージャーが日々の業務で活かすための実践ステップをまとめます。
- まずはプロダクトのビジョンや使命を再確認するところからスタート
- そこに「ユーザー視点での連続性」「社内リソースや技術の連動性」「市場・競合環境との相互作用」を結びつけていきます
- 次に、因果関係を視覚化した「ストーリーマップ」を作成し、各機能や施策がどこにつながるかを洗い出す
- 矛盾や重複を見つけたら、速やかに修正・追加の議論を行う
そして重要なのは、検証フェーズでも一貫して“ストーリー”を意識すること。ユーザーインタビューやABテストで得られた知見を再びマップへフィードバックし、全体最適を常に意識しながら“物語”のアップデートを繰り返します。
今日から実践できるアクション
・プロダクトビジョンの改めての言語化
自社プロダクトが目指すゴールや価値観を、チーム全員が共有できるよう文書化してみる。どの顧客に、どのような価値を提供し、なぜ自社が取り組むのか、物語の起点を明確にする。
・各施策の「物語上の役割」をメモする
リリース予定の新機能や既存機能の改善項目などに、担当者レベルで「この施策はストーリー全体のどこを強化するか」を簡潔に言語化してもらう。部分最適な議論に陥らないための小さな仕組みを用意しましょう。
・社内の「ストーリーレビュー会」を実施する
週次や隔週で30分程度の時間をとり、「最新の学びや数値、ユーザーインタビュー結果と、物語との整合性」を確認し合う場を設ける。全体最適を常にブラッシュアップするための習慣づくりです。
Q&A
Q1:「ストーリーとしての競争戦略」は大企業にも有効なのですか?
A1:はい。有効です。むしろ大企業ほど部門間連携や意思決定プロセスが複雑なので、縦割りで施策が乱立しやすい傾向があります。ストーリーとして共有することで、一貫性のある意思決定を行いやすくなります。
Q2:物語といっても、社内で“感性論”と捉えられてしまわないでしょうか?
A2:本書でいう「物語」は、実証可能な論理やデータの積み上げによるストーリー構造です。感性論とは違い、「なぜこの施策が必要か」「なぜこれが成果につながるか」という因果関係を明確に示すものなので、データ重視の環境でも納得を得やすいです。
Q3:すでに走り始めているプロダクトでもストーリーを再構築できますか?
A3:可能です。むしろ乱立した施策や機能に共通のストーリーを再度与えることで、いらない機能が見える化し、リソースを集中すべき領域が明確になるケースは少なくありません。
参考情報
・楠木 建 (2010) 『ストーリーとしての競争戦略』 東洋経済新報社
・Michael E. Porter (1996) “What is Strategy?” Harvard Business Review 74(6), pp.61-78.
・W. Chan Kim and Renée Mauborgne (2005) Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press.
・Eric Ries (2011) The Lean Startup, Crown Business.
・当サイト関連記事:【要約】『イシューからはじめよ』 – プロダクトマネージャーが圧倒的成果を生むために必要な「イシュー度の高い課題」を見極める方法
・当サイト関連記事:【要約】プロダクト開発の定番書『リーン・スタートアップ』をあらためて噛み締める
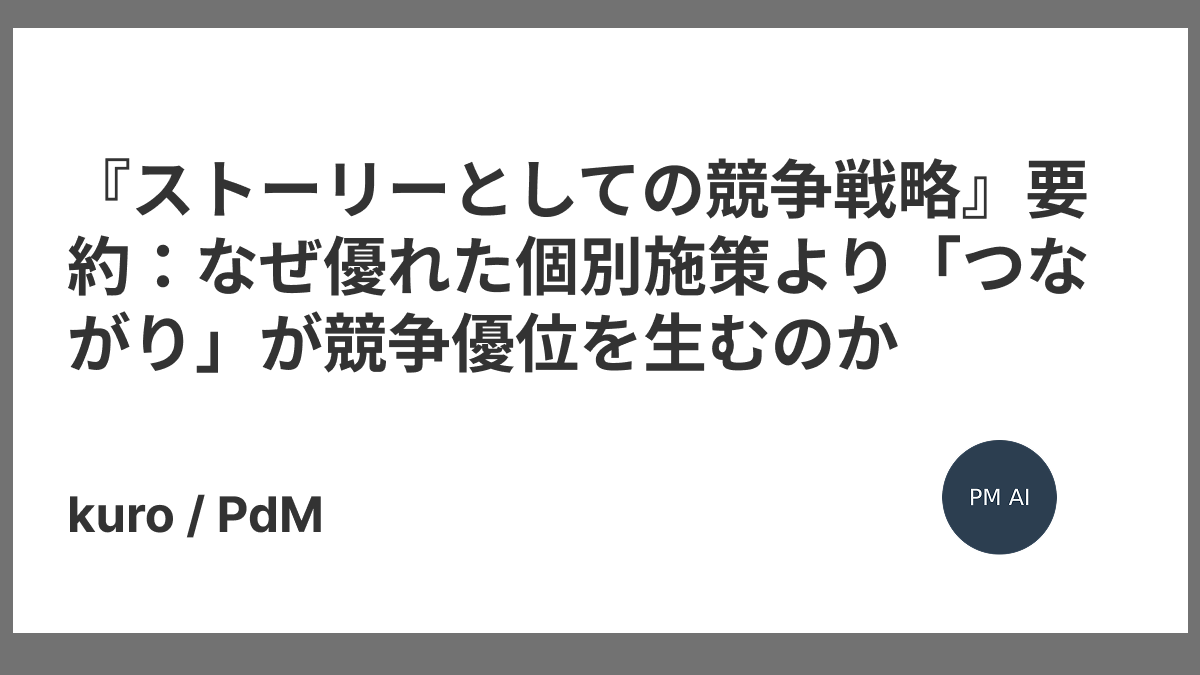


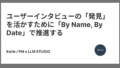
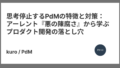
コメント