ユーザーインタビューは一見シンプルですが、サービスの「利用/導入前」「利用/導入直後」「熟練ユーザー」とステージが変われば抱えている課題も期待も変わります。
僕は700人超の顧客ヒアリングを行う中で、ステージを意識しないまま同じ質問をしていたときは、大きなインサイトを見落としていたことがありました。
本記事では、PdMやリサーチャー、マーケたー向けに、顧客の利用ステージ別でインタビュー内容をどう作り分け、得た情報をどうプロダクト開発に活かすかを、具体例や実務Tipsとともに解説します。
なぜステージを意識したヒアリングがPdMの武器になるのか?
プロダクトマネジメントの過程では、ほぼ100%「誰の課題を解くのか?」を鮮明にするためにペルソナを定義します。ところが、同じペルソナでもタイミングや利用歴で求める価値が大きく変わるのが捉えにくい現実。
- 導入前ユーザーは「本当にこの製品で課題が解決するのか?」を疑う
- 導入直後は「最初の成功体験」を得られず離脱するかもしれない
- 熟練ユーザーは細かい改善要望を抱えたり、新機能への欲求が強い。
こういったタイミング/ステージの変化を認識しないまま一律の質問をすると、本来見つけられるはずのインサイトを逃したりファクトを取り違えたりして結果プロダクトの意思決定の精度が下がることに。。。
だからこそ、ステージ別ヒアリングがPdMにとって強力な武器になります。
導入前ユーザー / 製品に対して“期待と不安”が渦巻く
ここで押さえるべき視点
導入前ユーザーは「潜在顧客」と言い換えてもいいでしょう。
- どうやって製品を知ったのか?(広告、口コミ、展示会、SNSなど)
- 導入を検討し始めたタイミングやきっかけは?(想定する課題・期待)
- どんな不安や懸念があるか?(価格、サポート体制、実績、社内説得など)
導入前ユーザーの声は、マーケやセールス面での施策にも直結するので、ここで得られるインサイトが、新規顧客の獲得効率を左右するケースも多いです。マーケなどにもインタビューに同席してもらうのがおすすめ。
質問項目の具体例とアプローチ
-
- 「直近1週間に、xxxという領域でコストや時間がかかったり想定通りに行かなかったりしたことはありましたか?」
主観ではなく、期間を区切って行動を聞く中で課題を特定する。 - 「なぜこのタイミングで製品導入を検討しようと思いましたか?」
現場で起きている課題や組織の変化などを詳しく聞き出すと、顧客の潜在ニーズが見える。 - 「比較検討しているサービスは何ですか? なぜ候補に挙がっていますか?」
競合サービスのポジショニングが分かる。価格、機能、サポート面などどこが魅力なのか、どこが不安なのかを深堀り。 - 「購入(導入)決定に誰の承認が必要になりますか?」
BtoB向けの場合、決裁者・利用現場・経理など複数レイヤーが絡む。社内政治の構造を探るのに有効(toCでも購入者と利用者が異なるケースがあります *教科書など)。
- 「直近1週間に、xxxという領域でコストや時間がかかったり想定通りに行かなかったりしたことはありましたか?」
ヒアリング後の施策でPMが見るべきKPI
-
- 資料請求 / トライアル申込率
- 問い合わせから導入決定までのリードタイム
- 検討ステージの離脱率(なぜ脱落したのか、失注理由)
- 購入数や率
導入直後ユーザー / 離脱要因や1stサクセスに必要な要素を確認
ここで押さえるべき視点
導入直後は「初期離脱が一気に起きるリスクゾーン」。
- アカウント発行や初期設定で詰まっていないか
- ユーザーが「最初の成功体験」を得られたか
- サポートは十分機能しているか
ここで負担が大きいと、ユーザーはネガティブな印象のまま使わなくなり、「解約」「お試しだけで終わる」といった事態にもつながります。
質問項目の具体例とアプローチ
-
- 「初回利用時、どの部分で戸惑いましたか?」
UI/UXの改善につながる。操作手順が多すぎるか、チュートリアルが不親切かなどを探る。 - 「導入前に期待していたことと、実際の使用感は違いましたか?」
ユーザーの期待値と現実のギャップを把握し、どこを埋めるべきか整理。 - 「サポートへの問い合わせやヘルプページは利用しましたか? その評価は?」
ヘルプドキュメントの充実度やCS対応スピードの改善に直結。 - (満足している場合)「このサービスを継続しよう、と思った瞬間はいつでしたか?」
「このサクセスの瞬間を民主化すべき!」という大事なモーメントを捉える
- 「初回利用時、どの部分で戸惑いましたか?」
ヒアリング後の施策でPMが見るべきKPI
-
- オンボーディング完了率(初期設定やアカウント登録が終わるまでの達成率)
- 初月アクティブ率(導入後1ヶ月以内にどれだけ利用されているか)
- 初期解約率 / トライアル終了後の継続率
- D7RR(初回ログインから7日以内の再ログイン率)
熟練ユーザー / 深い活用事例から次のアップデートを発見
ここで押さえるべき視点
熟練ユーザーは「ヘビーユースしているからこそ抱えている隠れた不便や高度な要望」を持っています。
また、愛着があるからこそ忖度なしにサービスの問題点を指摘してくれる可能性も高い。ここでのインタビューは、次の大幅な機能改善や差別化に役立つ貴重な機会です。
質問項目の具体例とアプローチ
-
- 「普段どんな業務フローで製品を使っていますか? 他のツールとの連携は?」
実際の運用フローを視覚化し、周辺ツールとのインテグレーションポイントを探る。 - 「改善して欲しい点はありますか? それはなぜ現状対応できていますか?」
不満を正直に聞くと同時に、今はどんなworkaroundをしているのかを掴むと、重要課題が見えやすい。 - 「このサービスの特に気に入っている部分や他との違いを感じた部分はどこですか?」
このKey Functionを初回ユーザーや導入前ユーザーにもとにかく広げていくべき
- 「普段どんな業務フローで製品を使っていますか? 他のツールとの連携は?」
PMが見るべきKPI
-
- LTV(Life Time Value)
- アップセル / クロスセル率
- NPS(ネットプロモータースコア)やSNSでの口コミ動向
- 購入単価
ステージを跨いだ価値変化を可視化する:実践フレームワーク
ステージ別にインタビューを行う場合、顧客のジャーニーマップを用意すると効果的。
たとえば、
-
- 導入前 → 知ったきっかけ、期待と不安
- 導入直後 → オンボーディング成功体験、サポート接点
- 熟練ユーザー → リアルな運用と高機能ニーズ
これらを時系列で繋ぎ、「期待値」「満足度」「不満ポイント」を一枚のマップにまとめる。すると、組織全体がユーザーの変化の流れを共有しやすいです。
このジャーニーマップに、インタビューで拾った具体的エピソードや数値(KPI)を重ね合わせると、ストーリーとして伝わりやすくなり、チームの意思決定が円滑になります。
今日から実践できるアクション
-
- ステージ別シナリオを事前に設計
「導入前→導入直後→熟練」と3つのシナリオを作り、それぞれで何を聞きたいか質問リストをまとめる。社内で共有し、誰がインタビューしてもブレない仕組みを。 - 導入直後ユーザーへの“集中モニタリング”
新規契約者には、導入1週間・1ヶ月後にショートインタビューを実施する仕組みを自動化。CSがその役割を担う例も多い。 - 熟練ユーザーへの定期ヒアリング枠をカレンダー化
半年・1年などのタイミングでリピートインタビューを実施。利用度の高いアクティブユーザーをピックアップしてフォローアップ。 - ステージ別ジャーニーマップを作成
チームのNotionやConfluenceなどに、ユーザーのステージごとの「課題」「感情」「利用状況」「KPI」を表で可視化。随時アップデートしていく。
- ステージ別シナリオを事前に設計
Q&A
- Q1. ステージ別インタビューを行うリソースが足りません。どう工夫すれば?
- A. すべての顧客ステージで毎回大量にインタビューする必要はありません。「導入前は毎月3名」「導入直後は毎週2名」「熟練ユーザーは四半期に5名」など、優先度を定めたサンプリングで十分。
また、カスタマーサクセスや営業が日常で拾っている声を定期的にPMが集約する方法も効果的です。 - Q2. ヘビーユーザーへのインタビューをすると、機能要望がどんどん膨らんでしまいます。
- A. そのままリクエストを受けるのではなく、「要望の背景」に必ずフォーカスしましょう。「なぜその機能が必要なのか?」を深掘りし、本質的な課題を見極めることが大切。
機能要望をマトリクス管理し、開発リソースとの兼ね合いで優先度を決定すると、混乱を防げます。 - Q3. 導入直後のユーザーは製品に慣れていないので、有益な情報が得られない気がします。
- A. むしろ使い始めのフレッシュな視点が重要。UIのクセや面倒な導線を“慣れていないからこそ”素直に指摘してくれます。
長期的に見ると、この初期ユーザーの声を取り込むことで離脱率を下げ、プロダクトの完成度を高めることができます。
参考情報
-
- Rob Fitzpatrick『The Mom Test』(2013)
- Jakob Nielsen and Thomas K. Landauer (1993). “A Mathematical Model of the Finding of Usability Problems.” Proceedings of ACM INTERCHI’93
- FoundX Review「ユーザーインタビューの基本」
- Shin note「全PMが知るべき『本当の課題』を知るユーザーヒアリング手順と失敗例まとめ」
- 「ユーザーヒアリングを組織に根付かせる4つの仕組みを考察した」(当サイト)
 ユーザーヒアリングを組織に根付かせる4つの仕組みユーザーインタビューの「組織化」に一度取り組んでみたものの、いつの間にか回数が減り、情報が共有されず結局属人化に逆戻り。。。。。。。。。(そして特定のPMが業務過多に)そんな経験ありませんか?僕はめちゃくちゃありました、というかだいぶ失敗し...
ユーザーヒアリングを組織に根付かせる4つの仕組みユーザーインタビューの「組織化」に一度取り組んでみたものの、いつの間にか回数が減り、情報が共有されず結局属人化に逆戻り。。。。。。。。。(そして特定のPMが業務過多に)そんな経験ありませんか?僕はめちゃくちゃありました、というかだいぶ失敗し...
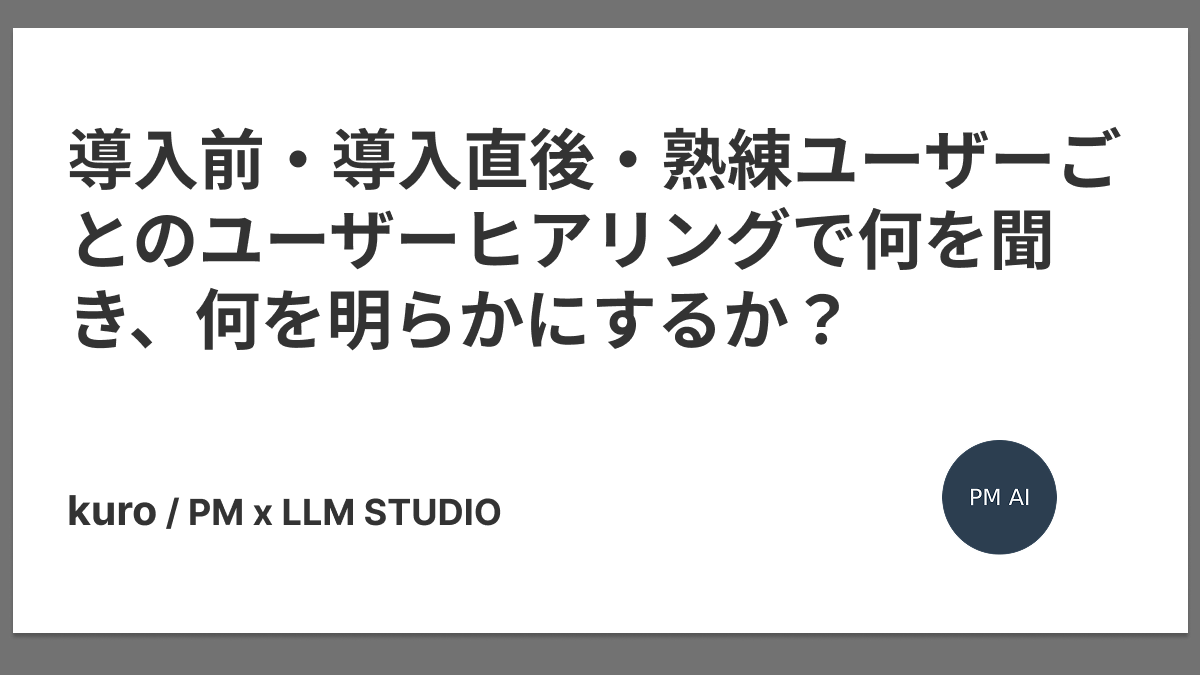

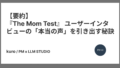
コメント