「上司がいない」環境でプロダクトを伸ばすPdMも多いのではないでしょうか?小規模スタートアップやフリーランスチームなどは典型的な例ですよね。
こうした“組織レス”な状態では、決裁フローが曖昧である反面、自分のリーダーシップ一つで組織が動くワクワク感や、スピーディに仮説検証を回せる利点もあると感じます。
この記事では、組織レスの開発現場の特徴を整理しつつ、PdMとして仮説検証を推進するための考え方やチームマネジメントのポイントを解説します。
組織レス開発現場のメリット
組織レスだと大企業のように承認プロセスが重たくないため、ユーザーから得たインサイトをすぐにプロダクトへ反映させやすいです。
“小さく試してすぐに学ぶ”というリーンスタートアップの考え方(参考:【要約】『リーン・スタートアップ』をあらためて噛み締める)を地で行きやすい環境といえます。しかし、スピード感を活かせる一方で、無計画なまま開発を進めてしまうと、結果的に方向性がブレやすいのも事実です。

超小規模組織でPdMのリーダーシップ
組織レスな開発現場では、PdM自らがビジネス面・開発面・デザイン面など多岐にわたる領域に関与し、リーダーシップを発揮することが求められます。ここで重要なのが、小さな組織だからこそ明確な仮説を持ってユーザーインタビューを推進する姿勢。すなわち、PdMが「どんな価値を提供したいのか」を明確にし、それを検証するための質問や観察項目を設計してこそ、チーム全体を巻き込む力になります。
人数が少ないと、レポートラインとか存在しないことも多いので仮説が緩くなってしまうケースもあるかと思います。ただ、超小規模組織だからこそ、一人一人のリソースの価値は高いはずです、それをゆるい仮説のまま進んで手戻り、は避けたいはずです。ここで言いたいのは、「手戻り/失敗はダメだ」ではなく「潰せる仮説は先に潰して本当に重要な仮説の検証に全リソース投下しようぜ」ということです。
僕はこれまで 700人以上のユーザーにインタビューしてきましたが、その過程で痛感したのは、「仮説が曖昧だと、インタビュー結果も活かされにくい」ということです。特に組織レスで決裁が曖昧な環境では、質的情報の価値が上がるため、仮説と定性的なファクトがモノを言うことが多いです。そこで筋の良い仮説があると、そこに向かって「検証」という建設的な議論が生まれるためです。具体的な仮説設定のフレームワークは、ユーザーインタビュー前に「筋の良い仮説」をチームで設定する具体的な方法やフレームに詳しくまとめています。

小規模ゆえにできるユーザーファースト施策
小規模なチームは、ユーザーの声を吸い上げるスピード感やフットワークの軽さで大企業に勝るケースがあります。意思決定者が少ないぶん、ユーザーリサーチの計画から実施、結果共有までを短いサイクルで繰り返せるのです。「やってみる→学んで改善する」をシンプルに回せることは、組織レスならではの強みでもあります。
具体的にユーザーファーストを体現するために、僕がよく実施しているのはインタビュー後の即時プロトタイプ化です。例えば、インタビューで出たユーザーのアイデアや課題感を、その日のうちに紙やスケッチツールで試作し、仮説を更新します。さらに、近年はGPTs Builderでプロトタイプをする方法も普及しており、ユーザーへの再インタビューも高速化できます。こうしたアジャイルな進め方は、上司を通さないですぐに動ける小規模開発チームだからこそ実践しやすい施策といえます。

チーム合意を取るための手法:書面化・ユーザーデータの活用
組織レスな環境では、口頭ベースでプロダクト方針を決めてしまうと、「言った/言っていない」のトラブルはないにしても、
- 「あれ、この時間で何決めたっけ?」
- 「ここの仕様決めた気がするけどなんだっけ」
などの状態になりがちです。
そこで、小さな組織だからこそドキュメントを作成しておくことが重要。ユーザーストーリーや機能要件、ターゲット優先度などを明文化し、チーム内で共有することで、合意プロセスがぐっと滑らかになります。
もう一つ効果的なのが、使える限りの量的なユーザーデータを根拠に使う方法です。特に質的データとログ分析データなど、定性・定量のエビデンスを組み合わせて提案すると、合意形成がスムーズになります。ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイドでも触れていますが、インタビュー結果を可視化してドキュメント化すれば、メンバー間の「主観的な意見の衝突」を減らし、ユーザー視点という共通の軸で議論が進められます。こうした手法は組織レスであっても、チームメンバー全員が同じ目線を持つために欠かせません。
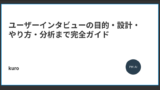
特に少人数チームだと意思が強い人が集まる傾向があるので、よりファクトと、それでも決まらない時はCEOの熱で決めたいですね。
参考情報
- Eric Ries (2011)『The Lean Startup』Crown Business
- Gary Yukl (2012)『Leadership in Organizations』Pearson
- Marty Cagan (2018)『INSPIRED』SVPG Press
- Geoffrey A. Moore (2014)『Crossing the Chasm』HarperCollins
- 当サイト記事:ユーザーインタビュー前に「筋の良い仮説」をチームで設定する具体的な方法やフレーム
- 当サイト記事:ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド
- 当サイト記事:ユーザーヒアリングを組織に根付かせる4つの仕組み
今日から実践できるアクション
・仮説を一枚紙にまとめる
「現状の課題」「開発したい機能」「想定ユーザーの困りごと」をシンプルに描き出し、チーム内で共有する。曖昧になりがちな意思決定を、仮説という形で“見える化”するだけで合意形成が進みやすくなる。
・インタビュー記録をドキュメント化する
インタビューごとに「いつ」「誰が」「何を聞いて」「どんな発見があったか」をテンプレートにまとめ、GoogleドライブやNotionなどで一元管理しておく。必要なときにすぐ引き出せるようにすることで、仮説検証のサイクルが加速する。
Q&A
Q1. 組織レス環境で「リーダーシップを発揮する自信がない」のですが、どうすればいいですか?
A1. まずは小さな範囲からリーダーシップを発揮してみるのがおすすめです。ユーザーインタビューの設計、プロトタイピング、定例会での意思決定プロセスなど、一つの領域を任されると主体性を発揮しやすくなります。また、ユーザーインタビュー結果を根拠に示すことで、“個人の意見”ではなく“ユーザーの声”としてリーダーシップを取ることが可能になります。
Q2. 小規模ゆえにユーザーインタビューをする時間が取れません。代替方法はありますか?
A2. 完全にインタビューを省くことは推奨しませんが、時間がないなら短時間のオンラインインタビューや、既存のユーザーログ分析を一時的に活用するのも手です。また、最新のAIエージェントツールでログを分析するなど、作業の自動化を進めることで、インタビューのハードルを下げられます。

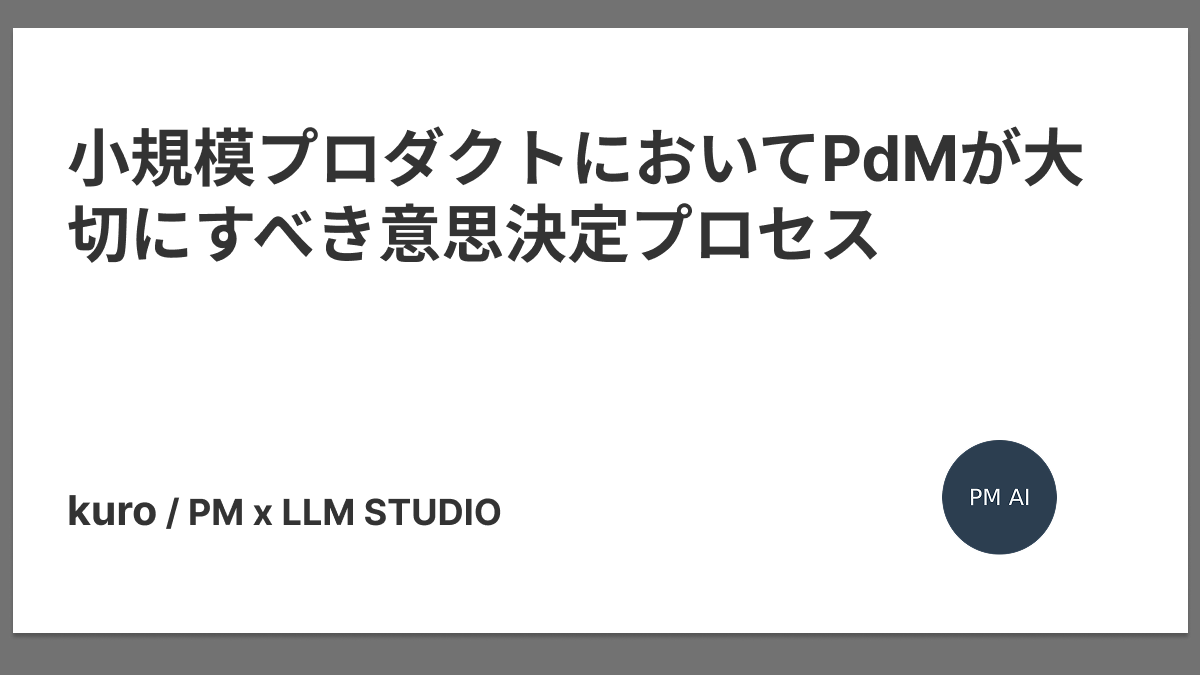


コメント