「また差し戻しか…」
- 上司や役員に提案資料を出すたび、なぜか毎回「うーん、ちょっと…」という微妙な反応
- 論理的に組み立てたつもりなのに、なぜか刺さらない
- ファクトも集めたはずなのに、「根拠が弱い」と言わる
この現状は要因は、論理構造の穴かファクトの不備にある可能性があります。
この記事の要約
- 提案が通らない根本原因は、論理とファクトの穴にあり
- 7つのステップで骨格を作り、14問のセルフチェックで品質を担
- プレブリーフ運用で事前合意を積み重ねる
提案資料のテンプレート
プロダクトに関する提案資料の流れはおおよそ以下のような形かと思います。
提案資料のおおよその流れ
- Context(状況整理) – 今、何が起きているのか?なぜその検討が始まったのか?
- Problem(課題設定) – 何を解決すべきなのか?
- 真因(Root Cause) – なぜその課題が生じているのか?
- 独自価値/USP – 我々だからこそできることは何か?
- 体験設計 – ユーザーにどんな価値を届けるのか?
- As-is/To-be – 現状から理想状態への変化は?
- KPIシミュレーション – 成果をどう測るのか?
その中で、論理的なエラーが特に起きやすいのは以下の部分が多い印象です
- Step 1→2: 現状から課題設定への飛躍(なんで色々ある中でその課題?)
- Step 3→4: 真因へのDiveを飛ばした解決策の提示(うーん、その解決策がハマるかなんとも言えないな)
- Step 5/6→7: 体験からメトリクスやsimへの差分(その他体験でその数字そんなに伸びなくない?)
論理崩壊の三大パターン
そして、どんなにファクトを集めても、論理構造が破綻していては説得力は生まれません。ここでは、よくある論理崩壊パターンを3つ紹介します。
パターン①:飛躍(So-what?)
症状: 前提から結論への筋道が見えない
具体例: 「MAUが減少している。だからコンテンツを追加してリテンションを復活させましょう」
この例では、MAU減少の原因分析とコンテンツ追加の関連性が不明。「なぜコンテンツが最もMAU回復につながるのか?」という疑問に答えられていません。
特によくあるのは、データを見て慌てて解決策に飛んでしまうパターン。これだと相手は「?」となってしまいます。
対処法: 「雲-雨-傘」フレームワークの活用
「雲-雨-傘」は、事実→解釈→行動を並べ立てる流れです
- 雲(事実): 曇っている
- 雨(解釈): 雨が降るかもしれない
- 傘(行動): だから今日は念の為傘を持っていこう
これを今回のケースに当てはめてみると、
- 雲(事実): MAUが3ヶ月連続で5%減少
- 雨(解釈): アクセス頻度が高いユーザーはコンテンツ接触度が高く因果推論でも他変数に比べてコンテンツのアクセス寄与が高いことが証明された
- 傘(行動): 中でも特にアクセス寄与度が高いコンテンツカテゴリを特定し、そのカテゴリのコンテンツを追加投入
パターン②:循環(Because…because)
症状: 理由と結論が同じことを言っている
具体例: 「ユーザー満足度を上げるべきです。なぜなら、ユーザーが不満を感じているからです」
これは「満足度を上げる」と「不満を感じている」が表裏一体で、論理的に何も進んでいません。
対処法: MECEチェックリストの適用
- 各論点がMutually Exclusive(相互排他的)か?
- 全体としてCollectively Exhaustive(漏れなく)か?
- So-What(だから何?)に明確に答えているか?
パターン③:矛盾(Aと言ってBも言う)
症状: 複数の主張が互いに対立している
具体例: 「短期で成果を出したいです。かつ、長期視点での投資も重要です」
これは一見もっともらしいですが、リソース配分の観点では矛盾。優先順位が不明確になります。
対処法: 制約条件や上り方の明示
「短期(Q1-Q2)は既存改善でクイックウィン、中長期(Q3以降)で新規投資」のように、時間軸や条件を明確にして両立させます。
ファクト崩壊の三大パターン
論理が通っていても、ファクトが弱ければ説得力は半減します。
パターン①:定量不足(算数が弱い)
症状: 数字がない、または数字の精度が低い
具体例: (極端な例ですが)「多くのユーザーが困っています」「かなりの効果が期待できます」
意思決定者は大体具体的な数値での判断を求めます。
「数字がない」ということはほぼないと思いますが、1つの数字からさらにその数字を分解して、という3-4段階ダイブした数字があると説得力が増しますよね。
対処法: Three-Layer分析
- 全体層: 全ユーザーの35%が該当機能で離脱
- セグメント層: 特にヘビーユーザーの離脱率が50%
- 時系列層: 過去3ヶ月で離脱率が20%→35%に悪化
パターン②:数字のみ
症状: 数字はあるが文脈や背景が不明
具体例: 「CVRが2.1%です」(だから何?という疑問が残る)
数字だけ示されても、それが良いのか悪いのか、なぜその数値なのかが分かりません。
対処法: コンテクストでサンドイッチ
- 前置き: 業界平均CVRは1.8%、自社目標は2.5%
- 数値: 現在のCVRは2.1%
- 解釈: 業界平均は上回るが目標未達、xxxxという深掘りを経た結果、主因は決済フローの複雑さとわかった
パターン③:網羅性欠如
症状: 都合の良いデータや論理・主張のみを提示
具体例: ポジティブなユーザーコメントのみを引用
これは意図的でなくても、確証バイアス(自分の仮説を支持する情報ばかり集める傾向)によって起こりやすいです。
対処法: Devil’s Advocate(悪魔の代弁者)アプローチ
提案に対する反対意見も同時に検討し、それに対する反論も用意します。これにより、より説得力のある提案になります。
論理を補強する思考
ここからは実践編。論理構造を強化するための具体的なツールを紹介します。
ツール①:Issue Tree & Hypothesis-Driven
Issue Treeは課題を階層的に分解し、真因を特定するフレームワークです。
MAU減少(-15%) ├─ 新規獲得減少(-30%) │ ├─ 認知度低下 │ └─ 競合流入 └─ 既存離脱増加(+20%) ├─ 初回体験の問題 └─ 継続価値の不足
各要素に対して仮説を立て、検証方法を設計することで、根拠のある課題設定ができます。

ツール②:Claim-Reason-Evidence
主張→理由→根拠の3層構造で論理を整理します。
- Claim(主張): プッシュ通知機能を追加すべきです
- Reason(理由): リテンション改善により月次売上が向上するためです
- Evidence(根拠): A社では通知導入後、7日継続率が23%→31%に改善
このフォーマットを使うことで、「だから何?」「なぜ?」「本当に?」という3つの疑問に先回りして答えられます。
ツール③:ピラミッド構造で”帰納の乱用”を防ぐ
複数の事実から結論を導く際、帰納法の乱用で論理が絡まることがあります。
悪い例:
- 事実A:競合が新機能をリリース
- 事実B:自社のNPSが低下
- 事実C:市場トレンドが変化
- 結論:新機能開発が必要
良い例(ピラミッド構造):
新機能開発が必要 ├─ 競合優位性の確保(事実A) ├─ 顧客満足度の回復(事実B) └─ 市場ニーズへの対応(事実C)
結論を頂点に、支持する理由を階層的に配置することで、論理の筋道が明確になります。
ファクトを補強するツールキット
続いて、ファクトの質と量を向上させるツールを見ていきましょう。
ツール①:三段ロケット分析(定量)
定量データを3つの視点で段階的に深掘りする手法です。
第1段:全体→セグメント→時系列
- 全体: 月間アクティブユーザー10万人
- セグメント: うち7割がモバイル、3割がデスクトップ
- 時系列: モバイルは成長(+5%)、デスクトップは減少(-15%)
この分析により、「モバイル最適化の優先度が高い」という具体的なアクションが見えてきます。
ツール②:三角測量(定性)
ユーザーの発話から信頼性の高いインサイトを抽出する手法です。
手順:
- ユーザー発話: 「この機能、使いづらいんですよね」
- インサイト: UIの直感性に課題がある
- 裏付け事例: 類似発話が5人中4人、操作ログでも迷いが確認
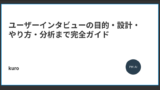
ツール③:公的データ & 競合ベンチマークの織り込み
自社データだけでなく、外部データも活用して客観性を高めます。
活用例:
- 総務省「情報通信白書」でEC市場成長率を確認
- SimilarWebで競合のトラフィック動向を分析
- App Annieでアプリストアランキングを調査
これらのデータを組み合わせることで、「業界全体の成長(+12%)に対し、自社成長(+8%)は劣後」といった相対的な位置づけが可能になります。
“国語チェック”×”算数チェック”14問セルフレビュー
資料作成後、以下のチェックリストで品質を確認しましょう。各項目にYes/Noで答えて穴があれば見直すイメージです。
国語チェック(論理構造)7問
- 結論ファースト: 最初の1分で言いたいことが伝わるか?
- 因果関係: 結論に対して「なぜなら」で繋がる論理的な流れがあるか?
- 具体性: 「それって具体的にはどういうこと?」に答えられるか?
- 一貫性: 資料全体を通じて主張がブレていないか?
- 優先順位: 複数の選択肢がある場合、なぜその案なのかが明確か?
- 反対意見: 想定される反論とその回答を用意しているか?
- 行動喚起: 聞き手に何をしてほしいのかが明確か?
算数チェック(ファクト)7問
- 定量根拠: 主要な主張に数値的な裏付けがあるか?
- サンプル数: 十分な母数でのデータ分析ができているか?
- 比較軸: 過去/競合/業界平均との比較があるか?
- 時系列: トレンドの変化を時間軸で示しているか?
- セグメント: 全体だけでなく、重要なセグメント別の分析があるか?
- 信頼性: データの出所と取得方法が明確か?
- 予測精度: 将来予測に根拠のある前提条件があるか?
このチェックリストは、プロダクトマネージャーが自分やチームの”顧客解像度”を確かめる質問リストと同様に、日常的に使える実践ツールとして設計しています。

合意形成を早める”プレブリーフ”運用術
そして、レビューを「最終テスト」ではなく「確認テスト」にするための運用術を紹介します。
これ、僕が一番効果を実感している手法です。本番でいきなり完成品を見せるから、「うーん…」となってしまう。事前に少しずつ合意を積み重ねることで、本番はスムーズに進みます(ただ、やりすぎるとスピードダウンもあるので気を付ける必要あり)。
3段階プレブリーフ・プロセス
| 段階 | タイミング | 形式 | 参加者 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階:1枚壁打ち | 資料作成開始1週間後 | A4 1枚のコンセプトペーパー | 直属上司のみ | 方向性の確認 |
| 第2段階:3枚壁打ち | 第1段階の3日後 | 課題・解決策・効果の3枚 | 関連部署のキーパーソン | 実現可能性の検証 |
| 第3段階:全体稿 | レビュー会の3日前 | 完成版のドラフト | レビュー会出席予定者 | 最終確認と質疑応答の準備 |
プレブリーフの実践ポイント
- 「未完成です」と前置きする: 完璧を求められるプレッシャーを軽減
- 具体的な質問を用意: 「この方向性で良いですか?」ではなく「A案とB案、どちらが実現可能性高いですか?」
- 反対意見を歓迎: 「他に考慮すべきリスクはありますか?」と積極的に聞く
この手法により、本番のレビュー会では「確認」レベルの議論になり、通過率が格段に向上します。
今日から実践できるアクション
- 直近の提案資料を14問チェックリストで点検
- 次回提案でプレブリーフ(1枚壁打ち)を実施
- CREフォーマットを使った論理構造の練習
さらに学ぶための推薦図書
- 『イシューからはじめよ』- 安宅和人:イシューからはじめよでも要約済み
- 『考える技術・書く技術』- バーバラ・ミント:ピラミッド構造の詳細解説
- 『INSPIRED』- マーティ・ケーガン:INSPIREDでPdMの提案術を学ぶ
Q&A
Q: 14問チェックで複数のNoがあった場合、どの順番で修正すべきですか?
A: 国語チェックの1-3番(結論ファースト、因果関係、具体性)を最優先に修正してください。論理構造の土台ができてから、ファクトの補強に移るのが効率的です。
Q: プレブリーフで反対意見ばかり出た場合はどうすれば良いですか?
A: むしろ成功です。本番前に論点が明確になったということ。反対意見を分類(実現可能性/優先度/効果予測など)し、それぞれに対する回答を用意して資料に織り込みましょう。
Q: 競合の詳細データが入手できない場合は?
A: 公開情報(プレスリリース、採用情報、ユーザーレビュー)と業界レポートを組み合わせて推定値を算出し、「推定」であることを明記した上で使用してください。完璧なデータより、論理的な推定の方が説得力があります。
参考情報
書籍・論文
- McKinsey Global Institute「The Age of Analytics」- データドリブン意思決定の重要性
- Harvard Business Review「Making Better Decisions」- 組織における意思決定メカニズム
- Barbara Minto「The Pyramid Principle」- 論理構造の構築手法
実践事例
- Airbnb: データとストーリーを組み合わせた提案手法
- Spotify: 仮説検証型開発における論理構造の重要性
- Amazon: Working Backwards手法による顧客起点の提案設計
関連調査
- PMI「Pulse of the Profession 2023」- プロジェクト成功要因分析
- Stanford Graduate School of Business「Decision Making Research」- 認知バイアスと意思決定
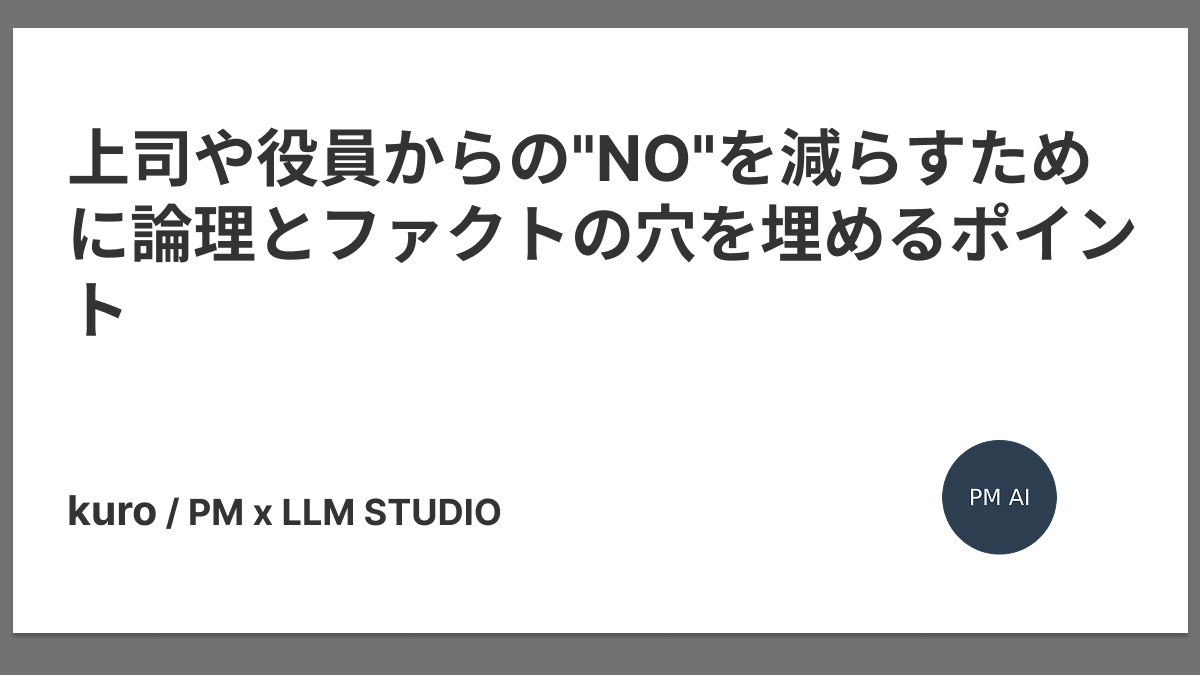
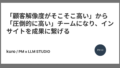
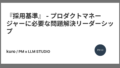
コメント