この記事の3行要約
- 日々舞い込む多様なアイデアや要望を記録せずに流すと、価値ある施策を見逃し、同じアイデアを再発明する無駄が生じる
- Notionなどでアイデアストックを構築し、分類とタグ付けで整理することで、必要な時に適切なアイデアを呼び出せる仕組みを作る
- アイデアは即座に実装せず一旦棚上げし、リリース後のレトロスペクティブなど適切なタイミングで再評価することで価値を最大化できる
アイデアは忘れ去られる
プロダクトマネージャーの仕事をしていると、日々多種多様なアイデアが舞い込みますよね。ユーザーからの要望、社内の雑談で出た思いつき、自分で閃いた施策など。気を抜くと、こうした大量のアイデアや要望が、記録に残らないまま流れていってしまう恐れがあります(そして再発明をするハメに)。
そして、本当に価値のあるアイデアは、すぐに実装したり検討したりするタイミングとは限りません。時期尚早な段階で評価されず、忘れ去られてしまうアイデアも多いのが実情。これを放置せずにストックしておくことで、未来の自分に時短をプレゼントできたり、その時の課題に対しては最もフィットするインパクトある一手を打てる確率が上がります。
実際に僕もPdMとして働く中で、数多くの社内外アイデアに触れてきました。アイデア管理が不十分だった頃は、「確かにあのアイデアは良かったのに、どこにメモしていたか分からない」という事態を経験してきました。そこで、アイデアをnotionなどに“ストック”し、常に見返せるようにしておく仕組みの重要性を痛感しています。
アイデアストックリスト:分類とタグ付け
膨大なアイデアを扱うための第一歩は、アイデアの在庫リスト(アイデアストック)を整備すること。エクセルやスプレッドシート、Notionなどのを使い、一括でアイデアを管理する仕組みを作ることが肝要です。
ポイントは、アイデアに対して「分類」と「タグ付け」を行うこと。例えば、機能に関するアイデア、集客施策に関するアイデア、改善要望などジャンル別に分類し、さらに難易度や想定インパクト、ユーザー属性などのタグを付けておくことで、後から必要な切り口でアイデアを呼び出せるようになるのです。これは一見地味な作業ですが、雑多に溢れたアイデアを整理し、正しく保管するうえで欠かせないステップ。
ちなみに、僕はこんな感じでnotionのページ内databaseを作って、その中の業務プロセスの順番を意識して、アイデアや知識をストックしています。
(実は、このサイトの各記事もそのストックから生まれているものがほとんどです)

“いつでも呼び出せる”状態を意識しておくと、アイデア整理が面倒になりにくいんですよね。notionだとスマホアプリからいつでもインプットできるから、飲み会の帰りのタクシーとかで、「あ、これいいかも!」って思ったこととか営業と話して「これ大事かも!」って思ったラーニングなどを即時ストックするようにしています。
また、もしユーザーインタビューで見つかったインサイトの管理に困っていたら、過去記事「ユーザーインタビューの「発見」を活かすために「By Name, By Date」で推進する」も参考にしてみてください。

優先順位評価:思いつきは一旦棚上げする
アイデアが生まれた瞬間は熱を帯びているので、すぐに取り掛かりたくなるもの。ただ、むやみに手を広げると、開発リソースやチームの集中力が散漫になり、結局どれも中途半端に終わる可能性が高いです。そこで大事なのが、アイデアストックに登録した後に、優先度をどう評価するかというステップ。
よく知られる優先度フレームワークには、たとえば「Impact(インパクト)- Effort(コスト)」マトリクスがあります。Impactが高くEffortが低ければ「やる価値が大」と判断しやすい。一方、Impactが高くてもEffortが非常に高いものは、長期戦を覚悟する必要があります。また、RICE(Reach, Impact, Confidence, Effort)のように評価軸を細かく設定すると、より定量的に優先順位を付けられます。
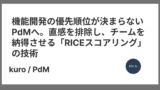
ただし、ここでのコツは「思いつきは一旦棚上げ」しても良い、という考え方です。アイデアの成熟度は、時間を置くことで増すことがあります。特にユーザーへのヒアリングや市場調査で得た追加情報を後から組み合わせると、大きく化けるケースも。
すぐに“不要”と切り捨てるのではなく、仮説ベースで棚上げする余裕を持つと良いです。
利用シーン別に呼び起こす:リリース後レトロで再活用
では、ストックしたアイデアはいつ取り出すのか?
おすすめは、「プロダクトのリリース後」に行う振り返り(レトロスペクティブ)の中で見直す方法です。リリース前後のユーザー反応から、新たな課題や追加で検討すべき改善ポイントが浮き彫りになるタイミングで、アイデアストックを見返すと良いアイデアが見つかることが多いです。
たとえば、新機能リリース後に思わぬ顧客課題が判明したとします。その課題を解決できる可能性のあるアイデアを過去のストックからピックアップしてみると、実装ハードルや効果検証の筋道が立てやすくなる。あるいは、半年以上前に却下したアイデアが、ユーザー数や売上規模が拡大した今なら実現可能になっているケースもあります。アイデアの「寝かせ」は決してネガティブな意味だけでなく、後から再評価して花開かせるチャンスを生み出してくれます。
日々のチームミーティングでも「アイデアストックを見直そう」という定期的な習慣づくりを意識すると、アイデアが散逸しにくくなる。アイデアストックをうまく再活用するためにも、しっかり分類やタグ付けを行っておくと後々楽になります。
アイデアストックマネジメントが生む未来
アイデアを実装して価値に変えるには、タイミングと検証が欠かせませんよね。
アイデアストックのマネジメントを徹底することで、実装すべき施策を見極め、余計な機能を削減することが可能になります。似た文脈として「「いらない機能」がなぜ生まれるのか?そして、我々はどうすれば良いのか?」という記事でも、機能追加の闇について触れていますが、適切なアイデア管理は無用な機能を生み出さないための防波堤にもなるのです。

また、アイデアストックは「PdMが一人で抱えるもの」という誤解を解くことも重要。チーム全体でアイデアを共有し、誰もがストックを見て「使えそうな施策」を探せる文化を作ると、組織全体でのアイデア生成が加速します。アイデアをPdMだけが抱え込まず、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドもアクセスしやすい状態を整備する。これこそ、アイデアストックマネジメントの真骨頂です。

今日から実践できるアクション
・アイデア用の一元管理表を作る
Notionやスプレッドシートなど、チームで閲覧可能な場所に「アイデア表」を用意し、ジャンル別にシートを分けたり、タグ付けを行う。誰でも簡単に検索できる状態を作っておく。
・アイデアはすぐに優先順位を決めない
思いついたり、ヒアリングで得たアイデアは、まずストックへ。次回スプリント計画やリリース後のレトロであらためて優先度を評価する。時間を置くことでよりよい判断ができる。
・チームでストックを見返す習慣をつくる
週次や月次の定例ミーティングで、アイデアストックをざっと眺める時間を確保する。メンバー全員にアイデア閲覧のフローを浸透させることで、PdMだけに依存しないアイデア創出サイクルが回る。
Q&A
Q1. アイデアの量が膨大になりすぎて管理しきれなくなったらどうしますか?
A1. 定期的にメンテナンスする仕組みを作ることをおすすめします。一定期間以上経過しても具体化されなかったアイデアは「保留フォルダ」に移動させ、さらに時間が経ったら削除検討するなど、2段階や3段階の仕分けフローを用いると管理が楽になります。
Q2. チーム全員でアイデア管理に協力してもらうには、どんな工夫が必要ですか?
A2. まずは「アイデアが成果に繋がった成功事例」を共有することが大事です。みんなが自分の出したアイデアが実装に繋がり、評価された実績を見ると、自然にアイデア投稿に意欲が高まります。あとはアクセス権やツールの使い勝手を整えて、ストック作業のハードルを下げることも重要です。
Q3. すでにリソースが限られた状況で、アイデアを棚上げしておく余裕はあるのでしょうか?
A3. むしろリソースが限られているからこそ、アイデアの“棚上げ”が有効です。実装すべきタイミングではないアイデアに手を出すよりも、定期的に一覧を見直して投資対効果を評価したほうが、結果的に余計な工数を使わずに済みます。
参考情報
- Eric Ries. (2011). The Lean Startup. Crown Business.
- Marty Cagan. (2018). INSPIRED: How to Create Tech Products Customers Love. Wiley.
- Jeff Dyer, Hal Gregersen, & Clayton M. Christensen. (2011). The Innovator’s DNA. Harvard Business Review Press.
- Harvard Business Review. (2018). “How to Tap Employee Innovation” [論文].
- IDEO. (2015). Design Thinking for Innovation. IDEO University.
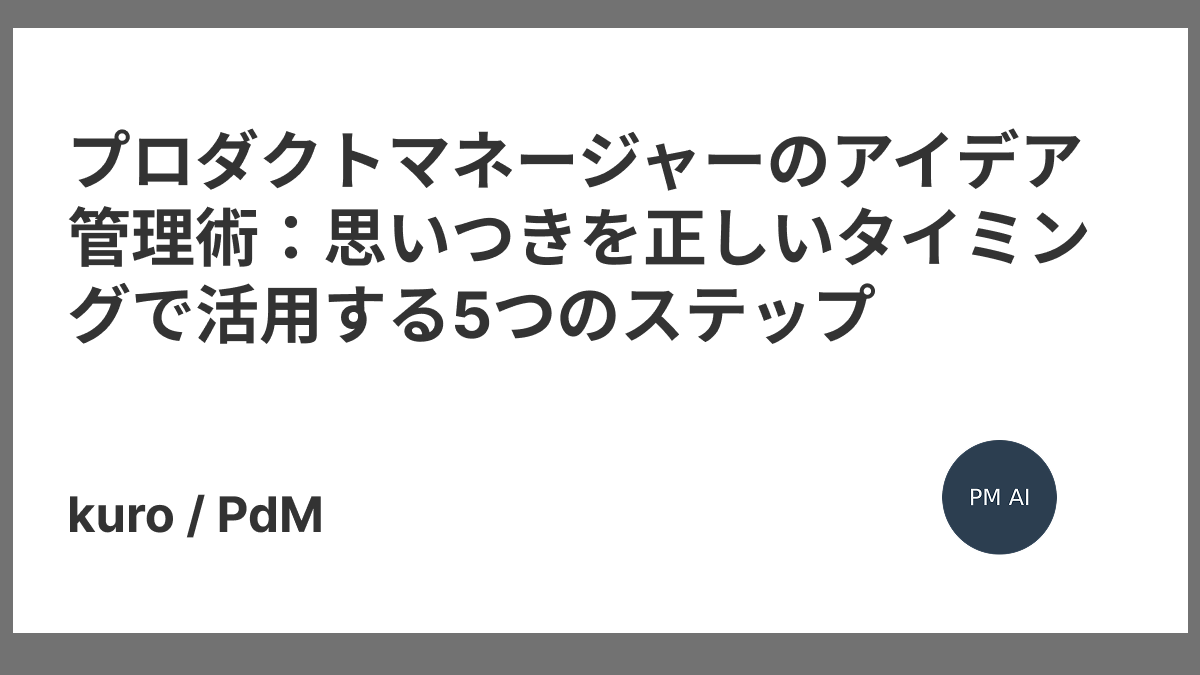
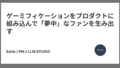
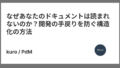
コメント