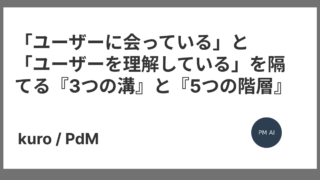 プロダクト企画
プロダクト企画 「ユーザーに会っている」と「ユーザーを理解している」を隔てる『3つの溝』と『5つの階層』
この記事の要約 【課題】 定期的にインタビューを実施しているのに、なぜか施策が当たらない。それは「会うこと」で満足し、「理解」の定義がズレたまま停止している可能性がある。 【原因】 インタビュー特有の「3つの溝(バイアス・環境・言語化)」に...
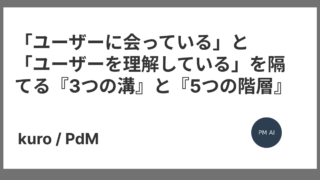 プロダクト企画
プロダクト企画 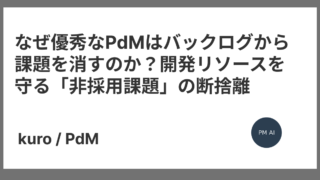 プロダクト企画
プロダクト企画 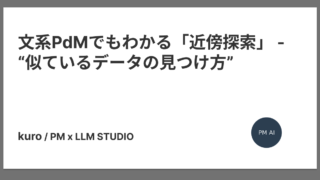 プロダクト企画
プロダクト企画 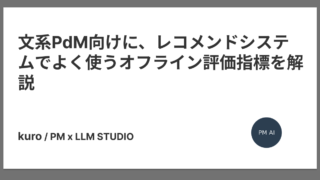 プロダクト企画
プロダクト企画 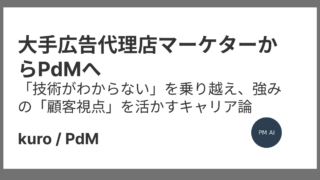 キャリア
キャリア 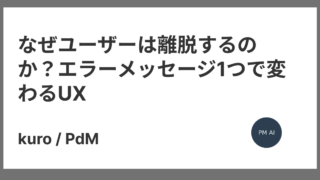 プロダクト企画
プロダクト企画 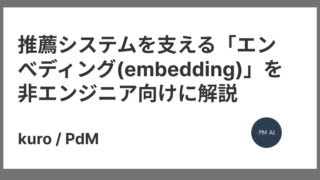 プロダクト企画
プロダクト企画 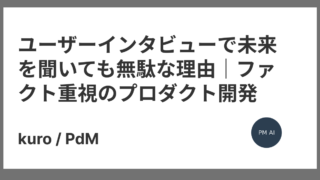 プロダクト企画
プロダクト企画 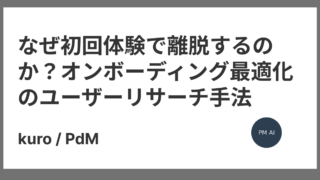 プロダクト企画
プロダクト企画 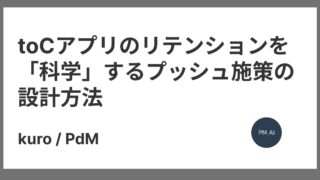 プロダクト企画
プロダクト企画 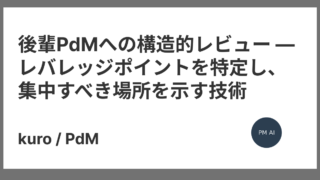 プロダクト企画
プロダクト企画 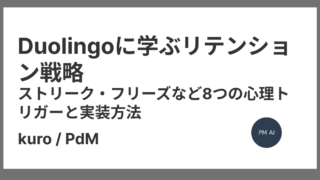 プロダクト企画
プロダクト企画 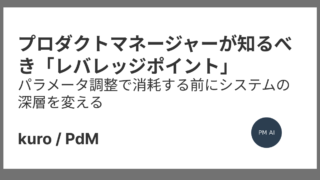 プロダクト企画
プロダクト企画 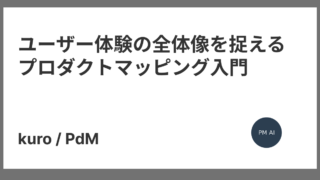 プロダクト企画
プロダクト企画 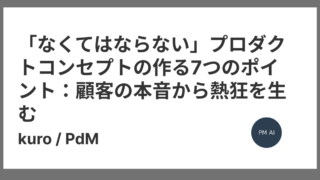 プロダクト企画
プロダクト企画 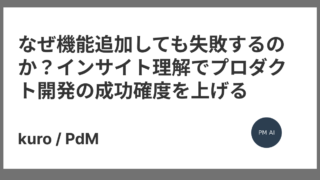 プロダクト企画
プロダクト企画 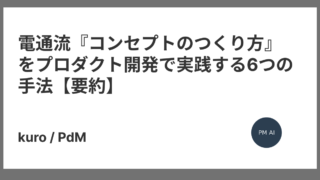 PM関連本
PM関連本 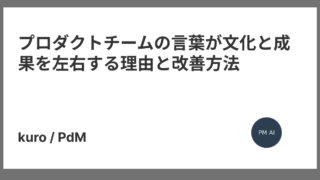 プロダクト企画
プロダクト企画 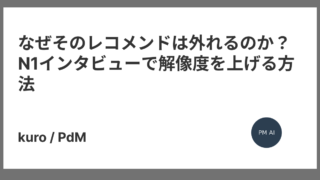 プロダクト企画
プロダクト企画 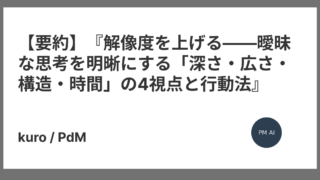 PM関連本
PM関連本 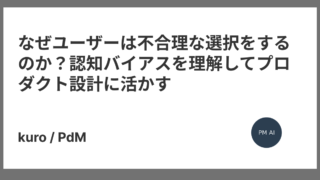 プロダクト企画
プロダクト企画 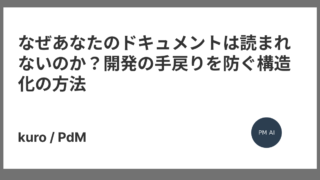 プロダクト企画
プロダクト企画 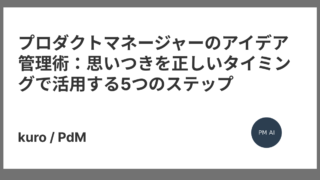 プロダクト企画
プロダクト企画 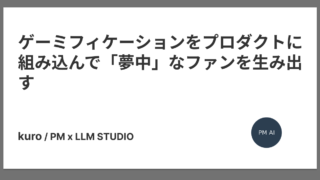 プロダクト企画
プロダクト企画 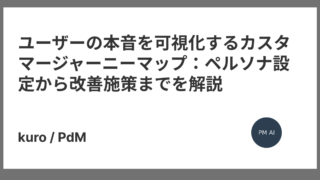 プロダクト企画
プロダクト企画 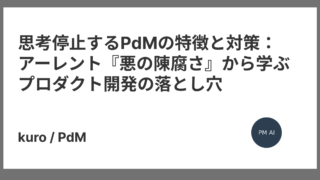 PM関連本
PM関連本 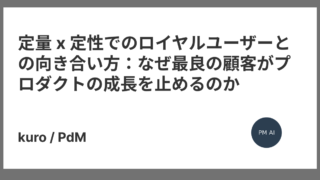 プロダクト企画
プロダクト企画 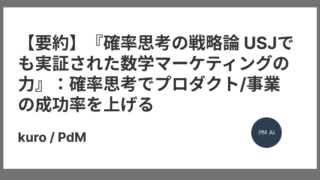 PM関連本
PM関連本 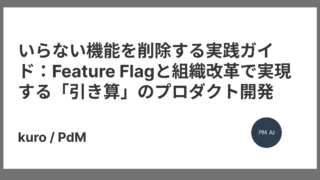 プロダクト企画
プロダクト企画 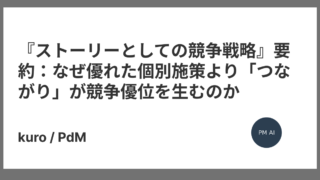 PM関連本
PM関連本