この記事の要約
- ユーザーインタビューで「Why(なぜ)」連発がうまくいかない心理的構造
- Whyで詰まった瞬間に使える「感情」「行動」「環境」3つの切り口による27の代替質問
- 質問の背景・選び方・タイミングも含めて“深掘りの型”を紹介
Whyが刺さらないのはなぜか?
Whyが効かない背景として大きく3つの壁があります。
- 圧迫感バイアス(問い詰められている感覚が生まれる)
- 認知負荷(即座に理由を言語化できない)
- 社会的望ましさバイアス(「正解」を答えようとして本音から遠ざかる)
「Why=答えなきゃいけない」という圧が働くことで、深掘りどころか「守り」に入るユーザーが少なくありません。
Whyが刺さらない時のサインと、やりがちな失敗パターン
Whyが刺さっていないなー、というときにはこんな感じのシグナルがあります。
- ユーザーが言葉に詰まる・目線が泳ぐ
- 「特に理由は…」「なんとなく」といった曖昧な返答
- Yes/Noで終わる会話
- 同じ答えの繰り返し
深掘りしたいあまり「なぜですか?」を連発し、逆にユーザーの心理的安全性を削ってしまって、表層的な「模範解答」しか得られないことがあるある。
Why地獄から抜け出す27の代替質問
では、Whyの代わりに何を聞けばいいのでしょうか?実際に「3つの切り口」×「具体質問」を合計27個紹介します。
1. 感情の切り口:ユーザーの気持ちを引き出す
Whyを感情に変換することで、抽象的な理由探しから「自分の感覚」を思い出しやすくなります。
- どんな気持ちでしたか?
- 一番ワクワクしたのはどのタイミングですか?
- 迷いがあったとしたら、どんなことが引っかかりましたか?
- 「その時」の感情を1〜10で点数をつけるなら?
- それって普段もよく感じることですか?
- もし友達に話すなら、どんな言葉を使いますか?
- 似たような場面で、同じような気持ちになった経験は?
- 今振り返って一番印象に残っているのは?
2. 行動の切り口:行動のプロセス・選択肢・タイミングで深掘る
Whyの“理由探し”ではなく、「どんな行動をとったか」という事実に着目する。
- その時、最初に何をしましたか?
- 選択肢はいくつありましたか?
- 他に迷ったこと、検討したことは?
- いつもはどうしていますか?
- この決断、普段と比べて違いはありましたか?
- やってみて「想定外」だったことは?
- もし最初からやり直せるなら、どうしますか?
- 類似のタスクで、他社サービスならどうしてますか?
- この行動のきっかけは何でしたか?
イメージ
toCアプリのリテンション改善で「なぜ毎日使わなくなったか?」とWhyを聞いても、「なんとなく忙しくて」で終了。「最後に使った日はどんな行動をしてました?」と問うと、「朝、通知が来たけどすぐ消して…」と具体的な行動ログが語られ、原因特定につながった。
3. 環境の切り口:状況や周囲の文脈から背景を明らかにする
ユーザーの選択や感情は、必ず“環境(コンテクスト)”の影響を受けます。
Whyでは得られない「その場」の情報を引き出すことで、思考がクリアに。
- どこで・誰と・どんな状況でしたか?
- 時間帯や場所は?
- 周りに誰かいましたか?
- その時、他にやるべきことはありましたか?
- 同じことを家や職場でやる時、違いはありますか?
- 他のサービスと同じシーンで使いますか?
- どんなデバイスやツールを使っていましたか?
- 使う前後で環境に変化はありましたか?
- 周囲の反応や空気感は?
イメージ
EdTechプロダクトで「学習しない日が続いた理由」をWhyで聞いても「特に理由は…」と止まっていた。「どんな状況でアプリを開いてましたか?」と聞くと、「仕事帰りの電車の中で…」と具体的なコンテクストが見え、設計改善に直結した。
27パターンの“使いどころ”と、Why質問NG例との比較
実際には、ただ質問を並べても使いこなせません。
ここでは「状況別の使い分け」と、Why依存型のNG例・リカバリー例を対比します。
| 状況 | Why質問(NG例) | 代替質問(リカバリー例) |
|---|---|---|
| 曖昧な返答 | なぜそう思いましたか? | その時の気持ちを10点満点で表すと? |
| 思い出せない様子 | なぜその行動を? | 何をしたか順番に教えてください |
| 無難な回答 | なぜそれを選びましたか? | 他に迷った選択肢はありましたか? |
| 状況が不明 | なぜそれが必要でしたか? | どんな場所やタイミングで使いましたか? |
このように、Why依存型から「感情」「行動」「環境」に言い換えるだけで、ユーザーが語りやすい空気をつくれます。
「NG質問集と改善例」も合わせて読むと、さらに精度が上がるはずです。

Whyに頼らない“深掘り設計”の原則:ファクト→感情→背景で立体的に掘る
Whyを外しても本質に迫れるインタビュー設計。その根本は「ファクト→感情→背景」の順で深掘ることにあります。
いきなり理由を聞くのではなく、まず事実(ファクト)を具体的に引き出す。その上で「どう感じたか」「どんな背景や文脈があったか」を追加で問う。これは『The Mom Test』や「質的リサーチ」の世界的定石でもあります。
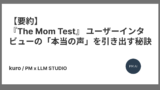
- Step1:まず「事実(行動・出来事)」を正確に聞き出す
- Step2:「その時の感情」や「困った瞬間」に焦点を当てる
- Step3:「なぜ?」ではなく「どうしてそうなった?」と背景や環境を探る
この順番なら、ユーザーに考える余白を残しつつ、本音・真因に迫れるのです。
また、社内でインタビューのPDCAを回す場合も、「質問パターンのバリエーション→ログ分析→振り返り」の循環が大切。LLM(大規模言語モデル)を活用すれば、過去のログから“Whyが詰まった”場面を簡単に抽出・分析できます(詳しくはログ分析の記事参照)。

現場で即実践するための“質問選び”と、リカバリー小技集
「27パターンをどう選ぶか?」に迷ったら、
・ユーザーの反応速度
・表情や声のトーン
・沈黙や視線の動き
これらの“サイン”を手がかりにします。
- 表情が曇った時は→環境や行動の質問で視点を変える
- 話が止まった時は→点数化や例え話を使ってみる
- 理由が曖昧な時は→他社事例や友人ならどうするかで広げる
そして、すべての質問を「Yes/Noで終わらせない」意識を徹底する。
複数人でインタビューを分担する場合は、質問リストを事前にバリエーションで用意し、現場で柔軟に差し替えられる仕組みも有効です。
定量分析やプロダクトログ分析との組み合わせで「事実の裏付け」があれば、インタビューの説得力はさらに高まります。具体的な流れや方法は「ログ分析→ユーザーインタビューの記事」で詳しく紹介しています。
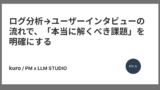
今日から実践できるアクション
- 次のインタビューでWhyを一度封印し、「感情」「行動」「環境」の切り口から最低3つ質問を用意する
- インタビューログを見返し、Whyで詰まった場面をピックアップ→リカバリー質問に差し替えたらどうなるかをチームで議論
- 定量データやプロダクトログのファクトから先に仮説を立て、Why以外の深掘り型質問を仕込む
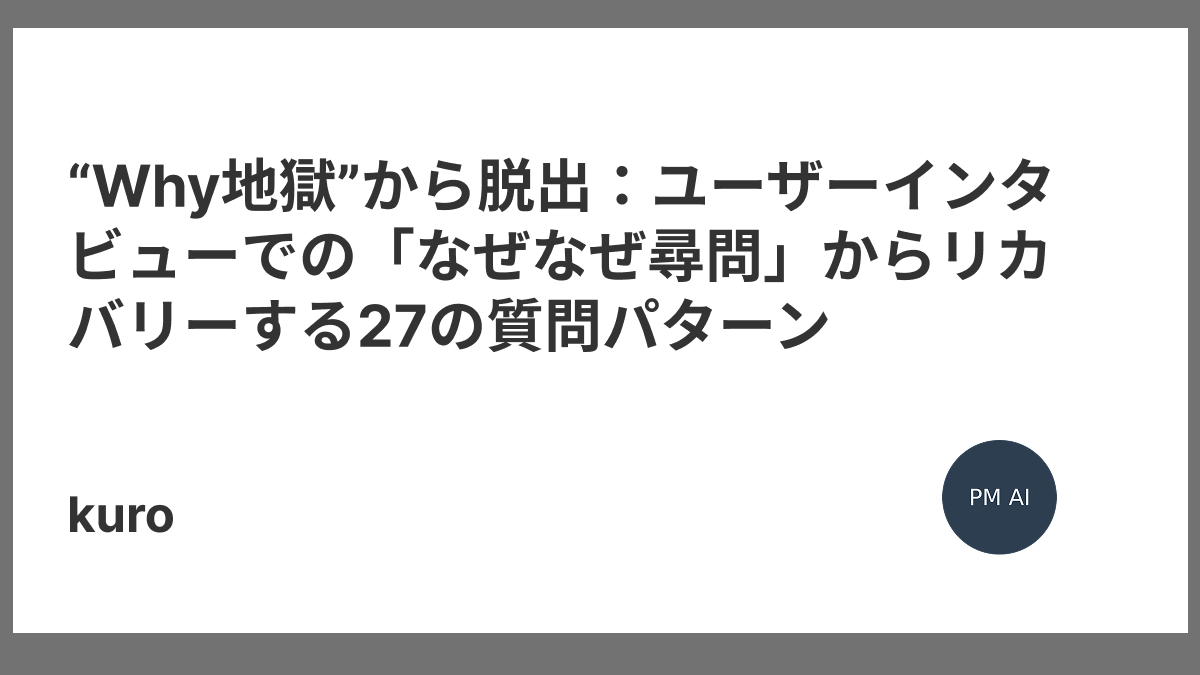
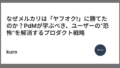
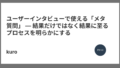
コメント