この記事の要約
-
プロダクト名は単なるラベルではなく、ユーザーの認知コストを下げマーケティング効率を決定づける「最初のユーザーインターフェース」
-
単なる思いつきや多数決で決めるネーミングは再現性がなく、コンセプトの言語化から音韻論に基づいた科学的なアプローチが打率を高める
-
愛される名前は偶然の産物ではなく、商標調査と記憶に残るフックというクリエイティビティの交差点に存在する
「プロダクトのネーミングがピンとこない」「サービス名が覚えにくいせいか拡散力が伸び悩んでいる」──特にプロダクト初期においてこうした悩みを抱えるプロダクトマネージャー、事業開発、マーケターは多いかもしれません。実際、名称が原因で認知度が広がりにくかったり、ユーザーの印象が定着しなかったりすれば競合に埋もれてる恐れがあります。
本記事ではネーミングのセオリーについて以下のような観点を紹介します。
- ユーザーの心理をくすぐり、自然と記憶に残る名称を生み出すプロセス
- ネーミングに関する心理学的アプローチ
- 著作権や商標リスクへの対処
- 海外展開を視野に入れた注意点
ネーミングがプロダクトの成否を左右する理由
大前提として名前が与える印象は想像以上に大きいです。
2020年に米国の調査会社が行った研究によれば、ユーザーは新製品を認知してから最初の30秒程度で「興味を持つかどうか」を判断するそう1。このとき、名称が魅力的に映らなかったり、覚えにくかったりすると興味を失うリスクが高まります。
さらに、デジタル時代では検索されやすさやSNSでのハッシュタグ化が可能かどうかも重要で、名前がカタカナで長すぎたり、英単語でも一般名詞に埋もれてしまうようなものだと、SNS上で話題にしにくい。また、ハッシュタグがすでに他の文脈で使われている場合、顧客が混乱するリスクも無視できません。
もうひとつ挙げたいのが差別化要素としてのネーミング。機能的には似たようなサービスでも、名前が違えばユーザーが抱くイメージがガラリと変わることがあります。例えば、タスク管理ツールのTrelloとAsanaは機能面が近い部分も多いですが、名前から想起されるイメージやブランドストーリーの違いでファン層が微妙に分かれています。
僕自身、副業でやっていたtoCアプリ開発で、名称に悩み途中で名称を変更した経験があります。製品自体は優れているのに、名前で伝わるメッセージが曖昧だと、ユーザーが「なんかよくわからない」という印象を受けてしまう。逆に、ちょっとした言葉選びを工夫するだけで「これって面白そう」と好奇心を刺激できる場合もある。ネーミングは、プロダクトの第一印象を左右する大きな要素です。
ネーミング検討プロセス
名前を決める際、最低限のプロセスを踏むことで地雷を避けつつ強力なネーミングを生み出せる確度が高まります。
1. ターゲットユーザーの言語感覚・共感ポイントをリサーチ
ユーザーが普段どんな言葉を使い、何に共感するかを知るのが出発点。ユーザーインタビューやSNS上の発言を分析すると、ヒントになる単語やフレーズが自然に浮かび上がります。たとえば、わかりやすいものなら若年層向けSNSであれば、短くてリズミカルな響きが好まれ、BtoBエンタープライズ向けソリューションなら、信頼感を醸し出す重厚なネーミングが合うケースなどなど。
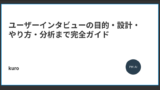
2. 複数案を用意してA/Bテストやミニ調査を実施
名前のアイデアはできるだけ多く出すのが基本です。社員や周囲だけで絞るのではなく、実際のユーザー層に対してミニ調査を行うと客観的な評価が得られます。SNS広告のABテストで複数の名称をランダムに表示し、どちらのクリック率が高いかを計測するというやり方も手軽。あるいはクラウドソーシングでターゲット層に近い人々へ意見を尋ねる方法も有効です。
3. 絞り込んだ案をチーム内でレビュー
初期の段階でユーザー評価がそこそこ良くても、法務リスクや既存商標との重複があるかもしれません。後述する商標リスクの確認を含め、チームレビューで最終調整を行うのが安全策。SpotifyやAirbnbも最初は異なる名称でスタートした事例があり、複数の案から最適解を探るプロセスがいかに大事かを象徴しているといえます。
複数のネーミング案をRICEのように多軸評価する
ネーミング候補をある程度絞ったら、さらにフォーマルに“評価”を行う仕組みを使いましょう。プロダクト開発では「RICEスコア」などのフレームワークを用いてアイデアを優先度付けすることがありますが、これをネーミングにも応用するイメージです。たとえば以下のような評価軸を設定して点数をつけます。
| 評価軸 | 内容 | 点数例(0〜5) |
|---|---|---|
| 検索性 (Reach) | GoogleやSNS上で他の文脈に埋もれずヒットしやすいか | 4点 |
| インパクト (Impact) | ユーザーが聞いた瞬間に惹きつけられるか | 3点 |
| ブランド整合性 (Confidence) | 既存ブランド理念や世界観と矛盾がないか | 5点 |
| コスト (Effort) | 商標出願やドメイン取得などに手間・費用がかからないか | 2点 |
イメージ事例として、もし候補が「A」「B」「C」の3案あるなら、各評価軸で0〜5点を付与し、合計スコアを比較します。たとえば
- 「A」は検索性が高いがブランド整合性が微妙
- 「B」は発音しにくいがユーザーインタビューではウケが良い
──というように、定性的なポイントを数値化して並べるとチーム内で議論しやすくなります。
とはいえ、最終的にはあくまで“指標”であり、スコアが高いものが必ずしも成功するとも限らないのが難しいところ。RICEのような多軸評価で客観性を担保しつつ、どの評価項目を重視するかチームで合意しておくとスムーズです。
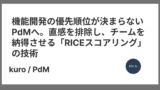
心理学的アプローチと注意点
名称を考えるときに「名は体を表す」と言われるように、言葉の持つイメージや連想を狙うのは自然な流れです。ただし、心理学の観点からは必ずしも“意味通りの印象”に縛られないほうが良い場合もある。そこが難しさでもあり、面白さでもある。
- 連想効果: ある単語を聞いたときに無意識に抱くイメージや感情。たとえば“Slack”は「怠ける」という英単語の意味を持つ一方で、略称(Searchable Log of All Communication and Knowledge)という解釈もあり、ユニークな連想を生んでいる
- 言語的タブーへの配慮: 多言語展開を想定するなら、特定の国でネガティブな意味を持たないかを要チェック。実例として、MitsubishiのSUV「Pajero」は一部のスペイン語圏で蔑称に近い意味があるため、海外では別の名称を使うケースがある
また、音の響きやアルファベットの配置によって「言いやすさ」「覚えやすさ」が変わります。脳科学的には、母音の配置やリズムが取れる名称は記憶に残りやすいとする研究もあります2。一方でやりすぎると子供っぽい印象になったり、サービスの性格と乖離する可能性があるため、バランス感覚を持つことが大切です。
PdMが押さえるべき著作権・商標リスク
ネーミングを検討する上で、いくらユーザー心理的に「最高の名前だ!」と思っても、商標の問題がクリアできなければ使えません。大手企業が異業種でも同じ名称を商標登録しているケースは珍しくなく、侵害するとリーガルリスクが発生します。
PdMとしては、ある程度アイデアが固まった時点でGPTやGeminiに聞き、その後法務担当や弁理士などに相談し、商標データベース検索を実施するのが安全策。国際展開を見据える場合は、主要ターゲット国での商標とドメイン取得状況も同時にチェックしておきたいところです。
著作権と商標権は別物である点にも注意。ネーミングに関しては主に商標が問題となり、著作権はロゴのデザインやコピー文書にかかる場合が多いので、「名前を使うだけなら大丈夫」という安易な考えは持たないほうがいいです。
名前に迷ったら、最後は“熱量のある人”の独断に賭ける
ネーミング案をRICEのような評価フレームワークで多軸評価して絞り込んでも、正直最終的な決定が難しいことも多いです。あらゆる要素を数値化しても、僅差で拮抗するケースが珍しくありません。加えて、ユーザーインタビューなどのリサーチ結果では予想しきれない“ブランドの化学反応”が起きるかどうかは未知数。
そんなときは、プロダクトオーナーやCEOなど、そのプロダクトに一番熱量を注いでいる人の勘やフィーリングを最終的に信じるのも大アリだと思います。もちろんデータやエビデンスを無視するわけではありませんが、名前には“ストーリー”や“思い”が乗る部分があり、そこは理屈だけで割り切れない領域とも言えます。
RICE評価などで客観性を担保しつつ、最後は熱量のあるキーパーソンに決めてもらう。このプロセスが納得感とスピードを両立させるコツだと、僕は感じます。
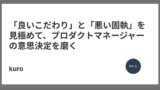
ネーミングこそユーザー心理への第一アプローチ
プロダクトネーミングは単なるラベルづけではなく、ユーザーがその製品・サービスをどう受け取るかを左右する重大なポイントです。
- 検索されやすくSNSでも拡散されやすいか
- 競合と差別化できる独自性を持っているか
- ユーザー心理をくすぐる“フック”があるか
- RICEのように多軸評価して候補を絞り込み、商標リスクや法務チェックを通しても問題ないか
- そして最後は、プロダクトに最も熱量を注いでいる人の直感やストーリーを重視する
この一連のプロセスを踏むことで、リリース後に「やっぱり別の名前にすればよかった」と後悔するリスクを格段に下げられます。もし今、ネーミングの迷宮にハマっているなら、まずはユーザーの声やデータに耳を傾けつつ、あなた自身が「これだ!」と思える名称を探してみてください。名前こそユーザー心理への第一アプローチなのだと、僕は信じています。
参考情報
- 1:Ipsos MORI “Consumer Decision Making Process” (2020) – 最初の30秒で印象が固まるとの調査結果
- 2:Michael S. Gazzaniga著『Cognitive Neuroscience』 – 音韻リズムの記憶効果に言及
- 3:Harvard Business Review(2013):「Tropicana Brand Overhaul and the Value of Brand Elements」
今日から実践できるアクション
- ターゲットユーザーに近い層を対象に、複数のネーミング案をA/Bテスト。SNS広告やクラウドソーシングでミニ調査を行う
- RICEスコアなどのフレームワークを用いて、検索性・インパクト・ブランド整合性・コストなどで数値評価する
- 海外展開を視野に入れているなら、早い段階で英語圏・欧州圏・アジア圏など主要国の商標データベースを検索する
- 社内レビューでは、弁理士や法務担当を巻き込み、商標リスクと類似商標の有無をチェックする
- 複数候補で評価が拮抗したら、プロダクトオーナーやCEOなど熱量のあるキーパーソンの最終判断を尊重する
Q&A
- Q. 既存プロダクトのネーミングを変えたいが、顧客が混乱しないか心配です
- A. 既存ユーザーへの影響を最小化するため、告知タイミングやコミュニケーション計画をしっかり立ててください。名称変更の意図やメリットを丁寧に説明すると混乱が減ります。
- Q. 社員のアイデアが豊富すぎて、なかなか候補が絞れません
- A. 初期段階では候補を絞らずに出すだけ出し、その後ミニ調査やA/Bテストで客観的な評価を得る方法がおすすめです。チームの議論だけで決めるよりユーザーデータを使うほうが確実と感じます。加えて、RICEのようなフレームワークを活用し、複数の評価軸ごとに点数をつけると整理しやすいです。
- Q. ネーミングとロゴを一緒に考えたいのですが、注意点はありますか?
- A. ネーミングを先行して決めてからロゴデザインに落とし込むほうがスムーズです。並行で進める場合も、商標や法務リスクを早期に把握し、ネーミングやロゴが衝突しないように調整する必要があります。
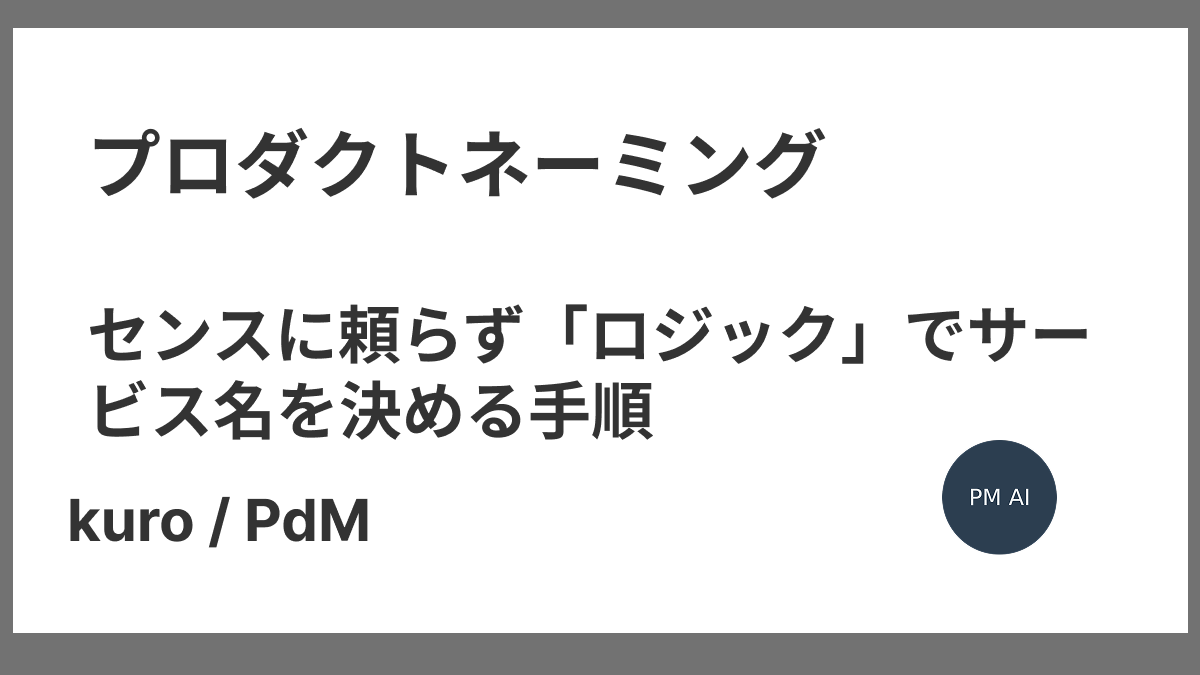





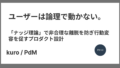
コメント