この記事の要約
- 失注ユーザーは利害関係が薄れている分、厳しい意見を惜しみなく語ってくれる。定量データで解約率や離脱タイミングを把握するだけでは不十分で、どのような感情を抱き何を期待していてそれがどこで崩れたのかを深掘りする必要がある
- Netflixは2011年の値上げで80万人が解約した際、失注ユーザーへのインタビューで「説明不足」「ユーザビリティ低下」を特定し方針を再検討。一方Quibiは離脱顧客の本音を捉える仕組みを回さずわずか半年で終了
- 失注インタビューでは解約に至る経緯・満足不満点・競合比較の3つを深掘り。厳しい意見を遮らず「もう少し詳しく」と深掘りし、チーム全体にオープンに提示することで解約防止やエンゲージメント向上のヒントが見える
失注ユーザーを振り返る価値
僕はこれまで累計 700人以上のユーザーインタビューを実施してきましたが、新規ユーザーの声だけでなく、あえて“失注ユーザー”の声を深く聞くことで見えてくる改善点が多々あります。離れてしまった顧客こそ、プロダクトに足りなかった価値を率直に示してくれる存在だからです。新規ユーザーの獲得に注力するあまり、失注ユーザーへのヒアリングを軽視すると、なかなか根本的な課題が見えてこないことがあります。
特に失注理由の把握や再発防止策を検討する際は、定量データだけでなく「なぜ離脱したか」を深く掘り下げる必要があります。数字だけでは見えない“本音”は、直接ユーザーの言葉を聞かないと捉えきれません。離脱した顧客はすでに利害関係が薄れている分、厳しい意見を惜しみなく語ってくれる可能性も高いです(前提として、顧客は答えを持っていないので、直接聞くのではなく離脱のファクトを集めて最後はPdMが情報処理しましょう)。
新規獲得ではなく“解約ユーザー”が教えてくれること
多くの企業は、新規獲得ユーザーのインタビューには力を入れても、解約したユーザーへのフォローが疎かになりがち。ただ、解約済みユーザーには、既存顧客の満足度や利用継続のモチベーションが下がる瞬間がリアルに詰まっています。
例えば以下のように継続利用を阻害するポイントが明確に浮かび上がるケースも多いです。
- 対応が遅い
- 使いこなせない
- 競合他社の機能が魅力的
- 導入効果が分かりづらい
定量データで解約率や離脱タイミングを把握するだけでは不十分。
- ユーザーがどのような感情を抱き、
- 何を期待していて、
- それがどこで崩れたのか
――このプロセスを“失注インタビュー”で深掘りすることで、プロダクトマネージャーとして次にやるべき打ち手がはっきり見えてきます。
定量データでは捉えきれない本音
解約防止のために「いつ離脱するか?」をコホート分析などで追うことは多いかもしれませんが、そこにユーザーの“本音”は必ずしも表れません。数字は事象を映し出すだけで(もちろんそれも重要ですが)、それが起こった背景や真の理由は質的アプローチが欠かせないのです。
僕自身、定量と定性が食い違うケースを何度も見ました。数字上は高い満足度を示しているようでも、
- 「実は裏で別のシステム導入を検討していた」
- 「面倒でアンケートを適当に回答してしまった」
といった声を、インタビューで初めて把握することも。
こうしたミスマッチを最小化するうえでも、離脱顧客へのディープインタビューは非常に効果的。参考として、定量と定性の食い違いに対処する方法を掘り下げた記事があるので、合わせてご覧ください。

失注顧客へのアプローチ方法:連絡手段やインセンティブ設計
失注ユーザーにインタビューを行う際は、まず「どうやって連絡を取るか?」が課題になります。退会時にメールアドレスを残してもらえているなら、直接メールでアプローチできますし、電話番号がある場合はショートメッセージやコールセンター経由という方法もあります。BtoBの場合は担当営業が関係を保っていることも多いので、営業経由でコンタクトを取るケースが一般的。
また、直接的な経路ではなく、ビザスクなどを使って募集すると失注先顧客の決済者と繋がれることも多いです。
インタビューを引き受けてもらうにはインセンティブが必要なケースが多いです。アンケート形式ではなく深く話を聞く分、ユーザーには時間的コストをかけさせてしまいます。そこで謝礼金や、別途のAmazonギフト券、あるいは試供品など、対象ユーザーが魅力を感じるインセンティブをセットするのが一般的です。ただし、あまりに高額な謝礼はバイアスを生む恐れがあるので適切に。
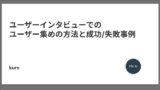
Netflixの成功事例とQuibiの失敗例
成功事例:Netflixの価格改定騒動
2011年にNetflixがDVDレンタルとストリーミングの料金プランを分割し、大幅な値上げを行った際、多数のユーザー離脱が発生。約80万人のユーザーが短期間で解約したと報じられ、株価も急落し、社会的にも大きな批判を浴びたのです。
しかしその後、Netflixは失注ユーザーから直接フィードバックを収集して原因を詳細に分析。「値上げ理由の説明不足」「パッケージ分割によるユーザビリティの低下」が主な不満点だったことが明らかになり、経営陣は方針を再検討。
具体的には、退会したばかりの顧客に対してインタビューやメール調査を実施し、「何にもっとも不満を感じたか」を率直に聞き出したと言われています。その結果、Netflixはコミュニケーション方法の改善や新たな機能開発に力を入れ、またプラン見直しを行ってユーザーの支持を回復しました。失注ユーザーが語った厳しい声を活かしたことで、サービス品質や顧客ロイヤルティの向上につなげた事例として知られています。
失敗例:Quibiの急速な事業閉鎖
2020年にローンチした短尺動画配信サービス「Quibi」は、有名なハリウッドプロデューサーや大手投資家からの巨額出資を集めながらも、わずか半年ほどでサービス終了に追い込まれました。ユーザーの早期離脱が相次いだ理由として、「スマートフォンでしか視聴できない」「コンテンツが十分に魅力的でなかった」などが指摘されています。
本来であれば、離脱を防ぐために失注ユーザーへのインタビューを行い、改善策を検討する時間はあったはずですが、市場投入スピードを優先するあまり十分なリサーチがなかったと言われています(実態はどこまでいっても分かりませんが)。サービス終了を発表する頃には大量のユーザーが離脱済みで、実態を深く探る機会を逃してしまった面も。離脱顧客が抱えた本音を捉える仕組みをきちんと回していれば、別のシナリオがあったかもしれないと分析する声も出ています。
インタビュー項目と注意点
失注インタビューで欠かせない項目は以下3つ。
- 解約に至る経緯
- 満足していた部分と不満を感じていた部分
- 競合との比較ポイント
具体的には、いつ・どのような不満が蓄積されたのか、社内でどんな意思決定プロセスがあったのか、競合に移った場合はどこが優れていたのかなどを、できるだけ深くファクトベースで聞くのがおすすめです。質問設計の工夫については、ユーザーインタビューの質問項目大全もご参照ください。

また、失注ユーザーからはネガティブな意見が出やすいです。そこで
- 「批判的な意見を遠慮なくお聞かせいただきたい」
- 「よりよいプロダクトにするための参考にしたい」
と、あらかじめ伝えておくことが重要です。相手が率直に話しやすい雰囲気を作ることで、より真に迫った課題を引き出すことができます。必要に応じて、ユーザーインタビューで起こるバイアスを徹底攻略するといった心理学的アプローチも有効です。

厳しい意見をどう聞き出すか?
僕はヒアリングの際、ユーザーが文句を言い始めたらそれを遮らずに、むしろ「もう少し詳しく教えていただけますか?」と深堀りするようにしています。背後にある潜在的な課題や、サービスに求めていたものが何なのかを探るためです。
離脱ユーザーの厳しい声からこそ、新たな機能開発や課金モデルの見直しといった、有益な提案が生まれるケースが少なくありません。
加えて、厳しい意見を言いやすい状況を作るには、アイスブレイクや共感を示すことも欠かせません。ユーザーが不満を感じる時点には必ず理由があり、それを受け止める姿勢が重要になります。
さらにインタビュー前に仮説を設計しておくと、仮説と実際の声との差分から得られる学びが一層大きくなります。興味のある方は、ユーザーインタビュー前に「筋の良い仮説」をチームで設定するを参考にしてみてください。

実際のプロセス、チーム共有、スプリントでの改修例
本記事で説明したような改善を実施する場合、基本的なプロセスとしては以下のステップを踏みます。
- 解約タイミングのユーザーを洗い出し、アプローチしてインタビュー設定
- インタビューで失注理由・不満点を定性データとして吸い上げる
- チームでインサイトを共有し、優先度の高い課題を選定
- スプリントで仮説検証を含めたUI改善・機能改修を実施
- 既存ユーザーにも導入後のフィードバックを収集して効果測定
特にインタビュー結果の共有では、厳しい声をチーム全体にオープンに提示することが大切です。良い評判だけを強調し、都合の悪い声を隠すと改善の芽を潰しかねません。ネガティブな声の中にこそ、解約防止やエンゲージメント向上のヒントが隠れています。インタビュー結果のチーム共有の方法や、社内プレゼンに役立つポイントは、経営層・上司・メンバーを動かすユーザーインタビュー結果の見せ方・使い方でも詳しく書いています。

失注防止策が新たな価値提案につながる
失注インタビューの結果から想起される施策を実行してみると、単なる離脱防止策にとどまらず、新たな価値提案につながる可能性があります。たとえば、自社プロダクトを離脱した理由が「サポート不足」だった場合、チュートリアル動画やオンライン講座の拡充が必要となりますが、それを強化することで新規ユーザー獲得も容易になるかもしれません。
実際に、離脱ユーザーの声を反映してサービスのオンボーディングを改善した結果、導入初期の離脱率が改善しただけでなく、既存ユーザーの活用度合いも向上し、アップセルにもつながった事例も。「離脱を防ぐ」という発想が「プロダクト全体をより魅力的にする」戦略へと展開されるのです。
ネガティブな声こそ、次の飛躍のヒント
多くの企業やPdMが、目の前の新規獲得やエンゲージメント向上施策に忙殺されがちです。しかし、失注顧客が発するネガティブな声こそ、時にプロダクトの大きな飛躍につながるヒントを含んでいます。離脱ユーザーの声を探り、どこで期待が外れ、何が足りなかったかを突き止める。そのプロセスは決して気持ちの良い作業ばかりではありませんが、得られる学びや改善インパクトは大きいです。
失注ユーザーからの厳しい意見をいかに拾い上げ、素早く施策に反映するか。PdMとしてその仕組みを整えておくことで、解約防止やプロダクトの進化、そしてさらなるユーザー価値の創出につながります。「ネガティブな声をチャンスに変える」姿勢を持って、ぜひ失注ユーザーへのディープインタビューを実践してみてください。
今日から実践できるアクション
- 直近1か月以内に解約したユーザーリストを抽出し、早めにインタビュー依頼を行う
- インタビューの質問項目を事前に仮説化し、優先度の高い論点に集中する
- 厳しい意見を歓迎する姿勢を示し、インタビューでは深堀りを徹底する
- 得られたインサイトをチーム全体で共有し、改善策を迅速にスプリントへ組み込む
- 改善策の効果を定量指標と再インタビューで検証し、サイクルを回す
Q&A
Q1. 解約ユーザーにインタビューしても、辛辣な声ばかりで凹まないですか?
A. 凹むことは多いですが、そこに本質的な課題が隠れています。厳しい意見だからこそ、改善すべきポイントが明確になり、より良いプロダクトを目指せるチャンスと捉えると良いです。
Q2. 離脱顧客から「再度使いたい」と思ってもらうには、どんな工夫が必要ですか?
A. まずはなぜ離脱したのかを深く知ることが大前提です。そこから改善策をきちんと実行し、改めてアナウンスする。もし再利用のオファーをするなら、試用期間やサポート体制を手厚くし、ユーザーが再び離脱しないような環境を整備することが鍵になります。
Q3. どのくらいのインタビュー数が必要ですか?
A. 離脱顧客の全体母数やプロダクトの種類にもよりますが、だいたい「似たパターンが見え始めるまで」が目安です。定性調査では5~8名あたりから傾向が見え始めると言われることが多いですが、可能なら10名以上実施するとより確度が高まります。
参考情報
- Reichheld, F. (2011). The Ultimate Question 2.0. Harvard Business Review Press.
- Harvard Business Review (2022). Customer Churn Reduction through Qualitative Insight. Harvard Business Publishing.
- Cagan, M. (2018). INSPIRED: How to Create Tech Products Customers Love. Wiley.
- 【要約】『The Mom Test』 ユーザーインタビューの「本当の声」を引き出す秘訣
- 【要約】『INSPIRED』顧客に愛されるプロダクトを生むプロダクトマネジメントの極意
- 「顧客インサイト」を理解した上で、発見し活用する
- ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド
- グランデッド・セオリー・アプローチでユーザーインタビューからインサイトを掘り起こす
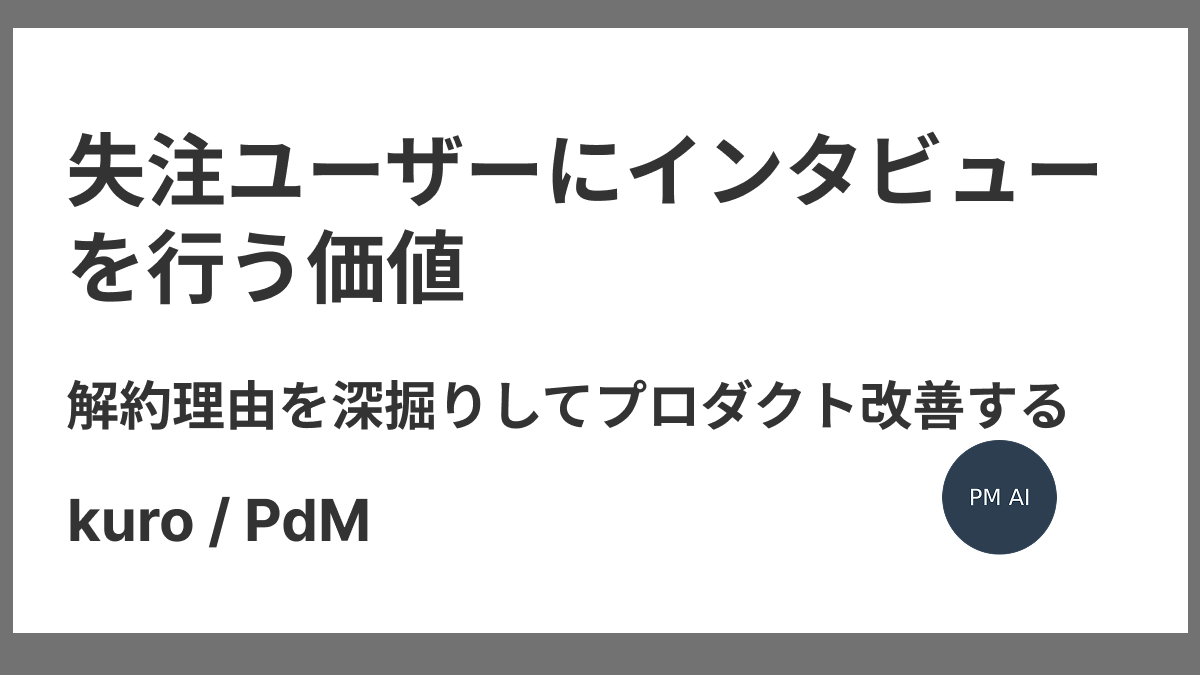
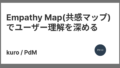
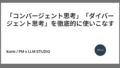
コメント