「機能をいくら磨いても、ユーザーになかなか熱狂的に支持してもらえない」「ブランディング戦略って必要なのは分かるけど、具体的にどう組み込めばいいのか…」と悩んでいませんか?
本記事では、プロダクト開発を推進する中で見落とされがちな「ブランディング」を、ユーザーリサーチの視点から深く考察していきます。
この記事を読むと、ブランドトーンとユーザーインサイトを融合させる方法が分かり、新機能追加やプロダクト刷新時に世界観を崩さないコツを学べます。
ブランディングとユーザーリサーチを掛け合わせる価値
プロダクトマネージャーにとって、まず押さえておきたいのが「ブランディング × ユーザーリサーチ」という視点です。単なる機能改善ではなく、ユーザーが抱く感情的価値や共感ポイントを理解することで、プロダクトの世界観やストーリーをより魅力的に仕立てられます。
UI改善とブランディングの違い
UI改善はユーザビリティ向上を目的とし、操作性・使いやすさといった機能面に注目します。一方、ブランディングは「このプロダクトは何を目指しているのか」「どんな世界観や価値観をユーザーと共有したいのか」など、感情面や社会的意義を含めた包括的アプローチです。
- UI改善:操作性・効率性・導線最適化
- ブランディング:理念・世界観・ストーリー性・価値観の共有
これらを融合すると、ユーザーにとっては「使いやすいだけでなく、共感できるから何度でも使いたい」と感じるプロダクトになります。
ブランディングで生まれる“共感”と“期待感”
ユーザーは、論理だけでなく感情に動かされます。たとえば、
- 共感:「このサービス、なんだか自分の価値観と通じる」
- 期待感:「これからのアップデートも楽しみ!」
僕の経験上、機能面だけを強化しても、長期的なファンにはなりづらいです。たとえばJTBD理論(Job To Be Done)でも、顧客が「雇用」している価値は技術要件だけでなく、ユーザーの感情的・社会的背景に根ざしているとされています。だからこそ、ブランディングを含めたユーザーリサーチが重要になるのです。
世界観・ストーリーを検証する質問設計のポイント
ブランディング視点のユーザーリサーチでは、通常のインタビュー項目に加えて「感情」「イメージ」「ストーリー」に焦点を当てた質問を組み込みます。
- イメージキーワードを問う
「本プロダクトを一言で表すと?」「イメージカラーは?」など、単語や色を引き出す質問をすることで、ユーザーが抱く世界観の断片が見えてきます。 - キャラクター化してもらう
「もしこのプロダクトが人だったら、どんな性格?」「映画の主人公に例えるなら?」など、ストーリー化することで抽象的な印象を具体化できます。 - 競合比較でブランド独自性を探る
「同じジャンルの他サービスと比べて何が違うと思いますか?」を聞くと、差別化要素やブランド強化のヒントが得られます。
こうした“ブランディング寄り”の質問を織り交ぜるコツについては、ユーザーインタビューの質問項目大全などの記事も参考になると思います。

顧客の声をブランド軸に再構築するフロー
ユーザーから得た声や感情を、どのようにブランディング戦略に落とし込むと良いのでしょうか。僕が実際に取り組んでいるフローを紹介します。
- インサイト抽出
インタビューやアンケートから得たキーワードをリスト化し、共通点を探る(例:「温かい」「前向き」「革新的」「安心感」など)。 - ブランドコアの定義
抽出したインサイトをもとに、「サービスが提供すべき価値や世界観」を一文のステートメントにまとめる。 - 具体的実装へ展開
- UIデザイン:ブランドイメージを反映した色使いやフォント選定
- トーン&マナー:文章表現やサービス全体のキャラクター
- 新機能設計:ブランドコアを損なわないか確認しながら仕様を決定
- 運用・評価
ユーザーの反応をモニタリングし、ブランドと現場の声とのギャップがあれば適宜修正を行う。
この流れはリーンスタートアップの考え方にも通じるものがあります。ユーザーの反応を素早く反映し、ブランド戦略とプロダクトを同時に成長させることが大切です。
デザインやマーケチームとの連携:ブランドガイドラインの作り方
ブランディングはプロダクトマネージャーだけで完結するものではありません。デザイン、マーケティング、エンジニアリングなど、多職能チームで一貫性を保つ仕組みが必要になります。
ブランドガイドラインに盛り込むべき内容
- 企業理念・サービスビジョン
チーム全員が迷ったときに見返せる「軸」として重要です。 - ビジュアル要素(ロゴ、色、フォント)
ブランドを視覚的に表現するルールを明文化して共有します。 - 言葉のトーン&マナー
プロモーション文やエラーメッセージなど、細部に至るまで統一します。
特に新機能の追加やマーケティング施策の都度、ガイドラインから逸脱しないかを確認しましょう。
事例:Airbnbの再ブランディング成功例
海外の民泊プラットフォーム「Airbnb」は、2014年に大規模なブランドリニューアルを行い、「Belong Anywhere(どこでも居場所がある)」というコンセプトを打ち出しました。これはユーザーインタビューで浮かび上がった「現地のコミュニティに溶け込みたい」「人とつながりたい」というニーズが元になったと言われています。
その結果、UI/UX改善だけではつかみきれないユーザーの共感を得て、世界規模での認知度アップと利用率向上につながりました。ブランドコンセプトとユーザーリサーチの相乗効果が表れた好例といえます。
新機能追加時にもブランドトーンを守る重要性
新機能を追加する際、既存のブランド世界観や価値観を守ることが大切です。せっかく構築したブランド軸から逸脱した機能を出してしまうと、ユーザーが「何だかイメージと違う」と感じてしまうリスクがあります。
世界観をブレさせないためのチェックポイント
- ネーミング・用語
新機能の名称や説明文が、既存のブランドトーンに合致しているか。 - UIのテイスト
ボタンやアイコン、配色がブランドガイドラインと整合しているか。 - 体験ストーリー
新機能によってユーザーはどんなストーリーを感じるのか。一貫性を保てているか。
今日からできる3つのアクション
- ブランドを聞き出す質問を追加する
既存のユーザーインタビュー項目に「イメージカラーは?」「どんなストーリーを感じますか?」などの質問を加えてみる。 - ブランドガイドラインのドラフトを作成
規模が小さくてもよいので、まずはチームで「ブランドの根幹」「言葉遣いのルール」を共有。 - 新機能チェックリストを用意する
新しくリリースする機能やデザインを、既存のブランド世界観と比較してズレがないか最終確認。
Q&A
Q1. 小規模プロダクトでもブランディングは重要ですか?
A1. はい、重要です。機能が少ないほど「ブランドイメージ」をしっかり打ち出すことで、ユーザーに強い印象を残すことができます。
Q2. ブランドリサーチとUI改善、どちらを優先すべきでしょうか?
A2. 使いにくさを放置するのは問題ですが、機能向上だけでは差別化が難しいケースもあります。UI改善とブランド戦略は両輪として並行して進めるのがおすすめです。
Q3. 生成AIが分析した結果をすべて信じても大丈夫ですか?
A3. 生成AIはあくまで補助ツールです。ハルシネーションが起こる可能性もあるので、最終的な意思決定は人間が慎重に行うべきです。
参考情報
- Kevin Lane Keller (2013) “Strategic Brand Management (4th Edition)”, Pearson.
- Marty Neumeier (2005) “The Brand Gap”, New Riders.
- 「Airbnbのブランドリニューアルに関する公式プレスリリース」(2014年)
- Harvard Business Review (2017) “Why Brand Matters for Tech Startups”, Harvard Business Publishing.
- ユーザーインタビューの質問項目大全:今日から使える具体質問例と定石
- 「プロダクト全体や新機能のコンセプト」を作る際のユーザーリサーチと併用
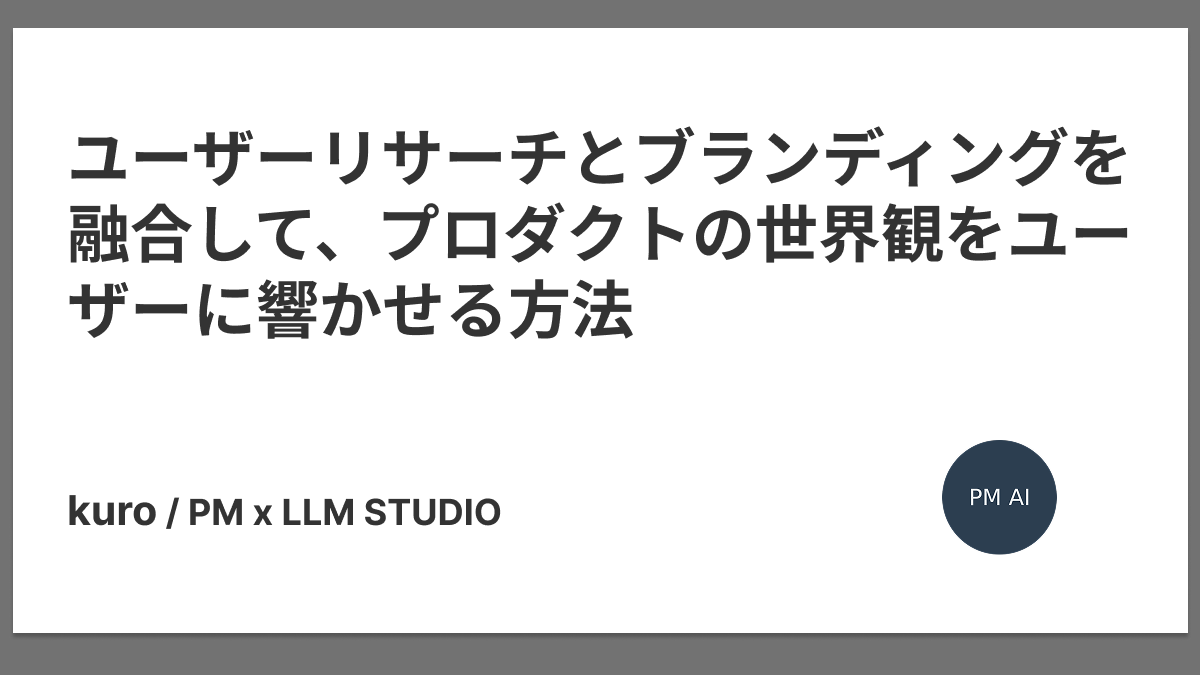
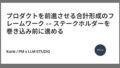
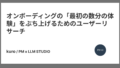
コメント