この記事の3行要約
- 電通の広告制作ノウハウをプロダクト開発に転用すると、機能の肥大化を防ぎ、10秒で価値を伝えられる明確なコンセプトが生まれる
- 「Not→But→Therefore」で常識を否定し新視点を獲得、SCAMPERで複数観点からアイデアを変形させることで差別化された製品が設計できる
- コンセプトを10文字のコピーに落とし込み、ユーザーインタビューで検証する小回りの利くサイクルが、精度の高い価値提案を実現しよう
優れたコンセプトが事業の未来を左右する
「コンセプトのつくり方 たとえば商品開発にも役立つ電通の発想法」(電通著)は、広告制作の現場で培われたノウハウを体系立ててまとめた一冊。
書籍タイトルにあるように、「商品開発にも役立つ」という言葉は決して誇張ではありません。広告の世界における“人を一瞬で振り向かせる”発想法や、短いコピーで価値を伝える技術は、スピードと競争が激化するプロダクト開発の現場でも極めて有効なことは容易に想像できると思います。
僕は博報堂でマーケティングとユーザーリサーチを学んだ後、現在はプロダクトマネージャー(PdM)を務めています。その中で特に新サービスの企画や立ち上げなどに関する仕事が多いのですが、まず最初の鍵になるのは「コンセプトをいかに明確に描けるか」だと感じています。
コンセプトはプロダクトの魂です。明確なコンセプトがあれば、機能仕様を検討する段階でも“何を実装して、何を捨てるか”を見誤りにくい。結果として、不要な開発やチーム内の混乱を最小化できます。
ただ、「コンセプトの大切さはわかるけど、具体的にどう作ればいいの?」という疑問を抱えているPdMの方は多いのではないでしょうか?本記事では「コンセプトのつくり方」を軸に、電通流の発想法をプロダクト開発へ落とし込む具体ステップを濃厚に解説します。既にコンセプトを意識して開発している方にも、さらに一段上の精度を目指すヒントになるはずです。
なぜ、プロダクト開発に広告的な発想が必要なのか?
広告クリエイティブでは、わずか数秒や数十秒の中で相手の心を掴まなければなりません。そのためには以下の要素を高いレベルで実現する必要があります。
- 伝える情報を絞る
- 強いインパクトを与える
- ターゲットの本質的な欲求に訴求する
これはプロダクトの世界でも同様。特にユーザーが膨大な情報にさらされている現代において、どんな価値があるのかを“瞬時に理解”してもらうことは競合優位を築くうえで不可欠です。
機能要求が次々に発生しがちなプロダクト開発では、明確なコンセプトがないと「なんとなく良さそうだから実装しよう」で機能が肥大化し、本当に必要なコア部分が埋もれてしまう恐れがあります。そこで、コンセプトから始める広告的な発想を取り入れると、「そもそもこの機能はユーザーのどんな欲求に応えるものなのか?」という問いに対して、一行のコピーやストーリーボードでスパッと示す力が育まれます。そのため、大事な判断がブレにくくなり、意思決定が速くなるのです。
『コンセプトのつくり方』に学ぶ、具体的な発想ステップ
本書の中では、電通が蓄積してきた多彩なクリエイティブ技法が紹介されています。ここではプロダクト開発との親和性が高いものを中心に、PdM視点を補足しながら解説します。「電通流なんて広告業界だけの話でしょ?」と思う方にこそ試してほしい実践的メソッドです。
①徹底的な事実収集とユーザーインサイトの深堀り
「コンセプトのつくり方」では、アイデア出しに入る前のステップとして、まず「生活者の事実(ファクト)を徹底的に集める」重要性が繰り返し語られています。広告プランナーも同様で、クライアントや市場を徹底リサーチし、“生活者のリアル”を捉えることから始めます。プロダクトの世界では、ユーザーインタビューやユーザーヒアリング、競合製品リサーチ、アクセスログ分析などが相当するでしょう。
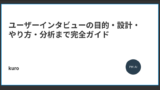
PdMは、こうした事実収集を「定量×定性」の両面で行っていきましょう。アクセスログやアンケートで市場感を把握しつつ、ユーザーインタビュー前に“筋の良い仮説”を設定して深掘りをしていくと、ユーザーが“何をどのように困っているのか”というインサイトが徐々に浮かび上がります。電通流でも「データを集めるだけでなく、その背景にある人間の心理や本音を想像力で補う」プロセスを重視しています。ここが単なるデータドリブンだけでは生み出せないクリエイティブの源泉なのです。

②「Not→But→Therefore」でズラして生み出す新しい視点
本書の中でも繰り返し強調されるテクニックが、「Not→But→Therefore」というリフレーミング手法です。これは、従来の常識や固定観念を一度「Not」で否定的に捉えなおすことで、「But」で違う切り口を提示し、「Therefore」で全く新しい発想へと展開していくステップ。
具体例を挙げると:
- Not:「評価制度の見直しは、膨大なミーティングと紙書類が付きもの」
- But:「そもそも上司が社員を評価する体制自体が古いのではないか」
- Therefore:「AIが日報やチャットログを自動解析し、客観的指標で評価ポイントを可視化する仕組みを作ろう」
このように、一見“当たり前”とされている要素に敢えて疑問符をつけることで、普通なら出てこないコンセプトの芽を発見できます。
広告の世界では、たとえば化粧品なら
- Not:女性向け
- But:実は男性も使いたい
- Therefore:男女共用を売りにした新ブランド
という例も。プロダクト開発においても、うまく“否定”を仕掛けると、差別化された製品アイデアが生まれやすくなります。
③ SCAMPERによるアイデア拡散と“とがらせ”の実践
本書の中には、広告キャンペーンや商品のコンセプトづくりで活用できる発想法として「SCAMPER」的な手法が紹介されています。SCAMPERは、Substitute / Combine / Adapt / Modify / Put to another use / Eliminate / Reverseという7つの観点でアイデアを変形・再構築する手法。これをプロダクト開発に置き換えると、たとえば:
- Substitute:現在のUIをチャット形式に置き換えたらどうなるか?
- Combine:既存のダッシュボードとSNS投稿機能を組み合わせたら?
- Adapt:他社が成功している○○の仕組みを、自社の教育サポート機能に応用できないか?
- Modify:週単位のレポートをリアルタイム更新に拡大/縮小したら?
- Put to another use:候補者管理システムを、人材育成データベースとして流用できないか?
- Eliminate:導入時の設定項目を一切なくして、ワンクリックでスタートできるようにしたら?
- Reverse:通常は社員がデータを入力するが、逆に会社側が先にデータを提供して社員がチェックする形式に変えたらどうか?
こうした観点で既存のアイデアを“とがらせ”ていくと、「確かにそれは面白い」と思える斬新なアイデアが見つかることが多いです。広告の世界でも、競合商品との違いを出すためによく使われる手法ですが、プロダクトでも差別化や顧客体験の発明に直結します。
④「ペルソナ・リサーチシート」で狙うべき感情を明確化
広告プランナーは、ターゲットを“抽象的に”ではなく“生身の人”として描くのが得意です。本書でも「ペルソナ・リサーチシート」の作り方が具体的に触れられています。これはプロダクト開発におけるペルソナ設計と共通点が多く、以下のような項目を詳しく記入していきます。
- 性別、年齢、職業、家族構成
- 日常のルーティンや趣味、利用しているサービス一覧
- 価値観や人生観、ストレスや願望
- よく使うSNSやメディア、行動パターン
電通的な考え方としては、「ターゲットが普段どんな小さな悩みを抱えているか」や、「どんなシチュエーションでどんな感情が芽生えるか」といった、定量データでは捉えにくい部分の想像を重視します。“ペルソナ”だけで終わらない。ジョブ理論(JTBD)と掛け合わせる方法にも記載しましたが、ペルソナに深いストーリーを盛り込むほど、チームが「この人のために作っている」という実感を得やすくなる。これがコンセプトの魅力づくりには不可欠です。
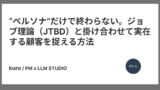
⑤「コピーライティング形式」でコンセプトを短文化する
広告の世界では、アイデアの中核を「キャッチコピー」に落とし込んでみるというプロセスを挟む場合が多いです。理由は簡単で、長々と説明しないと伝わらないアイデアは、人々の心を一瞬で掴めないから。プロダクトでも同じです。理想は「何ができるか」を聞かれたとき、10秒程度でパッとイメージさせられるかどうか。
たとえば人事系のHRテックなら「社員の離職予兆を、AIが自動で教えてくれるツール」といった一文で伝われば、相手は「なるほど、離職予防が主目的なんだな」とすぐに理解できます。PMがこのコピーライティング作業を行うと、チーム内の仕様検討でも「結局、離職予防に必要ないなら今は機能を追加しない」という判断が明確になります。逆に、「コピーがぼやけている」「何を提供するのかパッと伝わらない」という段階では、まだコンセプトが十分に固まっていない証拠といえます。
⑥「カスタマージャーニー連動」で“いつ・どこで”コンセプトが効くか検証する
本書では、コンセプトを考え出したら次に「実際に顧客が体験する流れ(ジャーニー)の中でどのように効いていくのか」を検証する大切さが強調されています。広告でいえばCMや店頭プロモーション、SNS拡散など様々な接点ごとにコンセプトがどう訴求するかをシミュレーションします。プロダクト開発においても、ユーザーがサービスを導入・利用するフェーズ、アップセル・リニューアルの段階などを時系列で見ながら「このコンセプトが優位に働く場面はいつか」をチェックしていくと良いです。
例えばBtoBサービスの場合、最初は担当者レベルの導入検討ですが、その後社内稟議で経営層が意思決定をします。その際、「離職予防に効きそうだ」と思ってもらえるコピーやデモ画面があるのかどうかが大きく影響します。ここでコンセプトが曖昧だと、担当者は経営陣に“買う理由”を説明しづらくなり、導入が立ち消えになるリスクが高まります。逆に、しっかり「こういう世界観で社員フォローを実現できる」と明示できれば、社内の意思決定が通りやすくなるわけです。
電通流の具体ワークショップ:コンセプト検証の実践手順
本書の後半には、複数メンバーでアイデアを出し合い、ブラッシュアップするワークショップの進め方が紹介されています。これはプロダクト開発でもそのまま応用できるため、簡単に手順をまとめます。
STEP 1:準備とファクト共有
まずは前述の「事実収集」で得たデータやユーザーインタビューのインサイトを、ファシリテーター役の人が資料にまとめ、参加者全員に共有します。
STEP 2:発想フレームの設定
たとえば「Not→But→Therefore」を使うと決めたら、ホワイトボードや付箋などを使いながら、チームで“Not”の洗い出しを行う。「何が従来の常識で、ここを疑ってみると面白そうか?」という問いを投げかけ、全員で意見を書き出します。
STEP 3:アイデア発散→収束
SCAMPERの各要素を順に当てはめてブレストするのも良いでしょう。たとえば「Substitute(置き換える)」で2分、「Combine(組み合わせる)」で2分、という具合に時間を区切ってアイデアを書き込む。ある程度数が出揃ったら、参加者が「面白い!」と思うものに投票して上位を絞り込みます。
STEP 4:コピーライティングで微調整
収束したアイデアを「一行キャッチコピー」で表現してみて、再度フィードバックを受けます。ここで「こんな言い方のほうがユーザーに伝わるのでは?」と議論が盛り上がり、アイデアがより洗練されるケースが多いです。
STEP 5:カスタマージャーニー連動の確認
決まったコンセプトを、ユーザーの利用ステップでどこに当てはめるか(導入前の説明資料やサービス内オンボーディングなど)をチームで確認します。ここで具体的なプロトタイプやデザインモックがあるとイメージしやすいです。プロダクトの場合は、プロトタイプ+ユーザーインタビューを実施し、実際の手応えを探るフェーズへ。

ユーザーインタビューとの組み合わせがコンセプトを強化する
電通流の発想法は、あくまでアイデアを生み出すためのフレームワークです。しかし、現実にはアイデアが「本当にユーザーに響くかどうか」を確かめなければ意味がありません。そこで、ユーザーインタビューやユーザーテストを合わせて実施し、コンセプトを検証する流れが効果的です。
例えば、キャッチコピーの仮案を用意し、ユーザーに以下のように聞いてみましょう。
- 「これを見てどんな印象を持ちますか?」
- 「自社の課題とマッチしていそうですか?」
※厳密には、こちらの記事にあるようによりファクトを集められる聞き方をする必要があります

その反応をもとに「インパクトが弱い」「焦点がズレている」といったフィードバックを得られれば、再度ワークショップで「Not→But→Therefore」にかけ直す。こうした小回りの利く修正サイクルが、コンセプト精度を飛躍的に高めます。
僕はBtoBユーザーインタビューをやる際に、プロトタイプと一緒にPRリリースやダミーのコピーを提示することをよくやります。テキストベースで「こんな世界を実現するツールです」と伝えてみると、ユーザーの脳内にイメージしやすいからです。もしピンとこない反応なら、「どうすれば伝わりそうか」を組み替え直します。

AIを活用したコンセプト制作の:電通流×LLM
本書が書かれた当時はまだ大規模言語モデル(LLM)のような高度なAIは普及していませんでしたが、現代のPdMにとってはコンセプト制作でもAIが大いに活躍します。たとえば……..
- ユーザーインタビューの要約やキーワード抽出をAIに任せて、分析を爆速にする
- 広告コピーの試案をAIに複数生成させ、チームで良いものを選びブラッシュアップ
- SCAMPERや「Not→But→Therefore」のフレームをAIに説明し、アイデア拡散の下準備をサポートしてもらう

ただ、AIが出してくる文案は過去データの集積に基づく“無難な”提案になりやすい面があります。そこで、電通の発想法が強調する「違和感を作る」「常識をズラす」「ユーザーの深い欲求に訴える」発想は人間ならではの力が必要です。要は「AI+人間のクリエイティビティ」のハイブリッドアプローチが理想的。AIを補助にしながら大胆な方向性を探ると、独創性とスピードが両立しやすいと感じています。
参考情報
・電通 (2003) 『コンセプトのつくり方 たとえば商品開発にも役立つ電通の発想法』
・Osborn, A. F. (1953) Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem-Solving.
・Harvard Business Review (2021) “The Key to Creative Innovation” Harvard Business Review, 99(4).
・当サイト関連記事:競争優位を築く「プロダクト全体や新機能のコンセプト」のつくり方
・当サイト関連記事:プロトタイプを使って、ユーザーインタビューで新機能の検証を行う方法・Tips
・当サイト関連記事:BtoB領域のユーザーインタビューの難しさや実施方法を解説
・当サイト関連記事:ChatGPTでユーザーインタビューの分析を爆速にする具体手法を解説
今日から実践できるアクション
1. 「Not→But→Therefore」で現状の常識を疑うリストを作る
チームで“当たり前”と考えている前提を洗い出し、それを「Not」してみる。そして「But」「Therefore」で新たな切り口を複数考える。ブレストの時間を30分でも設けるだけで、意外なアイデアが出てくる可能性が高い。
2. SCAMPERブレストを定例化し、アイデアを量産
週次または隔週でチームが集まり、SCAMPERの7要素を順番に当てはめてアイデアを出し合う。初めは質より量を意識し、無理にまとめず自由に発散する。後で集約しながら「コンセプト候補」を数本に絞り込む。
3. 新しいコンセプトを10文字前後のコピーに落とし込む
「文章を削ぎ落として10文字程度で表現する」という課題を自分に課してみる。たとえば「社員の変化をAIが先回りで通知」。もし言葉が冗長なら、まだ要点が絞り切れていない証拠となる。
Q&A
Q1: コンセプトづくりに時間をかけすぎると、開発が遅れませんか?
A1: 一見遠回りに思えますが、明確なコンセプトがないまま開発を始め、後から大幅な方向転換を迫られるほうがリスクは高いです。コンセプトを短期集中で固めておくと、不要機能をバッサリ排除できたり、チーム合意が早まるメリットがあるため、結果的にスピード向上に繋がるケースが多いです。
Q2: SCAMPERやNot→But→Thereforeをやっても、ありきたりなアイデアしか出ません。どうすればよいでしょうか?
A2: まずは徹底的な事実収集とユーザーインサイトの掘り下げが不足しているかもしれません。あまりに素材が少ないと、同じ思考の中で堂々巡りになりがちです。また、あえて“極端な仮説”を立ててみたり、“破壊的な逆張り”を意図的に入れたりすると、発想が広がる可能性があります。
Q3: コンセプトが固まらないままユーザーインタビューをしてもいいですか?
A3: むしろ大いにアリです。プロトタイプや仮コピーを用意して反応を伺うと、ユーザー側の本音やペインポイントを具体的に把握できます。その気づきを再度コンセプトに反映することで、より精度の高いアイデアに仕上がります。
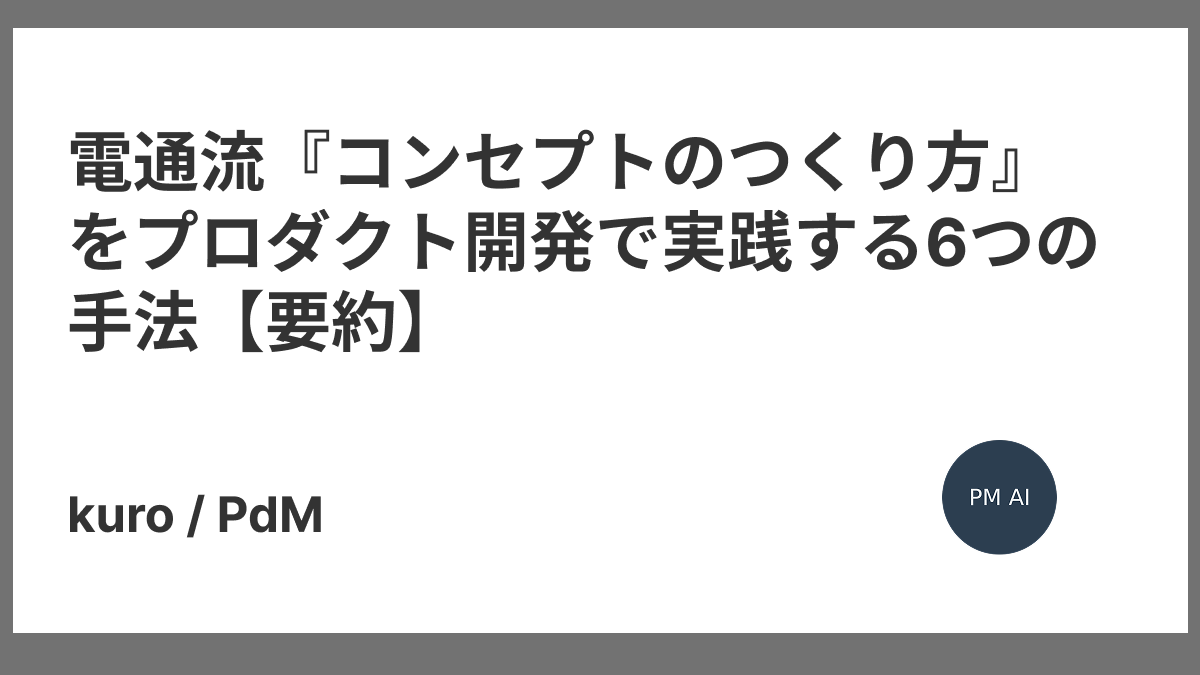



コメント