「顧客をどれだけ深く理解できるか」は事業成長の土台。
その「深い顧客理解」の重要性や実践方法をよく理解できる一冊が、西口一希氏の著書『たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング』(MarkeZine BOOKS)。
本記事では、この書籍をプロダクトマネージャーの観点から要約しながら、N1分析(一人の顧客事例を徹底分析する)を日々の開発やロードマップ策定にどう活かすかを解説します。
『たった一人の分析から事業は成長する』とは?
西口一希氏による本書は、タイトル通り「たった一人の分析」きっかけで顧客起点のマーケティングを動かし、大きな成長へ繋げる具体例を多数紹介されています。
著者はマーケティングの現場でデータ分析や顧客視点のアプローチを地道に進めることで、企業の意思決定が劇的に変わる瞬間を何度も見てきたそうです。
そこに共通するのが、「顧客を抽象的な平均値や数値で見るだけでなく、たった一人の顧客を丁寧に分析する」という発想。
プロダクトマネージャーとしても、「顧客起点で事業を伸ばす」という視点は極めて重要。しかし現実には、社内都合や既存プロセスに引っ張られ、ユーザーインタビューやデータを活かしきれないことが多いのではないでしょうか?
そこで“N1分析”がカギになるのです。あえてたった一人の顧客にフォーカスすることで、その人が置かれているリアルな状況から施策の優先度や開発の方向性を導き出すことが可能になります。
N1分析とは? ―「たった一人」が全体を変える要点
本書の肝となるのが「N1分析」という手法。
N1とは「サンプル数1」という意味で、統計的に有意な多数データではなく、たった一人の具体的な顧客(ユーザー)を深く掘り下げるアプローチを指します。
僕も感覚があるのですが、量的データだけを追っていると、どうしても平均像や大雑把な傾向に流されてしまいます(データの追い込みはもちろんやる前提で)。しかし、平均からは見えない“本当のニーズ”や“行動背景”が、一人の事例から浮かび上がることがあると著者は語ります。
それを起点に施策を組むと、顧客を“人間”として理解しているぶん、刺さる施策になりやすいと本書は強調します。
プロダクトマネージャーの立場でも、ユーザーインタビューで一人の使い方を徹底解剖する行為はこれに近いです。
たとえばBtoBの現場担当者Aさんの一日を時系列で追い、そこにプロダクトがどう関わっているかを詳細にヒアリング。その結果、「実は朝イチでデータ集計を急ぐ必要があり、今の画面では3ステップ余計にかかるから敬遠していた」と判明するなど、定量データの平均値を見るだけでは気づけないインサイトが得られる。
この“たった一人の深い分析”こそが本書の主題であり、顧客起点マーケティングの原動力となるわけです。
N1分析の具体手法:一人の顧客をどのように深掘りし、仮説化するか
本書ではN1分析を単なる“個別事例の観察”ではなく、「明確なステップを踏んで仮説を導き、施策に繋げるプロセス」として位置づけています。主な流れは以下の通りです。
①対象顧客を選ぶ
定量データや周囲の評判などをもとに、課題が明確に現れていそうな一人をピックアップします。
ここで重要なのは
- “問題が典型的に表面化しているユーザー”
- “継続率の高いエバンジェリスト”
など、分析結果が意義深い可能性が高い顧客を選ぶことです。
たとえば離脱率が高いサービスなら、実際に離脱予備軍っぽいユーザーを意図的に探すなどが有効です。つまり、その時々で最も課題が大きい部分に該当する顧客を選びましょう。
この際に、本書で別途紹介されている、顧客を9つのセグメントに分ける「9セグマップ」を活用しその中のロイヤル顧客に話を聞くなども有効です

どうしても最初から1人に選べない、なら10人程度インタビューしたその中で一番PdMが想定する課題を強く持っている人に2回目、3回目のインタビューをお願いしたりエスノグラフィー調査を依頼してみましょう。
②背景情報を収集
ネクストステップは実際にその人の生活パターン、利用状況、業務フローなどを多角的に把握するリサーチです。
可能ならその人のログや過去の発注・問い合わせ履歴などのデータも確認します。ここでのポイントは「本人へのインタビュー」だけでなく、社内の営業やカスタマーサクセス、ヘルプデスクからの顧客エピソードを引き出し、できるだけ豊かな背景情報を揃える点です。つまり、「N1の周辺」を徹底的に掘るのです。
先ほども少し触れましたが、このときに徹底的にやるなら純粋なインタビューだけではなく、顧客の生活に入り込む「エスノグラフィー調査」をしてみるのもおすすめです。

③行動・心理を深掘り
インタビューやエスノグラフィー調査の中で、
- なぜその操作をするのか?
- どのタイミングで困っているのか?
- どんな代替手段を使っているのか?
などを徹底的に聞き出します。
具体的には「そのボタンを押すとき、何を考えていた?」とか「もしその機能がなければ、どうやって対処していた?」などの突っ込んだ質問が重要。
ここで怠ると単なるアンケート回答に終わり、核心にたどり着けないまま平均論に埋没しがちです。
質問はこちらの記事を参考にしてください。

④痛みや欲求を仮説化
具体的に「〇〇の時に△△が面倒」「このUIが直感的でないため、別作業に逃げる」といった形で明文化します。
著者はこのステップを特に重視し、たとえばユーザー本人の心理を推測しながら“ペインポイント”や“ジョブ理論的な欲求”を言語化する手法を紹介しています。ここできちんと文章化しておくと、チーム内で共有しやすくなる点も大きいです。
⑤プロトタイプや施策を考える:
仮説ベースで「この部分をUI変更」「このタイミングで通知を送る」など具体案を練ります。
多くの現場でありがちなのは、ここで無数のアイデアが出すぎて混乱すること。しかしN1分析によって“この人ならどう使う?”が明確なため、アイデア同士の比較がしやすくなっているはずです。
プロダクトマネージャー視点では、プロトタイプを通した検証が相性抜群です。

⑥検証と拡張
その一人への改善が他の顧客にも当てはまるか、定量データや他のインタビュー事例で確認し、本格実装へ広げるステップです。
“N1→N50→N10,000”のように、最初は一人から始めても、徐々にセグメント全体や組織全体の施策にスケールアップするイメージです。
ここで追加のA/Bテストやベータユーザー募集を行い、最終的にロードマップで正式リリースを決める流れになるとスムーズです。
著者が強調するのは、「N1分析をやっただけで満足しては意味がなく、段階的に検証しスケールさせること」です。
「たった一人だけしか使わない機能では?」という声への対処として、検証フェーズで定量データとあわせて他のユーザーにも適用できるかを見極める。この“組織を動かすための段階設計”が本書の特徴的なポイントといえます。
PMの立場では、スプリント内で少数ユーザーに試して反応を見る→次スプリントで改善というアジャイルな流れにうまくはめ込むと、高速に仮説検証が回せると感じます。
N1分析 + ストーリーテリング + 定量で組織を動かす
難しいことに、現実のプロダクトマネジメントではたった一人の事例だけを振りかざしても、「それは特殊なケースでは?」という疑問が出やすいです。そこで、「一人の事例」に定量データを掛け合わせるアプローチが実際には必要になると思います。
具体的には、ストーリー+数字をセットで社内プレゼンする。たとえばユーザーAさんのエピソードを共有し、「ログ分析でも同様の操作離脱が70%確認された」と示す。こうすると上層部や他部門の納得を得やすいですよね。
“一人の分析”は超絶重要で、ここから始めることを僕はすごく大切にしています。ただし、あくまで始点なことにも注意。そこから他の顧客にも適用可能かをデータで確かめ、共通のペインであれば施策を広げる。
こうしたプロセスを回せば、「N1分析はマイノリティに振り回されるリスクが高いんじゃないか」という懸念を払拭可能です。
こういった取り組みがうまく回っていくと、その結果、組織全体が「顧客起点で考えなければ」という空気に変わっていきます。
今日から実践できるアクション
- N1分析専用インタビューを設計する
通常のユーザーインタビューに加え、“一人のユーザーを徹底的に掘り下げる回”を設定。
生活背景やビジネスの流れ、使い方の微妙なコツまでじっくり聞く。 - 施策や機能案を「N1由来」としてロードマップに記載
「この機能は顧客Aさんが抱える○○課題に対応」と、具体的に記しておく。
そうすれば社内で「本当にニーズある?」と聞かれたとき、根拠が一瞬で説明できる。 - データ裏付けでN1分析を補強
一人の声だけでなく、ログ分析やユーザーセグメントの定量データを合わせて「同様のパターンが他にも多数」と示す。
説得力がぐんと増す。 - 組織的にN1分析を共有する場を作る
週次や月次のミーティングで、誰か一人の顧客事例を取り上げてディスカッション。
初めは小規模でも成功事例が出れば、社内全体が顧客起点思考に動きやすい。
Q&A
- Q1. BtoBプロダクトでもN1分析は通用しますか?
- A. むしろBtoBこそ有効です。導入担当者・現場ユーザー・決裁者など複数ステークホルダーがいる場合、具体的に一人を深く知ることで全体像が見えてくる。
その事例を他の担当者にも当てはめ、類似の課題を確認することで、施策の汎用性を判断できます。 - Q2. 「たった一人」だけに振り回されるリスクはありませんか?
- A. 最終的には定量データや複数事例で裏付けるステップが必要です。
ただ最初のきっかけとして“マイノリティかもしれない一人”を深掘りすると、意外な共通の悩みが分かることが多いです。 - Q3. 組織的にトップダウンが強く、顧客起点の提案が通りにくいです。
- A. 「一人の事例 × データ」のストーリーテリングが有効。
具体的な顧客の生の声と数字をセットで示すと、トップも「確かにこれは無視できない」と感じやすくなります。
小さな成功体験を積み重ねるのが現実的なアプローチです。
参考情報
- 西口一希『たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング』(MarkeZine BOOKS)
- Eric Ries『The Lean Startup』(2011)
- 安宅和人『イシューからはじめよ』(ダイヤモンド社, 2010)
- Jakob Nielsen & Thomas K. Landauer (1993). “A Mathematical Model of the Finding of Usability Problems.” Proceedings of ACM INTERCHI’93
- ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド
- ユーザーインタビュー前に「筋の良い仮説」をチームで設定する具体的な方法やフレーム
- プロトタイプを使って、ユーザーインタビューで新機能の検証を行う方法・Tips
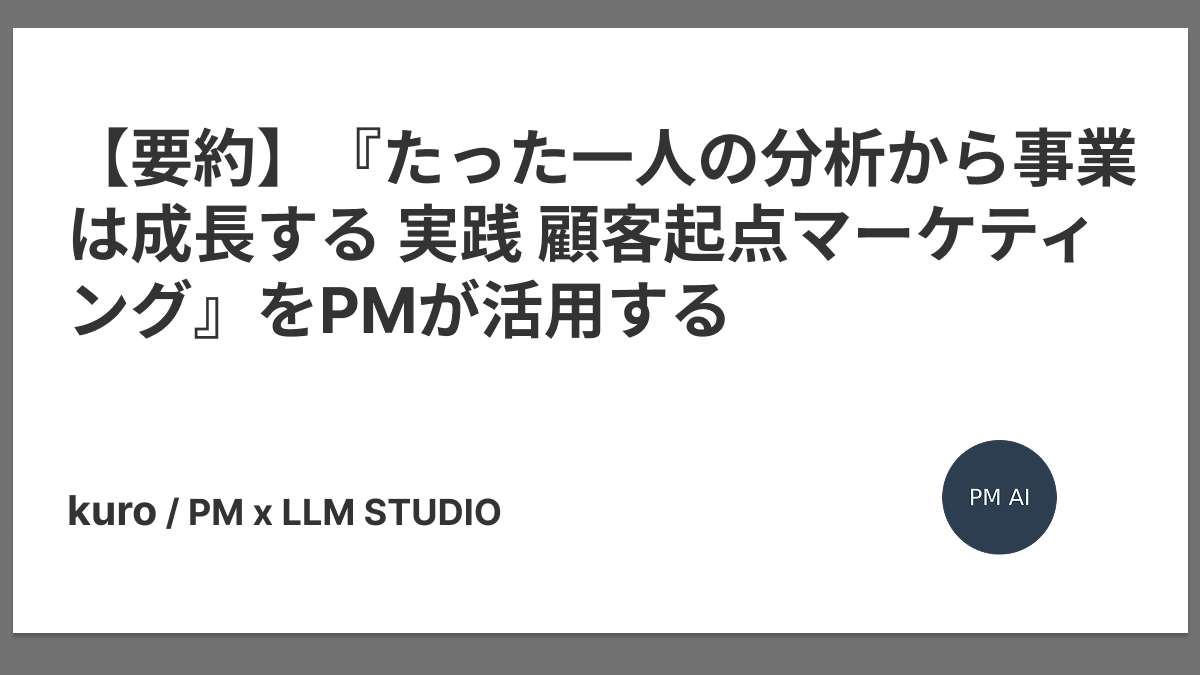



コメント