- プロダクトマネージャーは人事権なき責任者として、批判せず相手の立場を理解し、自己重要感を満たすことでチームを動かす必要がある
- 誤りを指摘する代わりに質問で気づかせ、相手のアイデアを尊重しながら自分の提案を「Yes, and」で積み上げることが効果的
- ステークホルダーごとに異なる動機(エンジニアは技術的挑戦、経営層はビジネス成果)を理解し、それぞれに響く伝え方をすることが成功の鍵
プロダクトマネージャーこそ知っておきたい『人を動かす』
『人を動かす』(原題:How to Win Friends & Influence People、著:デール・カーネギー)は、対人関係やコミュニケーションにおける永遠の名著。ビジネスパーソンであれば一度は耳にしたことがあるかもしれません。
この本が伝えるのは、単に“相手を操作する技術”ではなく、“誠実さと共感”を礎にした人間関係のつくり方。ビジネスシーンのみならず、あらゆる人間関係で応用できる原則が詰まっています。
僕はプロダクトマネージャーとして複数のステークホルダーを巻き込む日々を過ごしています。エンジニア、デザイナー、セールス、マーケ、そして経営層。みんな忙しく、それぞれ違う視点や目標を抱えていますよね。その中で、チームとしての方向性をまとめ、成果へ導くには、“誠実に、自分以外の人をいかに動かすか”というリーダーシップやコミュニケーション力が欠かせないと考えていて、まさに「人を動かす」で説かれるエッセンスが求められる局面が多いと感じています(日々勉強中)。
本記事では「人を動かす」の重要な要点をピックアップし、主にプロダクトマネージャーが実務で活用するための視点を加えて解説します。
「人を動かす」三原則が示す根本的な態度
デール・カーネギーは“人間心理を理解すること”の重要性を何度も説いています。
特に有名なのが、
- 批判・非難・苦情を絶対にしない
- 誠実な評価を与える
- 相手の欲求を喚起する
という三原則。
例えば、プロダクトマネージャーがエンジニアに機能改善を依頼する際、進捗が芳しくないときに頭ごなしに「なぜできないのか?」と詰め寄るのは逆効果ですよね(そこまで直接的に悪い言い方をする人はまずいないですが)。相手を批判するよりも、まずは事情を丁寧にヒアリングし、問題の背景を知る姿勢が大切です。
人は自分の置かれた状況や気持ちを理解してもらうと、それだけで前向きになりやすいもの。カーネギーはこの“相手の心情や欲求を尊重する”姿勢こそ、人間関係の土台としています。
特にプロダクトマネージャーは、エンジニアリングやデザインなど多方面の課題だけでなく、メンバーのモチベーションや負荷を理解したうえで合意形成を進める力が求められます。それこそが信頼につながり、最終的には「人を動かす」原動力になる、と僕は考えています。
「好かれる六原則」とチームビルディング
「人を動かす」では、相手に好かれるための六原則として、
- 誠実な関心を寄せる
- 笑顔で接する
- 名前を覚える
- 相手の話をよく聴く
- 相手が関心を持つ話題を話す
- 心からほめる
というポイントを挙げています。
例えば、開発チームのミーティングに参加するとき、誠実な関心を示す姿勢はただ「仕事の話」だけをするのではないと思います。相手が何を考え、どの技術領域に興味があり、どんなキャリアビジョンを持っているのか。それを理解するために雑談や小さな質問を交えつつ積極的に聴くことが大事です(個人的には飲みニケーションやランチコミュニケーションはこれに近い部分があると思っています)。
※あんまり意識高すぎる話は惹かれるので避けましょう
たとえ1分でも真剣に相手の話に耳を傾け、「それ面白いっすね!」「xxxはどうなんですか???」と興味を持つだけで、コミュニケーションの深度は上がります。
名前の扱いも重要。これはユーザーインタビューでも同様です。相手の名前をきちんと呼ぶだけで、そこには自然と親近感が生まれます(録画中に個人名呼ばないとか個人情報には配慮してください)。僕はこれまで累計700人以上のユーザーインタビューを実施してきましたが、まず最初に相手が何に興味を持ち、今どんなことに挑戦しているのかを積極的に聴く姿勢を徹底しています。いきなり本題ばかりぶち込まない、ということです。そこから関心を示せば、対話の流れがスムーズになり、より深いインサイトが得られるのです。
「人を説得する十二原則」が示すリーダーシップの核心
カーネギーは、人を説得するための具体的な十二原則も紹介しています。その中で、
- 議論に勝とうとしない
- 誤りを指摘するよりも遠回しに気づかせる
- 自分の過ちを率先して認める
といったアプローチは、プロダクトマネージャーとしてチームを牽引する上でも必須だと考えています。
たとえば、要件定義の場で意見対立が起きたとき、勝ち負けにフォーカスしてしまうと、相手のプライドを傷つけるリスクが高まる。結果的に関係性が悪化し、今後の協力体制まで崩れかねません。
また、自分に非があると感じたら率直に認める姿勢は、チームからの信頼獲得につながります。「僕の設計見通しが甘かったです。時間をムダにさせて申し訳ない」と素直に言うだけで、相手も受け入れやすい状態になります。そしてそこから「どのように修正していくか」を建設的に議論できる。人は、責められると防御姿勢を取りますが、こちらがまず誠実に非を認めると一気に心が開くという現象があります。
プロダクトマネージャーが活用するための具体例
では、この「人を動かす」の原則をプロダクトマネージャーとしてどう実務に活かすか?具体例をいくつか挙げます。
まずはチームメンバーへの目標共有の場面。PdMがリードして、新機能のOKRやKPIを設定することが多いと思いますが、このとき大切なのは、相手のモチベーションを引き出すという視点です。ただ「これが目標です」と押し付けても、人は自発的に動きませんよね。
そこで、
- 「チームとしてこの目標を達成する過程でこんなスキルが身につく」
- 「市場での評価が高まり、あなたのポートフォリオにもプラスになる」
といった形で、相手自身のメリットを明確に伝える。
そして、進捗状況を共有するときは、なるべくポジティブな評価を交えながら次のステップを提案する。「◯◯の実装、スムーズに進んでてめちゃ素晴らしいっすね!ユーザーインタビューのフィードバックをぜひ活かしてみたいんですが、一緒に試行錯誤しませんか?」といった感じです。経営層・上司・メンバーを動かすユーザーインタビュー結果の見せ方・使い方でも書いていますが、相手に価値を感じてもらう形で情報を提供する工夫が効果的です。

また、顧客との折衝の場面も同様。
機能要望が多岐にわたるとき、そのすべてを受け止めるのではなく、相手の深い欲求を理解するためにまずは聞き役に徹するのが原則。時にユーザーの要求を否定しなくてはいけないケースでも、カーネギーの原則に倣い「否定から入らない」ようにする。「そのご意見、他のユーザーさんも実は似たものを求めているんです。ニーズが高まっているので、ぜひ優先度を検討させてください」と、共感の姿勢を示したうえで、開発リソースや優先度をどう考えるかを一緒に擦り合わせる。これだけでも相手は自分の声が尊重されたと感じ、前向きに折り合いをつけやすくなります。
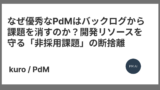
この、営業やCS、顧客から直接要望をもらったときのPdMの一言目の返ってすごく大切だと思っていて、細かい話なんですが一言目から「できない理由」を論理的に話すと相手が絶望するか憤慨します。そうではなく、
- 「ありがとうございます。そうやって意見もらえるの、PdMとしてはめっちゃありがたいです!」(心からの大感謝)
- 「ただすみません、優先度判断の中で今のご要望はxxxxという理由で最優先にはなっていないのです」(相対論で今できない理由を伝える)
- 「代わりに、いただいた要望の背景にある問題や実態をお伺いすることは可能でしょうか?検討中の別機能や運用・サポートで解決する可能性があるので。」(代替策の検討を提示する)
といった形で返答をすると次からも意見をもらいやすくなります。
「批判しない」ことの効果とリスクマネジメント
さらに、カーネギーの原則の中でも特に有名なのが、「決して人を批判しない」です。PdM間や他職種がミスを犯したときや、ビジネス上の損失が出たときに、まったく批判しないのは現実的ではないと思う方もいるはずです。しかし、「批判」は表面上厳しさを示しているように見えて、実は相手を委縮させ、問題解決から遠ざける恐れがあるアクションです。
自分自身で考えてみると、ミスを責められるより、
- 良い挑戦だったね!
- その意図は何だったの?
- どうすれば次はうまくいくかな?
という前向きな姿勢で接してもらえると心が開きやすい気がします。組織としても建設的に改善策を生み出すことができます。
ただし、これを「問題に目をつぶる」という意味でとらえるのは誤解です。事実を冷静に共有し、改善策を探るプロセスは必要。ただしそこに「お前が悪い」といった人格否定や、相手の行動を過度に責めるニュアンスを混ぜ込まないようにするだけで、チームの学習速度は上がります。
「心からほめる」文化を根付かせる仕組み
また、カーネギーは「人を動かす」上で、心からの称賛や感謝を惜しまないことを強調しています。プロダクトマネージャーとして、ほめる文化をチーム内に根付かせるのは非常に有効。なぜなら、PdMは結果に責任を持つ立場でありながら、実際の開発やデザインを行うのはメンバーだからです。メンバーが自分の仕事の価値を実感できるほど、主体的に動くモチベーションが高まります。
余談ですが、僕の大学のゼミの先生がこの「褒める」がめっちゃくちゃに上手かったのでコツを聞きにゼミ室にいった記憶があります。
一方で、毎日ただ「素晴らしいですね」と言い続けるだけでは表面的になりがち。そこで、「心からほめる」をチームのカルチャーにするには、具体的なエピソードに基づく称賛が重要。「あのユーザーインタビューの分析をスピーディにまとめてくれたおかげで、経営層の納得が早かった。すごく助かったよ。ありがとう」といった形で、どの行動がどんな成果やメリットにつながったのかまでセットで伝える。この詳細なフィードバックは誠実な評価を感じさせ、相手も「ここが評価されたのか」と理解できるため再現性が高まります。
これは僕も苦手なんですが、褒めすぎるくらい人を褒めていきましょう。
PdMは、プロダクトだけではなく人間の心の動きもデザインしなければならない職種
「人を動かす」に書かれている内容は、最新の心理学や行動経済学の知見とも多くの共通点があります。たとえば、ロバート・チャルディーニの『影響力の武器』で言及されている返報性の原理、コミットメントと一貫性などは「心からほめる」や「相手に貢献する姿勢を先に示す」といったカーネギーの教えと合致します。
また、心理学の分野では“積極的傾聴”や“ポジティブフィードバック”が人間関係におけるモチベーション維持に大きな影響を与えることが実証されています[1]。
プロダクトマネージャーは、プロダクトだけではなく人間の心の動きもデザインしなければならない職種です。テクノロジーがいくら進化しても、最後は人と人とのコミュニケーションがボトルネックになることがあります。
- エンジニアやデザイナーがスムーズに動けるように環境を整える
- 経営層には意思決定しやすい情報を提示する
- セールスには顧客理解を深める材料を提供する
これらはすべて、相手が動きやすいように心理的負荷を下げ、意欲を高める行為でもあります。そこにカーネギー流の“共感と称賛”“相手の欲求を理解する”態度を組み合わせることで、より強いリーダーシップを発揮できます。
僕も記事を書いていて改めて心に強く刻もうと思いました。
コラボレーションの成否は、相手を尊重し、共感し、動機付けするコミュニケーションができるかどうかに大きく左右されます。カーネギーの方法論は表面的なテクニックに見えるかもしれませんが、実践すればするほど“土台にある他者へのリスペクト”の大切さを再確認させてくれます。PMが持つべき“人間力”の磨き方を探している方にとって、本書の要点は確実に示唆となるはずです。
参考情報
・Dale Carnegie (1936) How to Win Friends & Influence People, Simon & Schuster
・ロバート・B・チャルディーニ (1984) 『影響力の武器』 日経BP社
・[1] Carl Rogers (1957) The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change, Journal of Consulting Psychology, 21, 95-103.
・当サイト関連記事:経営層・上司・メンバーを動かすユーザーインタビュー結果の見せ方・使い方
・当サイト関連記事:ユーザーインタビュー前に「筋の良い仮説」をチームで設定する具体的な方法やフレーム
今日から実践できるアクション
1. 「褒めポイント」を具体的に言語化する
日々のチーム活動で、メンバーが助けてくれた場面や改善案を出してくれた瞬間に着目し、その具体的な行動と成果をセットで言語化してほめる。これを意識するだけでもチームの雰囲気が変わる。思っている3倍人を褒めましょう(自戒の念をこめて)
2. 否定から入らないコミュニケーション
相手の意見が自分と異なる場合でも、まずは「共感」や「理解」を示すフレーズを添える。すぐ否定せず、「なるほど、そう考えた理由は何ですか?」と一度受け止めることで、相手が防御モードになることを防ぐ。(自戒の念をこめて②!)
3. 1on1や雑談で相手の目標や悩みに関心を寄せる
チームメンバーや同僚との1on1では、仕事の進捗だけでなく相手のモチベーションやキャリアビジョンを聴く。「今後どんな技術に挑戦したいですか?」などの質問を投げることで、信頼関係が深まる。(自戒の念をこめて③!!)
Q&A
Q1: 「人を動かす」は古い本ですが、現代でも通用しますか?
A1: 通用する。むしろ人間の心理や本質は時代を超えて変わらない部分が大きい。テクノロジーが進歩しても、人と人との信頼関係やコミュニケーションの原則は本書が説く内容と重なる部分が多い。
Q2: 批判や指摘をまったくしないのは難しいです
A2: 批判をしないのは「問題を放置する」という意味ではない。人格否定や非難ではなく、事実を一緒に整理し、「次どうするか」を建設的に話し合う姿勢がポイント。改善策は伝えつつ、相手のプライドを傷つけない配慮が大切。
Q3: チーム全体でこの考え方を実践したい場合、まず何から始めればいい?
A3: まずはPdM自身が実践し、小さな成功体験を共有するのがおすすめ。例えばメンバーを前向きにほめたところ、モチベーションが上がった・進捗が良くなったなどのエピソードをチームに伝えると、自然と真似が広がる可能性が高い。
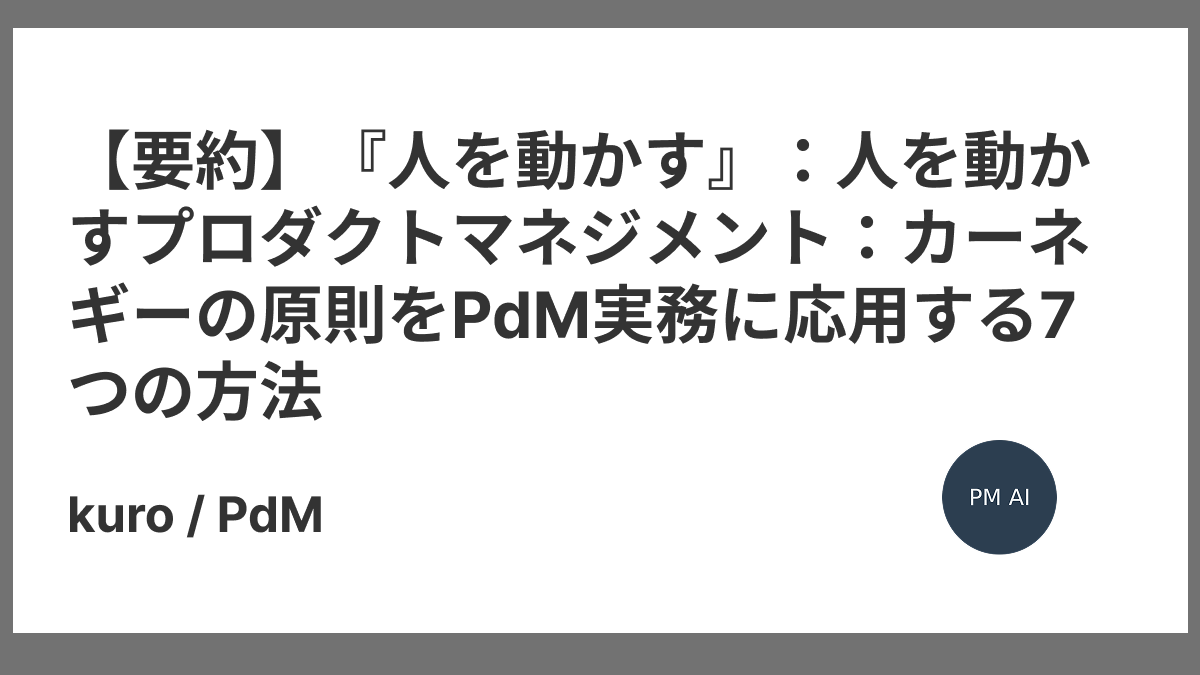


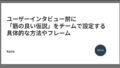
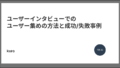
コメント