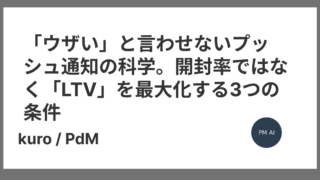 プロダクト企画
プロダクト企画 「ウザい」と言わせないプッシュ通知の科学。開封率ではなく「LTV」を最大化する3つの条件
この記事の要約 プッシュ通知はプロダクトとユーザーを繋ぐ最強の架け橋であると同時に、一歩間違えれば即座にアンインストールを招く「諸刃の剣」 「開封率」という虚栄の数字を追うのをやめ、ユーザーの文脈(コンテキスト)に寄り添った「Right T...
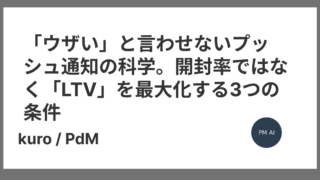 プロダクト企画
プロダクト企画 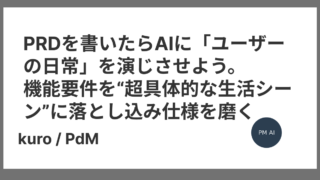 プロダクト企画
プロダクト企画 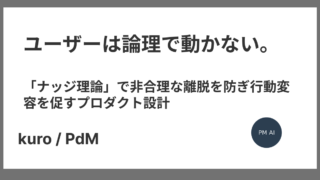 未分類
未分類 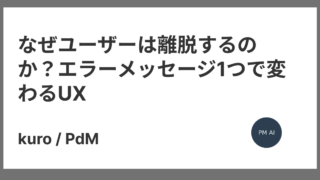 プロダクト企画
プロダクト企画 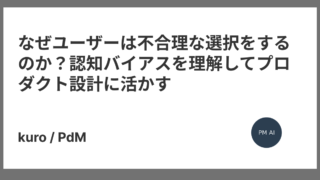 プロダクト企画
プロダクト企画 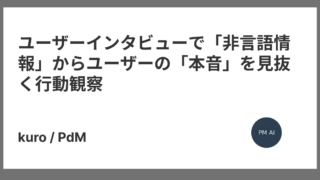 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 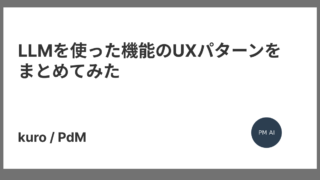 プロダクト企画
プロダクト企画 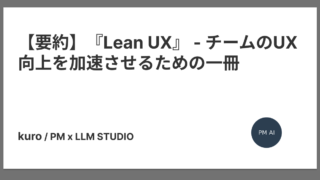 PM関連本
PM関連本 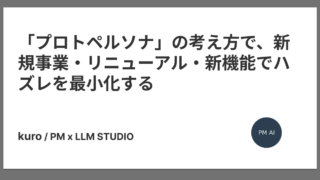 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 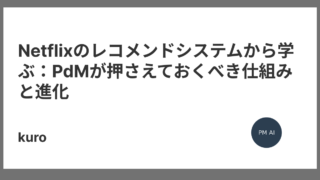 プロダクト企画
プロダクト企画 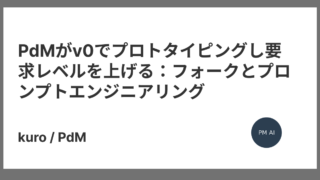 プロダクト企画
プロダクト企画 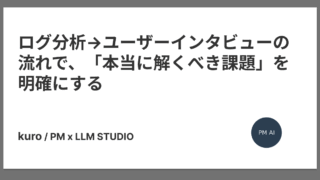 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 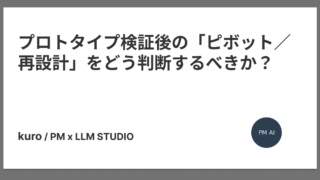 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 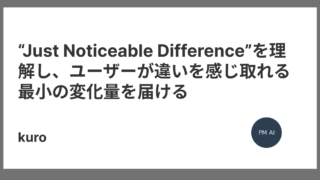 プロダクト企画
プロダクト企画 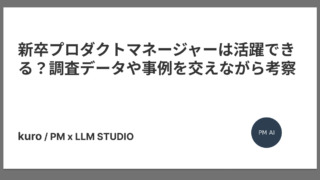 生成AI
生成AI 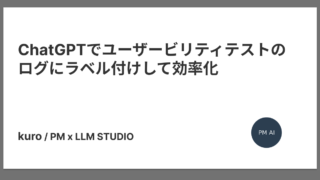 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 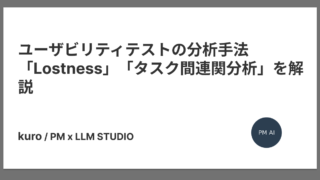 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 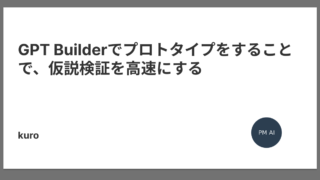 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 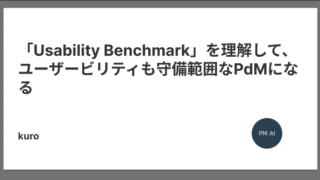 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 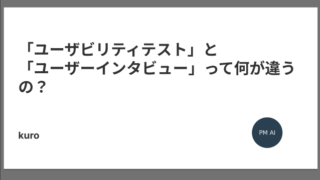 ユーザーリサーチ
ユーザーリサーチ 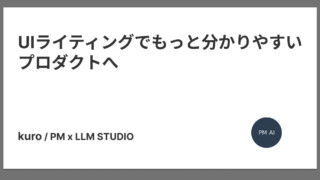 プロダクト企画
プロダクト企画