この記事の3行要約
- コンセプトの失敗は「実在しないペルソナ」と「あったら嬉しい程度の価値」が原因。Sean Ellis Testで40%以上が「なくなったら非常に困る」と答える必需品レベルを目指そう。
- ジョブ理論で機能的課題を解決しながら、誇らしさや解放感といった感情トリガーと、嫉妬や怠惰などのダークサイド心理を適切に組み合わせることで熱狂が生まれる
- 市場データの平均値ではなく異常値に着目し、尖ったユーザーに対する尖ったコンセプトを「血生臭い表現」で言語化することで差別化できる
「そのコンセプト、本当に刺さりますか?」
「プロダクトや新機能のコンセプトはある程度まとめたつもりなのに、ユーザーが想像ほど熱狂してくれない…」そんなもやもやを抱えていませんか?
実は、コンセプトを表面だけで固めると、「なんとなく良さそう」に見えても“化学反応”が起きにくいのです。本記事では、コンセプトの基礎を知っている方がさらに“枠を超えた共感と熱狂”を引き寄せる「ズバ抜けたコンセプト」にアップグレードするための7つのTipsを紹介します。
1 / “実在しないユーザー”を捨てる
「ペルソナは絵空事ではなく、実在する生身の人を象徴しているか?」
ここが曖昧だとコンセプトがふんわりします。
よくある落とし穴
「理想的なユーザー像」を取り繕っただけで、“実際のユーザー”の行動や思考が反映されていない。
具体策
-
- 名前・職業・年齢だけでなく、「普段どんなメディアを見て、どこにイライラし、どんな時にワクワクするのか?」を徹底的に聞き出す
- たとえ1人でもいいから「この人を絶対幸せにしたい」という生々しい存在を想定
- インタビューした中の実在する一人をペルソナとして設定する
期待効果
「誰を幸せにする/熱狂させるコンセプト?」という議論ができるので“実感”が宿り、“体重が乗った”コンセプトに仕立てることができます。

2 / “ないとヤバい”瞬間をえぐり出す
そのプロダクト、その機能は、「必要」とは言いつつ、実は「なくてもまあ大丈夫…」になっていませんか?「これがないと本気で困る!」と思わせるポイントを、コンセプトの中心に据えましょう。
よくある落とし穴
ユーザーが「あると嬉しい」と言う機能をメインにし、必需品というよりは“贅沢品”止まり。
具体策
-
- インタビューで「これが無いと、どんなダメージがある?」と深堀りする
- ユーザー自身が「それは困る…」と苦笑いするような実害を把握する
- 「Sean Ellis Test」を導入して、自分たちのプロダクトが「なくてはならない」状態になっているか?を定点的に確認する
Sean Ellis Test
Sean Ellis Testは、プロダクトやサービスがユーザーにとって「なくてはならない」存在になっているかどうかを測るためのシンプルな指標。 具体的には「このプロダクトがなくなったら、どれほど困りますか?」とユーザーに問いかけ、その回答から“必需品”度合いを定点観測します。
Sean Ellis Testの具体的な質問項目例
-
「もしこのプロダクトが明日から使えなくなったら、どの程度困りますか?」
-
非常に困る / まあまあ困る / ほとんど困らない
-
-
(追加質問例)「使えなくなった場合、業務や生活にどのような影響がありますか?」
-
「代替手段を探す手間が大きいか?」
-
「作業効率・コストにどの程度影響が出るか?」
-
判定基準(Sean Ellis Testでの目安)
-
-
回答者のうち「非常に困る」と答えた割合が40%以上を超えると、プロダクト市場適合(PMF)に近いとされる
-
40%未満の場合は、現状まだ“必要不可欠”とは言いきれないため、よりコアとなる価値の再設計やコンセプト、ユーザーセグメントの見直しが必要
-
期待効果
- “なくてはならない存在”として使われ続ける状態を実現するコンセプトか?
- “あったら嬉しい”程度の体験しか提供できないコンセプトか?
を見極めることができる。

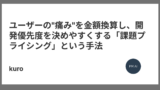
3 / ジョブ理論(JTBD)×感情トリガーを掛け算
ユーザーが達成したい仕事(ジョブ)と、心を動かす感情がセットになっているか?
論理と感情、両輪が揃うと「熱狂を生むコンセプト」が生まれます。
よくある落とし穴
ジョブ理論に則って機能的課題は解決したが、感情面が弱く、ユーザーの“ワクワク”が不足。
具体策
-
- ジョブを定義する際、「その成果を過去に得たとき、どんな気持ちになったか?」をインタビューで聞き出す。
- 誇らしさ、安心感、解放感、背徳感など、感情キーワードをリスト化して盛り込む。
期待効果
“行動面のニーズ”だけでなく、“心のニーズ”に応えるコンセプトに昇華して、リピート率や熱狂度を上げることができる
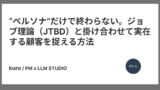
4 / 強烈な“刺さる言葉”をひとつ仕込む
コンセプトの文章に“雑”なフレーズばかり並べていませんか?
たった一言でユーザーの心を突き刺すキーフレーズが大事です。
よくある落とし穴
「〇〇の課題を解決するソリューションです」みたいな当たり障りのない表現。
具体策
-
- 数名でブレストし、“暴言スレスレ”、”血生臭い表現”など、あえて振り切って、思い切りの良いフレーズを提案し合う。
- ユーザー視点で「グサッとくるか?」をチェックし、ひとつ採用。
期待効果
そのフレーズを基点に社内外で話題が生まれ、コンセプトが“社内の流行りワード”化して拡散されやすい。

5 / “ダークサイド”の心理を(適切に)逆手に取る
ユーザーが公には言いづらい使い方こそ、実は高いモチベーションが隠れている。
恥や後ろめたさをくすぐると強烈なファンが生まれることも。
よくある落とし穴
明るいモチベーションばかり想定し、嫉妬、怠惰、背徳感などの負の感情を見落とす。
特に性格の良いPMにありがち。
具体策
-
- ユーザーの「実はこういう理由もあって…」という裏話を丁寧に拾う。
- その負の側面を肯定・サポートするメッセージをコンセプトに組み込む。
期待効果
表では言いづらい本音を拾うことで、社会やユーザーの実態に沿ったコンセプトになる。

6 / 市場データを“あえて”疑う
平均値や多数派ばかり見て、本当に尖ったニーズを見逃していませんか?
よくある落とし穴
定量データの“中央値”に合わせた設計で、ユニークな層を切り捨ててしまう。
具体策
-
- アンケート結果の“異常値”や“標準偏差が大きい項目”に注目する。
- そこにあるユーザーの極端なニーズを掘り下げると、新しいコンセプトの芽が出る。
期待効果
競合が拾わないニッチ層を狙い、“自分ごと化”しやすい独自路線を確立。
「尖ったユーザーに対する尖ったコンセプト」に仕立てることができる

7 / “いますぐ試せる仕組み”を本文内に用意する
コンセプトを記事にしてみて、それを記事を読んだ瞬間、「やってみよう」と思える導線がありますか?
行動に移した人がレビューやシェアを生む好循環が生まれます。
よくある落とし穴
コンセプトは面白いが、実行ステップがイメージできないので行動換気ができない、機能アイデアに繋がらない。
具体策
-
- chatGPTやGeminiなどを使い、ペルソナや顧客の課題、現状のペルソナなどの情報とコンセプトをセットでインプットし、PRリリースを作成してもらう
- その擬似PRリリースをチームで輪読し、コンセプトをブラッシュアップしながら新しいバージョンの擬似PRを納得するまで作成する
期待効果
「まずは自分たちがワクワクできるコンセプト」の壁を乗り越えやすい

深く“刺さる”コンセプトとは?
顧客に刺さるコンセプトは単にニーズを拾っただけではなくユーザーの裏心理やシビアな瞬間まで踏み込んだもの、だと僕は考えています。
なので、あんまり綺麗事を並べすぎても「人が動くコンセプト」にはなりにくいです。
今回紹介した7つのTipsを参考に、あなたのプロダクトに“根こそぎ”のインパクトを与えるコンセプトを再設計してみてください。
もし「これは使えそう」と思ったら、いいねやシェアをいただけると嬉しいです。あなたのリアクションが多くの人へこの情報を届ける大きな力になります。

Q&A
- Q1: ダークサイドを肯定しすぎると炎上リスクがあるのでは…?
- A1: 「負の感情を解消する」というポジティブなゴールを提示すれば問題ありません。あくまでユーザー自身の本音を受け止める姿勢の話です。
- Q2: 競合と正面対決では勝てそうにないが、ニッチ狙いが怖い…
- A2: ニッチの方が“自分ごと化”しやすく、熱狂的ファンを獲得しやすいです。まずは小さいコミュニティで成功し、そこで培ったブランドで徐々に拡大する戦略も有効。
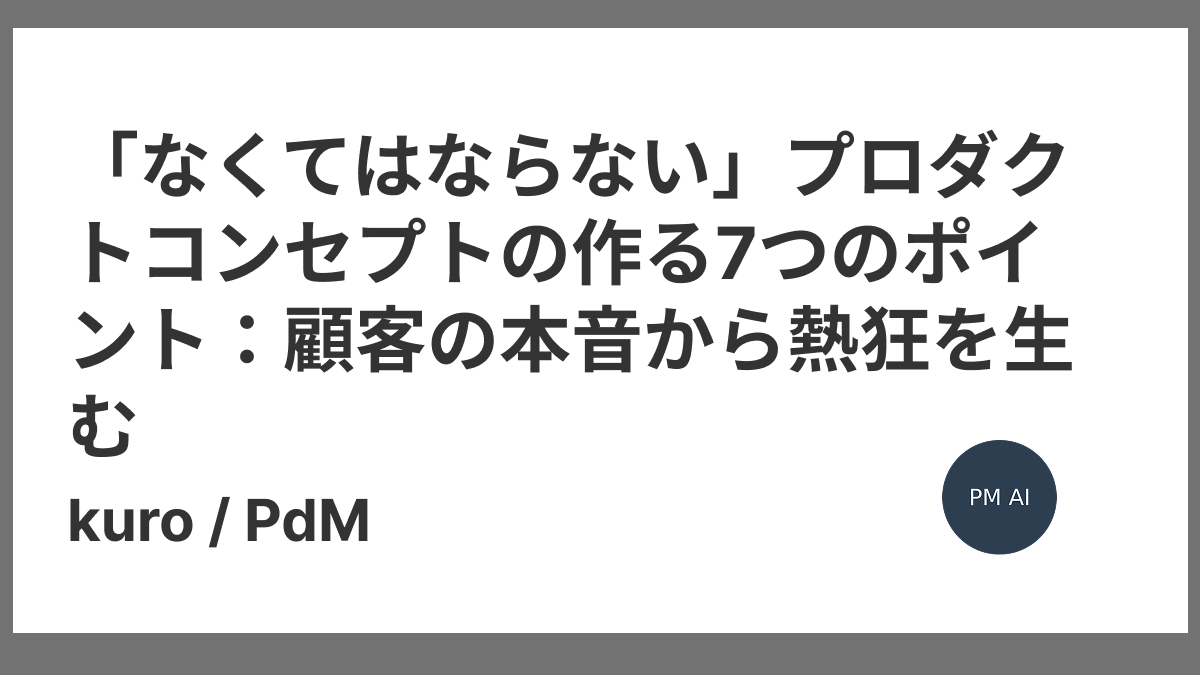

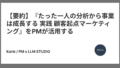
コメント