「ユーザーインタビューはやっているけれど、顧客の“本当に欲しい”驚き機能がイマイチ見えてこない…」
「当たり前品質はそこそこ整えたけれど、ユーザーをワクワクさせる“魅力品質”がどこにあるのか掴めない…」
こうした悩みは、ミドルレベルのプロダクトマネージャーにはよくあるのではないでしょうか。僕自身、数多くのユーザーインタビューをやってきたなかで、当たり前品質の改善は順調に進んでも、魅力品質をどう見極め、磨き上げるかは難しいな、と思っています
そこで本記事では、Kanoモデルの「魅力品質(Attractive Quality)」に特化し、それをユーザーインタビューで発見・検証するアプローチを紹介します。
Kanoモデルの「魅力品質」
魅力品質(Attractive Quality)は、ユーザーが「無くても不満ではないが、あると強い満足や感動を得られる」要素のこと。たとえば、アプリの地味な部分にさりげない遊び心を仕込む、サポート対応が想像以上にスピーディで手厚い、といった体験が「こんな機能があったんだ!」「こんなに助かるとは思わなかった」とユーザーを驚かせ、ファンを増やすきっかけになります。
逆に言うと、魅力品質はユーザーが明確に「これ欲しい」と言語化しにくい性質を持ちます。そもそもユーザーが想像していないからこそ“魅力”として跳ね上がるのです。そのため、形式的なアンケートや浅いインタビューでは埋もれてしまいがち。ここにユーザーインタビューでの“深堀り”や”コンテキスト情報の収集”が生きてくるのです。

ちなみに、Kanoモデルでは他に“当たり前品質(Must-be)”“一元的品質(One-dimensional)”などもありますが、本記事ではあえて魅力品質にフォーカスします。当たり前品質が欠けると深刻な不満を招くため重要度が高い一方、魅力品質こそが「顧客を熱狂的なファンに変える原動力」になるからです。例えば、当初Airbnbがホスト向けに提供したプロカメラマンによる写真撮影サービスは、ユーザーの期待を超える“魅力品質”だったとよく語られます。
(一応補足で、当たり前品質の欠落が多いとユーザーは離脱するので当たり前品質ももちろん大事です)
なぜユーザーインタビューが魅力品質の発見に有効なのか
ユーザーの“潜在的ニーズ”や“隠れた期待”を探るためには、彼らが現状抱える課題や使い方を深く理解する必要があります。そこで効果を発揮するのがユーザーインタビュー。一般的に、ユーザーは意識していないニーズやアイデアを抱えていますが、それを自分から積極的に話してくれるとは限りません。
だからこそ、少しずつ誘導尋問にならない形で質問を投げかけ、アイデアの種を可視化することが大事です。ただし、質問をうまくデザインしないと、「いま特に困っていないので必要ないです」という表面的な回答に留まってしまうことがあります。そこからの深堀りがポイントになります。
魅力品質を磨くためのユーザーインタビュー設計と質問例
では具体的に、ユーザーインタビューでどう質問すれば「魅力品質」のアイデアを引き出せるのでしょうか。僕が実務で意識しているポイントをいくつか挙げます。
1. 現状満足点と不満点を分けて聞く
「今のサービスで良いと思うところは? 不満や不足を感じるのは?」
当たり前品質の欠落があると、どんな魅力的品質を投入しても霞んでしまいます。まずは不満をしっかり把握してから、プラスアルファの期待に踏み込むと会話がスムーズに進みやすいです。
2. “未来シナリオ”を描かせる
「理想の世界として、もしあなたの業務が劇的に簡単になるとしたら、それはどんな状態ですか?魔法が使えると仮定して考えてください(ドラえもんの世界で考えてください)?」
ユーザーが普段考えていない“未来予想図”を持ち込む質問です。ポイントとしては「欲しい機能」を聞いても意味がないポイントで、理想の状態を一旦聞いてみることです。
ただし、ユーザーは正確に理想を語れないのでこの後の深掘りでイメージをすり合わせていくプロセスが必要です(誘導尋問にならないように注意)。
3. 競合サービスと比較してみる
「他の似たサービスやサービス外も含めた解決手段で『これ良いな』と思った機能はありますか?」
すでにユーザーが“知らずに味わった魅力”を回想してもらう形です。そこからインサイトを得て、自社サービスに取り入れられるか検討します。
4.「余白」から新しい使い方を探る
「このサービスを使うとき、他にどんなアプリや機能を同時に使っていますか?」
ユーザーが実際に組み合わせて使っている要素を探る質問です。そこでめんどうだと感じているプロセスをプロダクト側が吸収できれば、大きな“魅力”に化けることもあります。
さらに、インタビューの分析段階では、録音や文字起こしを活用しながら会話の裏に隠れたニュアンスを探ります。無意識に言いよどんだポイントや興奮した箇所を見つけたら要チェックです。「ChatGPTでユーザーインタビューの分析を爆速にする具体手法」などのテクニックも、リサーチ工数を削減しつつ発見精度を上げるのに役立ちます。
インタビュー結果をKanoモデルへ落とし込むフロー
インタビューで得たインサイトを、Kanoモデルにどう反映させるか。僕が実践する大まかなフローは以下のとおりです。
- キーワード抽出: ユーザーが発した印象的なワードやストーリーをピックアップする
- 課題やアイデアの類型化: ピックアップしたものを“当たり前品質”か“魅力品質”か、初期仮説を立てる(グレーゾーンは後で再検証)
- チーム内ブレストで具体機能に変換: 仮説段階で良さそうなインサイトを具体的な機能案に落とし込む
- Kanoアンケートやテスト: 「あったらどのくらい嬉しいか? なかったらどのくらい不満か?」の2軸質問で評価し、当初の仮説が正しいか検証する
- ROIとスコープの調整: 魅力品質はビジネスインパクトを測りにくい場合もある。開発リソースやリリースタイミングと照らし合わせ、優先度を決定
ここでKanoアンケートを実施するなら、インタビューの段階で大まかなアイデアを洗い出し、本格的にアンケートによる定量検証で「どのくらい魅力的に受け止められるのか」を把握する形が多いです。
また、一部の機能に関してはプロトタイプをユーザーに触ってもらい、インタビューを重ねる方法もあります。体感してもらうことで「あ、こういう機能は助かる」「いや、そこまでは求めていない」とリアルな反応が返ってきます。詳細はプロトタイプを使ったユーザーインタビューにまとめてあるので、興味があれば参考にしてください。
魅力品質の発見を“無駄打ち”にしないための検証ステップ
魅力的なアイデアが見つかった後も、実装してみたら「ユーザーにはハマらなかった…」という残念なケースは往々にしてあります。そこで重要なのが小規模な検証ステップです。いきなり全ユーザーに向けてリリースすると、万が一の失敗コストが大きくなります。
最小限でのリリースと観察
ユーザーセグメントを限定し、数%〜10%程度のユーザーに先行公開し、反応を定量・定性でチェックします。ログ分析やカスタマーサポートの問い合わせ増減をモニタリングすることで、ユーザーがポジティブに受け入れたかどうかを把握します。
もし受け入れられなかったら素早く修正、あるいは撤退の意思決定をするフレキシブルさも必要です。
感情的反応を拾うインタビュー
定量データだけでなく、ユーザー自身がその新機能にどんな感情を抱いたかを聞く場を作ります。「驚き」「意外性」「ワクワク感」があったかをストレートに尋ねると、魅力品質を見極める補助指標になります。ユーザーが一瞬言葉に詰まるような「想定外の喜び」があるならば、その機能には伸び代があると考えられます。
参考情報
- Noriaki Kano (1984), “Attractive Quality and Must-be Quality”, Journal of Japanese Society for Quality Control
- Airbnb公式ブログ:プロフェッショナル撮影サービスに関する成功事例
- 森川眞行 (2016), 『顧客インサイトを発見する方法』, 東洋経済新報社
- ユカイ工学などのスタートアップでのインタビュー事例紹介(各社note・ブログ)
今日から実践できるアクション
- 1. “魅力的アイデア”専用のインタビューログを作る
インタビューを行う際に「不満点」と「すでにあるアイデア」だけではなく、“魅力的品質候補”として思いついたキーワードを一覧化できる専用シートを作ります。会話中にユーザーのポロっとした発言を見逃さず記録することが重要です。 - 2. 次回アンケートにKano形式の質問を導入
インタビューから抽出したアイデアを簡易的にKanoアンケートにかけ、ユーザーに「もしこの機能があったらどのくらい嬉しいか? なかったらどのくらい不満か?」を尋ねます。ここで意外な機能が“魅力品質”扱いになる場合があります。 - 3. プロトタイプで小規模検証
有力な魅力品質が見つかったら、全ユーザーに広げる前にプロトタイプや限定公開で試験導入します。ログ分析・アンケート・インタビューの組み合わせでフィードバックを集め、価値を確信できたら本格実装に移ります。
Q&A
Q. ユーザーが「欲しい!」と言っていない機能をどうやって検討すれば良いですか?
A. まさにユーザー自身も気づいていない“潜在ニーズ”こそが魅力品質の源になります。インタビューで業務フローや使用環境を深堀りすると、実はこういう機能があったら面白いというヒントが出てきます。表面の「要望」とは別に、ユーザーの生活・業務・価値観まで踏み込むのがポイントです。
Q. インタビュー中に「そこまで魅力を感じない」という反応が多かったとき、すぐにその機能案を却下すべきでしょうか?
A. とはいえ、ユーザーインタビューだけで判断するのは危険です。魅力品質はユーザーがイメージしにくい場合が多いので、実際に触れてみたり、プロトタイプを体験してみると反応がガラッと変わることもあります。小規模検証で試して、データや追加の声を集めてから判断すると良いです。
Q. 当たり前品質とのバランスはどう考えればいいですか?
A. まず当たり前品質を一定以上に満たすことが大前提です。ここが欠落していると、せっかくの魅力品質もユーザーの不満や離脱によって埋もれてしまいます。チームのリソース配分を考える際には、当たり前品質を最優先にしながら、余力を魅力品質に回すイメージがおすすめです。
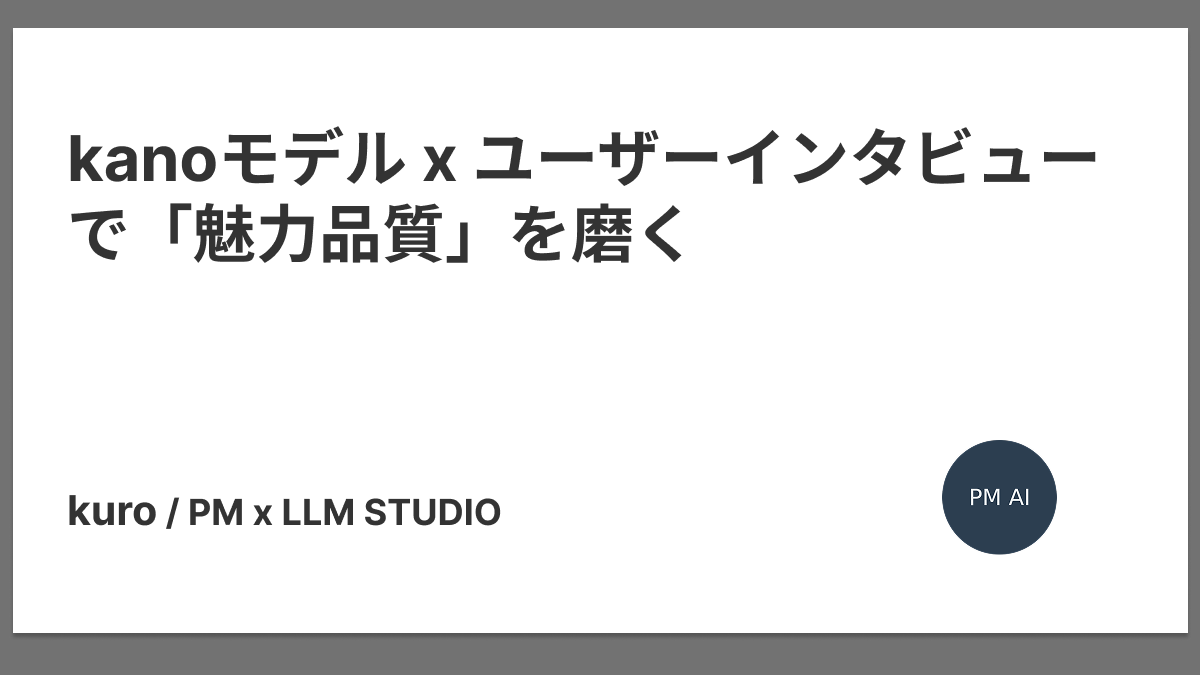
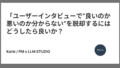
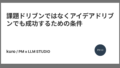
コメント