この記事の要約
- ユーザーインタビューで、“観察力”“共感力”“論理構築力”などの汎用スキルが身につく
- こうしたスキルは、チームマネジメントや経営視点の戦略立案など、多彩なPdM領域で応用可能
PdMの日常業務のなかでも、ユーザーインタビューはとりわけ奥が深い領域。
単に「機能やプロダクトの印象/使い勝手を確認する」ためだけではなく、ユーザーの潜在ニーズや心理、コンテクストを立体的に把握する手段として重宝します。また、インタビューを積み重ねるほどに磨かれていくのは「ユーザー理解力」だけではないと考えています。
観察力や共感力、論理構築力といった汎用スキルが自然と鍛えられ、あらゆる場面で役立つようになる。僕自身、累計700人以上のインタビューを実施してきましたが、それがチームリードや経営層への提案時にも活きていると強く実感しています。
ユーザーインタビューがPdMキャリアを飛躍させる
僕はマーケティング領域出身で、そこでユーザーリサーチを徹底的に叩き込まれてきました。そこでは「ユーザーは常に言語化されていない本音を持っている」と学びました。そして、その本音を引き出す過程で身につく力が、PdMとしてのキャリアを加速させる大きな鍵になると実感しています。
ユーザーインタビューでは、言葉の裏側を想像する場面が多々あります。機能改善の要望が実は別のニーズの表れだったり、課題をひとしきり話した後にポロッと出る本音にこそ大きなインサイトが隠れていたり。こうしたインタビューの“深掘り”や“洞察”が当たり前になると、デスクトップリサーチやチームビルディング、さらには経営層への提案時にまで応用できるようになるんです。
“観察力”がもたらすPdM視点の変化
ユーザーインタビューでは、発話内容だけでなく、表情や声のトーンなどの非言語サインから本質的なニーズを探り当てる場面が多いです。これを続けていると自然と“観察力”が鍛えられ、日常業務のあらゆるシーンで役立つようになります。

例えば、ユーザーインタビュー中に「この機能、まあそこそこ使います」という曖昧な回答をもらったとき、言葉自体は肯定的に聞こえますが、表情が少し曇っていたら「心の底から気に入っているわけではないのかも」と推測したり、会話の流れを変えて再質問することでより正確な手応えを得られるかもしれません。こうした観察力は、チームの定例ミーティングや、上司とのレビューでも活きます。メンバーが発言している内容と微妙な表情のズレを感じ取れれば、「何か引っかかりがあるのでは?」と踏み込んだ確認ができる。
また、観察力はマーケットリサーチや競合分析にもつながります。他社プロダクトを分析するとき、UIの配置や色使いだけをチェックするのではなく、「この配置はユーザーのどんな行動心理を狙っているのか」を想像する力が身につく。たとえば「Amazonで購入フローがやたらとスムーズに感じるのは、カート画面で追加オファーを見せる導線があるから」といった構造分析に思い至りやすくなります。
“共感力”が築くチームマネジメントとリーダーシップ
インタビューでユーザーと対面すると、「意見を押し付けず、相手の立場に立って話を聴く」重要性を痛感します。これはユーザーとのやりとりだけでなく、社内のチームマネジメントにも直結します。
例えば僕は過去、エンジニアが「この機能、ユーザーが意外と使い方を誤解しているみたいで…」とこぼすような場面です。以前であれば僕は「うーん、そんなことない気がするけどなー」「usability testのスコアも正常値だし」と軽く流してしまったかもしれません。
しかしユーザーインタビューを重ねてきた結果、「エンジニアが感じている違和感」の根底には、実際のユーザー行動を観察したインサイトがあるかもしれないと考えられるようになりました。ここで共感力を持って深掘りすることで、潜在的なUX課題が浮き彫りになるケースもあります。
この“共感力”は、ステークホルダーマネジメントの場面でも大きく働きます。例えば、セールスチームが「この機能がないとクライアントに売りにくい」と主張してきた場合も、即座に否定するのではなく「なぜそう感じるのか」を聞き出すと、セールストークで必須となる特定の訴求ポイントが見つかることがあります。そして、彼らの視点に寄り添いながら最終的な優先度を検討すれば、部署間での対立が最小限に抑えられます。
ユーザーインタビューで養った共感力は、開発チームや営業、CSといった異なるロールの間に「相手の言葉を一度受け止める」雰囲気を作り出すはずです。結果として、プロダクトロードマップを推進する際の合意形成がスムーズになり、リーダーシップを自然に発揮しやすい状態を築けます。
“論理構築力”を鍛えて経営視点を獲得する
ユーザーインタビューをした後に、そこで得た膨大な情報を整理して「本当の論点」を導き出す工程は、実はロジカルシンキングの訓練にもなります。抽象度の高い意見や感想を、そのユーザーが置かれている状況や利用シーンと紐づけて解釈し、最終的に「だからこの機能が必要」「この改善が課題解決に直結する」という筋道を立てるわけです。
こうした論理構築力が高まると、PdMとしての説明力も飛躍的に上がります。経営層へのプレゼンや、デザイナー・エンジニアへの要件定義説明など、どんな場面でも「なぜその結論に至ったのか?」を明瞭に示すことが可能になる。
たとえば「仮説→質問→回答→深掘り→検証」という一連の流れを意識するのは、インタビューだけではなくビジネスモデル検討にも使えます。ユーザーインタビューがもたらす論理構築力は、PdMの基礎体力ともいえるはずです。
“対話の型”とコミュニケーション
実際、上記で述べた3つのスキル(観察力・共感力・論理構築力)を最大化するために“対話の型”を身につけることが重要。具体的には以下のステップが有効です。
| ステップ | ポイント |
|---|---|
| 1. 聞く (Active Listening) | まずは相手の言葉をさえぎらずに傾聴。相槌を打つ際に「それは◯◯ということですか?」など、相手の言葉を要約して返すと理解が深まる |
| 2. 問う (Clarification) | 次に、もう一歩踏み込んだ質問で不明点を明確化。「いつ」「どうやって」「なぜそう思うか」といった問いを織り交ぜて事実と感情を切り分ける |
| 3. 引き出す (Deep Dive) | 最後に、発言の奥にある真の動機や背景を深堀り。そこから想定外のインサイトが飛び出すことが多い |
この“対話の型”は、ミーティングファシリテーションやユーザビリティテストでも応用可能です。より具体的なインタビュー手法については、「ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド」の記事に詳しくまとめています。
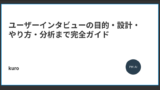
ユーザーリサーチから得たスキルを他領域に展開する
ユーザーインタビューを極めることで培われるこれらの汎用スキルは、PdMキャリアのほぼすべての領域に展開できると僕は考えます。たとえば以下のようなケースです。
- 組織マネジメント:チームメンバーが何を考え、どんなモチベーションで動いているのかを“観察・共感”しながらマネジメントすることで、意図せぬ衝突や意見対立を和らげられる
- 新規事業開発:経営視点で市場調査を行う際にも、論理的にユーザーの声を分析して、ビジネスモデルの仮説を組み立てやすい
- プレゼンテーション・対外折衝:論理構築力が身についていると、自社プロダクトのストーリーを説得力あるかたちで語れるようになる
たとえば僕は、過去に副業でスタートアップのCOO兼PdMをしていたとき、インタビューで得た共感や論理づけの手法をそのまま投資家向けのピッチ資料作成に転用しました。
ユーザーインタビューでPdMスキルを磨く
ユーザーインタビューは「ユーザーが本当に欲しいもの」を探り当てるためだけのツールではありません。観察力・共感力・論理構築力といった、PdMに必要不可欠な基礎スキルが集中的に鍛えられる“トレーニング場”でもあります。実際に700人以上のインタビューを経験する中で、僕は自分自身のチームマネジメント力や戦略提案力が大きく伸びたと感じています。
日々の開発やロードマップ更新に追われるPdMにとって、ユーザーリサーチは正直大変だと思います。しかし、その苦労を超えた先には、キャリアの幅をグンと広げてくれる汎用スキルが身につくはずです。これらのスキルを意識的に磨くことで、次のフェーズへと進む自分をイメージできるようになる。ぜひ、ユーザーインタビューを単なる「課題抽出ツール」にとどめず、キャリアアップの起点として捉えてみてください。
今日から実践できるアクション
- インタビュー時にチェックリストを用意する
どのような非言語サインがあれば深堀りの合図なのか、あらかじめチェックリスト化しておき、観察力を磨く手がかりにする。 - インタビュー後に要約ドキュメントを作成する
得られた情報をグルーピングし、要点を論理的に整理する練習を習慣づける。すると、チームへの説明やロードマップ連携がスムーズになる。 - チームメンバーへの“共感的ヒアリング”を試す
ユーザーだけでなく、開発チームや営業など社内関係者にも同様の“対話の型”を用いてヒアリングし、相互理解を深める機会を増やす。
Q&A
Q1:ユーザーインタビューの経験が少なくても、こうした汎用スキルは身につきますか?
A1:回数が少なくても、意識的に深掘りと観察を行えば確実に効果があります。まずは小さなインタビューでもいいので、“相手の言葉の裏にある感情や課題”を探る姿勢を大切にしてください。
Q2:観察力や共感力をチームに広めるにはどうすればいいですか?
A2:インタビューの振り返り会を開催して、非言語サインに気づいたポイントを共有するのがおすすめです。また、ユーザーヒアリングを組織に根付かせる4つの仕組みを考察したでも詳しく解説していますが、社内勉強会やスキル共有の場を定期的に設けると効果的です。
Q3:論理構築力をさらに高めたい場合、何か参考になる書籍や取り組みはありますか?
A3:『The Mom Test』(Rob Fitzpatrick著)や『INSPIRED』(Marty Cagan著)などは、インタビューの際に仮説を構築し、検証を重ねるプロセスが詳しく解説されています。読みながら実際のインタビューで試してみると、ロジカルに情報をまとめる力が伸びやすいです。
参考情報
- Rob Fitzpatrick (2013). The Mom Test: How to Talk to Customers & Learn If Your Business is a Good Idea When Everyone is Lying to You.
- Marty Cagan (2018). INSPIRED: How to Create Tech Products Customers Love. Wiley.
- ESOMAR (2021). “Global Market Research Report”: ユーザーリサーチが事業成長と意思決定スピードに与える影響を分析。
- ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド
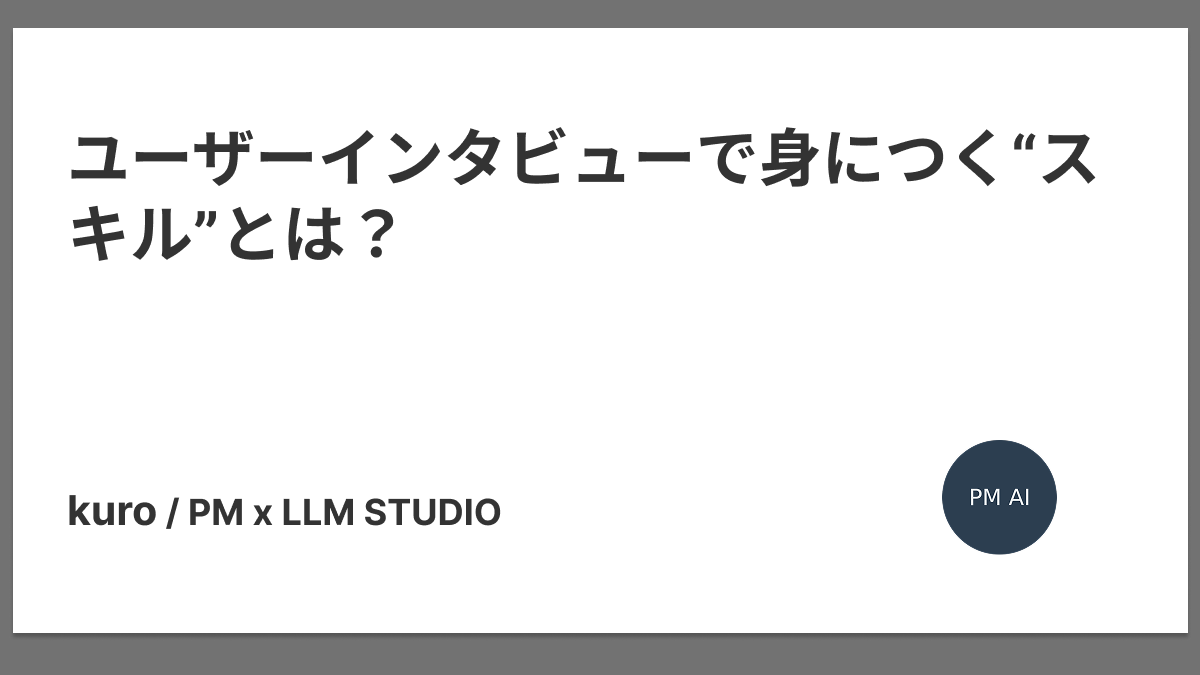
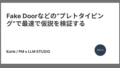
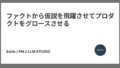
コメント