「せっかくインタビューで得た声を共有しても、経営層や上司が動いてくれない、チームがやる気を出さない」
──こんな悩みを抱えていませんか?
本記事では、ユーザーインタビューの結果をどう分析し、どう見せるとトップやメンバーが本気で動くのかを解説します。
経営層・上司・メンバーが動かない3つの理由
理由①:優先度がわからない
ユーザーの声は重要だとわかっていても、会社全体の案件が山積みだと後回しにされがち。どれほどのROI(投資対効果)やリスク軽減につながるのかが不明瞭だと、動きづらい。
理由②:情報が多すぎて要点がつかめない
テキストベースで長大なログや要約だけ渡されても、忙しい経営陣は深堀りして読む時間がない。
理由③:チームメンバーが当事者意識を持てない
「この課題、僕/私に関係ある?」と思われてしまうと行動に結びつかない。
ユーザーインタビュー結果の分析で説得力を生む3つポイント
①ROI・コストインパクト分析
経営層や上司を動かすには「投資対効果」の目線が欠かせません。
例えば、ユーザーがUIに不満を持ち離脱しているというインサイトを得た場合、1人の離脱が与える損失を仮定し、そこにユーザー数を掛け合わせる。
「この改善で離脱率が3%改善すれば、年間◯百万円の損失を防げる可能性があります」といった形で示すと、トップが即決しやすくなります。まずはフェルミ推定レベルで良いので、上司にインタビュー結果を数値に置き換えてみせにいってみましょう。
②RICE / ICEスコアで優先度を可視化
ユーザーインタビューから見えてくる多数の課題。それを整理し、RICE(Reach, Impact, Confidence, Effort)やICE(Impact, Confidence, Ease)などのフレームワークでスコア化しましょう。
- Reach=どのくらいのユーザーが影響を受けるか
- Impact=どれほど大きな効果があるか
- Confidence=確信度
- Effort=工数
を数値化し、優先度マトリクスを作成すると、上司やメンバーの合意を得やすい。
また、事業状況によって重視する評価項目は違うので、少量の課題にだけスコアをつけたら最初に評価軸を上司と擦り合わせにいってみましょう。
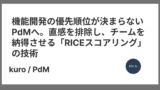
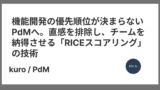
③定性×定量データのハイブリッド分析
定性インタビューだけでなく、アクセス解析や問い合わせログなどの定量データを掛け合わせると説得力が段違いに上がります。
例: 「◯◯画面で離脱するユーザーが24%存在。そのうち◯割が同様の不満をインタビューで述べている」
このように、定量データで「どのくらい深刻か」、定性データで「なぜそう思うか」を補完することで経営層も納得しやすくなります。
経営層・上司を動かすレポート&プレゼン手法
エグゼクティブサマリーを1枚でまとめる
忙しい経営層には、まずA4一枚に目を通してもらうのが鉄則。
内容例
- 背景
- 主要課題(3つ以内に絞る)
- 改善によるROI推定(費用対効果やリスク低減)
- 経営層や上司に求めるアクション(開発投資・優先度変更など)
この1枚のレポートが「意思決定のトリガー」になるよう、数字や引用を盛り込みましょう。
動画クリップ&ナラティブで感情面に訴える
経営層は数字だけで判断するわけではありません。
インタビュー動画クリップを30秒ほどに編集し、ネガティブな課題発言や強い要望シーンを見せる。「朝7時、通勤電車の中で◯◯をしようとしたら〜」と時系列でユーザーの痛みを物語風に語るなど。
数字+“刺さるストーリー”の両面があると、トップの動機づけが高まります。
特に動画は一発で課題の深刻さが伝わりやすい必殺技です(僕もよく使います)。
メンバーを巻き込む見せ方:チーム全体が動く仕掛け
小さな共有会+Snapshot配布で当事者意識を高める
メンバーが「自分の仕事と関係ある」と思わなければ動きません。
おすすめは週1回、15〜30分のスモールミーティングでインタビュー結果をサクッと共有する手法。「自分が作ったUIがこんなに苦痛を与えていたのか…」と実感できる動画クリップやビジュアルSnapshotを見せると、一気に当事者意識が芽生えます。
また、僕はslackでインタビューで見つけた課題をスレッドとしてライブで書き込んでいるのですが、その時に出てきた課題に関係ありそうな人をメンションしちゃいます。
その情報がきっかけとなって関係者のKPIが上がれば嬉しいはずなので。
タスク化してOKRやロードマップに落とし込む
インタビューで見えた課題を「誰がいつまでに改善策を検討するか」まで落とし込むことで、メンバーが動きやすくなる。
例: 「UI改善案を来週のデザインレビューで具体化」
OKRやロードマップツールにインサイトをインプットしておくと、定期的に進捗をモニタリングでき、忘れられにくい。特に課題は出てきたけどそこにタイムボックス(締切)を設定せず、結局誰も拾わなかった、はあるある。誰が、何を、いつまでに、どんな状態にするのか、を必ず握ってプロジェクトマネージャーがいるならその追跡をパスしましょう。

今日から実践できるアクション
- ROIシミュレーション
ユーザーが離脱するとどんな金銭的・ブランド的損失があるか概算してみる - RICE / ICEスコア作成
発見した課題をスコアリングし、優先度を明確化 - A4一枚エグゼクティブサマリーを用意
経営層や上司向けに「要点+ROI+結論」を1ページにまとめる - インタビュー動画クリップを30秒編集
強い感情が出た場面だけ切り取り、短くまとめて共有 - 15分のスモール共有会を週1回実施
Snapshot配布&メンバーで簡単に意見交換し、タスク化
Q&A
Q1. ROIの算出が難しい場合はどうすれば?
A. 完全な正確性を求める必要はありません。離脱率や問い合わせ数、あるいは開発コストの試算など、ざっくりとした推定でも「規模感」を提示できれば十分経営層は動きやすくなります。フェルミ推定でOK。
Q2. メンバーが「その課題は自分と関係ない」と思ってしまいます
A. そこでナラティブ化と小規模共有会が生きます。実際のユーザーが不満を口にする動画やストーリーを見ると、意外と「自分事化」しやすいです。
Q3. 上司が多忙で資料をちゃんと読まない…
A. だからこそA4一枚エグゼクティブサマリーと動画30秒が有効。
むしろ経営層は「読み込むより見せてくれ」と思っているケースが多いので、目と耳で短時間に把握できる仕掛けを作りましょう。
特に動画をslack投稿に直張りしておくと電車移動中とかにみてくれるので有効です。
参考文献・引用一覧
- [1] Nielsen Norman Group (NN/g). “User Research ROI: Demonstrating Value” (2020)
- [2] Ash Maurya. “Running Lean” O’Reilly, 2012
ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイド
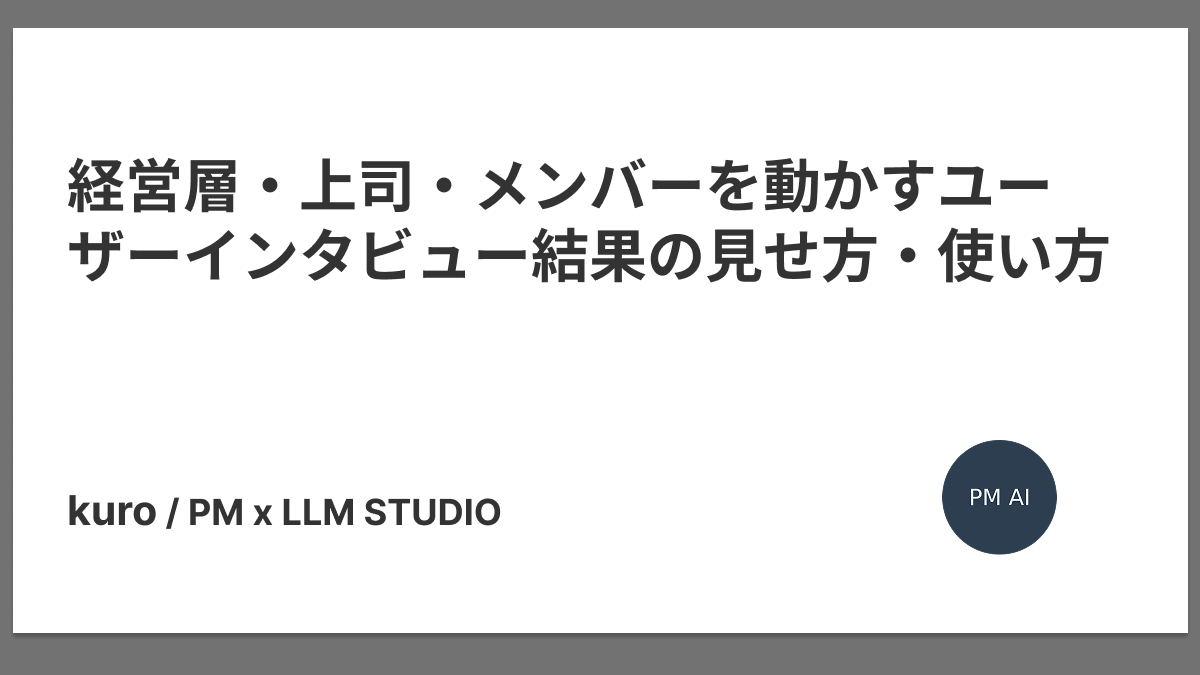
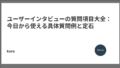
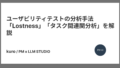
コメント