この記事の要約
- ユーザーが既存ツールの代わりにExcelや手書きメモなどの「非公式ワークアラウンド」を使う背景には、機能不足やカスタマイズ性の欠如といった本質的な課題が隠れている
- インタビューで裏タスクを発見し「ToDo-Pain-Gain」フレームワークで整理することで、ユーザーの真のニーズとプロダクト改善の機会が明確になる
- 裏タスクの公式機能化により、業務効率化と工数削減を実現でき、プロダクトの競争力強化につながる
「非公式ワークアラウンド」とは?
「非公式ワークアラウンド」は、正式に提供されているシステムや機能では対応しきれないニーズやフローを埋めるために、ユーザー自身が工夫して編み出す独自の仕組み。
手書きメモ、Excel表、付箋、チャットBotのマクロなど、その形は多岐にわたります。
こうした“隠しレシピ”は、ユーザーが自分のタスクを最適化するために生み出した必殺技とも言えます。
ジョブ理論を提唱したクレイトン・クリステンセン氏は著書『Competing Against Luck』にて、「ユーザーが代わりに何を雇用しているか」を見極める重要性を説いています。
つまり、ユーザーがどのような裏タスクを持ち、どのような手段でそれを達成しているかを観察することで、本質的な課題や解決すべきポイントが浮き彫りになるのです。
裏タスクを突き止める意義
非公式ワークアラウンドが生まれる背景には、いくつかの典型的な要因があります。
- 公式ツールの機能不足:必要な機能がない、または操作が複雑すぎる
- カスタマイズ性の不足:細かな業務フローに対応しきれない
- 心理的ハードル:新ツール導入の教育コストや組織調整に対する抵抗
これらの要因が重なり、自作ツールやメモで補う必要が生まれます。
裏タスクを突き止めれば、ユーザーがわざわざ“抜け道”を作る理由を知ることができます。
これはすなわち新たな改善機会で、突き詰めることができれば自社プロダクトのさらなるグロースのチャンスとなります。
裏タスクを見つけるためのインタビュー
ユーザーインタビューで「裏タスク」を深掘りする際は、質問の工夫が不可欠です。
- 「普段、特定のサービスではなく関数などを組み合わせたExcelや社員同士で使うメモなどはありますか?」
- 「既存ツールを使うとき、手間だなと感じる瞬間はいつですか?」
- 「既存ツールで対応できないタスクはありますか?それは週に何回、1回何時間程度発生していますか?」
といった問いを投げ、実際に資料やシートを見せてもらうと有効です。
- インタビューの設計や質問項目を整理したい場合は、ユーザーインタビューの目的・設計・やり方・分析まで完全ガイドもを参考にしてください
- 実際の質問例については、ユーザーインタビューの質問項目大全にまとめています
- インタビュー前にチームで仮説をしっかり立てたい場合は、ユーザーインタビュー前に「筋の良い仮説」をチームで設定する具体的な方法やフレームをご覧ください
コアジョブと心理的ハードルを可視化するフレームワーク
裏タスクを聞き出した後は、それを「ToDo—Pain—Gain」の3要素に分解します。
- ToDo:ユーザーが実際に行っているタスク
- Pain:公式ツールでは解決できない不満やリスク
- Gain:裏タスクによってユーザーが得られるメリット
この3要素を整理すると、ユーザーが裏タスクをやめられない理由や、本当に求めている機能が見えてきます。
“面倒に感じる操作ステップ”や“部署ごとの独自ルール”など、細かなニュアンスが浮き彫りになるのが醍醐味。
裏タスク発見を活かした機能改善イメージ
例えば、勤怠管理システムで、部署ごとに異なる打刻漏れ対策のため、担当者が毎日Excelでリマインドリストを作っているケース。
理由は、公式リマインド機能が「文面やタイミングを部署独自のルールに合わせづらい」から。
そこで、リマインド内容や送信条件を柔軟に設定できるようにすれば、打刻漏れの減少と担当者の作業時間短縮を実現できる可能性があります。
今日から実践できるアクション
- 1. インタビュー設計で「非公式ワークアラウンド」を前提に含める
具体的な質問を用意し、実際に使っているツールの画面やファイルを見せてもらうことが大切です。 - 2. 見つかった裏タスクを「ToDo—Pain—Gain」で整理する
抜け道を選ぶ理由が明らかになり、コアジョブが言語化されます。 - 3. 小さくプロトタイプを作って検証
裏タスクを公式機能化した場合の使い勝手を、少人数でもいいのでテストしてみます。 - 4. 社内への共有と優先順位付け
「いかに業務効率が上がるか」「どのくらい工数削減が見込めるか」を定量的に示すと説得力が増します。
Q&A
- Q1. 全ての裏タスクを洗い出すのは難しくないですか?
- A. すべてを拾い切る必要はありません。共通パターンや業務上のインパクトが大きいものに焦点を当てるだけで、十分な効果が期待できます。
- Q2. 裏タスクの発見から機能改善まで、どれくらいの期間がかかりますか?
- A. 開発体制や予算にもよりますが、小規模な改善なら1〜2週間でプロトタイプ検証が可能です。重要なのは“まず小さく試す”姿勢です。
参考情報
- クレイトン・M・クリステンセン, タディ・ホール, カレン・ディロン, デイヴィッド・S・ダンカン(2016)『Competing Against Luck』ハーパー・ビジネス
- Nielsen Norman Group (2019) “User Workarounds in the Workplace and How to Investigate Them”
- MIT Sloan Management Review (2020) “Understanding User Behavior Through Workarounds”
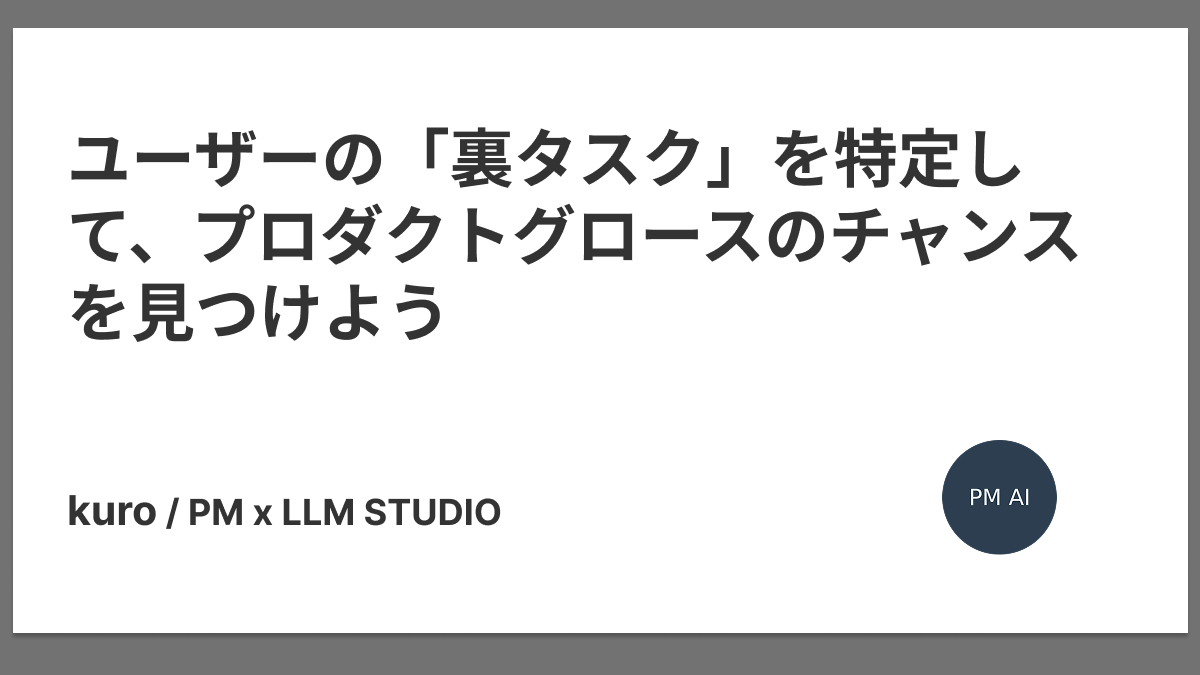
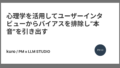
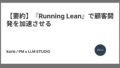
コメント